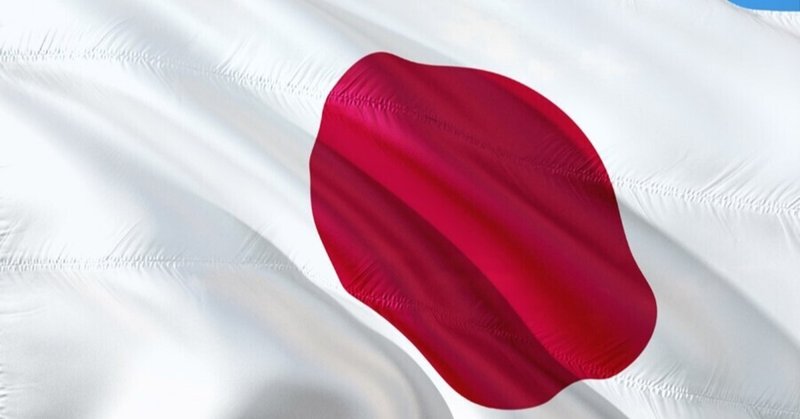
小説「京都 リ・バース」2 城塞の姫君 東の都編
神奈川県相模原市緑区。旧相模湖町は、相模原市に編入されるまでほぼ一万人の人口を擁していた。
相模川を堰き止めた人造湖である相模湖。その北東岸に位置する緑豊かな市街地である。湖やその周辺は、釣りやキャンプ、ボート遊びや遊覧船などで賑わい。過去、東京オリンピックでは、カヌー競技も開催されていた。古くは甲州街道の宿場町として、現代では中央自動車道のインターチェンジが交通の命脈として機能している。
近辺には「桂川」「与瀬」「嵐山」「吉野」と、京都に由来する地名が点在し、弘法大師が行脚の際、京都の地形や山容に似通ったところがあると、命名されたとの伝説が残っていた。事実、周囲は深い峰々が連なっている。
その人家から逃れるように距離を置いた深い山中に、広い豪邸が存在していた。
十数年で、日本のみならず世界規模へと急成長した新興企業。ユキムラ・グループ総帥の邸宅。重厚な造りの洋館は、本館を中心として左右対称に広く、別館を両脇に従える様式となっていた。屋敷を囲む広い庭、深い木々、堅牢な壁と最新のセキュリティシステムに囲われた『城塞』でもある。
そこで最も庇護されているのは、ただ一人。雪村修造の娘であるという真実は、地元の者には知られてはいない。噂として、愛娘が住んでいるだろうことは語られてきたが、ここ数年、彼女の姿を眼にした者はほとんど居なかった。修造には長男が居たが、留学生活が多く、長くここで暮らすということも少なかった。
多くの使用人が仕えてはいるが、誰もが口が堅く、誰かに尋ねられることがあっても、微笑んでさらりと流す。忠実な献身さは、どこから来ているのか。
権力によって強制されているふうでもなく、何らかの利益供与によって縛られているふうでもなく。誰もが粛々と、幸福な自負をもって、仕える主たちに関しては、けっして口外しないと決意しているようだった。
恐ろしい速さで事業を拡大展開していった雪村修造の手段は、強引な方法も多かった。獰猛な猛禽類のように、狙い定めた企業へは、速やかにあらゆる局面を想定した上で買収をかけ、確実に手に入れる。
それによって、強い恨みを買うことも。修造を落としいれようと、弱みを握ろうと考える者も多かっただろう。そのためにはプライベートな部分の過剰な警護は当然でもあった。
何より、彼女は未成年で、この春に中学生になる程度の若年。世間の好奇の目に晒させるのも酷だった。
人里から離れた静かな山間に居を置いたのも、彼女が誕生してからのことだった。元はある資産家の別邸だったらしい。
地元の者も、今ではそれが当たり前のように、もう雪村家を詮索することもなかった。
姿は目にすることは無くても、彼等もまた、使用人たちと似たような、愛すべき存在の成長を慈しむ心地に至っていたのである。
その切っ掛けは二年前。神奈川県を直撃した巨大台風が残した災厄だった。土砂崩れで道路を寸断され、周辺地域は一時孤立しかけた。防災情報から備えてはいたものの、想定以上の被害に統制庁舎は混乱に陥った。そんな中、雪村修造からの支援の申し出。邸内に設置された二機のヘリコプターの発着場を開放したことで、支援物資は速やかに届き、二人の急病人も緊急搬送が適った。自社から建設重機と要員を空輸で投入するという荒業で、道路状況の復旧もまたたくまに完了させ、二次被害、何軒かの民家への被災を回避させた。
住民の代表が修造の代理人を勤めた執事に礼を伝えると、「お嬢様のご幼少より、皆様にはお世話になっておりますので当然のことと、主から申し渡されております」と。屋敷を一度見て「お嬢様も、この度のことは大変お心を痛めておいでです。被害が出る以前に、お嬢様は主にもしもの備えをお願いになっていたのでございます」
だが、それよりももっと以前。雪村家が居を移してから一年ほどの間。栗色の髪の若い母親が、小さな赤ん坊を腕に抱いて、山里を歩いていた姿がよく見かけられていた。
その母親は目に映るもの耳に入る音、何でもが珍しいようで。誰にでも、それは何か? 何をしているのかと、柔らかい耳通りの良い声で尋ねていた。
そうして、赤ん坊にはまだわからないだろうに、その子にもよく見せてあげながら、話しを聞いてはうなずいたり、感心したり。母親は名乗りもしなかったが。離れずついてくる付き人たちから、豪邸の奥方だと察せられた。
上品な物腰、人を疑うことのない真っ直ぐな眼差しには、穢れが無く。浮世離れした好奇心で、商店の店先や、庭や縁側で時間を忘れ話し込んだり。赤ん坊を預けて、畑に入ってみたいと御付きの者を伺ったり。勿論、否であったが、代わりに畑の持ち主が、大根を二、三本抜いてみせた。に、誰もが振り回され、驚き、笑いあった。
その姿を目にした者、関わった者すべてを幸せな心地にし、彼等母子の未来の幸いを願わせるようになっていた。
二歳の娘を残して、彼女が亡くなってから。美しい母親の名前が、レイナ、であったことを、彼等は知った。
彼女の面影によく似た、白百合の花を一輪、野辺の朝、各家々が雪村家に続く沿道に向け掲げた。
早すぎる別れを悼み、残された幼子の未来を憂いた。
十年後の今年三月。今度はその子は、父親までも失った。
妻の死を悼む白百合の花を、朝霧が立ち込める中、一輪一輪、受け取って歩いた雪村修造。二歳の娘を片腕にしっかりと抱いた背中は、ただの父親でしかなく、ただの一人の男。ただの夫、であった。
◇◇◇
遅咲きの八重山桜は、まだ多くの蕾が固く閉じているのに。
大きく広がる枝々の中ほど。懐に抱かれるような一枝に、ただ一輪が花開いていた。
薄い花びらが幾重もふっくらと開いた一握りの花。精一杯上へ手を伸ばすが、届かない。
足元から湧き上がる風が、舞の長い黒髪を乱す。構わずに、もう一枝分、そろそろと幹を両足で抱えるようにして登ってみた。
剣道着の紺袴が木肌に絡み、登り難い。朝の一人稽古と、道場の水拭きは、舞の日課だった。着替えてから登るなど、頭に浮かばなかったのだ。
斜め上に伸びる太い幹に体を預け、細い枝の一つに左手を掛け身を乗り出す。右手がやっと、花を付けた枝に届いた。地表までは三メートル以上の高さ。この八重桜の木には、もっと小さな頃から何度も登っている。こんな枝先まで来るのは初めてだけど。
相模原の山深い周辺は、4月半ばの瑞々しい緑に包まれていた。その新緑と朝の冷気のしっとりとした清々しい大気。
風にふるふると揺れる淡い色の花弁は、唐突に、懐かしい面影を呼び覚ました。
頼り無い細い肩のその人。静かに優しく微笑んでいる桜色の頬。栗色の髪の、少女のような若々しい顔立ち。
「……お母様……」
彼女が物心つく頃には、写真でしか会えなかった人。
伸ばした指先が迷う。
「私は、どうしたらいいの……?」
尋ねても、母は微笑むばかり。フォトフレームの中の彼女は、腕に小さな赤ん坊を抱いていた。それは舞自身で、この時の母は、2年後に永遠の別れを迎えるなど知るはずもない。
あれから十年。片親でも、彼女は愛情深く育てられてきた。父親の、最大最強の庇護の元。
その父も。春を待たずに、この世を去った。
風が、母の面差しを天に召すかのように枝ごと花を揺らす。
「……お父様……。私は、どこに居たらいいの……?」
夢のような現実のような。迷宮に閉ざされ一人取り残された、という記憶。気付いた時には、パジャマ姿で、なぜか母が使っていた部屋の前に舞は居た。家政婦頭の塚野に抱えられ、彼女は舞の名を呼び続けていた。母が亡くなってから、ずっと鍵がかけられ、閉ざされていた扉だった。寄木で百合を象嵌した扉を、舞は叩き続けていたらしい。
また長い黒髪が風に巻き上げられる。今度は強く。体が浮いたような錯覚。重力を無くした感覚が身体中に湧き上がる。
「!」
我に返って右手を引き、重心を引き戻した。が、ガクンと、上体が沈む。
「……お嬢様っ……!」
悲鳴に近い呼び声が下から聞こえ、更に現実へと引き戻してくれた。
体重をかけていた左手の枝が大きくしなっていた。手を放すと、目の前で大きく跳ね上る。
もう少し遅れたら、折るところだった。折れた枝ごと下へ。落ちていたかもしれない。
「……大丈夫……。大丈夫だから、もう心配しないで……。ちゃんと私を見て?」
地上では、黒い立ち襟の上衣にロングスカートの婦人が、両手で顔を覆っている。上から見下ろすと、彼女の髪にはかなりの白いものが混じっているのが見て取れた。
「……いいえ、いいえ。もう怖くて見あげられません、お嬢様。ご無事なら、そこでじっとしていて下さい。
誰か早く登って、お連れして……。お願いですから、じっとなさって……!」
「もう平気よ。降りるわ、塚野。一人で降りられるわ」
「! い・け・ま・せ・ん!」
「……そんなに怒ると、体に悪いわ……」
「……。体に悪いのは、どなたのせいですか……」
「ごめんなさい……」
作業服の男たちの一人が軽々と登ってきて、舞を支えてくれた。二人の庭師が梯子を掛けるのを待って、大人しく、彼等の手を借りて地上に降りた。
「……危ないところでしたな」
老庭師の一人が、桜の木を見上げながら言った。樹齢四十数年。大人でも両腕で抱えきれない太さの幹。地上一メートルの低い位置から二股に大きく枝分かれしていて、子供でも登り易い。分かれた枝も太さがあるので、メイドたちの目を盗んで舞はよく登っていた。
「……ごめんなさい。皆さんに、心配をかけて……」
「お嬢さんにしては、ぼんやりなさいましたね? 木登りはお得意なのに」
「お止めするのが、お役目ですわ……!」
「はぁ。これは、すみません」
即座に塚野に叱責され、庭師と舞、二人は目を合わせ苦笑した。
「……迷ったの。あの枝を折ってもいいのかどうか」
高さ四メートルはある桜の木。その中ほど、大きく伸びた枝の一つにだけ花が開いていた。朝の風の中、舞を誘うように揺れていた。道場から戻る回廊の窓からそれを見つけた時、居ても立ってもいられなくなった。
「お父様にお供えしたら、喜んでくれるかもと登ってみたんだけど……。
あのまま咲いていた方が、あの花には。
この家を、眺めている方が、いいのかなって……」
まだ両手で顔を覆っている家政婦頭の塚野を見上げた。小さく震えている手。
「……ごめんなさい。悲しくさせて……」
塚野のポケットからハンカチを取り出して、手に握らせた。
「でもね。あの時、樹の上で、誰かが私の肩を掴んでくれたの。それで、危ないんだって気付いたの。
……あれは、お父様だったのかしら……。それともお母様かな……」
舞は、桜の樹を振り仰いだ。
背後で、涙を押さえる塚野が促す。
「もうお出かけのお支度を。紫月様がお待ちですわ」
良く晴れた青空に、一輪だけ開いた桜の花を抱いて枝々が揺れている。
舞は、小さくそこに呟いた。
「……あなたは、どなた? 私の、何なの……?」
応えは無かった。
これ以上、塚野たちを悲しくさせたくなくて、父と母の名を上げたけど。
彼女には、どちらでもないと確信があった。まだ出会ったことのない、初めて出会った命の気配。
無色透明な『存在』だけを感じた。
まるで、ささやかな挨拶のような。
今朝、夢のような記憶の中で、舞が『鍵だ』と宣告した声の主と、関わりがあるのかと照らし合わせようとしたけど。あまりに僅かな感覚すぎて、比べようがない。
「? いつもの皆さんとは、違うのですね?」
舞は、駆けつけていた二人のスーツの中年男性に気付いた。
「はい。本日より新しく警護に付く方々でございます」
塚野に促され、二人の男は、舞の前に並び一礼した。
「これまで警護を担当させていただいておりましたシステム部は、故雪村社長直属の部署でしたので、昨日のご法要をもって、契約終了となりました。現在、副社長預かりという形で、新しく彼等が契約されるまでは、我々警備部が担当させていただきます。
紫月様にも、そのように副社長からご報告させて頂いております」
「新しく契約、ですか?」
「……。恐らく、本日の親族会議で、グループの後継が決定されれば、その方との継続契約の運びになるかと」
慎重に答える彼らの後を、塚野が引き取った。
「紫月様が、グループをお継ぎになれば、今まで通りでございます」
確信を持った静かな笑みで、塚野は告げた。
「そうね。お兄様が、一番正しいお父様の後継者ですもの」
兄紫月とは、しばらく顔を合わせてはいない。それが舞を寂しい気持ちにさせていた。
彼の立場上、多忙なことはわかっている。ただ、相模原のこの家にほとんど寄り付かないことが、舞は不安だった。
昔から、紫月は留学生活が長く、家には帰らなかった。帰国しても、都内の邸宅の方を利便がいいからと好んでいた時期もあった。都内の雪村邸は、彼の母親。修造の前妻と三人で暮らした家だった。相模原の家よりも、愛着があるのは当然だろう。
二十四歳。一回り年の離れた兄。
母親が違うから舞を避けている、というわけではなく。紫月は紫月なりに、兄として、不在がちな父親への怒りを堂々と口にし、代わりに舞と過ごす時間をいつも作ってくれた。
それなのに。今は、何かに急き立てられているかのように、ゆっくりと過ごす時間も無い。
勿論。父を失った舞を心底気遣ってくれているが。
「今晩、お兄様がこちらに帰っていらしたら」
自室に戻り、着替えの支度をする塚野と二人きりになると、舞は切り出した。
「お夕食を皆さんと一緒には、どうかしら?」
すぐに考え直して。
「お兄様がお忙しいなら、今夜でなくても……。もう少ししたら、あの八重桜も満開になるでしょう? 木の下でオープンランチもいいと思うの。
あの桜は、お父様が子供の頃に植えたのですって。庭師の関谷さんは、その頃のお父様を覚えているって言っていたわ」
……満開の頃にも、紫月は来ないかもしれない。
いつもいつも。舞は、待っているだけ。
父が帰るのを。紫月が訪れるのを。
「皆も、お気遣いを喜びますわ。
そのように、紫月様に、お伝えできるよう手配致します」
舞の寂しさを察してくれている塚野。彼女の言葉に、舞は嬉しくなって、小さくうなずいた。
……速く、お兄様に逢いたい……。
言葉に出来ない弱音を、舞は心の中で何度も繰り返していた。
きっと。今日、兄に会えば、この気持ちは晴れるはずだから。
※ 2 城塞の姫君 完 2 城塞の姫君 (2) に続きます。
ここまで、お読み頂き有難うございました。感謝致します。心の支えになります。亀以下の歩みですが、進みます。皆様に幸いが有りますように。
