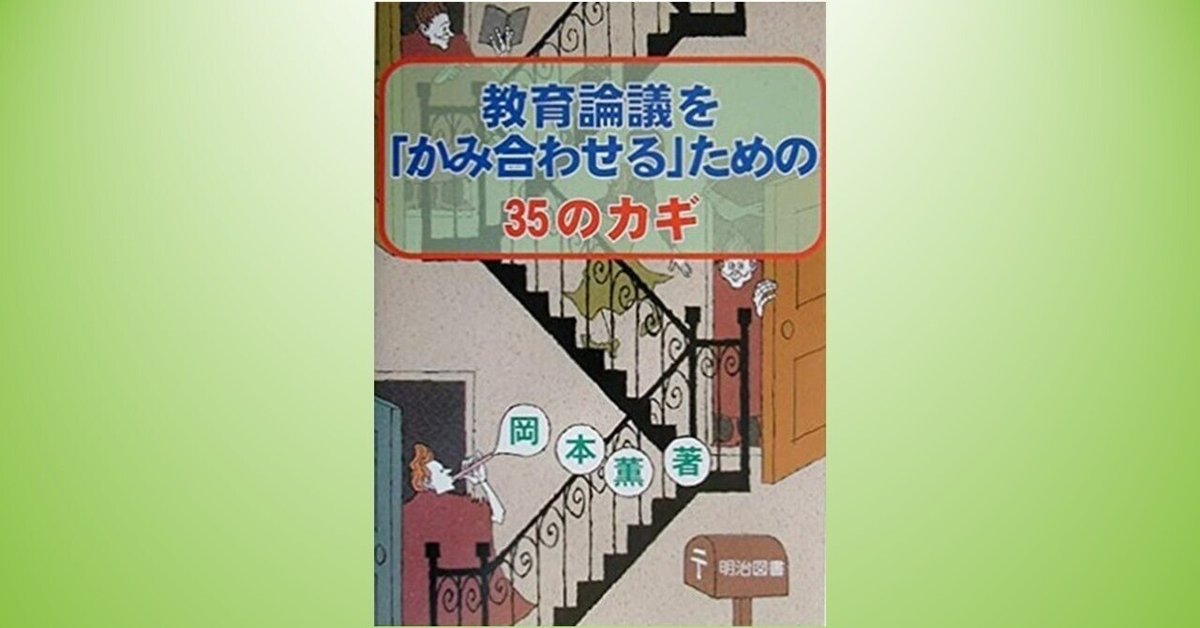
【読書ノート】岡本薫『教育論議を「かみ合わせる」ための35のカギ』(明治図書)
私が本書のことを知ったきっかけは、今から1年以上前の『内外教育』に掲載された、浅田和伸氏(当時は国立教育政策研究所長。現在は長崎県立大学長)による「まだかみ合わないよ、岡本さん」というタイトルの巻頭言を読んだことだった。その文章の冒頭から後半にかけて、次のような記述がある。
旧文部省(現文部科学省)で5年先輩の岡本薫さんは、若い時から頭脳明晰で弁の立つ、恰好いい先輩だった。途中で大学教授に転じたが、正直、中にいてほしかった。
その岡本さんが2003年、課長時代に出された「教育論議を『かみ合わせる』ための35のカギ」(明治図書出版)という本がある。最近だと、元大阪市立大空小学校長の木村泰子さんや前東京都千代田区立麹町中学校長の工藤勇一さんが共に影響を受けた本として挙げられていた。
同書では、日本で教育の議論がかみ合わない理由を分析する。要約すれば①目的・手段や原因・結果に関する論理的な思考ができていない②すべての子供に必要なことと、それ以外のことが区別されていない③皆が同じ気持ちを共有できるはずだという幻想④何でも心や意識のせいにする などだ。今読み返しても古さを感じない。つまり、状況は変わっていないということ。
私自身も、論理的でないな、飛躍しすぎだなと感じた経験は何度もある。例えば、学校で何か問題が起きると、何が原因か分からないうちから「心の教育」が求められる。教育内容の量と授業時間の比率は学校にとって切実な課題だが、「ゆとり」と聞いた瞬間に拒絶反応を示す人がいて、冷静な話にならない。〇〇教育(農村体験、プログラミング教育など)が大事となると、一足飛びに必修化という話が出る。自分の考え通りに他の人にもやらせたいという時にだけ、お上(権力)にそれをやれと求める……。いずれも似た話が岡本さんの本にもある。
本書では、岡本氏が『学校運営研究』(明治図書)に連載した35編の文章が、7編ずつ5つの章に分けられている。その各章のタイトルと要約文を読むだけでも、著者の主張がある程度は伝わるだろう。
Ⅰ なぜ議論の「すれ違い」が起こるのか?
「目的と手段」「原因と結果」などについての「論理的思考力」の不足が、議論の「すれ違い」を生んでいる
Ⅱ なぜ「一律」の議論しかできないのか?
「すべての子どもたちに必要なこと」と「それ以外のこと」を区別していないことが、「一律」の議論を生んでいる
Ⅲ なぜ「独善」に走る人が多いのか?
「自分」を基準にして「みんなが『同じ心』を持てるはずだ」と考えてしまう「同質性の信仰」が「独善」を生んでいる
Ⅳ なぜ政策論議が「空回り」するのか?
「システム」を変えずに何でも「心」や「意識」だと言う「悪しき精神主義」が、議論の「空回り」を生んでいる
Ⅴ なぜ「明確な方向性」を実現できないのか?
方向性を「選択」する勇気と「自ら行動する覚悟」の不足が、「方向性の欠如」を生んでいる
たとえば今、各自治体の教員採用試験では志願倍率の低下が続き、度重なる制度改正が行われているが、その「迷走」の理由は「Ⅰ なぜ議論の『すれ違い』が起こるのか?」の要約文によって説明ができてしまうだろう。
岡本氏による切れ味の鋭い文章は、教育に対する「傍観者」として読む分には痛快である。だが、かつて地方教育行政に関わっていた「当事者」としての自分自身にとっては、耳の痛い指摘ばかりである。
・・・岡本氏のこうした「ものの見方・考え方」は、いったいどのように形成されたのだろうか。本書を読むと、2つの経験が大きな影響を与えたのではないかと思われる。
1つ目は、氏の官僚時代の経験である。岡本氏はそのキャリアの中で、フランスにあるOECD(経済協力開発機構)での勤務を2回にわたって経験している。その中で岡本氏は、各加盟国の代表者たちと議論をするなかで、日本の学校の「当たり前」が諸外国ではそうではないという場面に何度も遭遇する。たとえば、こんな場面だ。
しかし、中でもみんなが最も驚いたのは、学校で「心の教育」なるものを行う……という発想でした。西欧・北米の常識では、「心」などというものは、「宗教」の世界に属するか「家庭教育」の対象となるものであって、「学校での心の教育」ということ自体が、驚くべき発想であったようです。彼らの多くにとっては、小中学校での義務教育とは、「読み書き算数」などの「知識・技能」を習得するためのものだったからです。
こうした経験が、日本の教育を客観的かつ批判的に見つめることにつながったことは間違いないだろう。
2つ目は、岡本氏自身の家族史に起因するのではないかと思われる。岡本氏の母方の祖父は、蚕糸試験場でカイコの人工孵化の研究をしていた人物だったが、軍需部門への転属を拒否したためか40歳を過ぎてから突然に徴兵され、有名な「インパール作戦」の最中に戦死しているのだ。
その後、祖父が命を落とした「インパール作戦とは何だったのか?」について調べた岡本氏は、愕然とすることになる。
ところが驚いたことに、こうした研究成果や出版物を読むと、インパール作戦の立案に関わって生き残った人々の殆どが、「実は私は、最初からこの作戦はマズイと思っていました」などと言っているのです。いったい誰が「決定」を下し、「責任」を負うべき人物は誰なのでしょうか。身内を失っている身としては、「それは軍部全体だ」とか「戦争というもの自体が悪なのだ」といったことでは納得できないものを感じました。
祖父を失った一家のその後の生活は辛酸なものだったという。それを考えると、岡本氏の刃は教育問題だけではなく、政治を含めた「日本というシステム」全体に向けられていると言っても間違いではないだろう。
・・・ちなみに、冒頭で紹介をした浅田氏の文章は、次のように結ばれている。
岡本さんは、日本人があらゆる分野で「議論」や「マネジメント」が苦手だといった本質的な問題と関係するとみる。そうなのだろうが、ではどうすれば「かみ合う」のか。答えは示されていない。それは私も含め、今の人たちが少しずつでもこの状況を変えていけるように考え、物を言い、行動していかねばならないのだろう。
そうなのだ。「かみ合わない」と不満を述べる暇があるのならば、まずは身近なところからでもこの状況を変えていくために行動をする必要があるのだ。今を生きる当事者として。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
