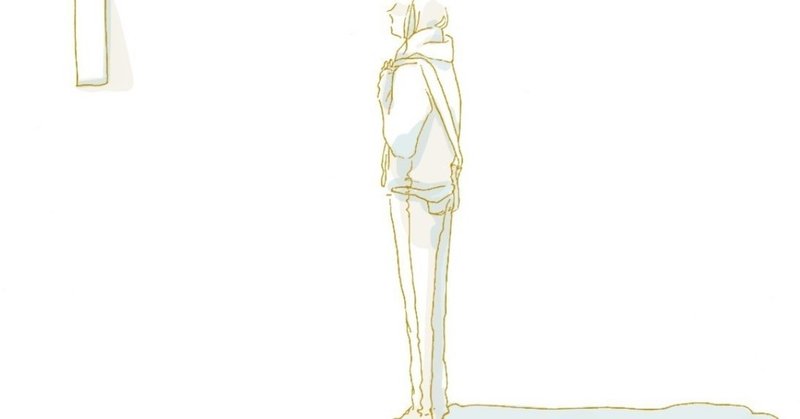
家出をする時は大体秋か冬、それか夏
目が覚めると、雨がアスファルトへ叩きつけられて反響する音が鳴っていた。窓の外で水が歌っている。
思考に影が差し、薄くカーテンを開いて目を凝らすと遠く近く雫が跳ねていた。
もはや感嘆に近い息をつきながら、少しだけ笑った。
目は冴えていた。日常では考えられないほど。
普段はまどろみながら繰り返す支度の質量を、「その日」は容易く軽くするのだった。
いつもどこかに、なにかを探している。
平日の昼下がり、休み続けた学校からの連絡を無視しながらするりと抜け出るように静かに足を踏み出した。11歳の秋だった。
自分の足で歩くことが先決だった。とにもかくにも出ることが第一優先で、行き先は決まっていなかった。
外は明るい。自分だけが淡く暗闇の膜をかけられていて、光に怯えている。光がどういうものなのかよくわからないけれど。
知らない道を歩きたかった。そうすれば知らないものに触れられると思った。知らない所に行きたかった。
普段は助手席に乗って流し見るだけの道を早々に通り過ぎて、何より行ったことのない道を選んだ。少し離れるだけで知らないものはそこここにあった。歩いて1時間もすれば自分以外のすべては知らないものだった。壁を眺めたり、家を眺めたり、木を眺めたりした。人通りがなくなり先が怖くなって引き返したりもした。
夕方になり日が落ち始めた。
少しずつ傾く影と下がる気温と、ほんの人匙の寂しさが顔を覗かせて、なんとなく知っている方向に繋がりそうな道を選ぶようになってきていた。
そして単純に疲れてもいた。サイレントで鳴り続ける携帯電話にも。
知っている場所に、戻ってきた。
電話に出ることもできない、家に帰ることもできない濡らした砂糖のようなこどもは辿り着いた建物の名称がわかる写真を撮ってメールで送ったのだった。
家から車で20分もすれば着くその場所で初めての逃亡は幕を閉じた。
外で警察対応をしている迎えの車内で泣くことに必死だったので、あの時周りの大人がどういう対応をこどもにしたのかあまり定かではない。
日曜の正午、友だちと出かけるからと嘘を吐いて手を振った。13歳の冬だった。
狭い内側から飛び出して、そこに見たい景色があった。歌をうたうひとに会いに行きたかった。行き先は決まっていた。
自分で戻った淡い暗闇の膜の内側に、恐らく偶発的に、ただタイミング良く、光が差し込んできた。怯えていたそのものは、未知であったがゆえにひどく怖がっていたのであって、本来焦がれてやまないものだったらしい。
事前に予約していた高速バスに乗り、片道2時間かけてひとりで知らない場所に降り立った。奮える内心と、無謀な無敵感と、背後で微かに香る罪悪感と、言い訳みたいな苛立ちと、欺いてやったという満足感で、大人には一方的に逃亡の旨だけを送り付けた。
どこにいてもひとりのような気がしていたので、ならばよっぽど際立つ人混みに紛れた方が幾分かましなのではないかと思っていた。最初から誰もわかってくれないことをわかるような場所で。わかってくれないことを責める相手もいない場所で。
そこには光が差していた。
たくさんの知らない大人に囲まれて浴びた光が、頭に響く大きな音が、派手に扉を叩いてきた。眩しかった。
夢が目の前にあるとき、自分の本体なんてものはぐちゃぐちゃになっていて、形を成そうとすればするほど混ざり合って、知らないなにかとして息だけをしている。
知らない自分に、触れている。
辿り着いた充足で満たされ、迫り来る罪悪に耐えかねて、結局また砂糖のこどもは現在地の住所を返したのだった。
夢の外には大人が待っていて、家から車で3時間強、約70kmのその場所で2度目の逃亡が幕を閉じた。
中で得た光の余韻に縋り付いていたら温度差に体を冷やされたので、あの時迎えの車内で一言も言葉を交わさなかったことを、はっきりと覚えている。
それ以来何も言わずに外へ出ることはなくなった。
歳を重ねるにつれて外へ出ること自体は増えたが、光を浴びることによって自分の影がはっきりと浮き上がってくるようになったから。影が目に見えると、自分のかたちがよくわかる気がする。
大人にやさしくされていること、やさしさの中に包まれた同情に傷付くこと、傷付いたからと過剰防衛してしまうこと。
そういうものに疲れると、孤独を感じながら得体もしれないなにかを求めて外へ出ること。そういう自分に酔うこと。
支度を済ませてほんとうのことを伝えて手を振って、何にも怯えず足を踏み出して家を出ると、先刻まであれだけ降り注いでいたはずの雨が上がっていた。アスファルトや葉は反射を携えて雫を滑らせ、痛いほどの陽射しが蝉と一緒に騒いでいる。これにはもう感嘆するしかないので、また、少しだけ笑った。
夏の朝がきた。
あの夜のことを、きっとわたしは忘れていく。
かつて絶対に忘れないと思っていたものを、明日のわたしは自らの意思で手放していく。
選び取っていく。
忘れたくない夜がふえていくほど、忘れていく。
だから残す。
夜に照らしてくれた光を、ここに、残す。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
