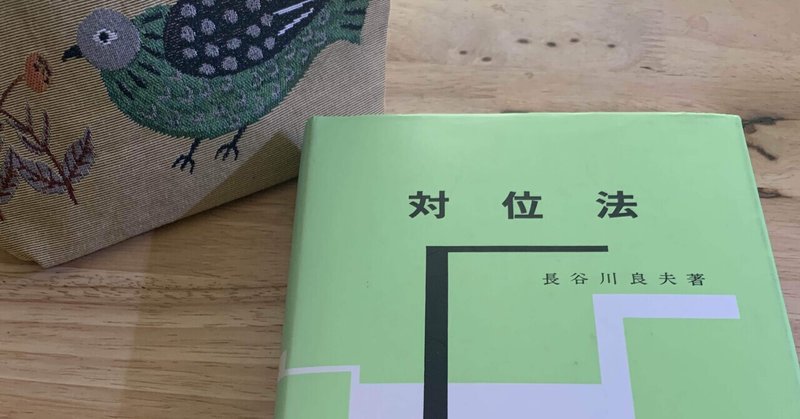
対位法を習得したい!② 序説に突入
今回は
長谷川良夫さんの「対位法」の序説を理解していきたいと思います。
わからないことが出てきたら他の本やネットで調べながら進めているので、亀の歩みです🐢
ちなみに、他の勉強や練習もあるので
ポモロードテクニックを使って、時間の使いすぎ防止をしています。
序説で書かれていること
序説はたった5ページですが、
・対位法とは何かか
・ポリフォニーとは何か
・リズムの二元性
について説明されていました。
対位法とは何か
ポリフォニー特有の作曲技法と書いてありましたが、バッハの時代以前から受け継がれてきた伝統的な手法で、メロディに対して別のメロディ(対旋律やカウンターメロディ)を付けていく技です。
ちなみに対位法は英語で
counterpoint(カウンターポイント)
と言います。
スティーブライヒの
「Electric Counterpoint」
の意味が少しわかったので喜んでおります!
「天空の城ラピュタ」や「風の谷のナウシカ」の雰囲気を感じるのは僕だけでしょうか?
この曲のギターはパットメセニー大先生が弾いています。
ポリフォニーとは何か
ホモフォニーの対語で
主旋律と伴奏の役割が分かれているホモフォニーに対して、各パートのメロディーが対等の立場で、和音を作りながらも主旋律として主張しているスタイル。
モノフォニーは単旋律のことです。
・モノ(mono)
単一の
・ポリ(poly)
たくさんの
からきているんですね
フォニー(phony)
はギリシャ語が語源で「響く」だそうです。
3つの時代のポリフォニー
①
1450年〜1600年(ルネサンス期)の声楽的ポリフォニー(声楽的的対位法・厳格対位法)
②
1680年〜1750年(バロック期)の器楽的ポリフォニー
(器楽的対位法・自由対位法)
自由対位法の最終形態がフーガなんだよ
と何かで書いてありました
③
現代のポリフォニー
12半音階に基づいて作られていて、①と②両方の影響が強いけど、①との関係が深いらしいです。
ここらへんは、勉強しながら特徴を掴んでいくしかないですね。
リズムの二元性とは何か
この本で言うリズムは、メロディー全体の流れの緩急の具合のことで、
段落性(韻文的)リズム
継続性(散文的)リズム
の2種類あるから理解してね
と書いてありました。
段落性リズムは
①拍子が明確に感じられる
②フレーズの関係がわかりやすい
③key(調性)がわかる
継続性リズムは対照的に
①拍子がわかりにくい
②フレーズ同士の関係は薄い
③key(調整)もわかりにくい
と説明されていました。
譜面が載っていましたが、段落性リズムは理解しやすかったですが、継続性リズムの方は
、グレゴリー唱歌のような単音聖歌を参考にすれば良いのね?ぐらいしかわかりませんでした。
本の継続性リズムの説明で載っていた譜面の曲はこれです
ちなみに
第一部はこの継続性リズムによる声楽的ポリフォニーの技法を研究するそう
理解できるのかわからないけど
最後まで、やってみて考えよう!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
