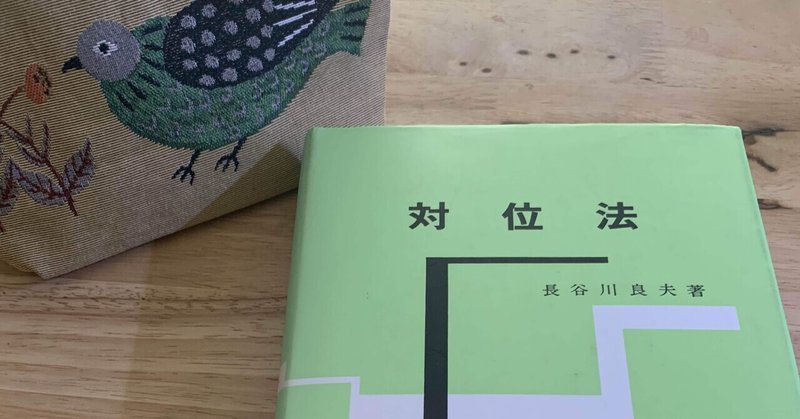
対位法を習得したい①
「美しい西洋音楽の旋律」の1つの正解を知りたい
そう思い立って、今まで少しずつ別の本やネットで勉強していましたが
どうしても腑に落ちないというか、なんでそうなるの?と思うことが多々あって
このまま、うんうん唸って考えているより
基礎からしっかり勉強した方が解決するんじゃないか?
ということで、色々な方が「基礎からキッチリ理解したいならこれ!」とオススメしていた
この本に挑戦することにしました!
今回購入した本
「対位法」
長谷川良夫著
めっちゃ、どストレートなタイトルです。
1955年が第一刷発行と、とても古くからある本なんですね。(僕が買ったのは、2008年第33刷発行です)
文体は個人的には読みにくい感じはなくて、使われている用語も、音楽理論の基礎が入っていればなんとか理解できそうです。
この本は3部構成&作成曲集になっていて
第1部が15章構成で
声楽的スタイルの線的技法(厳格対位法)
第2部が6章構成で
器楽的スタイルの線的技法(自由対位法)
第3部が3章構成で
カノン及びフーガ
目次だけでは、さっぱりわからなかったけど、「はじがき」と「例言」を自分なりにまとめると少しわかってきました。
どんなことを学ぶの?
第一部
は「厳格対位法」を学ぶ。
運声法の基礎からはじまり
2対位法〜4声以上の対位法まで学びます。
第一部は和声学とはそんなに関係ないから、知らなくても理解できるから大丈夫だぞ!
むしろ和声学とは対照的だからな!
ただし教会音楽を聴いたことないと
「え?なにれ?」ってなることあるからな気をつけんだぞ!
的なことが書いてありました。
第二部
はバッハの手法を中心とした和声的な「自由対位法」の単声の運声法に始まり2声対位法〜4声まで学びます。
歴史的な順番とは逆になるし、第一部からやんのが本筋だけども第2部からやってくれても良いぞ
先に二部をやってから一部にした方ががわかりやすい場合もあるからな
ただし、和声学がある程度わかってないと
しんどいから勉強しとくんだぞ!的なことが書いてありました。
同じ2声対位法でも「厳格」と「自由」では
考え方が違うってことですね
これは楽しみです!
第三部
はあまり説明が書いていなくて、インヴェイション、カノン、フーガなどの構成法を学ぶようです。
そもそもカノンやフーガをなんとなくしか理解できていないので、未知の領域です。
まとめ
ある程度の進めてみないと、この本の評価はできませんが、目次だけでもワクワクするので
欲しい知識は得られそうです。
練習問題も節目ごとに載っているので、学んだことが整理しやすくて良さそうですね!
序説で長谷川先生が理解への道は
理論書を読んで、楽譜を調べて、聴く!
そして手を働かせていくことで体得できるから!
とおっしゃっていたので
頑張りたいと思います!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
