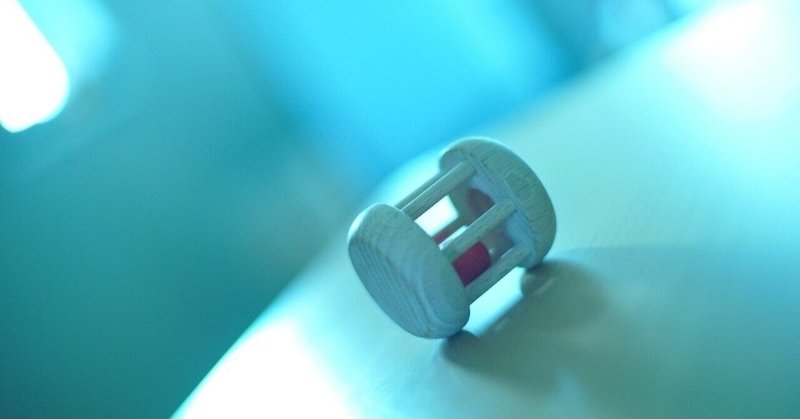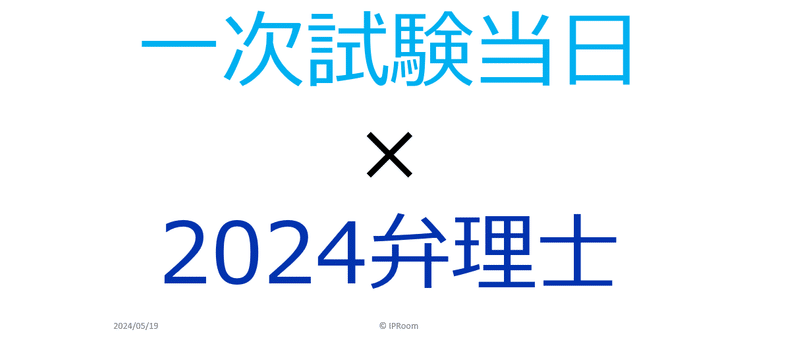記事一覧

「メディアに著作権を譲渡する」割合が27.4%。個人的には想定よりも少ない。しかし著作権の譲渡に見合う取り分をメディアは漫画家側に提供すべき。納得感をメディアと漫画家が共有するのが理想。そのための法知識を漫画家も備えておきたい。
https://kai-you.net/article/89735

産学連携と特許の趣旨と国民の利益。国としてはいずれも尊重すべき事項。どれかを優先すればアンバランスな状態を肯定してしまうことになるため、今後の国策に影響しかねない。お金が大きく動き、人の生命に関わるため、慎重に判断された事例と推測。
https://www.sankei.com/article/20240530-TDQZW5YDN5O7NALQIIAEMTUXNQ/

地域ブランドを保護する特別なルール。基本的に「地名+商品の一般名称」というありふれた名称は登録不可。それだと地域の名産品のブランド名と同じ又は似た名称の粗悪品が販売されても本家は何も言えずに困る。そんなときに地域団体商標制度を活用。
https://mainichi.jp/articles/20240527/k00/00m/100/257000c

外国で特許を取る費用は1か国あたり100~200万円。助成対象が最大300万円、助成額がその半分で最大150万円、1か国分の費用を賄えると思うと大きい。募集締切は6/14(金)で提出書類必着。書類作成を効率よく行えるか否かがポイント。
https://www.kipc.or.jp/topics/information/gaikokusyutugan-josei2024/

例えばアクションシーン、アイテム選択、抽選結果・表示といったゲーム中の流れを言語化することで特許として保護できる。ゲーム特許は約1万5000件。IOTやAIのような技術の進化に伴ってゲームの内容も変化するため特許が熱い分野と言えそう。
https://app.famitsu.com/20240525_2231855/

今までありそうでなかったコラボ。VCが投資先の知財の良し悪しを判断するのは難しいため専門家が支援。知財の価値評価は仮説に基づかざるを得ない。知財に対する経営者の考え方や会社の取り組み方はヒアリングに基づいてしっかり見極めるべき。
https://ipbase.go.jp/news/2024/05/news-240524.php

副業・兼業には本業(勤め先)の経験や能力を活かせるといいはずだが、勤め先の守秘義務、勤め先と副業・兼業先との関係、勤め先を開示するか否かといった点は重要なため、そう簡単ではない。知財活動の支援者も人材不足と言われるがこれらの点は課題。
https://saleszine.jp/news/detail/5952

シニア世代。ジョブ型が主流になってきた。マネージャー歴の長い人材を再雇用する場合、求めるスキル不足が原因で、希望の給与に達しないなんてこともありえる。知財活動実務にセンスや体力は必要だが年齢制限はない。リスキリングしてみるのはどうか。
https://x.gd/hUyD5
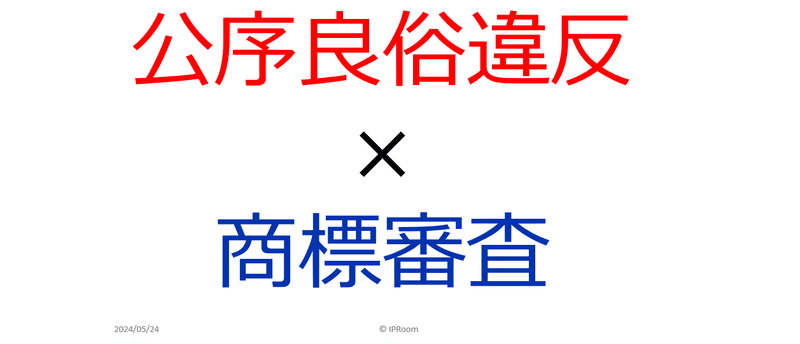
タレント事務所がタレントの芸名を許可なく商標登録できない理由は、主にその芸名が著名だから(商標法4条1項8号違反)だが、そのタレントの著名度によっては「社会的相当性を欠く」として公序良俗に反するから(商標法4条1項7号違反)である。
https://bunshun.jp/articles/-/70954
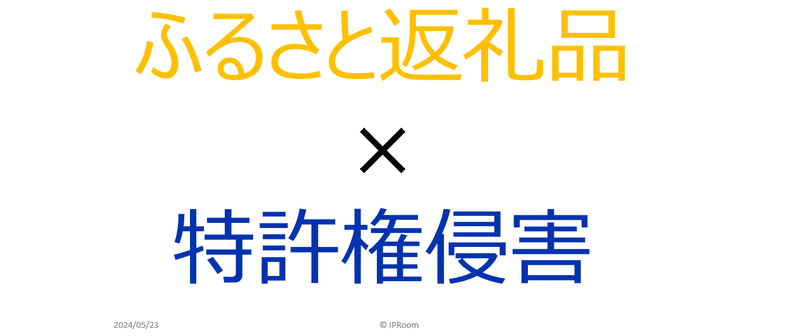
「焚き火台」でキーワード検索したところ登録済みの特許・実用新案併せて23件ヒット。一人キャンプの流行に関係しそう。ふるさと納税の返礼品として令和2年5月~令和5年8月まで掲載。すでに当事者同士で解決済みとのこと。珍しいニュース。
https://www.city.moriguchi.osaka.jp/kakukanoannai/kikakuzaiseibu/miryokusouzouhasshin/zei/17415.html
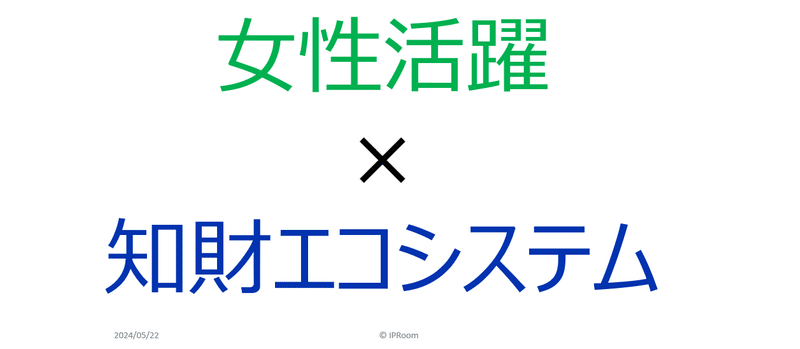
男女の発明者による特許の方が経済的価値が高いという報告や、職場の男女の「黄金比率」は男7:女3という調査結果もある。知財の現場でも女性の活躍が経済的な効果を増す要因と考えられている。知財活動は男女問わず活躍のチャンスがある。
https://www.meti.go.jp/press/2024/05/20240517001/20240517001.html
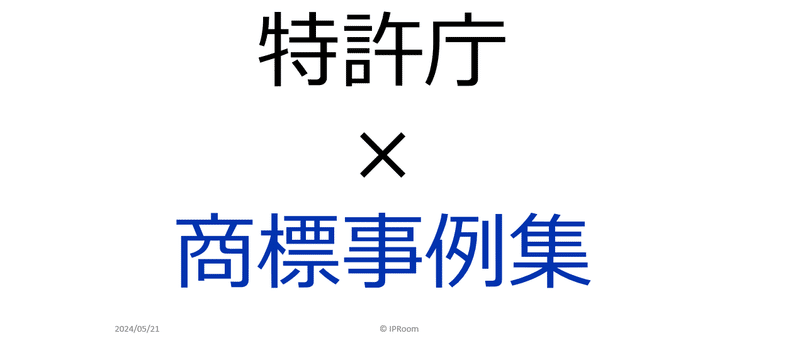
「ビジネスやるなら、商標だ!」強気なキャッチ―コピー。特許庁の覚悟を感じる。ネーミングやロゴでビジネスのオリジナル性を伝えるのはコスパが高い。もし認知された社名や商品名をパクられたら?取り返すのは難しく、取り返せないこともある。
https://www.jpo.go.jp/support/example/trademark_guide2024.html
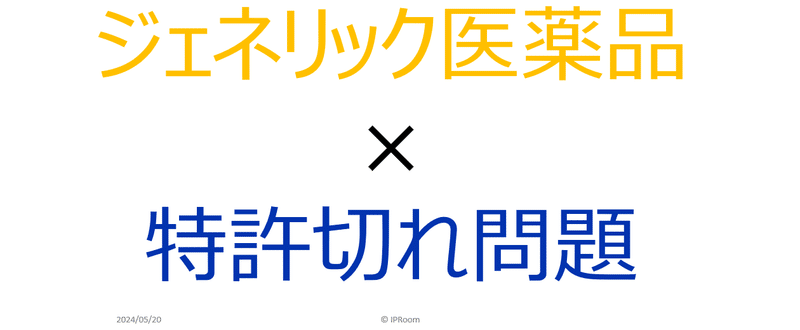
ジェネリック医薬品のように、特定企業の特許の有効期限が切れれば、他社から安価に販売されるため、国民にとってはその分の保険料が安くすむというメリットがある。しかし特定企業にとって競争力を維持できなくなるという悩ましいデメリットがある。
https://www.mixonline.jp/tabid55.html?artid=76533

日本でもAIを発明者と認められないという判決が地裁で下された。現状、主要国ではいずれも同様の判断。「AI×発明者」のタイトルは2回目。
4月27日つぶやき
https://note.com/yu_uchikoshi/n/n9c928afb396d
今回のニュース記事
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE170HY0X10C24A5000000/
副業・兼業には本業(勤め先)の経験や能力を活かせるといいはずだが、勤め先の守秘義務、勤め先と副業・兼業先との関係、勤め先を開示するか否かといった点は重要なため、そう簡単ではない。知財活動の支援者も人材不足と言われるがこれらの点は課題。
https://saleszine.jp/news/detail/5952

日本でもAIを発明者と認められないという判決が地裁で下された。現状、主要国ではいずれも同様の判断。「AI×発明者」のタイトルは2回目。
4月27日つぶやき
https://note.com/yu_uchikoshi/n/n9c928afb396d
今回のニュース記事
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE170HY0X10C24A5000000/