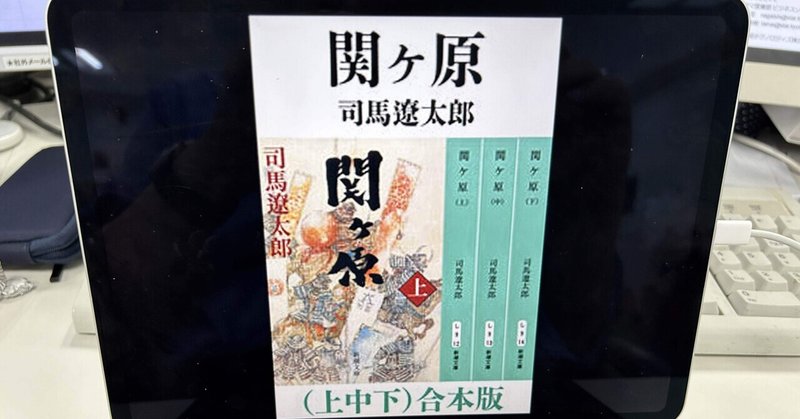
なるようになった物語:読書録「関ヶ原」
・関ヶ原<上中下 合本版>
著者:司馬遼太郎
出版:新潮文庫(Kindle版)

真田広之の「SHOGUN将軍」を見て、元になった「関ヶ原」の流れを改めて確認したくなって久しぶりに読んでみました。
「SHOGUN」シーズン2があるかもって記事が、読んでる途中で流れて来たりもしましたw。
多分最近の研究なんかを反映すると、司馬遼太郎の「関ヶ原」は古くなってる分が少なからずあると思うんですけど、僕はこの小説、好きなんですよね
読み終えて改めて
「なるようになった話だなぁ」
と。
信長→秀吉→家康
力ある者が天下を獲った物語。
「関ヶ原」で結構西軍が頑張ったり、この後の「大阪の陣」で、家康の評判が落ちたりして、なんだか「豊臣家を滅ぼす古狸・家康」って感じになってますけど、当時生きてきた人たちから見れば、秀吉が死んだ後の天下が家康のものになるっていうのは、規定路線に見えてたんじゃないですかね。
むしろその後200年以上続く江戸幕府をきっちりと築き上げたところの方がすごい話です。
小説では豊臣政権を継続させるところに石田三成の「義」を置いてますけれども、豊臣政権自身が織田政権の簒奪によって成立したって言う見方もあるでしょう。
秀吉自身の晩年の醜悪さや強欲さっていうのは、とても評価できるものではありませんしね。
原田真人監督の映画「関ヶ原」では、そういう点にも目配りがされていて、秀吉の晩年がかなりネガティブに書かれていました。
政権を安定させることが平和につながると言う考えに石田三成の「義」を設定したということでしょうけど、ちょっと無理がありますかね。
司馬さん自身が島左近に言わせています。
<左近は沈黙している。かれは三成を愛し、この男のために死のうと思っているが、しかし三成の救いがたい観念主義だけはどうにも好きになれなかった。
(諸事、頭だけで考える)
と、左近は三成の外貌のきわだった特徴である才槌頭を、ため息をつくような思いで見た。
正義、義、
などという儒者くさい聞きなれぬ漢語をつかいその漢語にふりまわされて、そこから物事を考えたがる。出てくる思案は、すべて宙にういている。
(人は利害で動いているのだ。正義で動いているわけではない)
そこを見ねば。
と、左近は思う。>
僕が石田三成を昔から好きになれないのは、多分こういうところ。
観念的な「正義」の危うさって言うのは、<今>の方が強く認識されているかもしれません。
ドラマの「SHOGUN」の元ネタは細川ガラシャのところ。
彼女の死が三成の「人質策」を破綻させた話のあたりでしょう。
<三成は、協議した。
要するに三成が主張する意見は、
「強引な人質政策をとれば、第二第三の細川夫人が出てくる。そうすれば東征諸将にかえって決意や戦意を燃え立たせるばかりで効がない。すぐ取りやめようということであった。>
<諸大名の屋敷は、城方の警戒兵が去ったために平静にもどっていた。
(人質の心配は去った。去ったとなれば、東征諸将は心置きなく家康に加担するだろう。あの遺骨のぬしの)
と、左近は細川忠興夫人伽羅奢のことを想った。
(伽羅奢殿の死は、家康にとって百万の味方を得たよりも大きいかもしれない)
左近は、城内にもどった。>
「関ヶ原」のポイントが<人数集め>にあったのが確かです。
そこらへん、「SHOGUN」はガラシャ事件に集約させた訳ですが(紅天)、やっぱり史実の方が面白い。
戦国武将たちの右往左往ぶりや思惑やら義侠心やら、国の大小に関わらず露呈するのが楽しいし、その滑稽さの裏には生き残りをかけた必死さがあることが深い読みを誘ってくれます。
さて、シーズン2があったらどうするか?
この「関ヶ原」をやるのか。
虚々実々は色々あるから、面白いことは面白いけど、
「じゃあ<紅天>は何やったんや」
ってなりますか。
それは「終わったこと」として、「大阪の陣」?
でもそれだとあまりにも虎永が<悪巧み>過ぎる?w。
真田昌幸・信繁親子あたりも面白いけど、大河でやってるからなぁ。
個人的には「黒田如水」なんか面白いんじゃないかと思うんですけどね。(本書のラストの余韻、大好きです)
「関ヶ原」が終わったと思ったら、九州から攻め上がってくる別の大軍が…
とか。
史実から離れ過ぎるけどw。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
