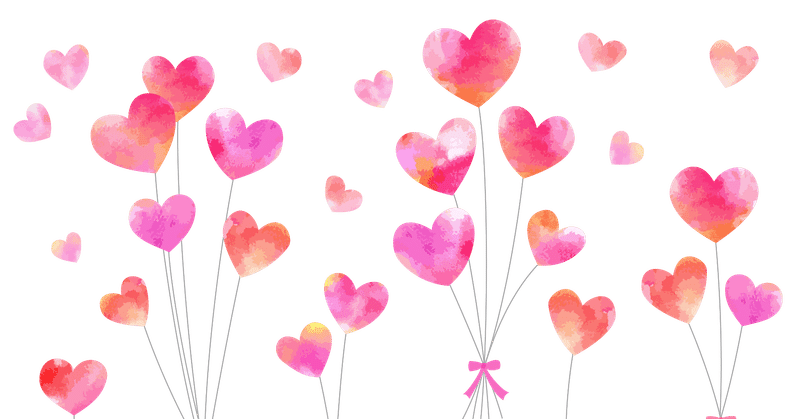
ヴィクトル・ニキフォロフの幸せな日々
こういうところは分かりやすい子なんだけど――
愛犬を足の間に挟んでちんまりとソファに座っている教え子の姿にヴィクトルはそっと笑いをかみ殺した。心ここにあらずといった様子ながら、左手でマッカチンをあやし、右手でスマートフォンを操作している。随分と器用なことだ。小一時間ほどそうやって時間をつぶしていたようだが、どうやらゲームにも飽きてきたらしい。勇利の視線は窓とスマホの画面を行ったり来たり。唇も尖り気味だし、おとなしくしているのもそろそろ限界なのだろう。
「ねえ勇利、退屈? リラックスできない? 仕方ないか。まだ着いたばっかりだし、いくらくつろいでって言ったところでなかなかそうもいかないよね。でも、これからはここが勇利の家になるんだから、できれば早く馴染んで欲しいな。ね、マッカチンもそう思うだろう?」
「わん!」
絶妙なタイミングの合いの手に、愛犬の頭をいい子、とひと撫でしたヴィクトルは、柔らかな笑顔と共に紅茶のカップを教え子に手渡した。
「はいどうぞ。美味しいから飲んでみて。少しは落ち着くと思うよ」
「そういうわけじゃなんだけど……ごめんなさい、ヴィクトル。なんか気を遣わせちゃったみたいだ……」
受け取ったカップを慎重にテーブルの上に置いた勇利は、どこか頼りなげに首を左右に振った。
「そりゃ想像してた以上に綺麗で広くて、ちょっとびっくりしてるっていうのはあるんだけど……」
と言いながら膝の間のマッカチンに視線を落とした勇利は、次の瞬間勢いよく顔を上げた。その改まった表情にヴィクトルの背筋も伸びる。
「感謝してます。本当にありがとう、ヴィクトル。僕をロシアに呼んでくれた。コーチだって続けてくれる。初めての国だし、まだ右も左も分からないし、不安ばかりだけど、でも頑張るよ、僕。『世界中のみんなが反対しても勇利のコーチは辞めないよ』って言ってくれたヴィクトルの顔に泥を塗らないように、足を引っ張らないように一生懸命滑るから、だから」
勇利はすっくと立ち上がり、そのままほぼ直角に身体を折り畳んだ。
「どうぞよろしくお願いします!」
ああ、この真っ直ぐさこそが勝生勇利だ、とヴィクトルは思う。そしてこういうところが自分を惹きつけてやまないのだと。教え子の24という年齢にそぐわない清廉さ、スケートに捧げるピュアな愛情と情熱、それは広いようで実は狭い男子フィギュアの世界で、既にある程度の地位と名誉を手に入れてしまった自分が、とうの昔に失ってしまった感情なのかもしれない。
「こちらこそ、だよ、勇利。分からないことや気になること、何でもいい、どんな些細なことでも必ず相談して欲しい。全力でフォローする。なんて言ったって俺は勇利のコーチで、身元引受人で、一番の味方で、そしてスケーター勝生勇利のファンだからね」
ヴィクトルの言葉にはじかれたように顔を上げた勇利の頬は桜色に染まっていた。はにかんだ笑顔が愛らしくて、この子の為なら何でもしてやりたいと改めて思う。
「はい!」
「金メダル、たくさん取ろうね。最大のライバルはおそらくロシアのヴィクトル・ニキフォロフになる。言っておくけど彼は強いよ。本当に強い。でも勝てない相手じゃないはずだ。打倒ヴィクトル! を合言葉に力を合わせて頑張っていこうね」
「……は、はい……?」
返ってきたのは戸惑い気味の返事と態度。そんな正直なところもまた、好ましいと思った。
「で、さっきから勇利は何をしたいの? ずっとそわそわしてるみたいだけど」
教え子が身体を動かしたがっていることくらい百も承知の上だ。今朝だってかなり長い時間ランニングに付き合ったつもりだけど、それでもまだ走り足りなさそうだったし、常日頃が練習の虫の勇利にしてみれば、いくらオフシーズンとはいえ、ずっと家に閉じこもっているなど時間の無駄以外の何物でもないのだろう。
「えっと、あの……あのねヴィクトル、あれ? 僕っていったい何日滑ってない? これでいいのかな? 本当に大丈夫なのかな? って思っちゃって。いや、分かってる。ちゃんと分かってるんだよ。挨拶回りも済んでないし、事務上の手続きだってまだ終わってない。だから今はまだリンクに行けないし、仮に行ったとしても受け入れてもらえない。そう頭では理解してるんだけど、でも」
「でも練習したいし、練習していないと体がむずむずして落ち着かないってところなのかな? 俺の可愛い子豚ちゃんは」
「……う、……ごめん、ヴィクトル。もう正直に言うね。リンクに行きたい、滑りたい、練習したい。でも……ああ、もう! それはやっぱり無理だから……そうだ! もう一回だけこのあたりを一周してきてもいい? 朝、一緒に走ってもらったから道は覚えてるし、迷子にはならないと思う。ねえ、ヴィクトル。いいよね? ね?」
「う~ん、勇利の気持ちは分からなくもないけど、まだ一人での外出は許可できないなあ。だから却下」
「え~っ……」
日本の常識はロシアの非常識、だとか、会話だってロシア語オンリー、英語はほとんど通用しない、だとか、勇利には覚えてもらわなければならないことが山のようにある。自分の命を守る術を身に付けることは最低限必要なことだし、ヴィクトルにはコーチとして、また日本の代表選手を預かったロシア側の責任者として勇利を守る義務もある。でも勇利だって海外留学の経験もあれば、それこそ身一つで世界中を転戦してきた日本のエースだ。それなりに国際経験を積んできているはずで、そういう意味では過保護になり過ぎないように、必要以上に子供扱いしないように、とヴィクトルは自身を戒めていた。とは言え、ロシア到着二日目の勇利に、まだそんな小難しい話をする必要はないだろう。それよりも何よりも、まずはサンクトペテルブルグの水と空気に慣れてもらって、自分の故郷でもあるこの美しい街を心から好きになって欲しい。
「そんな勇利に、俺からひとつ提案」
「えっ、なになに。どんな提案?」
しょぼんとうなだれていた様子から一変、マッカチンの首に両手を回して、キラキラした瞳でヴィクトルを見上げる勇利のキュートさといったら!「勇利、勇利の荷物ってそこにあるリュックとスーツケースだけ? 後から何か届くの?」
「ううん、これで全部。でも必要な物はちゃんと持ってきたから大丈夫」
「ふ~ん。大丈夫、ねえ……本当に? それだけで?」
「え? 大丈夫だと思う、けど……」
勇利の唇が不満げに尖った。
「だってヴィクトル言ったじゃん! 身の回りの物だけ持っておいでって。生活に必要な物はひと通り揃ってるから大丈夫だよって、確かにそう言った!」
「言った。言ったよ、確かにそう言った……でも勇利、勇利はロシアの冬をなめてるね。今日はわりと風も穏やかだし、おまけにこの部屋はがんがんに暖房を効かせてるからまあいいんだけど、でも天候が悪化したら今の勇利の恰好で外に出る。扉を開けて歩き出す。数分後――はい凍死決定、ご愁傷様、ってやつだ」
「え? 嘘? でもマフラーも手袋もあるよ? ジャージだって分厚いやつを持ってきたし、いつものダッフルだってある。そうそう、念のためダウンの上着も入れてきた。あれ? あのダウンって確か、ヴィクトルが買ってくれたやつじゃなかったっけ?」
「そうだけど、でも残念でした。あれはあくまでも日本の冬仕様のダウンだから、ロシアじゃ何の足しにもならないよ。まあこれから少しずつ暖かくなってくるけど、それでもあのダウンとダッフルだけじゃ即凍死案件なのは変わらない。どう考えても勇利のワードローブは足りなさすぎ」
「……そこまで? あ、わかった。ヴィクトル、僕のことを脅かそうとしてるでしょ? 凍死とか……怖いって」
ちょっと大袈裟だったかな? と思いながらも、ヴィクトルは真面目な表情を作って勇利に向かって右手を差し出した。
「行こう。勇利が凍死しないように最低限の服を揃えて、そうそう、食料品も買い足さなきゃ。俺は勇利のコーチだから、コーチには教え子を守る義務がある。勇利がロシアにいる間は衣食住についての文句は一切受け付けないからそのつもりで」
「はい、……って、あれ? なんか違うような……」
ぶつぶつと呟きながらも、勇利は差し出された手をちゃんと握り返してくれた。
「とりあえず、今ある服の中で一番暖かそうな服を着ておいで。まず服から買いに行こう」
「暖かそうなって言われても……ねえヴィクトル、今朝と同じ恰好じゃだめ?」
「それってジャージってこと? だめだめ、だめに決まってる。却下!」
「ですよね~。わかった。待っててヴィクトル。適当になんか着込んでくるから」
「適当って……あのね、勇利……まあいいけど」
上着を取りに自室に向かったヴィクトルの背中にかけられたのはこんな言葉。
「それとヴィクトル、今の僕は子豚じゃない。体重管理はほぼパーフェクトだ。見て分からない?」
「それは失礼。じゃ、シャワーの時にでもきっちり確認させてもらおうかな。いい?」
「もちろん。いつでもどうぞ」
どうやら今回の勇利は子豚化阻止に成功してきたようで、かなり自信ありげな口調だった。ただヴィクトルの祖国ロシアでは恋人も含め、自分にとって大切な存在の相手を子豚ちゃんと呼び慣らすことがある。そういう意味において、ヴィクトルにとっての勇利はその体形のいかんを問わず子豚ちゃん以外のなにものでもない。
その呼び名の中に秘められた自分の感情が、ただの師弟愛なのか友愛なのかそれとも性愛なのか。この時点ではまだ掴み損ねていたのだけれど。
ヴィクトルが勇利を連れて行ったのは、馴染みのセレクトショップ。価格も比較的リーズナブルだし、スタッフも親しみやすい。この店なら勇利もそこまで畏まらずに済むはず、そう思っていたのに。
「ねえヴィクトル、ちょ、ちょっといい……?」
満面の笑みで出迎えてくれたスタッフをよそに、思いっきり眉の下がった顔で、ヴィクトルの袖をつんつんと引っ張る勇利がいた。
「あのね、あの……すっごく言いづらいんだけど、一応僕にも予算というものがありまして……」
「ふ~ん、そう? でも衣食住には文句をつけない。さっきそう約束したよね?」
「いやいや、それとこれとは別問題だってば!」
もちろん最初から勇利に支払いをさせるつもりなどない。だからと言って
「はい、勇利。これ、買ってあげようか。似合うと思うよ」
「ほんと? 嬉しい! ヴィクトル、どうもありがとう」
な~んてあっさり受け取ってくれる子じゃないこともよく分かっていた。だからヴィクトルは、今の自分の気持ちを正直に告げることにする。野球で言えばストレート一択、直球勝負ってやつだ。
「拠点の変更も思ったよりスムーズに進んだし、引越しも無事に終わった。やらなきゃならないことはまだまだたくさんあるけど、それでもスタートラインには立てたんじゃないかな。これからが楽しみだね、勇利。本当によかった。本当に嬉しい」
「ヴィクトル……」
「だから今日だけは俺の好きにさせて欲しい。ファイナルの銀メダルと、同居のお祝いを兼ねたプレゼントってことでどう? 俺だってたまには格好いい真似のひとつやふたつ、してみたいじゃないか」
「……ヴィクトルはいつも格好いいからそれはいいんだけど……でも、迷惑かけてるのは僕の方なのに、それなのにさらにプレゼントとか、どう考えても得してるのは僕だけじゃん」
ほらね、そう言うと思った――
いつだって遠慮がちで控えめなヴィクトルの教え子。勇利の返事も態度もヴィクトルの予想通りのものだった。でも、頭ごなしの拒否じゃない。だからもう一押し、ああ言えばいえばこう言う方式で次々とたたみかけて押し切ることにする。
「じゃ、お互いの服を選ぶことにしようか? ちょうど俺も新しいルームウエアが欲しいって思ってたんだ。勇利が選んでくれる? 俺は勇利に服を買う。そして勇利は俺の服を買う。どう? これなら問題ないだろう?」
「は……?」
「嬉しいな! 勇利が俺に服をプレゼントしてくれるなんて! 初めてだよね? 楽しみだなあ。あ、勇利、ほら、これなんかどう? 色も綺麗だし、この生地とデザインなら春まで大丈夫そうだ。絶対に似合うよ。ちょっと試着しておいで」
教え子のぎょっとした表情がおかしいやら可愛いやら。
「え? ちょ、ちょっとたんま! そりゃ僕だってヴィクトルにお礼をしたいって気持ちはあるんだよ。一緒に暮らせて嬉しいし、感謝だってしてる。それも山のように。でもね、でも、僕にもそれなりに事情というものがあってですね……ああ、もう! だから、ロシアの英雄のものすごーく暖かな懐具合と僕の薄っぺらな財布を一緒にされても困るんだってば……」
耳元でごにょごにょと呟かれた勇利の愚痴を、ヴィクトルは華麗にスルーした。
「大丈夫大丈夫。全く問題ない。ほら、こういうのって気持ちだから」
そして浮かべる満面の笑み。
「どれにしようか? お揃いにする? お揃いが恥ずかしいなら色違いでもいいけど」
「だから違うってーー!」
「あー楽しかった。また来ようね」
「いえ、次は遠慮させて下さい……」
多少の(?)すったもんだはあったけど、結局ヴィクトルの粘り勝ち。ロシアの英雄のブラックカードと引き換えに大きな荷物が手渡されるのを、勇利はどこか遠い目で見つめていた。
「もちろん後で徴収させてもらうよ。だって勇利、今シーズンは腐るほどの賞金を手にする予定でしょ? だからシーズン終了後にコーチ料と合わせて清算ということで、よろしく!」
「う……、プレッシャーが……胃が痛い……」
心持ち前かがみで、胃の辺りを押さえている勇利。その背中をヴィクトルはぴしゃ!とはたいた。
「背筋曲がってるよ! リリアに怒られても知らないからね」
「えっ、リリア先生どこ? どこにいるの?」
「冗談だよ~ ほら、次行くよ!」
きょろきょろと左右を見回している勇利の手を引いて、ヴィクトルは意気揚々とショップを後にした。
この子と出会えて本当に良かった――
今更ながらヴィクトルはそう思う。信じられるのは自分だけ、確かなものは氷上で積み重ねてきた時間、流した汗と涙。やれロシアの英雄だ、リビングレジェントだともてはやされる裏側で、血反吐を吐く思いで努力に努力を重ねて、あらゆることを犠牲にして、今の地位と名誉を勝ち取った。すべては努力の成せる技、そこに奇跡などあるものか、そう思っていた。
でも今は違う。スケートの神様は確かに存在していて、しがらみや重圧に今にも押しつぶされそうになっていたヴィクトルに微笑みかけてくれたのだと。スケーターとして、それ以前に人として欠けている部分を補いなさい、もっと己の人生を顧みなさい、自分にも周りにも感謝しなさい、そんな思いから勝生勇利という存在を与えてくれたのではないかと。
そんな神の意志に応えられる自分でありたい。スケート界の頂点に君臨し続けると同時に、確実に次の世代へバトンを渡す。新たな伝説の幕開けをこの手で、この場所で、この愛で。
色違いのルームウエアの入った袋を、大切そうに抱えて歩く勇利の背中に、改めてそう誓った。
「ゆうり~」
教え子の背中に思いっきりダイブした。
「え? 今度はなに? もう買い物はやだよ」
無防備な腰に腕を回してぎゅっと抱きしめる。驚き慌てて後ろを振り向いた勇利の頬に軽くキスをした。
「わ~~っ! な、なんなのもう! 意味わかんない! キ、キスとか、何それ!」
「いや、好きだなぁって思ったらつい」
「つい、って……あのねぇヴィクトル、つい、でキスなんかしちゃだめだと思う。多分、よくわかんないけど」
「そうなの? それは知らなかったなあ」
「いやいや、常識でしょ。キスは恋人とするものです」
「じゃ、ハグは? 試合の時、勇利がいい演技をしたとする。コーチの俺はそんな勇利をハグで迎えたい。勇利は俺にハグされるのは嫌? それも勇利的にはアウトなの?」
「……いや、それは大丈夫、だと思う。コーチと選手としてそれはあり。アウトじゃない、セーフ」
はにかみながらそう答える勇利。どこまでもシャイでピュアな教え子が可愛くてたまらない。
「ああよかった。好きな子にハグもできないなんて、切なすぎるよ」
ヴィクトルがそう茶化せば
「……言っておくけど、僕の方が好きだからね。こちとら物心ついた時からずっとヴィクトルのファンなんだ。ロシアの冬じゃないけど、それこそ舐めてもらっちゃ困る。ヴィクトルより僕の方がずっとずっと、百万倍好きだと思うよ」
「……は? なにそれ……」
――とんでもない殺し文句だ。
腰に回したままの腕に力がこもる。ときめきが止まらなくて本当に困った。
それは数多の浮名を流してきたロシアの英雄が、勝生勇利に落ちた瞬間だった。
* * *
「ヴィクトル、遅い! マッカチン二世がもう待ちきれないって。先に行っとくよ!」
「だめーっ! ちょっと待って! 今行くから」
慌てて玄関先に向かえば、ヴィクトルを待っていたのは教え子と、最近この家にお迎えしたばかりのむくむくの子犬。どうやらマッカチン二世のお散歩兼ランニングの時間らしい。
「勇利、もういい加減その服捨てなさい。襟も袖もくたびれてるし、色も褪せ気味だよ」
「全く同じ台詞を言わせてもらってもいい?」
この俺がシーズン遅れの服に袖を通すなんて、とヴィクトルは苦笑いした。審美眼に反すること甚だしい。ロシアの英雄もいよいよ懐具合が厳しくなったんじゃないかとか、センスが衰えたんじゃないかとか、わけのわからない報道をされたらどうしてくれよう。イメージだって壊れるし、スポンサー契約にも影響がありそうで本当に困る。
でも――どうしても手放せないのだから仕方ない。
「お待たせ。さあ、行こうか。ねえ勇利、もしかして最近ちょっと太り気味? 子豚ちゃんの再来とか遠慮したいんだけど」
「はあ? 体重これっぽっちも変わりませんけど? これって完全にセクハラだからね。ヴィクトルの馬鹿!」
あの日手に入れた揃いのウエアは、十年たった今でもふたりの日常に当たり前のように存在している。
同じ年月をかけてようやっと口説き落とした愛しい恋人と共に。
――ヴィクトル・ニキフォロフの幸せな日々
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
