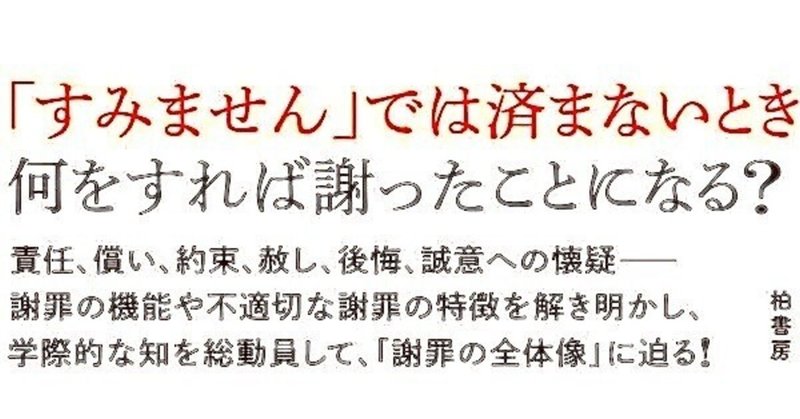
古田徹也 『謝罪論 謝るとは 何をすることなのか』 : 人の振り見て、わが振り直せ
書評:古田徹也『謝罪論 謝るとは何をすることなのか』(柏書房)
本書の「プロローグ」は、まず「子供に謝罪を教えることの難しさ」という、身近な話題から入る。その「プロローグ」の最初の見出しは「謝ることを、子どもにどう教える?」というものだ。
『親はある時期から、悪さをした子どもを叱る際、そういうときは「ごめんなさい」と言うんだ、と教え始める。すると、子どもはやがて、「ごめんなさい」と言うことはできるようになる。けれども今度は、場を取り繕おうと「ごめんなさい、ごめんなさい……」と言い続けたり、「もう『ごめんなさい』と言ったよ!」と逆ギレをし始めたりする。』(P3)
たしかに、「謝罪」というのは「形式」を伴うものだが、上の子供の事例のように、ただ「形式」さえあれば良いのではない(「形式が整っていなければならない」とも言えるだろう)。つまり、おのずとその「中身」が問われるのだから、当然むずかしい話になる。誰も、他人の「心の中」までは、正確にはわからないからだ。
また、だからこそ、その「心の中」を示すための「形式」が必要となる(つまり、前述の「形式が整う」とは、内面の「誠実さ」を感じさせる形式になっている、という意味である)。
それが「誠意の印」というやつだが、それだって、先の子供の事例と同様、何度も謝れば良いというものでもなければ、おおげさに謝れば良いというものでもない。また、札束を積めば良いというものでもない。それで納得する人もいるだろうが、かえって怒り出す人もいるだろう。
また、同様の「被害」に対して、同様の「謝罪」をしても、それで納得してくれる人もいれば、納得しない人もいるから、「これをすれば絶対確実」というような「謝罪」方法は、なかなか難しそうである。
そもそも、謝罪の原因になった、他者へのなんらかの「加害」というのも、軽重の問題だけではなく、種類も多種多様であり、しかも、その加害者及び被害者の人間性や社会的属性もいろいろで、これらの多様な要素が複雑に絡まり合う事象なのだから、それへの「謝罪」とひとくちに言っても、「尋常一様」では済まない、というのも当然のことなのだ。

だが、私の場合、本書を読んで、そう気づかされるまでは、「謝罪」という問題を、それほど複雑なものとは、考えていなかった。なぜならば、私にとっての「謝罪」とは、「謝罪一般」のことではなく、「私にとっての、謝罪とは何か?」というものだったからである。
だから、「プロローグ」の二つ目の見出しである「「謝罪とは何か?」と問われて説明しようとすると、我々は知らない」の後の、
『 謝罪とは何かを子どもに教えることは難しい、というだけの問題ではない。問いは我々大人にも自ずと跳ね返ってくる。我々は、謝罪の意味を自分自身に説明することができるだろうか。』
(P4、原文傍点部は、ゴシック体に代えた)
という「問い」を最初に読んだ際、私は「謝罪の意味を自分自身に説明することができる」と、そう思った。
そんな私の「説明」とは、自身の「(法的・倫理的な)罪」を認めたときは、その「罪」によって生じた「被害」について、被害者に対し「自分の罪だと認めて、詫びを入れ、可能なかぎりの被害回復を約束する」といったようなことである。
一見したところ、これで十分なようにも見えるのだが、これは「謝罪する側=加害者側」が、「私個人の場合」であって、他の人は、私と同様の謝罪はしないだろう。私よりも「容易なことでは謝罪しない」人もいれば、私なんかよりも「あっさり謝罪する」人もいる。一一このように考えただけでも「謝罪」というのは、「尋常一様」なものではあり得ないのだ。
つまり、「謝罪」というものの「現実的な全体像」を捉えた上で、「謝罪」という行為の「本質」を導き出すのは、容易なことではない。だからこそ、「謝罪とは、これだ!」と「決め打ち」で決めつけて済まそうとするのではなく、まずは「謝罪」という行為の「多様な現実」を把握しなければならない。
その「本質」まではつかめなくても、ひとまず、その一筋縄ではいかない、多様な実態を知らないことには、単なる「独断論」になってしまい、それは「個人的な信念や思想」にはなり得ても、「謝罪」というものを考えた(哲学した)ことにはならないのである。
例えば、個人的な「狭い了見」だけで「謝罪とは、ひとまず謝罪の言葉を口にして、頭を下げれば、それが謝罪だ」などという「独善的な思想」を持っているからこそ、政治家によく見られるような「見るからに心のこもっていない、口先だけの謝罪」などというものが見られるわけなのだが、ああしたものを「謝罪になっている」と考える人は、ほとんどいないはずだ。
あんなもので「謝罪」になっており、それで済むのであれば、いきなり殴っておいて「あっ、ごめんねー」で済むのである。
だが、当然、そんなことで済ませるわけにはいかないから、私たちは「謝罪とは何か?」ということを考えなければならない。
だが、あまり「一般論」的なことばかりでは、私たちは、なかなか「謝罪」ということを「リアルな問題」として考えることはできない。
だから、ここで、具体的な事例を、ひとつ挙げてみよう。
私が上に『元文科副大臣の谷川弥一衆院議員(82)』の例を挙げたのは、「謝罪」の問題を、抽象的な議論としてではなく、あくまでも私たちの生活に直結した問題として、リアルに考えて欲しかったからである。
上の『元文科副大臣の谷川弥一衆院議員(82)』のテレビニュース報道を見た人の多くは、「たしかに新聞記者のつきまといや、同じような質問のくりかえしにはうんざりさせられるだろうが、それにしても政治家は、国民に選ばれた公人なのだから、説明責任があるはずだし、説明するにしても〝態度〟というのがあるはずだ。だが、この思い上がったジイさんには、それがまったく無いのだから、こんな奴は厳しく処断されて然るべきだ」と、そう考えたはずだ。
だが、問題は、私たち自身が『元文科副大臣の谷川弥一衆院議員(82)』と同様の「立場」だったら、ああいう態度にはならないか、ということなのだ。
日頃は「社長、社長」とか「先生、先生」と持ち上げられていて「それが当然だ」と思っているような、「有名人や権力者になりたくてなって、その地位に満足しているような人」が、「名もなき新聞記者ふぜい」に、にわか正義風を吹かされ、しつこくつきまとわれたら「うるせえ、このゴミが!」とは言わないものの、そう考えたりはしないだろうか。
そして、それがつい「ああいう態度」に出てしまい、「馬鹿たれが!」と言いたいところを「自制」して、「あなた、頭悪いね」という言い方に「和らげられた」のではないだろうか。
つまり、私がここで言いたいのは、私たちは「悪いことをしたんだったら、私なら素直に謝罪できる」と、そう思いがちなのだが、実際には、そう簡単な話ではない、ということなのだ。
自分では「謝罪の必要な時には、適切な謝罪をするし、その必要がない時には、謝罪などしない」と、そう考えるはずなのだが、そういう「自分基準の謝罪」だけでは、『元文科副大臣の谷川弥一衆院議員(82)』の場合と同様で、被害当事者はもとより、「世間」もそれを「謝罪」だとは認めてくれないのである。
言い換えれば、それが「自分の謝罪」ではなかったら、自分だって「それを謝罪だとは認めなかった」公算が高いということなのだ。
つまり、私たちは「日頃、他人事ならば、とうてい認められないような謝罪を、自分自身が加害者となった場合には、やってしまっている」公算が高い、ということなのである。
だから、「謝罪」の問題というのは、たしかに「自分の謝罪の問題」として考えなければならないのだけれど、それと同時に「一般的な謝罪としての、多様な謝罪の現実」を知らなければならない、ということになる。それを知って「人の振り見て、わが振り直せ」でなければ、私たちは「客観的に正しい謝罪」が出来てないと、そう考えるべきなのだ。
例えば、「他人事」ではない「謝罪」問題としては日本の「戦争責任」と、それに伴う「日本国民」による「謝罪と被害回復(被害補償)」というのがある。
「従軍慰安婦」問題だとか「徴用工」問題だとか、「政治家の靖国神社参拝」問題だとか、こうしたことはすべて、「かつての日本による、朝鮮や中国に対する侵略戦争」の結果であり、当然のことながら、日本が「加害者」であり、朝鮮や中国が「被害者」であることは、論を待たない。

しかし現実には、テレビで得た にわか知識だけで「戦後保証については、すでに政治的に決着がついているのに、いつまでしつこく補償金をむしり取るつもりなんだ」と考えている日本人が、決して少なくはないはずだ。
「ネット右翼」だとか「政治保守」だけではなく、「自覚的なリベラル」以外の「すべて」とまでは言わなくても、「かなりの多く」が、そのような「被害者意識」さえ持っていると、私はそう見ている。
まあ、これは、気持ちとしては、私もわからないではない。いつまでも「謝れ謝れ」と言われたら、「いい加減にしろ!」と言いたくなるのは「人情」だろう。
ただし、それが「人情」だというのは、前記の『元文科副大臣の谷川弥一衆院議員(82)』の場合だとて、まったく同じである。答のわかりきった質問を、しつこくつきまといながらしてくる記者に対して「あんた、頭悪いね」と言いたくなるのは、「人情」だろう。
だが、言うまでもなく、「人情」だからといって、それが許されるわけではないし、ましてやそれが「適切な言動」であるわけもないのだ。
したがって、朝鮮や中国の人たちが、いまだに「謝罪と補償」を要求してくるのは、「当然のこと」なのだ。
なぜなら、日本人の大半は、先の「侵略戦争」について「まったく反省していない」ようにしか見えないし、実際そうなのではないかと、当の日本人である私でさえも、そう見ているほどだからだ。
つまり、「戦争加害者」そのものではないにしても、「加害者側の人間」である日本人の私ですら「今の日本人の多くは、侵略戦争について、十分に反省してはいない(そもそも無知だ)」と思うのだから、「被害当事者」である朝鮮や中国の人たちに「日本人は反省していない」と映るのは、当然のことなのだ。
で、こう書くと、「反省という心の問題は、たしかに困難が伴うが、しかし、少なくとも、それ相応の謝罪と補償はしているではないか。心のことを言い出したら、切りがないではないか」と、そうおっしゃる方もいらっしゃるだろう。確かにそうである。
しかし、ここで考えて欲しいのだが、あなたが「親兄弟を惨殺された」被害者家族だと仮定して、その犯人(加害者)が大金持ちだったので、「常識的な補償金」の数倍の金額を、ポンとあなたの前に投げてよこして、「済まなかったね。まあ、起こってしまったことは、取り返しがつかないんだから、これで勘弁してくれ。あんただって、最後は金目の問題なんだろう?」と言われた時、あなたは、こんな「謝罪」を、「謝罪として受け入れるのか?」という話なのである。
たしかに、「現実問題」で考える「あなた」は、その「金を受け取って」、その「謝罪」を受け入れ、それが「謝罪」であると認めるのかもしれない。
だが、「金には困っていない」人や、「名誉意識の強い人(プライドの高い人)」ならば、これが逆効果だというのは、論を待たないだろう。「ふざけるな!」と言い、「おまえは、まったく反省していない!」と言って、「心からの謝罪」を求めるだろう。そして、その「加害者」が「どうか、もうこれで勘弁してくれ」と「泣きを入れる」くらいの補償金を要求することだろう。仮に、出せないとわかっていたとしても、だからこそ「懲らしめる」ために、わざわざそれを要求することだってするだろうし、仮にそれを出してきても、その「態度」次第では、「さらに謝罪と補償を要求する」だろう。
なぜかと言えば、被害者の「踏みつけにされ、傷つけられた心」は、「こいつは、心の底から反省し、罪を償おうとしている」と「納得」させられないかぎりは、「永久」に満たされることはないからである。
ところがだ、日本の態度はどうだろうか?
日本を代表する政治家が、「戦後補償の問題は、すでに両国間において、政治レベルで決着のついている話である。したがって、あとは、そちらの国内問題として、適切に処理していただきたい」などと、対等な契約関係における「当然の権利」でも主張するかのように、およそ「加害者意識=罪の意識」を欠いているとしか思えない「木で鼻を括ったような」ことを、繰り返し口にする。
また、どうやら「日本人」の多くは、そんな政治家の「物言い」を「当然だ」として支持しているようだし、それでその政治家は国内的な人気を博しているようなのだから、こうした事実から論理的に導き出せるのは「(一部例外を除いては)日本人は、侵略戦争を反省していない」ということなのである。

だとすればだ、彼らが「許してくれない」のは「当然」ではないだろうか。
先の「親兄弟を惨殺された」ケースにおける遺族が、加害者から『「常識的な補償金」の数倍の金額を、ポンとあなたの前に放り投げて、「済まなかったね。まあ、起こってしまったことは、取り返しがつかないんだから、これで勘弁してくれ。あんただって、最後は金目の問題なんだろう?」と言われた時』と同様、そんな「謝罪」など「謝罪」とは認めず拒絶するだけではなく、むしろそれによって「絶対に赦すまい」という頑な態度になるのは、一一誇りある人間や民族であるならば、むしろ「当然のこと」ではないのか?
日本人だって、立場が逆なら、同じように反発して、そんな相手を決して「許さない」のではないだろうか?
それとも、日本人は「賢い」から、「大金さえもらえば、相手の本音なんかどうでも良い」のだろうか?
相手が「先祖の死を、金で売る犬畜生めが。そんな民族だから、侵略戦争なんかを起こしたんだし、この先だって起こしかねないと思われても当然なんだよ」と、そう思われても、あるいは、そう言われても、「平気」で、その金を掴んで、嬉々として帰っていくのであろうか?
実際、「政治家の靖国神社参拝」問題を、朝鮮や中国の人たちが、あるいは当該政府が「批判する」のは、当然のことだ。
なにしろ、靖国神社には「戦犯が祀られている」のだから、そこへお参りに行くというのは、その政治家が「先の侵略戦争」を支持しているも同然だからである。

「いや、そうではない。国のために命を捧げた人たちに、感謝と追悼の祈りを捧げたいだけだ」と、いつものごとく「見え透いた嘘」をくり返すのであれば、私ならば「それなら、これ見よがしに靖国参拝なんてパフォーマンスをするのではなく、神棚でも仏壇でもいいから、自分の家に祀って、それに毎朝毎晩、何時間でも祈っていろ。それなら、あんたの勝手だし、完全な〝私人〟の、純粋で熱心な追悼行為だと認めてやろう」と、そう言うだろう。
つまり、同じ日本人である私だって、これくらいの「道理」はわかるのだから、朝鮮や中国の人たちが「(一部例外を除いて)日本人は反省していない」と考えるのは当然だし、その判断は、日本人一般の言動から推して、まったく正しい判断・評価だと言えるだろう。
ならば、一一彼らが、そんな日本を「許さないのは当然」だし、「心からの反省」をさせるために、「心のこもった謝罪」や「身を切るほどの補償金の拠出」を求めたとしても、それはむしろ「当然のこと」なのだ。
しかしそれを、当の日本人が、「当然のこと」だと思っていないからこそ、それを執拗に求める必要さえ生まれてくるのである。
○ ○ ○
以上のように考えれば、「私は、誤った行いをしてしまった場合には、適切に反省するし罰も受ける。謝罪もするし被害補償も可能な限りさせてもらう」などと思っている「多くの日本人」が、いかに「自分のことが見えていない」か、「いかに自身を過大評価し、美化している」かが、わかるだろう。一一そんな「無自覚無反省な人間」に、「適切な謝罪」など出来るわけがないのである。
だからこそ、私たちは「謝罪」ということの「多様な形態」という「現実」を知った上で、その「難問」に向き合わなければならない。その「難しさ」を知らずして「謝罪くらいできるよ」などと思っている者は、端的に「馬鹿」なのであって、そんな人間に「一人前の謝罪」などできるわけがないというのは、「日本の政治家」などの「まったく心のこもらない謝罪」ひとつ見ても、わかりやすいくらいにわかりやすい事実なのである。

本書の著者は、書き方(文体)こそ平易であり、一見したところ読みやすそうに感じさせるのだが、その論述は「犀利かつ粘り強い」ものであり、決して「エンタメ哲学」のように、「面白いこと」を言ったり、「ぱっと見にユニークなこと」を書いたりはしていない。
「謝罪」をいう「複雑怪奇な難問」に対し、匍匐前進のように、じりじりと迫るがごとき記述が続いて、本書なかばにもなると、こちら集中力が途切れそうなほどの綿密な分析や記述も少なくないのだが、しかし、これこそが、本物の「哲学」なのだ。「哲学する」ということなのである。
著者は、単なる「ウィトゲンシュタインの研究者」などではなく、間違いなく「自分の頭と言葉で考える、実践的な哲学者」なのだ。
『○○○の哲学』などと題する、「ちょっと見に知的読み物」が氾濫する今のご時世にあって、執拗かつ真摯に「いまここ」を問い続ける著者に、私は心からのエールを送りたいと思う。
(2024年5月19日)
○ ○ ○
● ● ●
○ ○ ○
・
○ ○ ○
・
・
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
