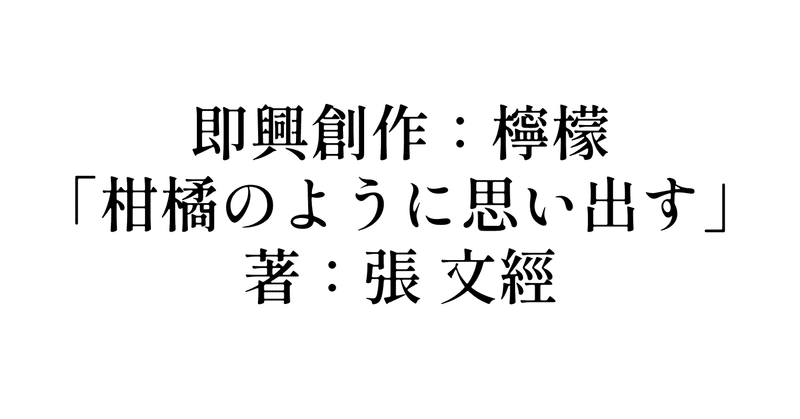
柑橘のように思い出す 著:張 文經
空がちかかった。冬であり、薄布のような雲がなんじゅうにもひきのばされて、空の青がいっそうふかまるきがした。
きみは雪をみたことがある?
わたしはそう言った。小さな山から下り、海におちていくみたいな道だった。
あるよ。彼が言うから、わたしはそれをわらった。
それはほんとうの雪? 溶けながら空になっちゃうみたいなものではなくて? 彼はあいまいに笑って返した。きっとわたしの話し方は、もう彼には光ではなかった。それだけがわたしにはわかった。
雪がたくさん降ったあとの昼の、ふうけいを見たことがある? 雪のうえを光が反射して、さんざめていて、時間の流れなんてなくて、ほんとうに全部しろくなってしまって。そんな風景を見たことがある? そんな風景のなかに、わたしが生きていたのを知っている?
わたしはそれを聞けなかった。わたしの生まれ育った街から、とおくはなれた半島の日差しはやわらかかった。わたしと彼の横には蜜柑畑があって、ひざしをまとった実たちは、空のなかに、えくすくらめーしょんまーくとして揺れた。わたしたち、はすっかり前に終わっていて、わたしと彼がただ、空の青に引き裂かれていた。
たとえば彼がわたしをころしてくれればいい。わたしたちはこのまま、目の前の海にながれこんでいく、小さな川になって、そのまま、もしかしたら消えていくときは少し悲しく、苦しいかもしれないけれど、それだって優しさだ。
たとえば、わたしをここに置いていってくれればいい。わたしに上着だけ渡して、一人で、自由になってくれればいい。わたしはそしたら待っていよう。わたしは待っていることなら、いくらでもできるきがする。そしたら、裏切られることなんか気にしなくていいし、わたしはわたしのままで、どこまでも彼を思って、作っていればいい。
たとえば、彼が一つでも歌を教えてくれればいい。わたしはそれだけをさいごまで覚えて、その歌をわたしそのものにしてしまって、わたしは波に足首をひたして、ずっと遠くに、その歌を投げていればいい。
わたしにはそれがあればいい。
蜜柑がわたしたちの横をすぎた。驚きであり、丸く、わたしたちの横の、細いみちを洗っていった。そのままそれらは、驚きのまま、海までいくんだ、たぶん、どこかの農家の車の荷台から落ちて、じゆうになって、誰に食べられることもなく、どこかで空気そのものみたいになってしまうんだ。
食べること、食べられることの、円環から抜け出て、空そのものになる。ほんとうの一人になる。わたしはいままでたくさんのものを食べてきた。きっとわたしは何かの形で彼だって、食べていた。
蜜柑。はじめて彼とふたりで歩いた日の帰り道、彼は蜜柑をポケットにいれていた。彼にとってそのとき、わたしはひとつの謎かけであり、もしかすると、世界を覗きこむための窓ですらあった。駅のホームで、彼はわたしに蜜柑を手渡した。
「これ、もしよかったら」
そう言ってからは、長い言い訳だった。彼のおばあさんが蜜柑のよくとれるところで育ったことや、一番好きな季節が冬であることなどをいった。子どものころから、蜜柑をよく食べて育ったことをいった。わたしは受け取るとき、たしかにかれの右手のひとさしゆびにふれて、その冷たさを確かめて、だから安心して、そのままに蜜柑を小さくかじった。果肉はわずかにしか含めなかったけれど、ちゃんとわたしは、その匂いと雫になった。彼はひょうじょうをこぼしたみたいに、ぼんやりとわたしを見ていたから、わたしは笑えばよかった。
「じゃあね」
とわたしがいって、かれは小さく手をふった。
それからわたしと彼は約束をして、わたしたちになった。わたしたちであるから、言い訳をする必要はなかった。
めざめるとき、かれは蜜柑を手に持っているときがあって、それから、かれがそれをわたしの頬に押し当てて、きみは少しだけ温かいね、というときがあって、それから、わたしたちが布団にくるまったまま蜜柑を食べるときがあった。その、じかんのぜんぶが、わたしには止まって思えたりした。薄暗い部屋の、一番の明かりは蜜柑の橙色で、わたしたちは剥いて、食べて、互いの体温を混ぜ合わせたゆるいひかりのなかに、休んでいればよかった。
蜜柑を剥いたきみの指を噛むと、かすかににがくて、けれどやっぱり冷たく、裏切るみたいにいい匂いがした。わたしはそうやってかれを食べていた。噛まれることで、きっと、彼だってわたしを食べていた。
あ、と彼がいう。彼はそのときあいまいに笑ってはいなくて、むしろはじめて指をさわったときの空っぽの眼、そのもので、わたしはなぜ彼に触れなくなったのか、悲しくなり、けれどもうわたしたちではないから、もう分かたれている。
彼はレモンを拾い上げる。そのへんにひしゃげた形が、坂をまっすぐに転がっていくのを許さなかった。海に迎え入れられることができなくて、小さな円弧をつくって、塀につきあたり、レモンは彼の足元に転げた。いい色だね、と彼がいう。
そうだね、今日の太陽の色でもないし、わたしたちの部屋に差していた光の色でもないし、きみの冷えたところでも、わたしの執着でもない色だね。わたしはそういわずに、うなずくこともできないで、ただ見ている。レモンの変な膨らみ、けっして豊かになりきらないで、彼のほそい手のひらの、内側をかたどるために生まれたみたいなかたちが、わたしには憎らしく思える。だけど、海にたどり着かないなら、きっとわたしと同じ。あるいは、わたしたちと。
病院に、彼のおばあさんを見舞ったことがあった。
九十歳のおばあさんは、もう少しずつ枯れていくみたいで、点滴もうたないことにしたから、静かに、死とよばれているものを待つだけだった。おばあさんはときおり、じぶんは百二歳だと口にした。かれは笑って、そうだね、と答えた。わたしはそのとき、それを優しさだと思った。
冬が終わろうとしていて、だから、わたしとおばあさんと彼とは少しだけ体を寄せ合っていた。わたしはおばあさんに挨拶したけれど、きっとわたしのことは見えていなくて、だから、昔からの知り合いに言うみたいな、「いつもありがとうねえ」という言葉をもらった。ねえ、見てよ、といって彼はレモンを取り出してみせた。
綺麗だった。まわりの光をすべて飲み込むみたいな、鮮やかな黄色で、静かに曲線をしていた。ひとつだけ、何かに裂かれたような傷が入っていて、そこが木になったみたいに、茶色く、固く変わっていた。わたしはその深い傷か、あるいはそれ以外のあまりの滑らかさか、をどこかで恐れて、すぐに目をそらした。
「ねえ、みてよ」
彼はわたしではなく、おばあさんにそう示した。そして傷を指で優しくなぞった。すこし表皮にまさつして、かれの指が、ほんとうに見えないほどかすかに震えるのがわかった。
「傷けられたところは、こうして木みたいになるんだ。木化っていうんだって」
おばあさんはそれを見て、小さく笑った。
「面白いね、綺麗な色だね」
彼はおばあさんの指先にレモンを触れさせた。指先は静かに乾いて、細い線のあつまりのようになっていた。木化だった。彼はそのことに気づいていただろうか。彼は光輝いてすら見えたから、きっと、気づいてはいなかっただろう。わたしは、本当にその場にいたのだろうか。実はいなかったのかもしれない。実は、わたしはひとつの漂う目みたいになって、そこを映し出していただけなのかもしれない。
けれど、わたしはそのとき、やっぱりいたんだ。わたしはそのとき、彼のおばあさんだった。八十年くらい経って、わたしが百歳になるとき、きっと彼は変わらず弱く、小さく笑って、ぼんやりと、レモンを抱えてわたしに会いに来る。
なんで、蜜柑じゃなかったの? わたしたちの部屋の光じゃなかったの? そういうことができないから、わたしは綺麗な色だね、という。わたしたちは時間に引き裂かれて、わたしは、彼から、彼じゃないものから付けられた傷で、すっかり木になっている。そうだ、わたしはやっぱりあのとき、いたんだ。
そして、彼に看取られるのを、確かに思い描いたから、わたしは彼をわたしの一生にしようと、思えたんだ。
わたしはそんなことを忘れたことにしていた。
どこにも行き着かなかったレモンは、彼の手のなかに収まっていた。
おばあさんはきっと海に行き着いた。わたしたちは、長い時間のなかで、きっとすこしずつ、海に落ちていく。きっと彼は、それを認めたくないのではないか、とわたしは思う。
ねえ、きみは本当の雪をみたことがあるの? こんどは口にしない。
きみには蜜柑は美しかった? それとも、わたしの分身でしかなかった? それらをいうことはできない。彼にかけてばかりだった謎が、どこにも届かないから、わたしはただ空がちかいな、って思う。空がちかい? ほんとうはそんなのどうでもいいのかもしれない。ただ、わたしがレモンにも蜜柑にもなれないまま、傷ついて木になることだけを覚えて、長い長い海までの道を忘れて、それで、きみなしで死んでいくとしたら、それを悲しみ以外になんていえばいい? きみはそれを何て呼ぶ? きみはそれに、何か名前をつける。きっと、思いのよらない名前をつける。
けれど、全部言い訳だから、わたしは、その言い訳が好きだったから、もう、聞きたくはないんだ。
「もうぜんぶ、終わろうね」
わたしはそれだけ言う。
それだけしか言えない。わたしがわたしのなかで言ったことも、すべて、言い訳で、溶けていく、道筋の連続で、海になんか行き着かないから。
きみはまた問うみたいに黙る、から、わたしは彼の手からレモンを叩き落とす。その柔らかい、跳ねるのを、手につかんで、わたしは、一人で、急ぎ足で、道を下りていく。海に近づいていく。けれど、それは、死ではない。きっとたくさんの魚たちがいて、波が揺らして、死ではない。わたしたちは、そんなのでひとつになれない。わたしの孤独そのものにすらなれない。
ひとりで歩いていく。彼が立ち尽くしているのがわかる。彼が立ち尽くして、一人で納得しているのがわかる。
「ありがとう」
彼がうしろでいって、わたしは日差しをかきわけて、海なんてない、蜜柑も、レモンも、ない、ところに落ちていく。言葉だけわたしのなかに渦をつくって、ちがう、彼や、彼の周りのものの、わたしに残した傷だけ残って、それが言葉みたいに見えている。ありがとう、と大きな声で彼が言う。その意味がほんとうはわたしにはわかる。わかる。わたしはいつか彼を許してしまうだろう。百二歳になって、一本の木になるとき、わたしは許しているだろう。
それは何の悲しさだろう。わたしはレモンをかじる。わたしの歯を、わたしじしんを少し、美しくして、わたしは食べる。円環をすりぬけて、わたしは振り返る。かれが遠くにたちつくしている。動かなくなって、空のなかに見える。そこまで届かないことを知りながら、歯型のついたレモンを投げつけた、とき、わたしはほんの少しだけ空を、気持ちよく思った。
きもちいいな、とわたしはわたしの、言葉、で確かめた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
