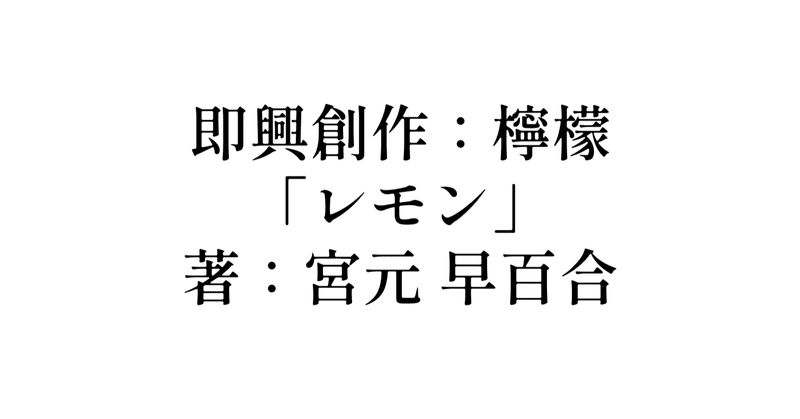
レモン 著:宮元 早百合
タケルは悲しい子どもだった。幼稚園のころから何度も車道に飛び出した。言葉でいいあらわせない悲しみがかれを何度も突き動かして、そうさせた。車はどれも自動ブレーキで止まってしまった。あぜんとして車を見つめる彼の首根っこを、母親がつかんで歩道に引きずり戻した。そのことで叱られると、よけい悲しみに包まれた。
小学校に通いはじめる直前、家族で旅行に行った。また親の目を盗んで抜け出した。母親もこのときばかりはタケルを見つけられなかった。彼はどこまでもあるき続けた。紫の小さい花が一面に咲く野原を抜けて、白い穂のなる草原を抜けてもあるき続け、果物の木がたくさんあるところに出た。
かいだことのない澄んだにおいのする空気の向こうで、オレンジの太陽が眩しかった。等間隔で並ぶ木々が不気味な影を落とし、枯れ葉が渦を巻いていた。タケルは初めて、ほんとうに戻れなくなる可能性について考えた。自分は庇護下にあって自由を欲していただけなのだと思った。
「タケル」と、地面のあたりから彼を呼ぶ声がした。いよいよ暗くなりはじめる地面に目を凝らすと、石ころのようなものがあった。タケルはじぶんの手のひらより一回り大きなそれを拾って、耳の横で振ってみたりした。
「タケル」それは言った。「こっちだよ」
指も何も持たない、ただの丸い塊だったが、タケルにはそれがどの方角を指してそういっているのかが理解できた。かれは声に従って引き返し、やがて農場の入り口にたどり着いた。母親は泣いて彼を抱きしめた。宿屋の明かりの下で彼を導いたそれを見直すと、石だと思ったのは大粒のレモンだった。
タケルはそれから何度も家出するようになった。学校でいじめられたときも、理由なく父親に殴られたときも、壁に穴を開けてしまったときも家を出てどこへともなく歩き続けた。かならず地元のスーパーに寄ってレモンを買い、ポケットに入れて歩いた。繰り返すうちに大胆になって山に入ったり、海岸線に辿り着くまで歩くようになった。帰り道が分からなくなるまで歩いて、疲れが限界に達したとき、レモンを空に掲げると、腕は必ず帰り道に向かって倒れてくれた。そうしてタケルはどんなに遠くまで行っても家に帰ることができた。その理由を尋ねられることはなかったが、彼が自分から話すこともなかった。
タケルの家は貧乏だった。東京で大学に行って金になる仕事をするのだと彼は決意しており、フリマアプリで参考書を片っ端から買って読んだ。模試と受験料のためにバイトに行くことになっても、彼はレモンの声に従ってバイト先を決めた。模試の結果から受験先の候補をいくつかに絞り込んだが、最後に決めるときはやはりレモンに尋ねた。そんなときも、レモンはいつも正しい道を教えてくれた。
大学生活はうまくいかなかった。東京で生きているだけでタケルは満足してしまって、学校に通うのをやめてバイト代で生活するようになった。親元を離れたことで彼の中には自信が満ち溢れていた。ある夜に新宿で泣いている女を拾った。女は若く見えたが、歳上で会社員だった。それからもたびたび彼の家を訪れ、ついに住み着き始めるようになって、ようやく彼のなかに迷いが生まれた。彼はスーパーの野菜コーナーを探し回ってレモンを一つ買った。
女が見ている前でタケルはレモンを天井に掲げた。腕はゆっくりと女のほうに倒れた。
それ以来、レモンは答えなくなった。
タケルはバイトを増やしたり、やっぱり減らしたり、飲食店で働いたり、辞めたりした。大学から通知が来て、退学した。女には止められた。レモンは何も言わなかった。
葬儀場で働くようになった。給料は良かった。生き物を燃やすこともあり、そういった日はボーナスが出た。葬儀場だけで生活できるようになると、タケルは他のバイトをやめた。時間が余るようになったから、絵を描いたり、ギターを買って弾くようになった。そのどれも、彼女は嫌がった。彼が趣味を増やすにつれて彼女のほうはやつれていくように見えた。仕事の愚痴が増えた。親に虐待されていたという話をするようになった。タケルはそういうときは黙って話を聞いた。どうすればいいか分からないときは黙っているのが彼のやりかただった。
ある日、あまりにも彼女の愚痴が長すぎたので、タケルは嫌になって部屋を飛び出した。自転車に乗って皇居のほうへ向かい、銀座を通り過ぎ、海岸公園まで走った。地理はバイト時代に覚えたから、身一つで十分だった。彼は海岸の空気が好きだった。釣りをする老人にちょっかいをかけて、気のいい相手と駄弁るのも好きだった。日付が変わるまで彼は海岸公園にいて、自転車で戻った。
帰ってきた彼を見て、彼女は包丁で自分の首を刺した。そうして床に倒れ込んだ。近寄ってみると泣いていた。涙できらきらと光る目が美しかった。その目は何かを訴えていた。タケルはうなずいた。
タケルは包丁を拾って、彼女の首をもう一度刺した。念のためもう一度。彼女が動かなくなるまで見ていた。それから服を着がえて部屋を出た。
タケルはコンビニに行った。幸運にも果物コーナーがあり、レモンが売られていた。彼はコンビニを出て少しだけ家の方向に歩いて、車通りのなくなった交差点の真ん中でレモンを掲げた。
レモンは今度こそ意思をもってある方向を指した。それに従って歩くと、電話ボックスがあった。彼は実家に電話をかけて、両親とそれぞれ少し話をした。
タケルは十五年くらい刑務所の中にいた。それから社会に戻って、老人になるまで生きた。小さなアパートで孤独死していたのを、異臭で気づかれた。タケルの死体は干からびたレモンを握りしめていた。あとになって、死体と一緒にレモンを焼いてほしいという旨の書かれた遺書が見つかったが、そのときには既に共同墓地に葬られていた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
