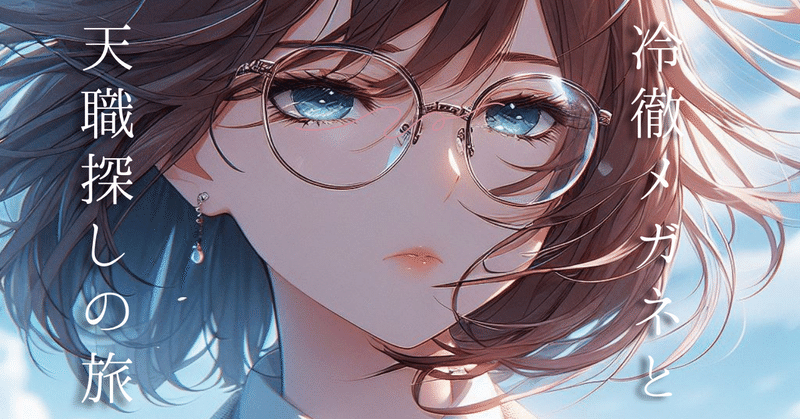
小説:冷徹メガネと天職探しの旅 第1話
あらすじ
IT企業に営業職として勤める荒田優一は突然退職勧告を受けドン底に突き落とされる。自信を喪失していた荒田だったが、姉からの紹介で氷のように冷徹だが凄腕のキャリアカウンセラー天神零華と出会い人生を変える天職探しを始める。天神の冷徹な言葉にダメージを受けながらも天職探しのレッスンを通じて荒田は仕事と自分自身に向き合うようになる。荒田の物語を通じて自己分析や転職のやり方も学ぶことができるお仕事小説。長編小説。
1.憧れたオフィス
もう30分以上は経つだろうか?上司の小言は終わらない。足が疲れるので左右に体重移動を小さく繰り返している。外は大雨だ。この会社のオフィスは16階にあるので晴れていると東京駅が一望でき景色が良いが、今日は雨でその景色を見ることはできない。
「荒田!話を理解しているのか?」
僕は小さくうなずく。呆れたような顔をして上司は犬を追い払うようにして手で席に戻るよう促した。僕はフリーデスクという名の定位置に戻りPCの電源を入れた。
周囲は観葉植物が置かれ、スタンディングデスクなどもある映えるオフィスだ。まさにIT企業と言った雰囲気で採用HPに載っていると若者なら誰もが憧れを抱くだろう。僕もその中の1人だった。
しかし内情は誰も周囲に目を向けず静寂が空気を支配している。なんとも働きにくい職場だ。観葉植物の青々しさがその空間にぽっかり浮いている。
「また長かったな」
「30分以上はあった。それだけの時間があればお客様へメール返信できるよ」
隣に座るのは同期入社の佐藤。5年前に新卒で10人入ったが気がついたら同期は佐藤1人となっていた。
「何かミスでもしたか?」
「一人の顧客に時間をかけすぎている。顧客単価もしくは顧客数を上げる。どちらかを最優先事項に置けと指導受けたよ」
PCを開くと案の定お客様からのメールが大量に届いていた。
「荒田さん!ちょっと教えても貰いたいことがあるんですが」
「いいですよ」
「この見積書作成のやり方なんですが…」
僕は谷口さんのPCを覗き込み見積書作成の修正方法を伝えた。谷口さんは僕より10歳年上の中途入社社員だ。前職では飲食店で接客業をやっており、IT業界と営業は未経験らしい。年上の方なので最初はどう接すれば良いかわからなかったが谷口さんは年の差を気にせずグイグイ来るのでいつの間にか仲良くなっていた。教育担当が他にいるのに、僕のところへよく質問をしに来る。
「ありがとうございました!」
谷口さんは満面の笑顔でPCを片手に自分の席へ戻っていった。
「また質問受けてたのか。教育担当に任せれば?」
佐藤が呆れたように呟いた。
「教育担当は忙しくてなかなか教えてくれないらしい」
「谷口さん同じこと何度も聞いてくるよな〜。いい加減覚えろって」
「俺らが新卒の時もそうだったよ」
「あんなに酷くは無かった」
会社で一緒に働くメンバーなんだから支え合うのがいいのではないかと言おうとしたが、この会社では少数派なので口にはしなかった。もしかしたら社会全体がそういう考え方で僕の考えの方がオカシイのかもしれない。モヤモヤを消すために僕はお客様のメールに集中することにした。
メールを全て返し終えたころには19時になっていた。時間を確認すると急にお腹が空いてきた。まだやるべきことは残っていたが、明日の自分に期待することにしてPCの電源を落とした。外に出てみると雨は止んでいた。雨上がり特有の匂いがした。僕はこの匂いが好きだ。なぜか落ち着く。
「荒田さん!」
谷口さんが大きめのリュックを揺らしながら早足でこちらへ向かって来る。
「飯でも食べに行きませんか?」
独身の僕は家に帰っても1人でコンビニ弁当を食べるだけなので谷口さんと夜飯を食べることにした。
2. 憧れの人
東京駅周辺には様々な飲食店がある。世界各国の料理が楽しめる場所だ。そんな場所だが我々が良く行くのは大衆居酒屋だ。なぜなら安くて大量に食べれるからだ。皿に山盛り盛られたモヤシ炒めと餃子を食べながら僕と谷口さんは他愛のない話をした。
「ここの餃子は絶品ですね」
ニコニコしながら谷口さんは餃子を頬張る。僕は醤油では無くて、お酢に胡椒を混ぜて餃子を食べていた。
「荒田さん、それ何ですか?」
「お酢に胡椒です。これで餃子を食べると絶品ですよ」
さっそく谷口さんもお酢に胡椒を混ぜて餃子を食べていた。
「美味い!酢胡椒いいですね。どこで知ったんですか?」
「前テレビでやっていたんです」
本当は以前付き合っていた彼女が教えてくれた食べ方だった。そのことを言うと何だか未練たらしいと思い言わなかった。店内は仕事帰りのサラリーマンで溢れている。上司と部下、同僚、一人で食べに来ている人と様々だが一様に少し疲れているように見えた。外から見れば自分も同じように見えるのかもしれない。
「藤原マネジャーはホント何なんっすかね?」
谷口さんは餃子を酢胡椒でビシャビシャにして口に放り込む。
「数字のことばかり追求してきて、ろくなアドバイスもくれないじゃないですか」
僕は曖昧に笑いながらモヤシ炒めを口に放り込んだ。シャキシャキとした食感が美味しく濃い目の味付けもご飯を進ませる。
「それでは今日のスポーツです。MLBでは…」
お店の端に置かれたTVでは野球について報道をしている。日本人選手がまたMLBでホームランを打ったらしい。日本中が夢中になっている選手だ。
「大川選手またホームラン打ったんっすね!このままなら本塁打王狙えますよ」
谷口さんは口に餃子を含みながらまくしたてた。
「まさか日本人がMLBで本塁打王取れるかも知れないなんて、凄い時代ですね」
大川選手の活躍は漫画以上と言われている。
「何十億稼いでいるらしいっすよ」
谷口さんは何かを妄想している。
「凄いですよね…年齢は28歳で僕と同い年なのに。同じ人間なのになんでこんなに差がつくんだろう」
大川選手は大好きで応援をしているが、自分と同い年なので引け目を感じることが多々ある。
「比べちゃダメっすよ」
谷口さんが笑いながらビールを飲み干す。TVは野球報道を終えビジネスの特集に入った。どうやらエンジニア特集のようだ。
「エンジニアって働く場所も選べて給料もいいみたいっすよ」谷口さんはタバコを吸いながらTVを見ている。いつの間にかモヤシ炒めと餃子は空になっていた。
「リモートワークできるのは最高ですよね。それに給料がいいなんて羨ましすぎる」
僕は水滴がついたコップを持ち上げ冷たい水をチョビチョビと飲んだ。今の仕事でリモートワークをするのは不可能に近い。営業はお客様と直接合って商談する方が成約率が高い。一方で社内のエンジニアはリモートワークしといる社員もいる。給料も噂では高いらしい。いつか自分も働く場所を限定されずに南の島ででも働けたらなと妄想が広がった。
「転職しないでくださいよ〜」
谷口さんが不安そうな顔で僕を見る。
「転職しませんよ。したくても僕の能力じゃ転職できるかわからないですし」
「そんなことないっすよ。でも荒田さんが転職しちゃうと淋しいっすから」
「ありがとうございます」
今の新規営業はかなりキツイ。辞めたいと思うことは多々あった。だけど新卒から入った会社で転職活動をしたことも無く、営業の成績も中の下の僕が転職を成功させることは難しい気がしていた。このお店にいるサラリーマンも皆何か不満を抱えながら今の職に居なければならない人も多いのではないかと勝手な親近感を持った。少し丸まった背中が仕事の悩みを語っているようだった。きっと僕も同じ背中をしている。
3.商談
「こちらの商品はお客様の電話対応の時間を削減することができます。1回の電話対応で10分ほど時間がかかっているとします。1日に10本以上電話があると100分は電話対応に時間がかかっている計算となります。弊社のAIを使った電話受付システムを使用して頂けばその手間を無くし、従業員様を他の有益な仕事に集中させることができます」何百回も繰り返したセールストークは自動的に口から出てくる。
「AIのシステムでの音声認識はどの程度のレベルでできるんだい」
今日の商談相手のお客様は中小企業の社長だ。決裁権を持っており、上手くいけばすぐに導入をしてくれる。
「ありがとうございます。AIの音声認識レベルは通常の人と変わりないと言われています」
この質問もいつも貰うので答えが自動的に出てくる。
「実際にAIが対応するのをご体験頂ければと思います」
僕は胸ポケットから社用携帯を取り出しアプリを起動させた。
「もしもし、株式会社アップストールの荒田と申します」
携帯の画面が波模様を映し出す。
-お電話頂きありがとうございます。株式会社FVA電話AIアシスタントでございます。お手数をおかけ致しますがご要望の担当部署、名前とご要件をお教え下さい。担当部署がご不明な場合はご要件のみお教え下さい-
流暢な女性の声が流れてくる。一昔前の一度聞いたら合成音声だとわかる機械音では無く、言わなければわからないごく一般の女性の声だ。
「経理部の佐藤様に請求書の件でご連絡しました」
僕はいつもの要領で携帯に話しかける。
-畏まりました。経理部の佐藤宛、請求書の件でよろしいでしょうか-
「問題無いです」
-少々お待ち下さい-
保留音と共にアプリに通知が届く。アプリには電話内容が記載されている。
「このアプリを社員の皆さんのパソコンにインストールして頂き、担当社員に通知が届くようになります。今までの一次請けをする負担を無くすことができます」
社長は驚いた目で携帯をマジマジと見ている。
「今のAIはこんなに流暢に話して理解力もあるのか」
恐怖感と期待が入り混じった声で社長は腕組みをした。
「今のAI技術は想像以上に発達しています。私の仕事も奪われかねませんよ」
「本当にそうだな」
社長と僕は目を合わせて笑った。声が大きくコンプラに引っかかることを時々言う社長だが僕は少しの時間話しただけで好きになっていた。
「さっそく見積書が欲しい」
社長は前のめりぎみで口早に言った。
「ありがとうございます。見積書の内訳ですが社員様事にアプリをインストールして頂き、その数によって見積書を作成させて頂きます。社員様の総数は120名でよろしいでしょうか」
「そうだ」
ここで藤原マネジャーの言葉が頭によぎる。-できるだけ高めのプランを説明して顧客単価を上げろ-
「アプリには3つのプランがありますが最初に複雑な作業は混乱をきたすので1番シンプルなプランをオススメします」
「わかった。それで見積書を作って」
「また全員にアプリをインストールして貰わず部署毎に数名アプリをダウンロードして頂くだけでも対応が可能で経済的です」
つい自分がお客様の立場であったらどのような情報が欲しいか考え話をしてしまう。例えそれが会社の売上に貢献しなくてもだ。今回も顧客単価は上げられず、販売数もマックスでは無い。マネージャーが小言を言うのが想像できて少し憂鬱な気持ちになってきた。いつの間にか外では雨が降っていた。社長室の窓に大粒の雨があたっている。
4.家族
「アイスチョコミントしかないの?」
「奥探せば他のもあるんじゃない」
母の適当な返事を背に僕は冷凍庫を探った。
実家から2駅のところで一人暮らしをしているので土日はタダ飯を食べるために実家へ帰っている。冷凍庫には大量のアイスがギチギチに詰められている。全てチョコミント味だ。姉の灯里 が買ってきてストックしたものだ。僕は姉の異常なチョコミント愛のせいで逆に嫌いになった。僕はアイスを食べるのは諦めてカントリーマームを5つ取り出して食べ始めた。
「チョコミント食べてもいいのに」
姉の灯里がチョコミントアイスを食べながら僕の隣に座った。
「チョコミントはいいや」
「変なやつ」
あなたの方が変なやつだろと思いながら僕は2つ目のカントリーマームに手を付けた。姉はチョコミントをペロペロ食べなならスマホをイジっている。家ではチョコミントを食べていつもゴロゴロしているが会社ではwebマーケターとしてバリバリ働いており、かなりの給与も貰っているらしい。
「最近仕事はどーなの?」
「良くも悪くもないよ。若干悪い」
「早く転職しなーユウにその仕事合ってないんじゃないの?給与も低いし」
「うるさいな、そんな簡単にできないよ」
「ふーん」
焼肉でも食べに行こ!ぐらいの軽いノリで転職は勧めてくる姉を見てなんだか羨ましくなった。
「私にもちょーだい」
姉は僕のカントリーマアムを2個取ってムシャムシャと食べた。甘いものばかり食べているが何故か体は細く、弟の自分でも悔しいが美人だと思う。
「カントリーマアムもチョコミント味出さないかな〜」
絶対出して欲しくないと僕は強く思った。
「今彼女は?」
「いないよ」
「だから実家にいるのね〜」
姉は笑いながら僕の背中を叩いた。
「姉ちゃんだって実家にいるだろ」
「これは親孝行よ。可愛い娘の顔を親に見せなくちゃね」
30歳を超えているのに何が可愛い娘なんだと疑問に思ったが口には出さなかった。姉は美人なのにまだ結婚の予兆が無い。自由に生きるのが好きなので、誰かと一緒に暮らす結婚生活には興味が無いのかもしれない。
「何か困ったことがあったらお姉ちゃんに言いな。アドバイスあげる」
「いらないよ」
「人生の先輩のアドバイスは大切。それに紹介してあげるかもよ〜」
「紹介!?」
姉の知人は美人が多い。僕は鼓動が早くなるのを感じた。一方で顔も仕事もパッとしない自分がそんな美人を紹介されても上手くいくイメージがつかず、勝手にテンションが上がったり下がったりした。
「どんな人がタイプなの?」
「えっ」
急な質問に僕はドギマギしてしまい思考がまとまらない。
「時間切れ〜」
姉はニヤニヤしながらリビングへ移動して、ソファにダイビングをした。ソファに横たわりなら謎の運動開始した。
「食後の運動〜」
足を開いたり閉じたりしている姉を見て少しでも期待をした自分を恨んだ。その反面悩みが無さそうな姉が羨ましいと感じた。僕は正直仕事もあまり上手くいっていない。上司との関係も良くない。プライベートでも趣味があるわけでも無く、彼女もいない。羅列していくと落ち込んでくる。楽しくイキイキと仕事をして、彼女もいるような生活は遥か遠くだ。もしかしたらそのような生活をしている人はサンタクロースのように存在せず、メディアやSNSが作りだした幻想なのかもしれない。特にかっこいいわけでも無く、誇れる強みが無い自分には間違いなく無縁の世界だ。
「また難しい顔して〜」
姉は広げた足から顔を覗かせてこちらを見ている。腹筋に力をいれているのか少しプルプルしている。同じ親から産まれたのに、どうしてこんなに顔と性格が違うのか不思議に思った。
5.社長
「何でアプリを社員数マックスで取ってこないんだ!」
予想どおり藤原マネジャーの説教を受けることになった。
「すいません」
「すいませんじゃない!プランだって簡易プランだ。前回話した顧客単価と売上数の話理解できてないんじゃないか?」
僕は無言でうなずくしかなかった。興奮気味で怒りに満ちていた藤原マネジャーの顔がサッと笑顔に変わった。
「社長!お疲れ様です!」
藤原マネジャーは満面の笑顔で社長を迎えた。気付かない内に社長が営業のフロアに来ていたようだ。急に社長が後ろに立っていたので僕も緊張をした。
「熱くやってるね」
社長は満面の笑顔でマネジャーと僕に話かけた。日焼けした顔に真っ白な歯が眩しいくらいだった。社長は大手銀行に勤めた後、30代でAIに可能性を感じて独立、起業した。10年間たらずでこの会社を社員数100名以上、売上60億以上にした凄腕の人物だ。僕も新卒の時に社長の話を聞いてAIの将来性と社長のカリスマに大きいなインパクトを受けた。
「申し訳ありません」
マネジャーはニコニコしながら汗をぬぐっている。社長も笑顔でマネジャーの肩をポンッと叩いた。
「仕事熱心なのは素晴らしいが、あまりヒートアップしすぎないようにね」
「畏まりました」
マネジャーは恐縮しっぱなしだ。社長が不意に僕の方に体を向けてきた。僕は緊張してグッと背中に自然と力が入るのが感じられた。
「荒田君」
「はいっ」
突然名前を呼ばれて声が裏返ってしまった。
「新規の契約が取れたみたいだね」
社長はマネジャーの手元にあった契約書を受取りサッと目を通した。
「これからもお客様にAI技術で貢献できるように営業を頑張ってね」
「はい」
「何かあったらいつでも社長室に来てくれ。ドアはいつも開いている」
社長は白い歯を覗かせたビッグスマイルで親指を社長室に向けていた。
「ありがとうございます!」
社長は僕の肩を2度優しく叩いた。
「藤原マネージャー、例の話があるから後で社長室に来てくれ」
「わかりました!今お伺いします」
その言葉を聞くと、社長はサッと社長室の方へ帰っていった。藤原マネージャーも足早に社長の後についていき社長室へ消えた。その姿を僕は眺めていた。嵐が急に来て去っていった感覚だった。社長のオーラ二圧倒された。そして100人以上も社員がいる中で営業の1人に過ぎない自分の名前を覚えてくれていた事に感動をした。なぜ自分がこの会社に入りたいと思ったのかを思い出した気がした。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
