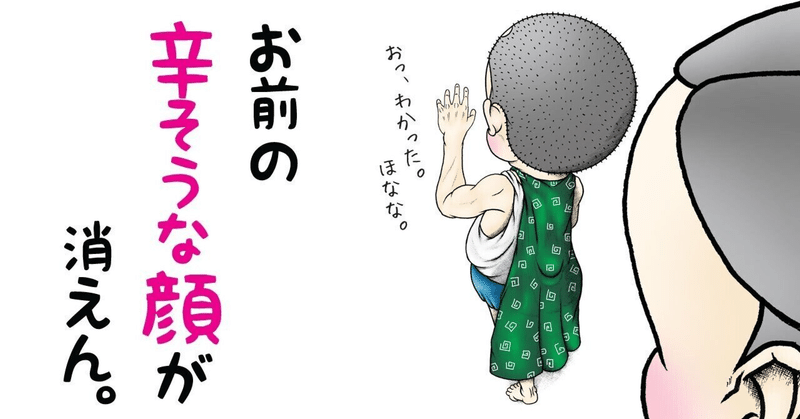
我が子が学校に馴染んでいないなら(2)
長男の場合は環境が勝手に変わってくれた
我が家の長男についても、五年生になるタイミングで転校を視野に、学校経由で近隣の小学校に空き状況の確認だけはしてもらっていた。
しかし、新たに転任してきて長男の担任となった先生とは相性が良かったため、転校はしなかったのである。
そういえば、四年時の夏には既に、長男を担任から離すべく、別クラスに変えてもらえないかと両親から○長には打診していた。ダメ元ではあったが、やはり前例なし、周囲の反応もあるため出来ないと言われている。
新しい先生になっても色々あるにはあった。しかし、質的には全然違っていて、振り返っても悪い感情はない。
結局色々あったのも、上層部の「こうあるべき」があって、そこから外れた長男に対して、上層部が「よろしくない」と明確に表明している状況があり、よって長男の担任の先生がプレッシャーを感じ始め、親もその状況に気づいて何とかせねばというモードになるから親子関係もおかしくなる、というパターンであったように思う。
なんとかするのであれば、とっとと子どもを救うべく「逃がす」ことが必要だった気がしてならない。特に、中学以降の長男を見ていると、なんで小学生の時にあんなことで悩んでいたんだっけ?と思う。
結局、学校の先生から目をつけられる状況が改善したのは、それまでの○長、副○長が、長男が小6になるタイミングでいなくなったからだった。そして新たな校長と副校長先生は長男に対して寛大であった。
こうして環境が勝手に変わり、担任の先生も、上から「指導力不足」と指摘されることもなくなり、さぞかし救われたことだろうと思う。長男と管理職との間で立ち回るのはご苦労があったはずだ。
居場所を作ってくださった先生たちへ、ありがとうございました
そして小学校生活を語る際に外せない極めて重要な存在として、長男には図書室の司書さん、そして図工の先生の存在があった。
司書さんの話
図工の先生の話
図工の先生とは直接お話ししたこともあり、その際には長男のことを時代にあった子だと思うと言われた。先生からすると、本当はやりたくなくても、みんなに合わせてやってしまう、そんな子が多いと言う。そんな中、長男は正直であり、それで良いと思うと言ってくださった。
「ほんとドラ(長男)ちゃん可愛くて」と言って、ずっと図工室にいていいよと言ってくださっていた。そして、「誰かひとり、たくさんじゃなくていいと思うんですけど、一人か二人、そんな風に思ってくれる大人がいたらそれで十分だと思うんですよ。それは絶対にいますから。ドラちゃんのこと可愛がってくれる人は。」と言ってくださった。
さらに、先生から見ても、長男が小6の時の先生たちは「当たり」と思ったそうで、私もそう思っていたが、おかげで長男は最終学年の学校生活をストレスなく過ごしている。
図工室に居ついてからは教室に行かなくなったわけだが、以降、担任の先生が毎日給食を図工室に持ってきてくださっていた。上げ膳据え膳である。途中からそれを知って、返却くらいは自分でやるようにと伝えたのだが、結局甘えてしまったと思う。
卒業を控え、給食について長男から担任の先生にはお詫びとお礼を伝えているのだが、「伝わってたんだな~って嬉しかったですね」と先生が笑顔でおっしゃってくださっていた。
卒業式はちょっと複雑だった
長男は小6になって以降、運動会は参加したが、文化祭や音楽会などは見送っている。教室にも行っていないし、友達との接点も減った。卒業式はそつなくこなしたが、その練習にも参加していない。担任の先生が放課後に長男と二人で流れを確認してくださって本番に参加したのだった。
卒業式の日には改めて私と夫より、担任の先生と図工の先生にはお礼を伝えさせていただいたのだが、先生達と夫でなんだか会話もはずんでいるようでほっとした。担任の先生は当初「公平性」を考えたときに、何をもって公平とし、どのようにクラス運営をすべきか悩んだこともあったと思う。
そういう意味では、一つの教室の中で個に応じた教育を実施することはやはり難しかったと言えるだろう。構造的にも先生一人では無理だと思う。ただ居場所だけはしっかり確保していただいた。加えて必要な所作が身につくように対応下さったのだから、もう十分だと思う。
長男については、卒業式のあとに友達と写真を撮ったりする時間に居心地が悪そうにしていた。理由の一つには、長男自身が自分が他の子と同じように行動していないことで、周りからあまりよく思われていないだろうといった思いを持ってしまっていたことがある。親もそこは同じ気持ちで肩身が狭いような妙な感じがあった。
長男に伝えたこと
卒業式での所在無げな長男を見ていると、中学に入ってからのことが一瞬不安になったし、本人も自分は社会不適合者だと自虐的に言う始末だった。最終学年は先生達との関係は良かったわけだが、同学年の子達との間には居場所はなかったのかもしれないと思った。図工室がなければ登校していなかったんじゃないかと、卒業式の日の長男を見て思ったのだった。
そして今現在、長男は元気いっぱい、授業も友達関係も全力で楽しんでいる。
そんな長男に、一言だけ、親から伝えたことがある。
それは、小学校時代に参加しなかった授業について、それは後足で砂をかける行為とも言えなくはないのだということ。
ただここはもう仕方なかったとも思っている。長男だって頑張ってみたが参加が厳しかったわけである。長男を責めるつもりは全くないのだが、しかし一言それは言っておく必要もあろうということで、父親から伝えたのだった。
結論は変わらずで
どうしても悩んでいる時は、その状況での打開策を考えることが多いと思うし、そこから出た場合にうまくいく保障もない中では躊躇すると思う。特に初めて直面した時は。我が家は2回ほど経験したことで(学校と塾)、頑張ってはいけない逃げるべき状況があるということを嫌でも学んだように思う。
移住を一例として出したが、日常の中でその子が最もその子らしくいられる時間を増やしたり、割合を調整するだけでも違うと思う。
