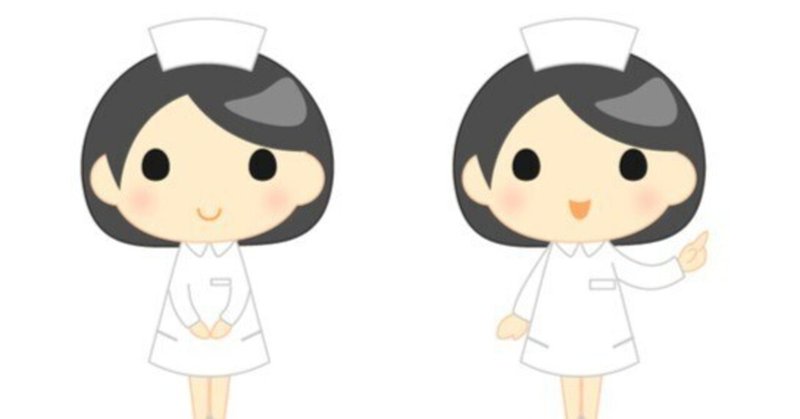
【医師コラム】新人看護師の早期退職 私の小児神経学研修
■新人看護師の早期退職が問題の深刻化
2021年、2022年と新人看護師の早期退職が問題となっています。
新人看護師は、どの病院にとっても得難い大切な人材です。私の勤務していた大学病院でも、半年以内の早期退職者が40%を超えたため、病院としてこの問題に取り組むことになりました。
プリセプターのせいではないのか?
研修システムは?
はたまた医師が厳しかったのか?
確かにそのような意見もありましたが、分析ではコロナ禍で看護学生が病院実習をほとんど、すっ飛ばして来たこと。コロナ禍で看護学生同士や看護師たちとの交流が減ったことが原因だと考えました。これまでは看護実習が2年あり、医療現場で辛い体験やレポート作成など、仕事をしていく上で大切な時間を過ごしてもらいました。さまざまな経験をして、もがき、仲間と踏ん張る。それは社会に出るのに大切な時間なのです。
それがなかったので、このような事態になったのではないか、という話にまとまりました。
■働きながらも葛藤する日々
前置きが長くなりましたが、ここからが私の話です。
私は早く経験を積みたいと小児神経学研修をするために、医局に対してケンカ同然に飛び出し、国立小児病院神経科へ行きました。
大学医局からはもう少し経験を積んでから行くべきだと言われました。しかし当時の私は、医局に残るのではなく、国立小児病院神経科に行った方が自分にとっていいと判断し、行動したのです。医師には経験も時間も必要です。迷っている時間もありません。
ですが、国立小児病院神経科に行ってから感じたことは、小児神経科医として求められるものは大きく、今の私に続けることができるのかということです。そういった思いが出てくるたびに、やっぱり大学医局に残るべきだったのか?と悩みました。けれど、弱気になった自分に「いやまだまだイケルさ」と励まし、ごまかし続けたのです。そうしていると、やがてストレスで寝られない、食べられない、病院に行こうとすると足がすくむ、というようなことが起こりました。
ただここで辞めたら、大学医局からも国立小児病院からも何を言われるかわかりません。だから、踏ん張るという道しかなかったのです。
■何が自分にとって大切なのかを改めて考えること
そんな中、私は下記のようなことを信じて行動していました。
・知識は勉強で得ることができますが、経験は積み重ねていくしかありません。
・軽~中等症例の経験だけでは奥行きは得られません。重症・複雑・難治の症例経験を積むことが絶対的に必要です。
・半人前、一人前と認められるまでは、丁稚の心構えも持っていてください。
・信じる信じないは別にして、「10000時間の法則」を濃厚に実践してみてください。
例 10時間×365日×3年=10950時間
12時間×286日×3年=10296時間
14時間×365日×2年=10220時間
だから、今頑張るしかない、と思うようにしました。けれど、「3年かけて手に入れたものと2年かけて手に入れたものは違うんだよ」と、私の姿に見かねた国立小児病院の先生に言われたのです。
その先生は外科医の経験を15年経てから、新生児科医が大変尊い医師の姿だと思い、新生児科医になりたいと思うようになりました。ですが父親と同じ外科医にならなくてはならないと悩み10年を過ごします。そして私と同じ後期研修医として新生児科医として、勤務していました。
その先生の姿を見て、そういう生き方もあるんだとようやく理解できました。私は遠回りをすることを恐れていましたが、遠回りをしたらした分だけ、何か他の人とは違う自分の道ができているかもしれないと思い、退職を決意。私は市中病院で、小児科医として過ごす中、やはり小児神経科医となりたい思いがかたまっていきましたが、3年ほどしたころ、学会発表を縁にある大学教授に誘われ、小児神経科医として、再びスタートを切ることになったのです。
それからは、時間、経験と仲間が私を後押ししてくれました。辞めていった新人看護師たちも、再び立ち上げることができますように。そう願っています。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
