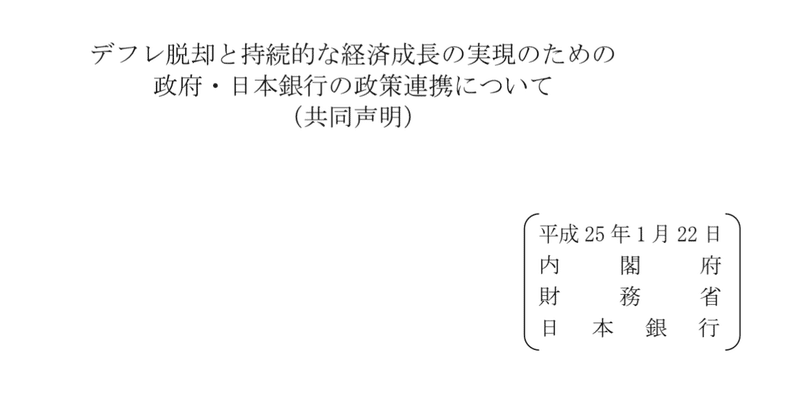
2013年政府・日銀の共同声明を読む
最近なにかと経済ニュースで話題になってる「政府と日銀の共同声明を改定するのではないか」とする一部報道。
2022年12月19日、官房長官の記者会見で「そのような方針を固めた事実はない」と否定したが、この先どうなるか分からない。
魚拓
で、そもそもこの「共同声明」ってなんなの?という話。
1.正式名称
デフレ脱却と持続的な経済成長の実現のための政府・日本銀行の政策連携について(共同声明)
です。
※通称は?→「共同声明」、「アコード」とか
※※麻生さんが「ホンダのアコードじゃねえんだから」うんたらかんたら言ってた記憶がありますが、首相官邸の共同声明のURLに「nichigin_accord」が含まれてたし、別にアコードでもいいんじゃねって思います。
ただ、今回の共同声明にアコード(accord)という訳を当てるのが妥当かどうかは分かりません。
※※※麻生財務大臣によると「ジョイントコミュニケ」だそうです。
2.誰が出してる?
内閣府(旧経済企画庁かな?)・財務省・日本銀行です。
各機関のサイト上から同じ内容の文書が公開されています。
ここでいう「政府」とは、内閣府と財務省のことになります。
なお、首相官邸のサイトでも共同声明の内容が確認できます。
3.本文と解説
以下、引用部分で特に出典を明記していないものは、共同声明の本文からになります。
1.デフレからの早期脱却と物価安定の下での持続的な経済成長の実現に向け、以下のとおり、政府及び日本銀行の政策連携を強化し、一体となって取り組む。
共同声明の目的が書かれています。2014年に消費増税をキメておきながら、「(政府と日銀が)一体となって取り組む」とは理解に苦しみますけどね。
2.日本銀行は、物価の安定を図ることを通じて国民経済の健全な発展に資することを理念として金融政策を運営するとともに、金融システムの安定確保を図る責務を負っている。その際、物価は短期的には様々な要因から影響を受けることを踏まえ、持続可能な物価の安定の実現を目指している。
日本銀行は、今後、日本経済の競争力と成長力の強化に向けた幅広い主体の取組の進展に伴い持続可能な物価の安定と整合的な物価上昇率が高まっていくと認識している。この認識に立って、日本銀行は、物価安定の目標を消費者物価の前年比上昇率で2%とする。
日本銀行は、上記の物価安定の目標の下、金融緩和を推進し、これをできるだけ早期に実現することを目指す。その際、日本銀行は、金融政策の効果波及には相応の時間を要することを踏まえ、金融面での不均衡の蓄積を含めたリスク要因を点検し、経済の持続的な成長を確保する観点から、問題が生じていないかどうかを確認していく。
経済発展と金融システムの安定を図るとする理念については、日本銀行法によるものだろうと読み取れます。
第一条 日本銀行は、我が国の中央銀行として、銀行券を発行するとともに、通貨及び金融の調節を行うことを目的とする。
2 日本銀行は、前項に規定するもののほか、銀行その他の金融機関の間で行われる資金決済の円滑の確保を図り、もって信用秩序の維持に資することを目的とする。
第二条 日本銀行は、通貨及び金融の調節を行うに当たっては、物価の安定を図ることを通じて国民経済の健全な発展に資することをもって、その理念とする。
本文に戻ります。
「物価安定の目標」といえば、共同声明に書かれているこの部分を指します。
「消費者物価の前年比上昇率で2%」とあるように、 "日本銀行" はCPI2%上昇を目指します。政府は数値目標を課されていません。冒頭の記者会見のニュース記事で、官房長官が
「日銀においては政府との連携のもと、物価安定目標の持続的安定的な実現に向けて努力されることを期待する」
と他人事なのはそのためです。今に始まったことではなく、安倍内閣の時代からずっと似たようなことを言ってきました。
「物価安定の目標」のことを、報道では「物価目標」「物価目標2%」などと「安定」が抜けている書き方がされているのを見かけます。主にヘッドラインで見かける印象があります。が、「安定」は大切です。一瞬だけ2%に到達したらOKではありません。安定して2%程度の物価上昇率で推移していくことが大切です。
「2%」って総合?コア?コアコア?どれなの?って方へ。
総合です。
平成二十五年一月二十二日に政府及び日本銀行が共同で公表した「内閣府、財務省、日本銀行「デフレ脱却と持続的な経済成長の実現のための政府・日本銀行の政策連携について(共同声明)」」(以下「共同声明」という。)での物価安定の目標における消費者物価は、消費者物価指数の総合指数であると承知している。
参議院議員大久保勉君提出物価安定目標における消費者物価指数に関する質問に対する答弁書
さて、また本文に戻ります。
「できるだけ早期に」と書いてありますが、2022年現在、物価安定の目標は未達成のままです。
「金融政策の効果波及には相応の時間を要する」らしいので、9年も10年も波及するのに時間がかかるのでしょうか?長くないっすかね?
・・・あれ?消費者物価総合は2%超えてたよね?と思われた方・・・・・だが、ちょっと待って欲しい。
実際、2022/10/28時点で日本銀行の「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」政策は継続しています。
物価安定の目標達成までこの政策を継続すると書いてあるので、未達成だから継続しているわけです。
3.政府は、我が国経済の再生のため、機動的なマクロ経済政策運営に努めるとともに、日本経済再生本部の下、革新的研究開発への集中投入、イノベーション基盤の強化、大胆な規制・制度改革、税制の活用など思い切った政策を総動員し、経済構造の変革を図るなど、日本経済の競争力と成長力の強化に向けた取組を具体化し、これを強力に推進する。
また、政府は、日本銀行との連携強化にあたり、財政運営に対する信認を確保する観点から、持続可能な財政構造を確立するための取組を着実に推進する。
「機動的なマクロ経済政策運営に努める」らしいのですが、その結果が消費増税だから参ってしまいます。
「政府」に数値目標は書いてありませんね。日銀だけに数値目標を課してるのは、流石にずるくない?
4.経済財政諮問会議は、金融政策を含むマクロ経済政策運営の状況、その下での物価安定の目標に照らした物価の現状と今後の見通し、雇用情勢を含む経済・財政状況、経済構造改革の取組状況などについて、定期的に検証を行うものとする。
今こそ経済財政諮問会議には、マクロ経済政策運営の司令塔になってもらいたいところです。
るんるーん♪
