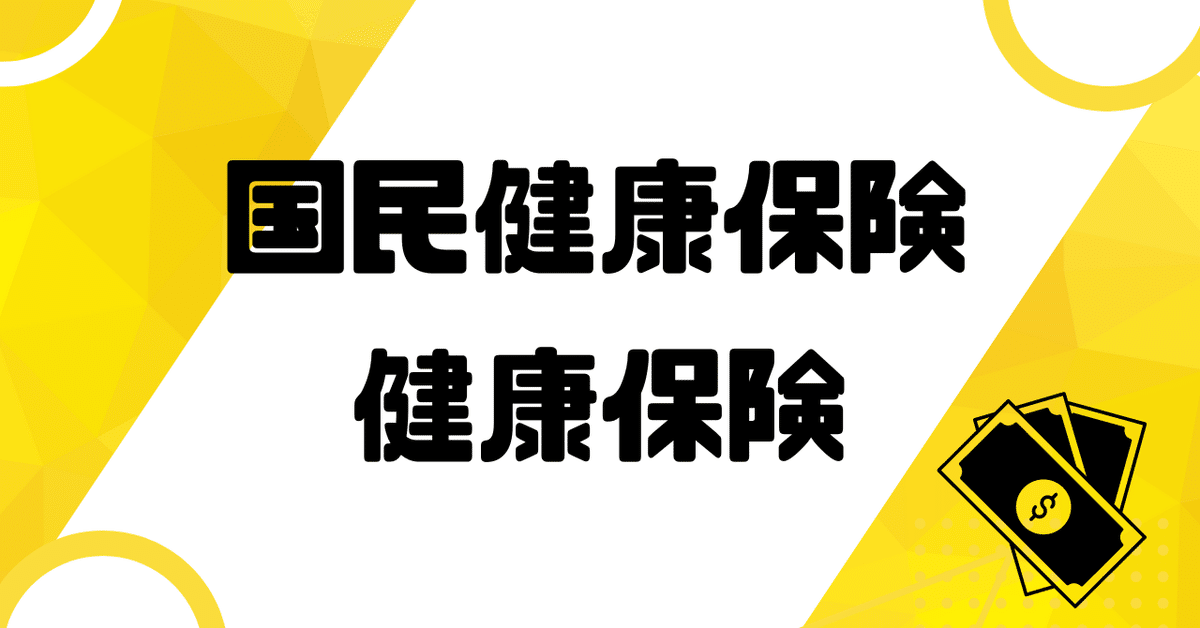
3割負担で済む!絶対に知っておくべき国民健康保険・健康保険の知識
どうも!
リテラです^^
皆さんは、国民健康保険や健康保険について考えたことありますでしょうか?
実は、これら健康保険は、皆さんの収入から毎月3〜4万円も引かれているのです。
実際に、私も給与明細を見たときには愕然としました…
そして、これだけ毎月引かれているお金なのだから、最大限それを活用しようと思いました。
今回は、そんな国保や健保の仕組みや活用法について解説していきます!
ぜひ最後までご覧ください!
はじめに
この記事を読むべき方
・国民健康保険・健康保険という言葉を、見るだけで頭がクラクラするから、シンプルに理解したい!
・そもそも、何のために入るの?毎月いくらお金払ってるの?など基本的なことを知りたい
・会社を辞めて、健康保険から国民健康保険への加入手続きをしないといけないけれど、よく分からない…
上記、悩みや疑問を抱えている方にこの記事が力になれると思います。
注意点:この記事内で話す内容は、時期・場所・政府からの発表などにより変化する場合があります。あくまで、1つの参考としてご覧ください。
絶対に払うお金
日本人として暮らしている以上、絶対にかかってくるお金があります。
それがこの国民健康保険・健康保険です。
他にも、国民年金や厚生年金などの年金がありますが、詳しくは以下の記事で解説しているので是非参考までに紹介します↓
ちなみに、私は、20代半ばに会社を辞め、個人事業主となってから、国民健康保険や健康保険(任意継続についても!)の違いを改めて知ることになりました。
そして、もっと早く知ることで自分の生きる選択肢を増やすことができることを痛感しました。
この記事を書いていく中で、国民健康保険や健康保険について私自身も横断的に知識を増やすことができたため、是非気になる部分だけでも読んでいただけたらと思います!
なぜ国民健康保険・健康保険の知識を知る必要があるのか?
もし、国民健康保険・健康保険が何なのかわからないよ!という人は先に目次から「そもそも国民健康保険・健康保険とは何なのか?」を読んでもらと思います。
さて、そもそもこの小難しい漢字をなぜ知る必要があるのか?について考えていきましょう。
その理由は大きく分けて以下の3つあります。
①医療費負担が軽減される(原則、1〜3割負担。保険証を持ってないと10割)※詳しくは参考へ
②保険証は、身分証明の公的書類として使える
③出産や病気ケガのときに、手当金がもらえる(国民健康保険と健康保険でその待遇に違いがある)
順を追って説明していきます。
①医療費負担が軽減される
おそらく多くの方は、病院へ行った際、受付の方にこう聞かれるのではないでしょうか?
「健康保険証を見せてください」
冒頭でも言いましたが、国民健康保険証・健康保険証(以下「健康保険証」と記載する)を忘れた時にこのセリフは、悪魔のフレーズになります(苦笑)
なぜこの時健康保険証を見せるかというと、医療費が3割負担で済むからです。(7歳以上70歳未満の場合)
しかし、もし健康保険証を家に忘れたらどうなるでしょうか?
その場合、一時的に10割負担を迫られることになります。(例えば、診察代等が1,500円〈3割〉であれば、5,000円〈1,500×10/3〉の額を一時的に支払わなければいけなくなります)
※後日、領収書と健康保険証を受付へ持っていくことで返金してもらえる
このように、保険証は年齢に応じてにはなりますが、本来は10割かかる医療費を1〜3割負担に軽減する上でとても大切な証明証となります。
年齢別の医療費負担を説明すると下記の通りになります↓
・75歳以上の者:1割(現役並みの所得者:3割)
・70歳〜74歳:2割(現役並みの所得者:3割)
・70歳未満:3割
・6歳(義務教育就学前)未満:2割
上記の通り、年齢と一部所得基準により1〜3割の負担で医療制度が使えるのはありがたいことですね。
また、現役並みの所得者の基準などが気になる方は以下の厚生労働省の資料を参考にしてもらえたらと思います。
参考:
厚生労働省「医療費の一部負担割合について」
https://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/dl/info02d-37.pdf
②保険証は身分証明の公的書類として使える
自分自身の身分を証明する書類は、日常でも多くのところで使われます。
いくつか挙げるとすると
・携帯を契約する
・クレジットカードを作成する
・銀行口座を開設する
など、成人を迎え、社会サービスを使うことが増えると、非常によく使うかと思います。
そして、一番よく身分証明書として使われるのが、「運転免許証」です。
しかし、持っていない…という人もいると思います。
そこで登場するのが「保険証」です!
この説明に関しては、埼玉建築士会のPDF資料が参考になるので以下に示します↓

上記資料で、注意すべきは
「保険証は、身分確認書類として2点用意する必要がある」
ということです。
そして、今後、身分証明書の基準はマイナンバーカードの登場によって変化してくると思いますが、まだしばらくの間は、上記の資料の基準が適応されていくと考えます。
ただ、身分証明書の一つとして使える点は覚えてもらえたらと思います!
③出産や病気ケガのときに手当金がもらえる
こちら国民健康保険と健康保険で違いがあるのだが、以下の資料を見ると、その違いが一目瞭然ですね。

参考:東証マネ部「国民健康保険と健康保険の共通点と違いは?」↓
注目するところにマーカーを引きましたが、特に比較すべき部分ピックアップすると以下の5つです。
1 出産手当金
2 傷病手当金
3 保険料の計算
4 保険料の支払い
5 家族が増えた場合の保険料
それぞれ、上記5つについてメリットが大きい方に数字を割り振ると
国民健康保険:3(単身者や独立し始めの人)
健康保険:1245
結果は、健康保険が国民健康保険よりもメリットの数で4つも有利ということがわかります。
3に関しては、離職する人、独立して収入が低い人(具体的には、月収が28万円以下の人)は、国民健康保険の方が、健康保険(この場合は、会社を辞めた後に前職の健康保険に2年間加入できる「任意継続」のこと)よりも有利になります。
逆に、月収が28万円よりも上になると健康保険の方が良いということです。
また「任意継続」の内容については、以下の記事を参考に↓
参考:Pe-BANK「フリーランスになるあなたにとって、国民健康保険と任意継続保険のどちらが得か」
よって、ほとんど健康保険に加入する人に軍配が上がります。
ただ、だからといって、国民健康保険はダメ!とするのではなく、その事実を知った上で、どっちの保険証でいくのか、自ら判断することがとても重要です。
そもそも国民健康保険・健康保険とは何なのか?
まず、簡単に「国民健康保険」と「健康保険」についておさらいしてきます。
国民健康保険:
国民健康保険制度は、他の医療保険制度(被用者保険、後期高齢者医療制度)に加入されていない全ての住民の方を対象とした医療保険制度のこと
参考:
健康保険:サラリーマンなど、民間企業等に勤めている人とその家族が加入し、病気やけが、またはそれによる休業、出産や死亡といった事態に備える公的な医療保険制度のこと
参考:
サイトを使って調べるとどうも小難しく感じたので、端的に言いいますと
▶︎ 一部の人を除きほぼ国民全員が平等に入れる保険:「国民健康保険」
▶︎ サラリーマンなどの民間企業などに勤めている人、その家族などが入れる保険:「健康保険」
といこうことです。
ここで定義をしっかりと押さえておくことで、それぞれれに加入すべき人がどこような人かが分かります。
そして、自分自身は現在どちらに入っている方がメリットが大きい、なども判断できると良いです。
まとめ
いかがでしたか?
改めて国民健康保険・健康保険になぜ入るかを以下にまとめます。
・医療費負担が軽減される
・保険証は、身分証明の公的書類として使える
・出産や病気ケガのときに、手当金がもらえる
上記を知り、自分はどちらの保険に入っていて、それにはどのようなメリットデメリットがあるのかを、考えていくことが大切ですね!
以上のように、このnoteでは主に「個人で稼ぎこの世知辛い生き抜く力の発信」をメインでいくので、それに賛同できる方は是非いいねとフォローをいただけたら幸いです!
また、ここで書いた記事の内容は、今後また変化する可能性があるので、引き続き記事の内容を更新していきたいと思います。
最後まで読んでいただきありがとうございました!
それでは、また^^
サポートをすることであなたの個人で生き抜く力を最大限に引き出すことを応援いたします^ ^ どうぞよろしくお願いします!
