
凌ぎの一打【麻雀】★★★
守備力の低い強者はいない。
守備力と一言で言ってもその内訳は、
・危険度認識
・カウント能力
・それまでの手組み
と細分化される。
実戦例
実戦例を見てみよう。↓

2軒のリーチを受けている場面。
ただでさえパニックになってしまうような状況だが、この場面で何を優先的に考えるか。
まず大切なのは
・手詰まっていることの確認
当たり前の話だが、これを確認するのに10秒かかっていては、1番右の牌が飛んでいってしまう。
左から自分の手牌を見ていって、3~4秒くらいで済ませたい。
この確認が早ければ早いほど、よりマシな牌を切るための思考に時間を割くことができる。
次に確認するのは
・枚数カウント
これは下家のリーチを受けたときからチェックする。
ノーチャンスに気づかなかった…!では凌ぎの舞台にすら立てていない。
今回の場面では、7mが3枚、8mが3枚見えていることを確認。
さて
・手詰まっている
・9mはノーチャンスじゃない
ここまで確認して、ようやく何を切って凌ぐかを考える。
2軒リーチで手詰まった時に思い出すべきことは
・片方に絶対通る牌を切る
・追っかけの方が本手率が高い
ということだ。
それを踏まえて、もう一度同じ場面をば。↓
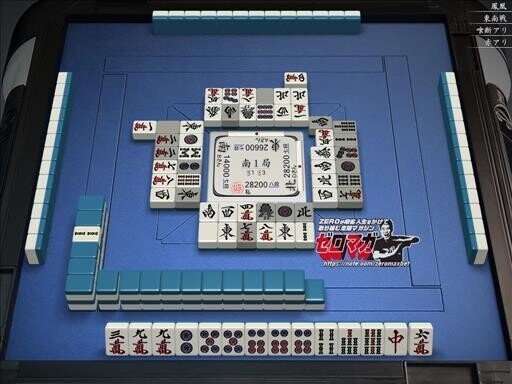
今回は先制リーチが
字牌連打→5m切りリーチ
と愚形の可能性も高いこと。加えて、追っかけリーチが親であることを考えると、とりあえず親に絶対通る牌を探すべき局面と言える。
そこで「対面の親に絶対打てない」と考えた時、親に対してほぼ通る牌が存在することに気付いた。
それはどの牌だろうか?
親の立場になってみて考えて欲しい。
ZEROの選択

打9m。
少なくとも親に69mで放銃することはない。
なぜか。
親は5m→4mと切ってリーチしている。
つまり69mで当たるとしたら1巡前のターツ選択で
4578mから5mを切ったということだ。
それはおかしい。
なぜなら先制リーチに7m8mが通っているからだ。
一方で4mは危険牌の1つ。
つまり4578mと持っていたら7m8mを落とすでしょ、ということ。
445578m
4455678m
などでも8m(7m)を切りそう。
凌ぎは戦争
こういった手牌読みは、最初の
・手詰まっている
・枚数カウント
といった基本情報の確認。そして
・追っかけが本手
・親には打てない
といった優先順位の把握、を経てから辿り着ける戦略である。
適当に打っていると、手詰まっていることの確認だけで全てのリソースを使ってしまう。
制限時間のある天鳳において、凌ぎは戦争だ。
決して気を抜いてはいけない。
おまけ&まとめ
おまけとして、今度は上手く凌げなかった例を。

上家のリーチに対し、6sがいわゆる間四間で打ちづらいなーという場面でツモった3p。
ここであなたは何を切って凌ぐか?
ストレートに6sをぶち込んでもいいんだけど、自分がトップ目かつリーチ者がラス目なんだよね。
ZEROの選択

打6p
通りそうな678pを切って立て直す算段。
しかしどうせ1メンツ落とすなら、イーシャンテン維持の打3pの方が明確に良い。
リャンメンが入ったら6sを切る価値はあるからだ。
暗刻の牌を切る…という選択肢は、盲点になりがちなんだよな。
俺だけか?w
イーシャンテンで踏みとどまることを、
「場に残る」
「生きている」
と表現する。
Mリーグの実況でも
「場に残っているのは黒沢さんだけ」
と言ったり、漫画でも
「マキオ…生きていたのか!」
などというシーンがよくある。
強者はこの踏みとどまる力が高い。
読みなどを駆使して、ギリギリまで場に踏みとどまり続ける。
しかし同じことを繰り返すが、読みを駆使するための土台となっているのは、手詰まっている確認・枚数カウントなどの基本的な部分だ。
リーチを受けたら、萎えている他家を横目に自分はそこで気合を入れ直し、通った牌はなにか?次に無筋をツモってきたら何を切るか?押し返せる可能性はあるのか?などをツモ番が回ってくるまでに考えよう。
すると余ったリソースで読みを入れることができるようになるのだ。
最後までお読み頂きありがとうございました! ↓スキすると毎回違うメッセージが表示されます!
