
あり得ない日常#63
奥さんの実家に住めるという男性はどのくらいいるだろうか。
農業が中心の貧しい社会から発展を遂げ、一人一人が会社に属することで生活ができるようになった。
国には、給料という実に明確な所得を得る人が多くなればなるほど税金を取り逃すことが無くなるというメリットがある。
また、農産物で高い所得を得ることはそう簡単なことではない。高度な工業や商業を産業として持つことで、全体の所得向上につながるわけだ。
所得が向上すると、割合で決まる税金も当然増える。
そうして、この国は発展してきた。
貧しい時代や、今も発展途上国としてある海外の農業国も、畑が無くては生きてはいけなかった。
先の大戦から高度経済成長を遂げ、21世紀前半にはすっかり就職することが当たり前に定着した頭からは想像が難しいかもしれない。
先祖代々受け継がれてきたものは、藁ぶき屋根の家と何とか家族が食べてけるくらいの作物を産み出し続けてくれる畑だけ。
山があればまだいい方だ。
お金なんてものは街に出れば手に入るかもしれない。
鶏は重要なタンパク源なので、減らしすぎないように気をつけないと、卵すら食べられなくなってしまうだろう。
畑は広ければ広いほど作物が取れる。
でも、すべての野菜を作る事はできない。
なので地域に住む人との物々交換のための作物が必要なのだ。
そうやって、乳牛を持つ家とは牛乳と交換したり、自家で作っていない作物と交換したりして食卓を豊かにするしかない。
そのための畑の維持にも労働力は欠かせない。
だから、子供は重要な労働力になる。
8人兄弟なんていう家も珍しくなかったのはそのためだ。
男の子が産まれなかった家は絶えてしまう。
そのため、跡取りとして他の家から養子を迎えることも珍しくなかった。
兄弟が多い家がほとんどなので、長男がいる家から迎えればいい。
女の子しかいない家は、婿を跡取りにできる。
そうやって代々受け継いできた家と畑を、子々孫々食うに困らないように、また自分の代で家が終わらないようにそれぞれが役目を果たしてきたのである。
多くの主義が世界を取り巻いているようだが、次に大きな戦争ともなれば、またそんな時代に、いやそれ以上に厳しい時代になるのかもしれない。
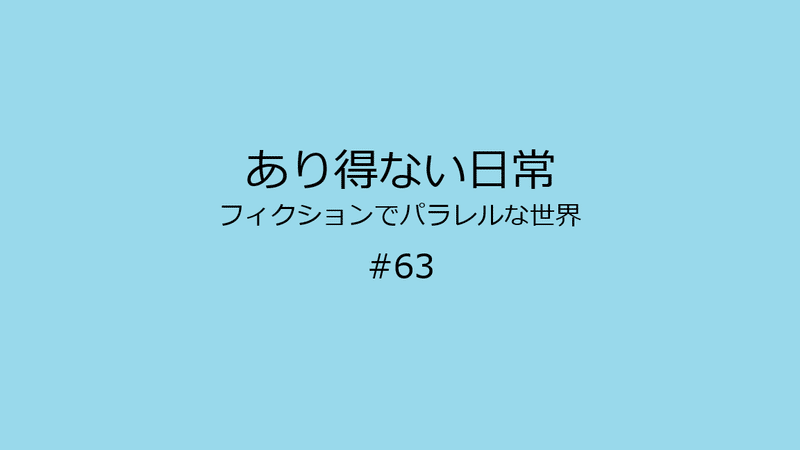
※この物語はフィクションであり実在する人物や団体とは一切関係がありません。架空の創作物語です。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
