
あり得ない日常#55
由美さんのお母さんは、肝臓がんだったという。
貧血のような、めまいのような、まあ寝ていればそのうちよくなると言い、一日横になっている日も少なくなかったが、ある日たまたま行った血液検査を皮切りに見つかった。
ただ、その時にはすでに遅かったらしい。
転移している可能性もあって、医師はさらに精密な検査を勧めたが、真実さんは痛み止めの薬を希望するだけでそれ以上は望まなかったという。
由美さんが二十歳を過ぎたあたりだった。
真実さんは50代の半ば、旦那さんのおじいさんはさらにそのひと回り上という年齢差のある、それぞれに紆余曲折ある人生の道半ば、遅くに授かった一人娘を持つ夫婦。
おじいさんはすでに定年退職をしていて、年金制度がちょうど廃止になってすぐ後の事だった。
健康保険制度は財団化し、国民皆保険制度は事実上廃止されている。
どこをどう頼ったらいいのかそれまでの常識が完全にひっくり返った社会の中、たったひとりの妻の身体に起きた大事。
当時の由美さんの目に映る父は、なんとしても救いたいという思いに無情な鉄槌を下す社会を憎みこそしないものの、やるせなさと自身の無力さを嘆いていたという。
そして、死を受け入れた様子の妻を何とか説得したい。
これからも変わらず生きていて欲しい。
当時のおじいさんは、自身も七十歳近い体で、役所や財団、そして共済組合からの情報収集で日々奔走していた。
「母はね、泣いて嫌だという私に、今までが奇跡だったのよって優しく言うんだ。あなたはお姉ちゃんの分まで、出来すぎるくらいにしっかり育ってくれたって。」
それでも、あきらめて欲しくなかった由美さんは、学校を辞めてでもお母さんに出来ることをしたいと訴えたという。
「そしたらね、怒るんだ。でもその後には必ず笑顔で、人はいつかどこかで必ず死ぬんだって。今じゃないって思う人もいるかもしれないけど、私はそれが今だとしか思えないって。」
具合が悪そうに横になる真実さんに、おじいさんは毎晩のように涙ながらに語り掛けたという。
まだまだ、一緒にいてくれよって。
由美さんは、それはもう冷静には聞いていられなかったと涙声で言った。
当時入っていた共済組合の医療補償では、入院補償や手術治療補償があったものの、結局それらを用いても延命が限界。
もうすぐ60歳を迎えようとしていた真実さんには財団からの支援も期待が出来ず、一応申請はしたもののやはり却下された。
つまり、最新の投薬や、先進医療を望むのであれば、多額の費用を自費で負担する必要があるのだ。
おじいさんが自身の退職金を全額投じても、向こう一年生き延びることができるかという程度。
あとは由美さんが、何らかの融資を受けて費用に充てるしかない。
もうすでに、そこまで追い詰められていた。
「ある時ね、お母さんが私を呼ぶんだ。そして、手を握ってさ。お父さんをよろしくねって。お嫁さんにいく姿を見届けられないかもしれなくてごめんねって。」
泣くことしかできなかったという。
いやだよって。
調子がいい時は近くの公園まで散歩をすることもあった。
春は桜が花をつけるし、鳥の声が心地いい。
寝てばっかりじゃ歩けなくなるからねって言いながら、日々確実に弱っていく姿に心が締めつけられる思いでその姿を見送りながらも、前向きに日々を生きる母にしっかりしなきゃと自分に言い聞かせていたという。
「そしたら次の日ね、ちょっと買い物から帰ってきたらいなかったからさ。散歩かな、大丈夫かな見に行こうかなって、見当たらなくて。」
いつものように相談に出かけているおじいさんに連絡をするも、「入れ違いで帰ってくるかもしれないから、落ち着いて少しだけ待ってみよう」という話になって、由美さんは家で待っていた。
しばらくして警察署から電話がかかってきたという。
「お父さんをよろしくね。」
由美さんにとって、ちゃんとした母と子の会話では、その言葉が最期になってしまった。
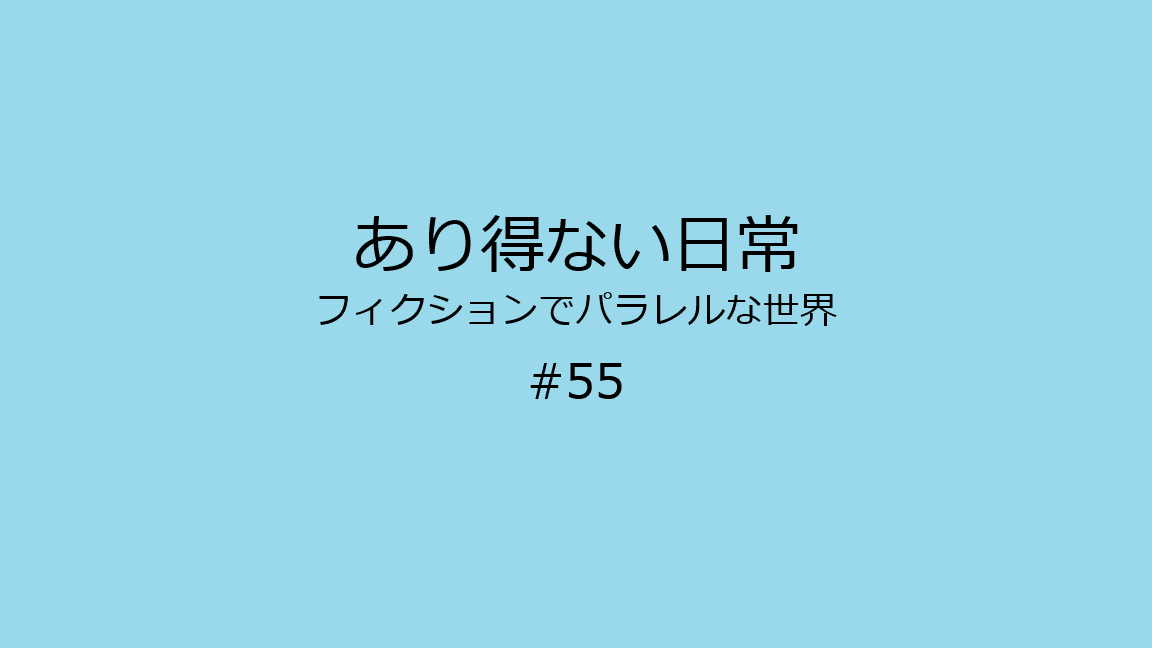
この物語はフィクションであり、実在する人物や団体とは一切関係がありません。架空の創作物語です。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
