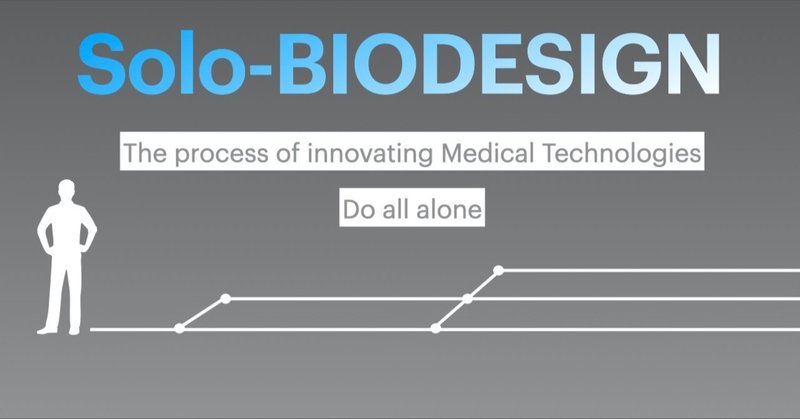
ひとりBIODESIGN 疾病の基礎1
目的:
イノベーターとして症状について必須レベルの知識を身につける。これにより、専門家などの外部の有識者に説得力を持って話せるようになる。
疾病研究の進め方:
まず、医学書や医学サイトなどの一般的な情報源などで一般的な知識の理解を深める。次に、生物学、生理学的知見から病気がどのように作用しているかという背景(病状メカニズム)を理解する。※病床研究は退屈だと言って省略すると先見の明を書くことになるらしい!
病床解析へのアプローチ:
教科書では、下記の6つの領域に注目する手法を紹介している。6つの観点に基づいて疾病を構造化しつつ、関連する疾病領域に関しても注意を払っていくぶんか広い見方をする必要がある。ただし、疾病の基礎を評価することと病気を処置するための治療方法を理解することは異なるという点を頭に留めておかなければいけない。
①解剖学と生理学
ニーズに関連した臓器や器官、体の構造に関して学ぶ。これを通して、異常な状態を理解する基礎を身につける。重要な語彙や背景を理解できるようになるのに加えて、調査でフォーカスする臓器や領域を見極められるようにする。
②疾病生理学 (病気の機能、原因、疾患の進行)
疾病がどのようにして正常な身体組織や機能に影響を及ぼすかを理解する。次に、リスクファクターと因果関係を同定する。例えば、遺伝学、年齢、関連疾病及びライフスタイルなど。最後に、疾病の進行と疾病が異常な機能に結びつく割合を理解する。例えば、日ごと、週ごと、年ごと、影響の出るピーク年齢や疾病のステージごとの変化のタイプなどの例が挙げられる。
③臨床症状
疾病が患者に及ぼす影響に関して調べる。臨床症状自体が、治療の改善やニーズへの新しい治療開発のターゲットとなり得る。ここで明らかにするべきこととしては、例えば、以下のような点が挙げられている。
・患者は何の不調を訴えて医者に会いに来ているか
・患者はどういった症状を感じているのか
年齢や世代、民族などが異なった要因かで起こる事象も考慮しておく必要があるそうだ。
④臨床転帰 (ある病気にかかったときに結果としてどうなるかということ?)
一般に疾患に関係している測定可能、かつ信頼できるデータを集める。もっとも重要な二つの臨床結果は、罹患率と死亡率。
罹患率は、疾病及び関連する合併症の重症度。その評価は、QOLについての質問やより特別なエンドポイントである6分間の歩行距離、入院期間など。死亡率は疾患に基づく死亡数から計算される値となる。
⑤疫学
疫学とは、「明確に規定された人間集団の中で出現する健康関連のいろいろな事象の頻度と分布およびそれらに影響を与える要因を明らかにして、健康関連の諸問題に対する有効な対策樹立に役立てるための科学」らしい。これを通して、疾病の発生率(新たに診断されている年間患者数)、またその時点で疾患と関連性のある全ての患者人数などを把握する。
⑥医療経済へのインパクト
この段階では、医療のトータルコスト(年間の医療費や入院費、労働経済損失)にフォーカスする。また、コスト分配に関して深く理解するために、コストは薬剤治療やデバイス治療にかかるのか、それとも入院や外来治療にかかるのかを把握する。また、どのファクターが一番の高コストなのかも把握する。(コスト削減は大きなニーズとなっているらしい)
次回は、上記を参考に糖尿病の疾病分析を行う予定である!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
