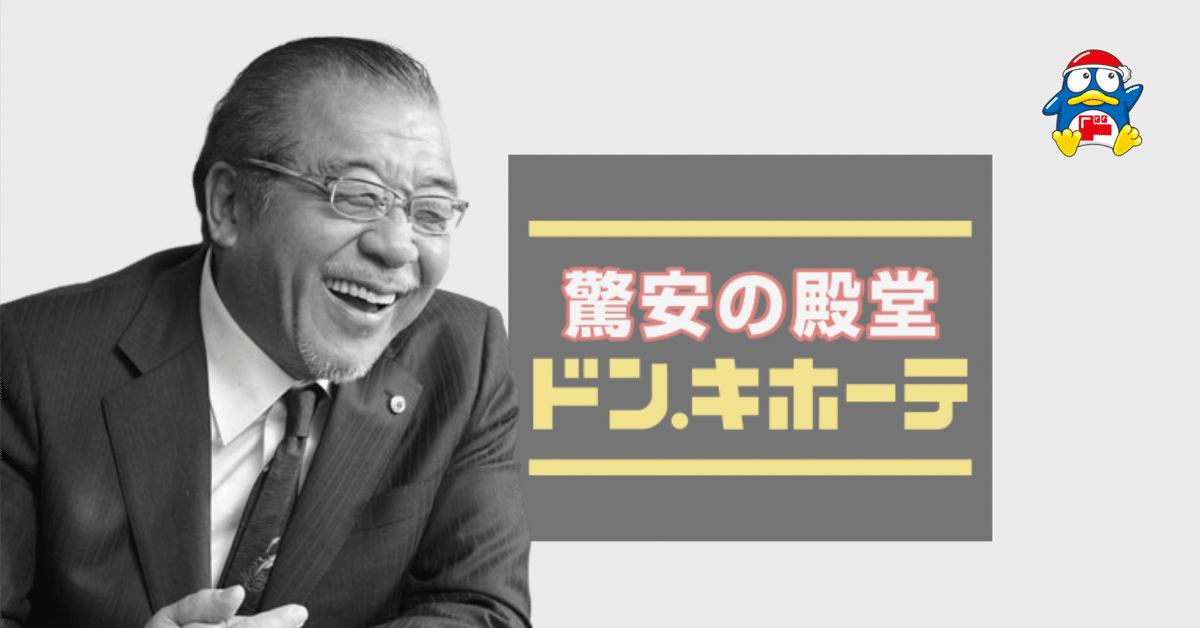
ドンキ 安田隆夫: 逆張りの安売り王
ドン・キホーテが今すごく面白い。
既存のドンキは金融がミックスされて集大成を迎え、沈みゆく船だったGMS業態を買収し「MEGAドンキ」として再建に成功。今まで取れなかったファミリー層を開拓したことで成長を持続。
尖った商品開発でPB「情熱価格」の売れ行きも好調で、終いには食を武器にグローバル展開成功への足がかりも掴みつつある。

その好調さが2.5兆円を突破した時価総額にも反映されている。
このドン・キホーテを一代で作り上げ、70歳を超えた今も海外展開を最前線で推し進めているのが創業者・安田隆夫氏だ。
ドン・キホーテに流通のプロはいらない。
(ハウツー本にある)「まずはその道の優良企業に就職して経験を積め。そこでしっかり知識を習得し、技術を磨きながら、資金を蓄えてその日に備えよう」
これは完全なウソである。
と、当時ダイエー、ジャスコ、イトーヨーカドーらが隆盛を極め、成功のレシピとなっていた「チェーンストア理論」の常識を疑い、"個店主義"・"ナイトマーケット"をキーワードに、非常識な店「ドン・キホーテ」を生み出した。
今、考えてみると経験・知識ともゼロだったからこそ、ドン・キホーテのコンセプトをつくることができた
最強の素人であり、ストリートスマートを体現する人物である。この常識外れな起業家、安田隆夫氏を徹底研究してみた。
※この記事は2万字ほどあるので、興味ある箇所だけや、いいねで保存して後で読んでいただけると幸いです。
初期
岐阜県に生まれた安田氏は、小・中学校時代はずっとガキ大将だった。
人に言われた通りにやることが大嫌いで、反抗して、人と違うことばかりやっていた。負けん気も強かった。
時は流れ、高2になると、勉強をがんばるように。
岐阜県・大垣という退屈な町と実家から、早く出て行きたかった思いで、親が納得するには東京の難関大に行くしかないと考えたからだ。
成績はみるみる上がっていき、狙いどおり慶應に合格し上京。
そして、この慶應入学が安田氏の起業の原点へとつながっていく。
周囲の華やかな慶応ボーイたちと、田舎のイモっぽさ丸出しの自分を比較して、「ああ、こいつらいいな」と心底羨み、嫉妬した。
負けず嫌いの安田氏は、その現実を受け入れられない。
どんなことになっても、こいつらの下で働く人間にだけは、絶対になりたくない。ならば自分で起業するしかない。ビッグな経営者になって、いつか見返してやろう
そう固く心に誓う。実際はじめの起業の動機として、生々しい。
この決して高尚とは言えない、ごくごく私的な情念と決意が、私のビジネス人生における原点だ。
大学を卒業すると有名企業ではなく、あえて誰でも入れる小さな不動産会社に就職し、ノウハウを吸収して独立のチャンスをうかがった。
しかしオイルショックの影響で、わずか入社10ヶ月で倒産し失業。無職のプー太郎となってしまう。
所持金5円…泥棒市場を開業
失業後、すぐに生活費は底をつくものの、特技の麻雀でプロ顔負けの腕前をいかして、賭け麻雀でなんとか食いついないだ。
だが負けがこむと、所持金5円まで追い詰められる。
今の人には信じられないかもしれないが、10円の金にこと欠いたことがあった。本当に5円しか持っていなかった。(略)仕事を探すにも求人広告の載った新聞も買えなければ、面接に行く電車賃にも足りない。
自販機にて「お金を入れたけど出てこなかった」とウソを言って、100円をだまし取り、ゴミ箱から拾った新聞で求人を探したこともあった。
このおばちゃんからだまし取った100円玉を握りしめて駅に行った。ゴミ箱からスポーツ新聞を拾い、日払いの仕事を見つけて、その100円で電車に乗り面接に行った。自分でも嫌になるほど情けない話だ。
そんな人物が今やForbes長者番付で日本9位、人間の無限の可能性を感じる。

「自分は大学まで出て、一体何をやっているのか。さすがにこれはまずい」
そう思った安田氏は、自堕落なその日暮らしにピリオドを打ち、実業の世界で勝負しようと決意した。
必死で軍資金800万円稼ぐが、アイディアは何も浮かばない。
そんな悩んでいたある日、何軒かディスカウントストアに立ち寄って、「これだ!」と見つける。
なぜかどこの店に行っても、決まって店主は、入ってきたお客をジロリと 一瞥するだけで、声さえかけて来ず、無愛想きわまりない。だが、逆に私は自信を持った。
これで商売が成り立つのなら、俺にもできそうだぞ
泥棒市場がつくった原型

こうして安田氏は29歳の時、雑貨のディスカウント販売をスタートし、開く店の名前は「泥棒市場」と名付ける。とにかく目立つしかないと考えてのネーミングだった。
売る物に最初は苦労する。ほかのお店と同じく質流れ品や企業倒産の処分品を検討するも、あまり儲からなそうだと断念。
お金を先に払ったのに納品されず逃げられたこともあった。
1日の売上が2,000円しかなく、とうとう全財産800万円は底をつき、仕入れもできなくなった。
ここまで追い詰められ気づいたのが、金も信用もないのに、まともな仕入れをやって勝てるわけがない、ということだった。
この気付きから方針を切り替え、大きなメーカーや問屋の倉庫の裏口に通い詰めた。
表からではムリでも、裏口から廃番品やキズもの、サンプルや返品商品などの処分品を格安で分けてもらえるようお願いすれば、いけると考えた。
通ううちに、色んな"訳あり商品"を分けてもらえるように。
この苦肉の策で、タダ同然で仕入れた山のようなガラクタの激安商品がヒットした。経験が無かったことが逆に功を奏したと言う。
ピンチに陥ったときも、流通業の体験があったら、廃番やサンプルなどというタダ同然のものを仕入れる発想は生まれなかっただろう。おそらく、掛け売りできちんとした品物を仕入れようと考えたのではないだろうか。(略)幸いに倒産しなくても、絶対にナイトマーケットの可能性には気づかなかっただろう。従ってドン・キホーテという店をつくろうと思わなかったに違いない。

また、仕入れた商品が次々と店に届くが、ヒトを雇うお金も、倉庫を借りるお金もないので、安田氏1人で狭い店に商品を押し込んでいた。
段ボールを積み上げ、積むだけだと何の商品か分からないので、手書きのPOPを棚に貼りまくる。
結果的に、これがドンキ名物「圧縮陳列」「POP洪水」の始まりに。これもある意味、追い込まれて生まれた発明だった。
開業数年後には、たった18坪の店が年売上2億円の大繁盛店に。流通業の素人が始めた「やってはいけない店の見本」のような非常識な店がヒットした。
ここに安田氏の「常識を信じない」哲学が詰まっている。
それは、従来の流通、販売、マーケティングの成功法則が必ずしも正解ではない、ということだ。少なくとも、それらの理論が新たな市場や顧客満足を生み出すものではない、ということの証しといえる。
今でも私は、小売業にとって最良の教師はお客さまであり、現場は最高の教室だと確信している。それを唯一の拠り所に、私は自らの素人商法を決して曲げず、自分なりに進化させていった。その根源には、「常識を信じない」という体験論的な哲学がある(これは私の生来の性分でもあるのだが)。
革命的バッタ問屋
店自体は順調だったが、雇っても従業員にすぐ辞められ、在庫管理の発想もなく大雑把経営だった。
これでは多店舗化も難しいと感じつつも、大きなビジネスは目指したかった。
そこで、思い切って「泥棒市場」を他に譲渡し、スケールするために卸専業でいくことに決め「リーダー」という卸売会社を設立した。
卸売業でもこれまでの常識とは違う手法をとる。
従来のトラックに商品を詰め込み、営業マンが全国を巡回販売するというスタイルではなく、効率の良い電話とFAXによる営業手法を採用した。
同業者からは、「電話だけで売れるわけがない」と散々言われたが、これが大当たり。
当時怪しげな会社だったため、優秀な人材を採用できず、男性社員が全員パンチパーマをあてていた状況からの「苦肉の策」でもあった。
そんな連中を外回りに出して、変ないさかいを起こされては困る。第一、まともに仕事などせずサボるに決まっている。(略)だから逃げられないよう彼らを社内にカンヅメにし、私が目を光らせながら電話営業をさせたというのが始まりだ
トントン拍子で「リーダー」は、設立数年で年商50億円という、関東最大級の現金問屋にのし上がり、毎月、何千万円も利益が出るようになる。
しかし、安田氏は満足できなかった。仕入れと販路が限られる問屋ゆえ、これ以上の規模拡大の難しさを痛感したのだ。
泥棒市場で気付いた仮説を証明したかった想いもあった。
そこで「泥棒市場で培った安売りノウハウ」×「リーダーで得た資金力と商品力」で再び小売業で勝負することに。
ドン・キホーテを開業するも、苦戦

40歳になった安田氏は、「ドン・キホーテ」という名称で小売に再参入する。
泥棒市場での体験によって、初期から「深夜零時までの営業」「圧縮陳列」等による”衝動買い”を生むエンタメなお店がウケる、と確信があった。
安田さんはその席で新業態である「ドンキホーテ」の経営戦略を私に熱く語られた。店舗も府中と杉並の宮前の2店舗しかない時の話である。人々の衝動買いを誘うエンターテインメントの要素を入れたユニークな店作りは、当時から必ずヒットすると安田さんは訴えていた。
出店立地にこだわり抜いたため、2年以上1号店のオープンまで時間がかかったが、何とかオープンできた。
だが、最初は全く軌道に乗らない。
ドン・キホーテの店づくりがあまりにも流通業界の常識からかけ離れすぎて、従業員が思うような動きをしてくれなかったからだ。
手取り足取り、マンツーマンで教えても「圧縮陳列」は単に雑多な商品の積み上げにしかならない。安田氏は当時、「そろいも揃って、こいつらアホか」と思ったという。
客はつかず、毎月1,000万円の赤字続きで、卸売の収益で補填していた。
普通なら大手量販店の幹部をスカウトして、経験者に店を任せるところだが、あえてそれをしなかった。
管理手法型の人を呼んできて、『毎月これだけ売り上げを上げてくれ』とね。でも、それをやったらミニ大手チェーンのようになってしまう。それだけはやめようと踏ん張りましたよ
そうしたプロを入れることについて、こんな発言もしている。
ドン・キホーテに流通のプロはいらない。
(略)「それじゃあ、店の運営がうまくいかないんじゃないのか」と、思われる方もいるだろう。確かに、すぐにはうまくいかないこともある。しかし、それはそれでいいのだ。プロとは、安定を好むものだ。自分の積み上げた知識やノウハウを壊すことを嫌う。
ドンキ、最大のサクセス要因の誕生
悩み抜いた末に、安田氏は発想を変えた。
サラリーマンである社員に理屈を言っても難しいので、自分が味わった疑似体験をしてもらおうと、「教える」のでなく「自分でやらせる」ことにした。
それも、一部ではなく思い切って全部任せることにした。
結局、独自の経験値を言葉で共有することは不可能なのだ。すなわち、「原体験の未共有による意識の乖離」というやつだ。これが最も辛い、創業期最大の生みの苦しみとなった
従業員ごとに担当売場を決め、仕入れから陳列、値付け、販売まですべて丸投げした。しかも、それぞれ専用の預金通帳を持たせて商売させた。
すると、担当者は到着した商品をすぐ、目の色を変えて陳列するようになった。自分で好き勝手に仕入れた以上、責任を持って売り切る意識が芽生えたのだ。
皆必死で考え、いつの間にか圧縮陳列とドンキ的仕入れ手法を勝手にできるようになっていた。
結果的に私は、「泥棒市場」時代の自分と同じ環境に彼らを追い込み、そこでの原体験を疑似共有させたことになる。要は自ら考え、判断し、行動する「体験環境」を用意してやれば、従業員たちに〝頭脳と創造性〟がひとりでに育ってくるのである。
これが、のちにドンキ最大のサクセス要因となる「権限委譲」「個人商店主システム」の始まりだ。またも現場で格闘していたことで生まれた方法だった。
こうして1号店は軌道に乗り、年間5億円しか売れなかった店が3年目の売上で14.4億円、さらには月商4億円の大繁盛店にまで化けた。
ただ、守りを固めていたことで、2号店開業まで4年かかることになる。
私は万年強気で攻撃的な経営者、と世間から見られているようだが、実際は違う。むしろ私の実感としては、守りのほうが得意な経営者だと思っている。(略)だから私の信条は「攻めは他人がやらないことをアグレッシブに。しかし守りはベーシックに」だ。そもそも守りの基礎ができていなければ、アグレッシブな攻撃など怖くて仕掛けようがない。
「権限委譲」「ナイト・シングルマーケット」「CV+D+A」
ここまで歴史を辿ってきたが小休止し、この重要な3ワードを安田氏の考えとともに深掘りする。この3ワードはドンキの根幹であり、安田氏の本・発言、そして会社HPなど度々登場している。

ほかの企業がマネできないのも、このワードの1つ「権限委譲」に集約されていると断言するほどだ。
深夜まで営業して、しかもフランチャイズで展開しているわけでもない。それなのに低価格でにぎやかなお店作りをしている。
この矛盾をいかにして解決するか。ここのノウハウがわからないから、他の企業は真似できないんです。
我々は、なぜできるのか。そのヒントはやはり権限委譲です。
権限委譲
各売場担当者には大幅な仕入権限や、プライシング、自由裁量権が与えられていて、個店に委ねられている。
逆に本部は個人が出す売上などの結果を厳しくチェックし、それが報酬や待遇に直結する。半年ごとに報酬が変わる「半・年俸制」を導入している。
安田氏もファンドマネージャーのようだと表する。
私どもの店舗のスタッフたちは、金融商品ではなく実態商品を取り扱っているファンドマネージャーなんですよ。
本当にそれほど権限移譲している。他の個店経営と名乗っている一般的なチェーンストアとは根底から違います。
そしてこの権限委譲に、ゲーム的競争原理を持ち込むことで更に上手くいく。これくらい権限が渡されていると、経営の”疑似体験”ができるし、仕事が「ワーク」から「ゲーム」になり面白くなるという。

中でもユニークなのは、営業本部を2部制にわざわざ分け、社内にライバルを作ったことだ。(いまは統合した)
意識的に競い合わせて切磋琢磨するように考えたもので、これは企業内に2つの会社があるようなもの。
ドン・キホーテという業態にライバルが不在で、同業で張り合える競争相手がいなかったのもその理由だ。
ライバル不在は、強さでもあるが弱さにもなる。オンリーワン業態として駆け上がるのは早いが、それだけに成熟化も早く、成長の限界にぶち当たる可能性が高まるからだ。 私はそれを懸念し、あえて社内にライバルを作った。しかも徹底的に張り合えるよう、意図的に自己完結的な組織にした。
人事交流も一切なかったから、完全に別会社のようなもので、仕事の進め方も人事評価の仕組みまで違った。それでも口を挟まず、結果だけを問う究極の権限委譲をした。
この2つの営業部の部長はそれぞれ、現場上がりからこの切磋琢磨で急成長の原動力となり、2人ともがドンキの社長になった。
そう、これは人材育成システムとしても機能していたのだ。
上から教えて育てる「教育」ではなく、競わせて育てる「競育」のほうが、はるかに身につくものが大きく早い。つまり仕事のゲーム化による競い合いは、二重の意味で重要な人材育成システムなのである。
このように「信じて任せる」ことが安田氏の権限委譲スタイルであるが、プロセス管理はむしろ危険であり、その代わりに社風とモラル・倫理を整えることでヘッジするのが重要だと説く。
そしてパフォーマンスを測定することでチェックする。
プロセスコントロールをしても保証はないですよね。つまり、管理型の徹底で全てのリスクヘッジができるわけではない。だったら、どのみち保証がないのだから、信じた方が良いと思います。プロセスコントロールはかえって危険です。
(略)そして、権限を委譲していく代わりに、モラルは向上させないといけません。質実剛健な社風に明確な倫理基準、そしてチェッキングは当たり前です。チェッキングなくして権限委譲はありえません。
ナイト・シングルマーケット

ドンキがオープンした1989年は、ダイエーをはじめ既存小売チェーンによって「主婦・ファミリー」×「昼間の市場」は開拓され尽くされていた。
そんな中、ドンキが目をつけたのが「ナイトマーケット」と「シングル層」だった。
ナイトマーケットの発見は、泥棒市場の体験にも遡る。
当時、安田氏が閉店後に作業をしていると、「まだやってるの?」と営業中と勘違いされ、道行く人に声をかけられることが多かった。
1円でも売上が欲しかった安田氏は、彼らにモノを売るようになる。
深夜に来店するお客はアルコールが入ってることもあり、ゴミ山の商品も面白がって買ってくれた。ここに安田氏は可能性を見出した。
たとえば、「もしかしたら書けないかもしれないボールペン一本十円!」などと人を食ったようなPOPもバカウケした。私はそこに、未開拓かつ大いなる市場の可能性を見出したのである。
「夜のお客さまは、主婦など厳しい買い物しかされない昼のお客さまとは全く違う」 それに気づいた私は、進んで深夜営業を開始した。
こうした現場経験から、買い物は目的買いだけではなく、衝動買いという買い方もある。人は目的が無くても買い物をする。
ということを安田氏は掴み、ナイトマーケットをもとに衝動買い業態としてドンキを作り上げることを目指した。
昼のお客さんは、買う商品が決まっている目的買いだから、見やすく、買いやすい従来の陳列でいい。ところが深夜のお客さんは、ほとんどが衝動買い。唯一、消費行動の中で残された衝動買い市場を業態として作り上げたかった。これは夜祭りに集まる心理と同じなんですよ。
また、シングル層の拡大は、人口動態的に確定的な未来だった。

そして不況期にあっても、都市部に住む実家暮らしシングルや、子無しカップルは豊かだった。
さらに日本の小売チェーンは、分かりやすい「デイタイム・ファミリー」に群がっていた一方で、「ナイト・シングル」はうまい具合にコンビニが種まきしてくれていて、丁度良いチャンスがあった。
そこをドンキが刈り取り、真空地帯で急成長した。
CV+D+A

ドンキの業態は、「CV+D+A」と定義されている。
要は、"便利で安い”だけでなく、"楽しいお買い物空間"を作ることを重視したコンセプトということだ。
実際モノを売ることより、空間づくりを指導されるという。
軽部氏が入社したとき、真っ先に教わったことが「物を売るんじゃない。空間創造なんだ。面白い空間ができれば、ついでに物が売れるんだ」ということだった。
たしかにドンキは「激安」を謳ってるし、それを目的に来店もされるが、全商品がどこよりも安いわけではない。
「激安商品を入手する行為」ではなく、「激安感を楽しむ行為」を提供している「買い物の劇場」というのが安田氏の整理だ。
モノではなく、流通を売っているという表現の仕方もしている。
つまり、われわれが売るべきもの、勝負すべき土俵、そして差別化のポイントは「モノ」ではなく「流通」なのである。
この独特な業態を構成する要素が「スポット4割の商品構成」「圧縮陳列」「POP洪水」である。
スポット4割の商品構成

商品の構成を定番6割、スポット4割にすることで、常に4割の商品が入れ替わる。いつも新発見がある売り場となり、飽きない体験を提供できる。
衝動買い客に対応するには
静止画ではなく動画のような店でなくてはならない
と、商品がスポットで変わることで衝動買いを誘うと言う。
そしてこれほど機動的だと、本部管理では実現が難しい、と業態の特異性と先述した権限委譲マネジメントが紐づいている。この矛盾を解決してることがドンキの業態を唯一無二にしているポイントだ。
それには、とても本部管理では追いつかない。各店の自己完結型にするしかないんです。
おまけにスポット商品は利幅も大きい。定番商品の粗利率が20%前後なのに対し、スポット商品は30%前半。
つねに需要のある定番商品の横に、安さを強調したスポット商品を陳列。
ついで買いを喚起したり、定番商品を多少安く販売しても粗利ミックスで利益を確保している。
圧縮陳列

一坪当たり100品目以上をぎゅうぎゅうに詰め込む「圧縮陳列」により、ジャングルのような売り場に仕上がる。これが”宝探し感”ある買い物の楽しさにつながる。
「人は目的が無くても買い物をする」というインサイトはこの陳列にも生かされている。
「見やすく、わかりやすく、買いやすく」は、常識ではないのである。これは一定の顧客層にのみ通用する〝ひとつの〟陳列方法にしかすぎないのだ。
(略)しかし、夜中にコンビニで雑誌を立ち読みしている人々のように目的買い意識の稀薄な顧客層には、この手法は効果がない。「何か面白いことはないか、何かいいものはないか」という半分暇つぶしで店に来ている人たちにとっては、設計図どおりの整然とした店など、なんの刺激もなく、つまらないだけなのだ。
圧縮陳列で「見落とし感」「後ろ髪引かれ感」を演出し、また来店したくなる飢餓感、来店動機も作り出す。
常にお客さまの”見落とし感”が残るように演出し、お客さまが「後ろ髪を引かれながら」店を出るような気持ち、すなわち「近いうちにもう一度来たいな」と思っていただかなくてはならない。
その狙いは、「(お客が)常にチェックしないと気がすまない店」にすることだ。これがドンキの店づくりにおける、要諦中の要諦である。
加えて、スーパーを上回る品揃えなのに、店の広さが1/5〜1/10で済むという坪(販売)効率を高めると共に、バックヤードも不要にするメリットもある。
POP洪水

もう1つのドンキ名物が、洪水のように店中に貼られているカラフルなPOPである。
例えば「売れば売るほどドンキは赤字」のようなPOPで楽しい気持ちを演出する。
また、スポット商品は定番商品とちがって、単に並べておくだけでは価値が伝わらず売れないため販売力が求められる。その上、返品ができないリスクもある。
そこでPOP洪水やジャングルのような売り場によって、スポット商品の価値を届けたり、顧客の店内滞留時間を延ばして、衝動買いを増やす販売力UPの武器としても機能している。
まとめると、、、ドンキは”圧縮陳列”や"夜の時間"など上述した要素を組み合わせることで、「時間消費型流通業」として価値を提供している。
ドン・キホーテは「もの」を売ってはいるが、それが業態成立の唯一の本質ではなく、ドン・キホーテで面白い時間を過ごす、という行為が成立する「時間環境」こそが、ドン・キホーテという業態を存立させている大きな中心要素なのである。
多店舗展開と株式公開

1号店から4年たった頃、2店舗目を出店するが、1号店のときと同じく場所探しに苦労する。
待ちの姿勢では解決しないと思った安田氏は、業界新聞で今後の店舗リストラ策が報道されていた大手チェーンに飛び込み訪問し、「退店予定物件があれば、ウチに任せてほしい」と持ちかけた。
ドンキ独自の「ソリューション型出店」という手法の誕生きっかけだ。
これは居抜き出店とは異なり、本来は退去したいが、違約金をとられたりと契約期間の縛りがあって、営業せざるを得ない店舗を肩代わりしてその店舗に出店するというもの。
相手方のメリットも単なる居抜き出店より高くなる。
こうして、大手チェーンが退店したがってる店舗にソリューション型出店をし、実質的に大手の店舗開発力を格安で手に入れることで出店を拡大していった。
93年に2号店を作り、出店が加速するとどんどん売上が伸びていく。

ちょうどこの頃に社内でも「将来の株式の公開もあり得る」と発言し始める。
ただ初めは能天気に
株式を公開すれば大金持ちになれる
と浮かれていたという。
当時のドンキは安田氏の願望を叶える道具でしかなく、「社会の公器」となるために我欲を捨て社欲へ転化しなければと考えた。
そこで「公私混同の禁止」「役得の禁止」「不作為の禁止」「情実の禁止」「中傷の禁止」の御法度五箇条を定めた。
これは社内のルールのためでもあったが、同時に安田氏自身が「創業経営者にありがちな独裁者や暴君にだけは絶対なるまい」と、自らを縛るためのものでもあった。
あの時点でドン・キホーテは、安田商店から企業へと生まれ変われたのではないか。私の中でもドン・キホーテは、個人の欲望と野心を叶える手段から、社会的任務と社会貢献を遂行するための対象物に、明らかに変質した。
そして、1号店の開設から8年目、スピード店頭公開を果たす。

上場後も5年で売上7倍、利益10倍の驚異的なグロースを維持。無借金経営でここまで到達したことも凄みを増す。
順調に伸び続け、50歳の頃には年商1,000億円を超え一部上場企業となった。ドンキ業態をスタートして10年余りという速度だ。
目立った競合が出なかったのもドンキが独走した理由だが、それは”安さ”と”楽しさ”という矛盾をバランスしていることが重要であるという。
結局、多くの企業はどちらかに振ってしまうんですよ。とことん販管費を下げて安くするか、お店のクオリティを上げてリッチにするか。
でも、どちらかに振ってはいけない。
できるだけ低価格にしたい。だけども、お客さまが面白いと思う店頭も譲れない。この永遠に相いれない矛盾を、どう実現し改善するか。
この矛盾のバランス方法の手段が、上で触れた店舗への大胆な権限委譲であるが、これもまた権限委譲と多店舗チェーンという相容れないものを両立していて、カンタンに真似できない。
参入障壁の極めつきは、マネジメントそのものにあるだろう。(略)少なくとも通常のチェーン企業が当社のような権限委譲システムを採用すれば、すぐに現場は大混乱をきたし、それこそ企業としての体を成さなくなるだろう。
こうした矛盾を両立させることを安田氏は「止揚ビジネス」と呼び、重視している。
すなわち、どこにでもある並みの企業は「あちらを立てればこちらが立たない」に留まるが、勝ち組企業は「あちらもこちらも立てる」能力を有するがゆえに、現代の勝ち組たり得る。
ごく単純に言えば「美味しくて安い」とか「早くて正確」といったようなことだ。だから、今どきの成功ビジネスにおける必須要件は「止揚(しよう)への挑戦」にある。
二者択一の「OR」ではなく、「AND」という言い方も。
結局、ビジネスというのは二者択一とかではなく、常に「こちらも立て、あちらも立てる」という「AND」でなければ成功しないからだ。
つまり、「AND」を止揚と捉えるなら、そもそも止揚すべき二つの事柄が矛盾するというふうには考えないということ。たとえば、塩と砂糖を混ぜるといちばんいい味が出るように、料理の世界では「AND」が当たり前だ。
経営もまったく同じではないか。実際に実現するのは難しいことではあるが、「AND」が成功の要諦なのである。
ドンキは「便利」「安い」「楽しい」という相反する3つの要素を止揚したから爆走できた。
成長の鈍化と失敗
ずっと勢いよく伸びてきたものの、2006年6月期に売上成長が13期ぶりの10%台に留まってしまった。また、経営効率も落ちてきて、この頃から安田氏はドンキという業態の成長の限界を感じ始める。

限界点を意識せざるを得ない状況が7〜8年後に来る
次の一手が何もないというのは、経営者の怠慢だ
と、この年以降の次なる成長のために、業態開発とM&Aに乗り出していく。
一つ挙がったのがコンビニだった。2000年代に流通業で利益を上げていたのが、コンビニとアパレルSPAしかなく、今からSPAは違うと判断し、一番巨大な市場がコンビニだったからだ。
しかし、単にコンビニに参入しても難しいため、3割引で売るというコンセプトと、集客のために弁当・総菜を差別化することにした。
そのためドンキとしては、”中食”のノウハウが欲しかった。
そこで持ち帰り弁当を運営する「オリジン東秀」に目をつけ、オリジンの株式を一部取得。ドンキとの共同プロジェクトを持ち掛けるも、中々話が前に進まなかった。
最終的に安田氏はオリジンに敵対的TOBを実行するに至るが、イオンがホワイトナイトで現れて頓挫してしまった。

仕方ないので結局、自前で「情熱空間」というコンビニ業態を開発することに。
だが、想定以上にコストがかかり上手くいかず、「情熱空間」は失敗しわずか1年で撤退した。
数店舗開いた時点で、私は当時の担当者に「すまん、俺が戦略を誤ってしまった。申し訳ない」と謝りました。
決して担当者たちのミスではないから、やっていた人には一切ネガティブな人事はしないことを約束して、撤退しました。
コンビニのシステム産業としての側面を理解できてなかったのが原因という。
最も難しいのが、システム投資が膨大なこと。我々にはシステム的な素養が、あの時点では根底から欠けていたし、そうした人材を獲得するすべもなかった。(略)
あの情熱空間の店舗は、当時のセブンイレブンより、一日の売上は高かったんです。だから、商売はうまかった。ただ、システム産業としてのコンビニという側面を、本質的に理解できていませんでした。
GMSの再生でさらなる飛躍

常に新たな業態創造をやり続けるのがドンキであり、撤退戦を上手くやりながら、めげずに挑戦を続ける。
ことほどさように、商売と経営は難しい。もっとも新たな業態開発は、十の挑戦、いや百の挑戦で一つか二つ当たればいい方である。大切なのは、傷を大きくしないうちの見極めと見限りだ。早期撤退を断行するからこそ、次の挑戦が可能になる。
コンビニの次はGMSに目をつけた。
少子化時代において、若者ターゲットの既存ドンキ業態の限界を打破するためと、ドンキが弱かった食品部門が欲しくてGMSである「長崎屋」を買収した。
50億円の赤字だったが、買収後MEGAドンキへ業態転換を進め、店舗あたりの平均売上高は2倍に拡大。4年で黒字化を達成して、GMS再建に成功した。
GMSの最大の問題は、売り場のほとんどを占める非食品が売れないことにあった。一方、ドンキは非食品に強く、生鮮食品への知見がなかったため、相乗効果が抜群だった。
ドンキお得意のエンターテイメント性のある売り場を作り、そこに食材購入で日常使いするGMS利用客を取り込むことで、食品をフックに集客して非食品への購入を増やしていった。

MEGAドンキは、既存のドンキ業態とも差別化されており、ドンキでは手薄だった昼間のマーケット&ファミリー層も開拓できるようになり、新たな成長のドライバーを手に入れられた。
安田氏に言わせれば、ドンキとMEGAは同じ総合ディスカウントストアでありながら対局的な業態であるという。
ドンキという業態は客層と利用の仕方がかなり絞り込まれており、逆にMEGAは間口の広い展開がなされる。それもあり、ドンキという店が好きか嫌いかと人に尋ねれば、どちらかにはっきりと分かれる。ドンキはそれを確信犯的にやっている。一方、MEGAは特に好き嫌いを言いようがない業態だと思う。こちらは「なくては困る店」を目指している。
長崎屋を再建しGMSという業態の再生に自信をもったドンキは、ダイシン百貨店を買収しこちらも再生に成功。
これら成功から成長可能性を見出したが、難題にぶつかる。従来のドンキと違って、MEGAドンキを出店できる大きな物件は限られる上に、競合に警戒されてドンキに物件を渡そうとしなかった。
ではどうすれば大量出店できるのか。出した答えがユニーへの経営参画だった。ユニー・ファミマHDの筆頭株主である伊藤忠商事の社長と、安田氏が会談したことがきっかけになった。
2017年、ユニー・ファミマHDからユニー株の40%を取得。2019年に残る60%を買い取り、完全子会社化した。

19年に業態転換した25店舗は、1年ほどで
売上高が332億円→466億円(+40%)
客数が1,513万人→1,893万人(+25%)
粗利益高も75億円→102億円(+36%)
と大幅に改善し、売上構成も非食品が伸びた。ドンキパワー恐るべしである。
ドンキ流のPB商品
2009年には、PB商品をスタートさせた。
変化に対応しづらいPBにはずっと否定的だったが、規模が巨大化したことで、お家芸であるスポット商品が全店に回らなくなって、品揃えバランスが崩れてきたからだ。
こうした否定的だったPBへの取り組み変化や、GMSへの業態拡張はじめ、”変化”することも安田氏の信条だ。
結局、今いちばん強い小売業は「毎日創業」ができる企業である。
そのためには、未来予測よりも、すぐ変化対応できる状態を作ることだと。自らを「変化対応業」とも言っている。
だが、未来の予測は極めて困難であり、不可能といっていい。それ故、打つべき手は「変化に即時対応できる柔軟性を維持すること」に尽きる。その結果として、未来予測の的中率を上げたと等しい状況に至らしめることができるのだ。
圧縮陳列などでさえ、変えることを厭わない考えだ。
ここで誤解されがちなのが、ドン・キホーテは「圧縮陳列」や「動画の売り場」を絶対セオリーとしていると思われることだ。そんなことはない。これはただ今現在、最も有効な手法であるから実行しているにすぎない。時代に合わなくなれば、すぐに変える。
PB開発に話を戻す。PBのコンセプトは、とにかく低価格で、メーカー品についている機能を省いて必要最低限だけ残すこと。まず先に販売価格を決め、その価格に合せて開発している。

更に近年パワーアップし、↑のような独特な長文コピーを毎週議論しこだわっている。
SPAと明確に違うのは、生産まで踏み込まないことであり、”編集小売り”に強みを置くドンキならではの戦い方を意識している。
象徴的なのは、GUの「990円ジーンズ」に対抗して販売した「690円ジーンズ」。
GUはSPAであるため商品そのものから上がってくる利益が構造上高く、同じ土俵で戦うのは不利である。そこでドンキは流通粗利で勝負した。
商品そのものから上がる粗利にそもそも大きなハンディがあるのだから、やはり前項でも触れたような独自の流通戦略による付加価値で粗利を稼がなければならない。すなわち、商品粗利ではなく流通粗利をとれ、ということだ。
つまり、このPBにおいても上で触れた「時間消費型流通業」として、流通の付加価値から利益を取ろうという発想である。

売上1兆円超のドンキの中核「ディスカウント事業」において、PBの売上比率が18%近くまで成長してきている。
”日本”を武器に海外へ

はじめの海外進出はひょんなキッカケだった。ハワイで4店舗展開していたダイエーUSAが手に入ったことだ。
元々は海外に行く気すらなかった。「海外よりも先に、国内ですべきことがまだある」と考えており、自分の代でやることじゃないとまで思っていた。
しかし、既に開発済みの物件かつハワイという立地の好案件が回ってきて、これは二度とないチャンスと思い、海外進出を決める。
もともと出るなら米国だと思っていました。アジアはそもそもドンキっぽい。香港の日本人街なんて行ったら、ドンキよりよっぽど猥雑です。日本でも下町より山の手の店の方が売り上げがいい。周囲と違えば違うほど、ドンキは売れるのですよ。
このように当初の海外戦略は成熟した国での展開で、北米中心に出店しておりアジアには出していなかった。
しかし方針を転換しアジアに目を向ける。2015年に安田氏がシンガポール移住し、日本の食材のあまりの高さに憤りを覚えたことがきっかけだ。
独自の考えを作り込んでるのに、やはり”変化対応”する華麗な朝令暮改ぶりだ。これはユニクロの海外展開のときにも垣間見える。
安田氏が憤ったのは、日本の食材の値段が高いことは流通の問題ではなく、ハーモニープライスという専門問屋が横並びで価格を維持していることによって、値段が高止まりしていたからだ。
また、ターゲットが数万人しかいない駐在員向けだったことも、プライシングが高くなっていた原因だった。最初から狙ってる需要が小さいので、高く売らざるを得ないからだ。
そこをドンキが、マーケットの大きな現地の人向けに、価格破壊することに勝機を見出した。
法律違反は許されませんが、おきて破りならば当社の得意分野です。当社の仕入れ力で調達した商品を直接輸出するなど、さまざまな手を尽くして商慣習に風穴を開け、価格破壊を実現する。従来価格の半値を目指します。
目論見は当たり、1日10万円売れれば日本なら大騒ぎのイチゴが、タイでは1日2〜300万円売れ、シンガポールでは焼き芋が1日3,000本、香港でもモモに行列ができて1日何百万円も売れた。

テナントベースで、ルイ・ヴィトンよりも、海外ドンキの方が売上が良いらしく、安田氏も、日本の食品のポテンシャルは自動車産業に次ぐほどだと。
特にアジア圏では、日本ブランドの食品はヴィトンやシャネルのような、ブランドものの位置付けですからね。(略)私は日本の食品は、自動車産業に次ぐ輸出の花形になれると思っています。
こうして日本食を武器にする戦略が決まりアジアへの出店を加速。過去3年でアジア店舗数を19→30→40と増やし、今後2年で更に1.6倍に増やす計画にもなっている。
そして最後の勝負としてアメリカにも照準を合わせ、鼻息が荒い。

圧倒的にアメリカ人は、消費力がありますし、食う量もケタ違いですし、何でも買ってくれます。
アメリカはなんとしてもモノにしたい。アメリカくらい待ち望まれていておいしいモノが供給されてない国はない。
ビジョナリー・カンパニーへの挑戦
歴史的には前後するが、2010年(61歳の)頃に安田氏は「ビジョナリー・カンパニー」を読み、ドン・キホーテを自分の死後も繁栄する会社にしたいと考えた。
ちょうど企業経営の追求と、自らの欲求の間で迷っていた時期でもあった。
あえて当時の心境を正直に告白すれば、企業経営の追求と、自らの恋々とした欲求の狭間で大いに迷い、私の心は千々に乱れていた。
元々安田氏は、慶應同級生への嫉妬から始まった起業家人生である。
「もっと金を儲けたい」「認められたい」といった俗なものが、個人的な欲求としてある中で、ドンキをどうするかという岐路に立つ。
そんな迷いの中、「ビジョナリーカンパニー」を読み、これ以上金も名誉もいらないという境地に至った。
そこで源流という、企業理念集を作り始める。
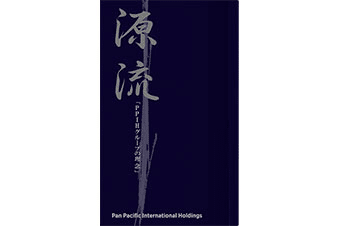
上場するときに作った「御法度五箇条」はあったが、実利的なもので企業としての明確なポリシーや理念は曖昧だったからである。
安田氏が一字一句書いていき、2011年に初版が刊行され、以後改訂版も発刊。「これがあれば、ビジネス書を読む必要がない」と言われるほどに仕上がっている。
源流の位置づけは、CEOよりも上位にある。
当社のCEOは、後任の大原孝治へとバトンタッチした。しかしそれは、会社法上のCEO交代に過ぎない。当社には、より上位の、真のCEOとも言うべきものが存在する。 それが企業理念集「源流」だ。
社内には「源流推進本部」なる組織も作られ、社員たちに対して源流の啓発に励み、2015年(66歳のとき)CEOをバトンタッチし現在は非常勤取締役になっている。
ちなみに創業者の選択肢の1つである、世襲については冷静な視点である。
大企業の経営トップになれる人材は、確率的に言うと、一千人に一人いるかいないかだ。私に一千人の子供がいれば、一人くらいはなれるだろうが、実際には四人しかいないから、その確率は二百五十分の一となる。つまり、私にとって世襲は非現実的なものだ。
言葉通り、安田氏の後に3人社長を引き継いでいるが、全員社員の中からだ。
そして現CEOの吉田氏は毎晩、「源流」と対話しているという。
「読んでいると、安田(会長)としゃべっている気持ちになるんですよ。言葉遣いが『ザ・安田隆夫』だから」
ちなみに現CEOの吉田氏は2007年にドンキに入ることになったが、その誘い方の馬力も安田氏っぽい。
コンサルタントという立場でPPIHと関わっていたが、創業者である安田隆夫氏から毎晩のようにかかってくる入社の誘いの電話に根負けした
今は若手社員と過ごす時間がいちばん多く、その交流の場を本人の言葉では「ティーパーティー」と呼んでいる。4時間行うこともあり、社内で人気が高いという。
(安田会長は)若い人が大好きで、優秀な人に1人でも多く会いたい。役員になるとほめられなくなるが、その前の世代の社員たちはすごくほめている。本当に変わり続けている人で、社内で圧倒的に人気がある。
人の顔と名前も覚えていて、役員が知らない店舗のスタッフも、安田会長だけがわかっている。
こうして「源流」に、安田氏の理念を詰め込み、自らも積極的に若手社員と交流し伝承することで、安田氏のDNAが時代を超えてドンキを繁栄させることを実現しようとしている。
安田隆夫の知恵
素人の強み
素人の場合は違う。最初から既存の手法を知らないのだから、大手と同じ手法になるわけがないのである。必然的にやることは全部オリジナル、自分で体験し、自分で考えたことばかりだ。これが、素人の強みになる。大手に打ち勝つ最大の秘訣はこのオリジナリティ、ユニークさだといっていい。(略)これが今日、ドン・キホーテが存在する最大の秘密である。
社員の”減損会計”を実施する
人材産業たる小売業は、あらゆる経費の中で人件費が最大ファクターとなる。(略)それもあり、当社では今、社員の”減損会計”を実施している。すなわち、既存社員がもし中途採用社員として当社に応募したら、いくら払うかを査定しているのである。実際にはかなりの乖離があることが判明している。もちろん、その結果を社員に突きつけ、迅速にしかるべき手を打つのも指導者の役割である。
ビジネスの勝負は、点の総量を競いあうエンドレスゲーム
何とかここまで到達できたのは、何回負けても絶対に〝大負け〟はしなかったからである。
ビジネスの勝負は、野球やサッカーのように一点差でも勝てばいいというものではない。つまり一試合ごとの勝率を競うゲームではなく、どこまでも点の総量(得失点差)を競いあうエンドレスゲームだ。
だから「小さなたくさんの失敗(負け)」と、「数少ない大きな成功(勝ち)」があればいい。要は大勝ちによるプラスが、小さな負けで積み上がったマイナスを上回ればいいのだ。ところが実際にはこれが難しい。なぜなら、えてして人は「負け」には敏感だが、「勝ち」には意外なくらい鈍感だからである。
企業は自己実現の場
企業に対する真のロイヤリティを高め、企業がビジネスに勝利し続けるために必要なものは、社員旅行でも野球大会でもない。それは「自己実現の場の提供」である。(略)
「自分が主役になれる場がある」と言い換えてもいい。それさえあれば、目くらましのような行事などなくとも、社員のロイヤリティは自然に醸成される。
「勝利者の論理」と「勝利のための論理」は全く別物
業界常識に従うとは、そうした先発企業と同じ土俵、同じルールで戦うことを意味する。さらに言えば、業界常識は勝利者の論理であって、勝利のための論理でない。だから、後発企業が先発企業のマネをしても絶対に勝てない。
経営者は権力者ではない
単なる中小企業のオヤジなら、自分が一番できると威張っていてもよい。だが、大企業になろうと思うのなら、一般社員にもできるように仕事を単純化して、なおかつ落とし込む必要がある。そのときには、自分自身の能力をあえて無力化させるために、自分の権限を自ら剥奪しなければならないのだ。経営者は権力者ではない。
(略)当時の私は、社内の誰よりも商品知識を持っていたし、誰よりも販売が上手だった。社員に対しては「お前たちはオレとレベルが違うのだから、早くオレの域に追いついてこいよ」という話ばかりしていた。しかし、これでは、いつまで経っても差など埋まるはずはなく、経営者としてもレベルが低い。
参照
https://bizboard.nikkeibp.co.jp/kijiken/summary/19990322/NB0983H_409154a.html
https://bizboard.nikkeibp.co.jp/kijiken/summary/20060227/NB1329H_739178a.html
お茶しましょう〜 DM→@yu8muraka3
