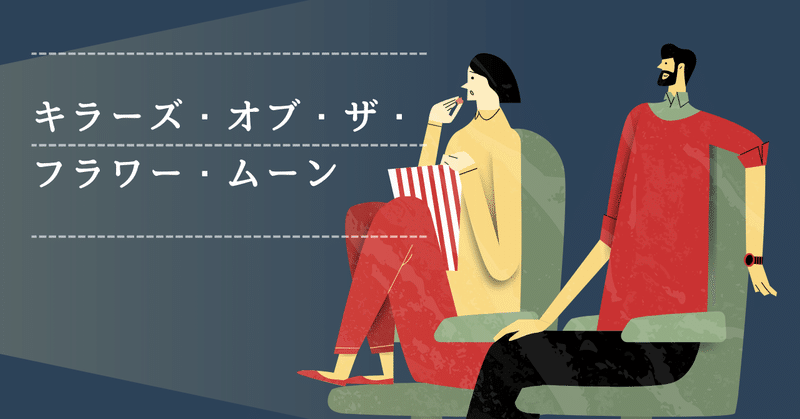
『キラーズ・オブ・ザ・フラワー・ムーン』〜アメリカの闇の歴史を描く傑作〜
今回も新作映画評論。
取り上げる作品は巨匠マーティン・スコセッシ監督作、そしてレオナルド・ディカプリオ、ロバート・デニーロを迎えたことでも話題の『キラーズ・オブ・ザ・フラワー・ムーン』
こちらをみてきましたので、感想をアップしていきたいと思います。
『キラーズ・オブ・ザ・フラワー・ムーン』について
基本データ
公開 2023年
監督 マーティン・スコセッシ
脚本 エリック・ロス
原作 デヴィッド・グラン『花殺し月の殺人 インディアン連続怪死事件とFBIの誕生』
出演者 レオナルド・ディカプリオ/ロバート・デ・ニーロ/リリー・グラッドストーン 他
あらすじ
地元の有力者である叔父のウィリアム・ヘイル(ロバート・デ・ニーロ)を頼ってオクラホマへと移り住んだアーネスト・バークハート(レオナルド・ディカプリオ)。
アーネストはそこで暮らす先住民族・オセージ族の女性、モリー・カイル(リリー・グラッドストーン)と恋に落ち夫婦となるが、2人の周囲で不可解な連続殺人事件が起き始める。
町が混乱と暴力に包まれる中、ワシントンD.C.から派遣された捜査官が調査に乗り出すが、この事件の裏には驚愕の真実が隠されていた……。
3時間越えの超大作
まずは見る前に・・・。
この作品はランニングタイムが206分、約3時間半と非常に長い。
こうも長いと、やはりそれなりに準備が必要で・・・。
ということで、まず完全にこれは与太話にはなるが、途中トイレに行くとなると、これはかなり痛手で。
そうならない為に、一つワンポイントアドバイス。
それは事前に「もち」を食べること。
理由としては、「もち」の原料である炭水化物。
それが体内でグリコーゲンの原料となり、そのグリコーゲンが体内の水分子と結びつき体内に蓄えられる。
そのため、体外に出る水分が少なくなり、尿意がなくなり、トイレに行く回数が少なくなる。
ちなみに、「もち」なんかないよ! という方はコンビニの大福などでも代替可能なので、ぜひお試しを。
僕も「よもぎもち」を食べて快適に3時間半の映画鑑賞を楽しむことができました。
ということで、与太話はこの辺りにして、そろそろ映画について語りたいと思います。
実際にあった連続殺人
今作品は1920年大初頭にアメリカ、オクラホマ州オーセージ郡でオセージ族の土地で石油資源が発見された後に発生した連続殺人事件の模様を描いた、ノンフィクション小説『花殺し月の殺人 インディアン連続怪死事件とFBIの誕生』が原作になっている。
元々、アメリカ先住民の一つであるオーセージ族。
彼らは元々住んでいた土地を追われ、オクラホマ州に追われることになった。
物語の冒頭でも描かれるが、オーセージ族は元々の信仰などを捨てることになり、白人と同様の文化・教育を受けることになるなど、アイデンティティを失いつつある状況になっていた。
しかし、この未開の地で石油が発見。
次々に石油油田が開発され、その利益を受け取るという形でオーセージ族はこの世界で最も金持ちになったのだ。
しかし白人たちは即座にその利益を狙って、あの手、この手と彼らに迫る。
アメリカ政府は、先住民であるオーセージ族を「無能力」であると一方的に決めつけ、彼らに「油田」や「資産」を借りする能力はないと「後見人制度」を制定。
オーセージ族の資産を同地域にすむ白人が自由に管理することができる。
そんな、とんでもない制度を制定してしまい、白人たちは私服を肥やすことになる。
一方オーセージ族は生活費などを使うにもお伺いを立てないといけないという、非常に不公平な状況に追いやられたのだ。
つまり元々白人に土地を奪われ追い立てられた彼らは、その地で富を手にいれるが、それすらも一方的に奪われる状況になってしまったのだ。
しかも、オーセージ族と婚姻関係を結ぶことで、オーセージ族でなくても石油の受益を相続できるということになった。
つまり彼らと婚姻を結び、その相手がいなくなれば、全ての利益を獲得できるようになったのだ。
このように後見人制度・受益権相続という二本柱で、白人はオーセージ族からどんどん富を掠め取っていくのだ。
そして、今作品はそんな二本柱を悪用しオーセージで富を蓄え、そして裏で悪事に手をそめる「キング」ことウィリアム・ヘイル、その甥っ子でオーセージ族のモーリーと婚約したアーネスト。
彼らの悪事と、オーセージ族殺人事件を捜査するために派遣された連邦捜査官(FBI前身組織)トム・ホワイトのサスペンス要素が描かれていく。
普通なら・・・。
さて、今作品のメインテーマである「オーセージ族殺人事件」
この事件の真相を解き明かしていくサスペンス要素を全面に押し出しても良かったはずだ。
事実原作の主役は連邦捜査官トム・ホワイトだ。
しかし、そこはスコセッシ。
仮に、その作劇ならば「白人捜査官のヒーローもの」になってしまい、白人たちが犯した罪という部分が蔑ろになってしまう。
だからこそ、原作では非常に小さな扱いであるアーネストを主役にし、彼らが犯す殺人という視点を映画の中心にして、作品を作ることにしたのだ。
その為、今作はこうした捜査官の活躍というのは非常に省略して描かれ、3時間半もの時間の大半はアーネスト、ウィリアム・ヘイルの犯す罪にフォーカスしている。
あまりにも自分の意思がないディカプリオの縁起がいい
今作のディカプリオ演じるアーネストは犯罪に手を染めるが、そこに自分の意思は存在せず、叔父である「キング」ことウィリアム・ヘイルの指示に盲目的に従っている。
そもそも彼は戦後あてもなく叔父を頼り、彼の指示に従い生活をしている。
そんな彼がオーセージの町を裏で操る「キング」の指示に反発することもできるはずなく、なし崩し的に犯罪に手を染めていく。
そんな彼はオーセージ族のモーリーと出会い、そして婚姻関係を結ぶ。
そこには確かに愛情もあるのだが、それに反してアーネストは妻の同胞を殺す手伝いをしていく。
しかし妻の病気である糖尿病の治療に必死になるなど、愛情はあるしオーセージ族の未来を案じる、だけど殺人はするという、どうしようもない二面性をあらわにする。
この映画の恐ろしいところは、アーネストは常に場面場面に空気に流されて答えを出すだけで、その場しのぎの言葉しか発さないということだ。
妻の前では「オーセージ族」のことを思う旨のことを言い、彼らが連続して怪死していることに心を傷める素振りを見せながら、キングの前では彼の指示に従い「オーセージ族」の殺人に大きく関与をしていく。
彼のその場限りの行動は、ここまで酷いことはないにせよ、我々が日常的に行ってしまうことでもある。
そんなあまりにも愚かな行為をアーネストは繰り返す。
今作は愚かさとは擁護されるべきではないと断罪している。
何かに流されて自分の意思とは関係なく行動する彼の姿。
それは、自分の頭できちんと考えずに行動をしてしまう、空気に流されやすい人間という性質、そしてそれがいつか破滅を迎えることを示している。
今作品で終盤行われる密室での駆け引き。
一度は自身の行いを顧みて、殺人に関与した事実を語ろうとしたアーネスト。
そんな彼に「キング」を無実にするために集まった弁護士たちが詰め寄るシーン、そこでのディカプリオの演技力はまさに今作の見どころだ。
というのも、流れに流され続けたアーネストも何度も自分の指示でオーセージ族が死んでいく様子を見て、明らかにこれはおかしいと思っていると見えるシーンはある。
特にリタとビル・スミスの殺害シーンの惨劇をみた彼の後ろ姿は後悔の念があったように見える。
家に爆弾を仕掛けられ、そしてバラバラになった遺体。
グロを全面に見せることはしないが、焼けた家財の下に手首の残骸があるなど、あまりにも酷い惨状が描かれる。
良心の呵責に悩まされ、一度は勇気で「キング」に立ち向かおうとしたが、多くの「キング」を信奉する者に囲まれその決意が揺らぐ。
というのも、ここで「キング」の信奉者はアーネストを恫喝することもなければ、ただ優しく「お前のためだ」と諭すのだ。
この状況で、これまでのアーネストを見てきて、絶対に揺らぐと思ったら、やはり人間は流されてしまう。
そんな人間の弱さをディカプリオは見事演じていた。
自己肯定感の高い「悪人」
今作品の悪人である「キング」は表向きは人当たりのいい「良識な人」だが、裏では殺人にも手を染める「悪人」だということが今作で描かれる。
しかし今作で「キング」はアーネストと違い、本当に自分が「悪いこと」をしているという自覚すらないのではないか?
そう疑われるように、描かれている。
作中最後に彼が書いたとされる手紙が引用されるが、この大量殺人の首謀者にも関わらず、彼は「オーセージ族に愛されていた」「彼らは真の友だ」などと宣う。
もはや「悪事」に手染めたという自覚すらない、なんなら自分は「良きこと」をしていると思い込んでいるのだ。
彼は殺人を犯して得た富を使いオーセージを発展させた。
自分は本当にいい人間だと思い込んでいる。
この思い込みの激しさには、映画を見ていて驚かされた。
おそらくその根幹には、やはりオーセージ族への差別意識があったのかも知れない。
演じたロバート・デニーロもキングの心情は心情は一才理解出来ないと答えていた。
しかし、これはフィクションのキャラクターではなく、実際にこのような人間が本当に実在し、悪事にて染めていたのだから驚かされてしまう。
そして、今作の原作で明かされるが、実は「キング」のような人物は他にも多数存在していた。
しかも殺人事件の大半は町ぐるみで行われていた、そのため全容はいまだに闇の中の部分も多いのだ。
今作で連邦捜査官は一連の事件を「キング=ウィリアム・ヘイル」が首謀者として解決したことになっているが、実はこれは早く分かりやすい手柄が欲しかった為に、彼を全ての犯人に仕立て上げたという側面もある。
作中最後にプロパガンダ的なラジオショーでこの事件の話を解決した捜査官を英雄視するかのように描かれるが、これも国民に対するアピールだ。
(しかもこれも実話)
こうしたとにかく結果を求めて真実を闇に葬りかねない責任転嫁の恐ろしさもまた今作では確かに問題提起として描かれているのだ。
最後の返答
今作の終盤、罪の告白をしたアーネスト。
その妻の糖尿病の治療に際して「インスリン」を注射で投与していたが、それは恐らく毒薬だったことが描かれている。
彼女は夫に「私に投与していたものは何?」と問う。
ここでアーネストは「インスリンだ」と告げるが、それが引き金でモリーは彼と袂をわかつ。
ここで何を言えば正解だったのか?
そんな議論が巻き起こっているが、アーネストは自分が彼女に投与していたものが「毒薬」だったことを認めたくない、そんな心情もあり「インスリンだ」と信じていたのだ。
これはキングが「善行をしている」と本気で思い込んでいたこととも合致する。
「悪事」をしていたとしても当人が「正しいことをしている」と思い込むことで現実を歪んで認知し、そしていつしかそれが「事実」であるかのように錯覚してしまう。
こういうことは往々にしてあるし、特別なことではない。
自分の身にも起こることである、そういう風に教訓にしなければならない。
ちなみにこのモーリの糖尿病だが、彼女たちはオーセージ族が白人文化に同化していく政策が施行されてから生まれた世代だ。
だからこそ食生活の変化で体を蝕まれていた。
逆に言えばそうした世代だからこそ、アーネストと結婚をする決断が出来たとも言える、逆にその前の世代である彼女の母親は、そんな娘の決断に嫌悪感を示したが、この母娘の描写も、オーセージ族の歴史を見る上では重要かも知れない。
まとめ
この作品は実際に起きた事件をもとにしている。
先ほども述べたが、事件の全容はいまだに明らかになっておらず、真相は闇の中にある部分が多い。
今作では「キング」が容疑者として裁かれたが、恐らく彼のような人物が無数にいて殺人を指揮していたと言われている。
人間は「欲」に負けると「悪魔」になる。
そんな悪魔と愛する人の間に板挟みになり、流され続けるアーネストを演じるディカプリオの芯のない演技はさすがという他なかった。
最後に彼がモリーに見捨てられるシーン。
彼は勇気を出して「罪の告白」という善行を行ったが、しかし自分は妻に対しては「いい人間だった」と信じたかった思いが、彼らの関係を最後に破綻させた。
人間は自分が「正しい」と思い込むことで、事実を誤認すらしてしまうのだ。
今作は殺人シーンなどが淡々と描かれ、映画の流れも非常にゆったりとしている。
3時間半と長丁場だが、このスローペースもまた必要な尺間だったと言える。
ということで、ぜひ劇場でノンストップでこの作品を味わうのが一番良い楽しみ方だと思うので、ぜひ劇場で見てほしと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
