
ファルマコンを探して (9) これじゃあ“絵好ミック・アニマル”だ‼︎
すごい時代だったんだなぁ、と思わず溜息を吐きたくなりました。バブル期にまさに泡のごとく湧き上がっては弾けて消えていったアートビジネスに関連した資料に目を通しての感想です。「月刊美術」1990年4月号の特集「アートビジネス最前線」はそういった意味でかなり刺激的な内容でした。
今となっては「え、あそこが!?」と思うような会社が絵画の販売に手を出していたりします。たとえば、自動車のディーラー。日産自動車販売はフランスの大手版元と提携してフランス版画を販売していました。
「女性のお客さんが目立ちますね。金額は16〜17万円のものが中心です。作家はイレーヌ、アイズピリ、シャロワなどですが値のはるカシニョール、ビュッフェなども足が速いようです」
自動車のディーラーといえば、トヨタ自動車系列のディーラーが個人で絵画ビジネスに参入した例もありました。愛知を中心にトヨタの販売店のオーナーがはじめたギャラリー・アーバンは名古屋の本店のほか、東京、そしてパリやニューヨークにも店を構えるほど一時期は事業を拡大していました。
そのほかスーパーでも絵画が販売されていました。西友は大泉OZ店・荻窪店にギャラリー「ART&YOU」を89年秋にオープン。30〜100万円の価格帯のリトグラフやシルクスクリーンの作品を販売しました。「インテリア感覚で10〜20万円の内外版画を買ってゆく客が多い。」とのことです。
また、ディスカウントの波も押し寄せていて相模原のスーパーの一角にオープンしたギャラリーでは値引き価格が表示されていて更にそこから値引いて、という割安感を強調して版画作品の販売をしていたようです。
「北海道から飛行機で170万円のシャガールを買いにこられたお客様をはじめ、名古屋から車でケンドーンを、都内からヤマガタをという具合に、この周辺より遠方からこられるお客様が多いですね」
、、、何だか頭がクラクラしてきました。
他にも「銀ブラのOLがふらっと立ちより買っていく気軽さが人気」などという記述もあり、バブルの時代は普通の会社勤めの人でも20万ぐらいの価格ならポンと出せるぐらいの給料はもらっていたということですね。心の底からうらやましいです。
そんな時代のなか、絵画をズバリ投資の対象にしたビジネスが生まれるのも、当然の流れだと言えるかもしれません。それがマルコーの「パートナーズ・イン・アート」です。
これはマルコーが購入した絵画を一口500万から1000万円で販売し、五年から十年後にオークションで売却して利益を分けるというシステムです。マルコーはワンルームマンション投資で80年代に急成長した会社で、ワンルームマンションに続く新たなる投資先として絵画に目をつけたようでした。

「芸術新潮」90年9月号にもこの「パートナーズ・イン・アート」は取り上げられていました。

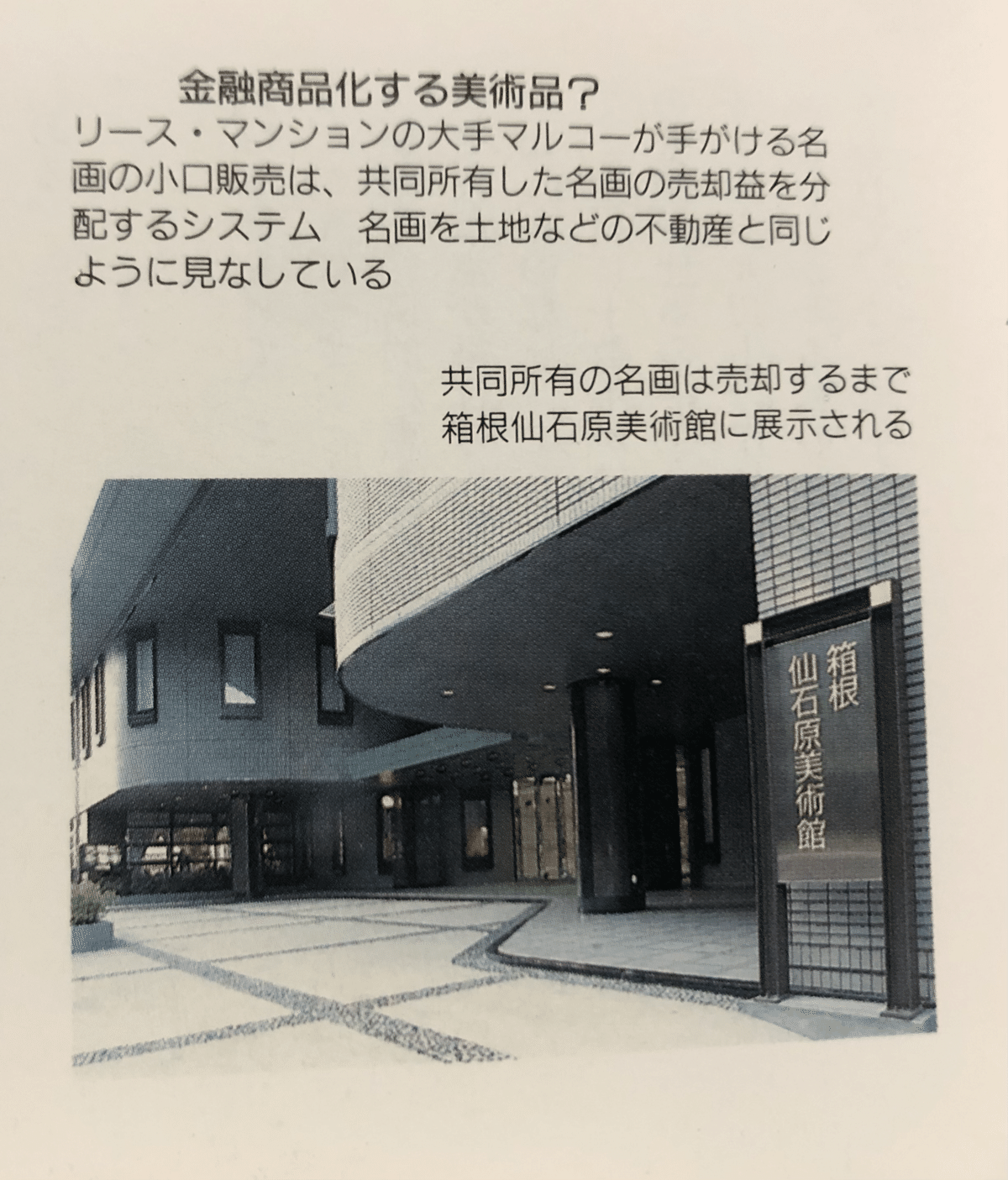
一口500万のシャガールが99口完売、とか、ルノワールは一口1000万、モディリアーニは一口500万と景気のいい数字が並んでいます。90年1月に売出しを開始して夏の時点ですでに総額100億円の絵画を扱っていたのだとか。
画像にもありますが、オークションで売却するまではマルコーが管理して、マルコーが所有する「箱根仙石原美術館」にて展示されていました。
「三彩」89年8月号にはこの美術館のオープンについて記事にしています。「リ・カーヴ箱根」というホテルの一角に美術館は作られていて、シャガールのカラーリトグラフ、特に「アラビアン・ナイト」は世界に10部しかないという13点セットのものが展示されていることが紹介されています。
記事には隣接する土地に美術館を建設予定、とありましたが、もし実現していたらいったいどんなものになっていたでしょうか。
現代においても作品を投資対象として扱うことに否定的な動きがありますが、当時もやはり反発があったようです。
「芸術新潮」90年9月号は「絶対に値上がりする」というのは投機商品の勧誘ではよく耳にする言葉であり、作品購入額が明らかでないことを指摘しつつ投機で価値が上がるのと美術品の芸術的価値は別物だと指摘しています。
その辺りがもっと露骨に出ているのが「サンデー毎日」90年8月26日号。「マルコーの絵画財テクの“正体”」というタイトルで3ページにわたって記事にしています。賛否それぞれの意見を載せていますが、「ハイリターンの商品にはハイリスクがつきもの」と言い、「一番儲かるのはマルコーだ」と結論づけています。
というのも、価格には利益が上乗せされていて更に売却時の利益(値上がりした分)の23%をマルコー側が取るという仕組みになっていたからでした。
今回のタイトル(「これじゃあ“絵好ミックアニマルだ‼︎”」)はこの記事の見出しから引用しましたが、「絵好ミックアニマル」というフレーズは記事のなかの国立国際美術館館長(当時)の三木多聞氏の発言から取られたものです。なかなか上手いこと表現するなあ、と思わず笑ってしまいました。
しかし、「芸術新潮」にしても「サンデー毎日」にしても、たった一年後に早くもこのシステムが崩壊してしまうことなど、まったく予想もしていなかったのではないでしょうか。
91年8月、2777億円の負債を抱えて、マルコーは会社更生法の適応を申請して倒産しました。5〜10年後にオークションで売却して利益を出すどころか作品は差し押さえられてしまい「パートナーズ・イン・アート」に出資した人たちは結局損をしてしまいました。
前回に引き続いて紹介する糸井恵氏の著書「消えた名画を探して」(時事通信社)には、出資した人たちのその後に触れられていました。それによると約120人の出資者がマルコーの関連金融会社に損害賠償を求める裁判を起こして2000年春に和解が成立。出資の際に組んでいたローンの残りを免除すると同時に、その関連金融会社が解決金を支払うなどの内容だったそうです。
一方で絵画はすぐさま美術館から引き剥がされることはなかったようです。名称こそいつの間にか「リ・カーヴ美術館」に変わっていましたが、上の画像にあった「横たわる裸婦」や「ユダヤ女」、そして「アラビアン・ナイト」などは何事もなかったかのように箱根のホテルの一角でひっそりと展示され続けていました。
他の絵画に比べたら幸福な経緯をたどったと言えるこれらの作品ですが、残念ながら「リ・カーヴ美術館」 は2007年9月25日に閉館となりました。おそらくその後は売却されたものと思われます。
「消えた名画を探して」を読んでいるとバブル期の「負の遺産」は30年経ってもまだ眠っているものが多くあるのだろうという気持ちになります。前回取り上げた「ピエレットの婚礼」も含めて、また日の目を見るときが来るのでしょうか。個人的には来ると信じて楽しみに待ちたいと思います。
〈トップ画像について〉
日産や西友がどのタイミングで絵画ビジネスから手を引いたのかははっきりしませんが、ギャラリーアーバンに関しては倒産時に大きなニュースになっています。それが1991年で、マルコー倒産も同じ年だったことを考えると、どうもこの年が美術業界において大きなターニングポイントになっているようです。
昨年末に見に行った、青森県立美術館に展示されているシャガールの「アレコ」。この作品はアーバンが購入したことで日本に入ってきました。アーバン倒産後の1994年に青森県が東京の画廊より購入、その後も公開に至るまでゴタゴタがあったことなど、今回はじめて知ることばかりで非常に驚きました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
