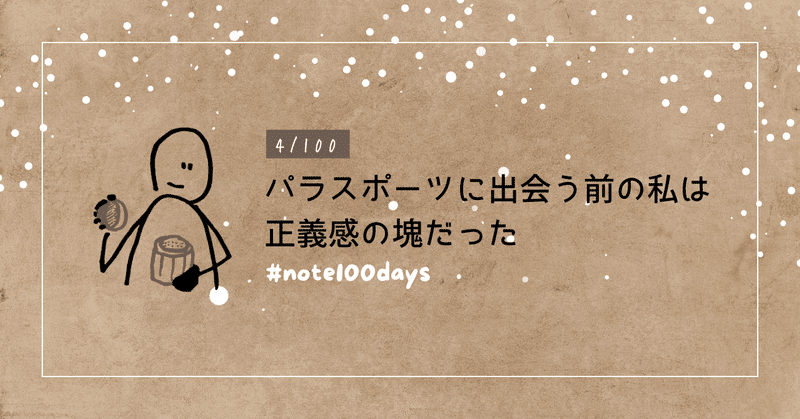
パラスポーツに出会う前の私は正義感の塊だった(4/100)
こんにちは。まえゆかです。
昨日更新したのは、パラスポーツとの出会いの場面。
大学院生としてのボランティア活動でパラスポーツに関わりだした私。
この頃は、今ほどにパラスポーツにハマるとも仕事になるとも思っていませんでした。
大きな転機になったのは、私の価値観を揺るがすパラアスリートとの出会いがあったから。
その前に
誰とのどんな出会いだったのか。
それを語る前に、当時の私がどんな考えを持って、大学院での研究生活をしていたのかをちょっとだけお話します。
私は、子供の頃から漠然と小学校教諭になることを夢見ていて、高校生の頃からは発達障害や特別支援教育に関心を持つようになっていました。
進学先が初等教育課程のみだったので、特別支援教育は自己研鑽の一環として勉強しつつ、シンプルに小学校教諭を目指して大学生活を過ごしました。
在学中のアルバイトで、都内の区立小学校の通級支援学級の指導員になり、改めて特別支援教育への興味が湧きますが、専門教育を受けていないので、いずれ特別支援学級の教員になれたらいいなと思って過ごしていました。
教員採用試験を通過し、採用面接の際にちらっとそんな希望を面接官の先生に話したと思います。
「特別支援学級は学校内の人事だからこの面接では考慮できないけれど、特別支援学校への配属希望はありますか?」
と問われ、
「専門性はないけれど興味はあります」
と答えたところ、特別支援学校への配属を告げる電話が3月に届きました。
特別支援学校での3年間
知的障害と肢体不自由部門の併設で小学部から高等部まで約200名の児童生徒が在籍する地元の学校へ配属になりました。
1年目は小1。2年目も小1。3年目は小6。
いずれの学年でも、知的障害の子どもたちの中に1人だけ肢体不自由の子がいる学年を担当しました。
教員として過ごした3年間は、天職と言えるくらいに楽しい3年間だったと今でも思っています。
でも、私は3年目で退職を決断し、大学院に行くことを決めました。
多くの先生方から考え直したほうがいいと助言をいただき、校長先生からは休職を許可するから退職ではない形で進学したらどうかと提案もしていただきました。
でも、私は長い研究生活になることを覚悟して、退職を選択します。
私が”楽しい”だけでいいのだろうか
こどもたちと過ごした時間は、本当に毎日が楽しかったです。
教師として未熟な面が多々あって、苦労した部分もありますが、こどもたちが可愛くて、仕事の大変さよりも楽しさの方が勝っていました。
でも、ふと我に返る瞬間もあります。
この子たちが卒業したら、どんな生活を過ごすのだろうか、と。
知的障害の1年生の授業の中での最重要事項は、身辺自立でした。一人で着替えをして、食事ができるようになることです。
1年生から入学してくる児童の多くが重度障害のため、入学時点では生活面で自立してない部分も多々あります。
将来、生活介護施設などを利用する場合も、地元では定員オーバーの状況になっている状況で、高等部の卒業後の進路で施設の週1、2日の利用しか通らなかった…なんて話はリアルに聞いていました。
必然的に残りの日が在宅となり、保護者の方がお仕事を辞めないといけなくんった、なんていう話も聞きますし、重度の方が進路先の選択に困るケースが多く、より身辺自立している利用者さんの方が通りやすい、なんていう噂を聞いたりもしていたので、先生方も結構意識していたと思います。
身辺自立ができるようになったら、次は「ホウ・レン・ソウ」。
授業の様々な場面で「できました」と確実に言えるようにトレーニングしていきます。
作業的な学習でボールペンの組み立てなどもします。
小学生で、ですよ。
これも卒業後の進路を意識してのことです。
習得するペースがゆっくりだからこそ、小1からコツコツと積み上げていくような授業内容が組み込まれていました。
保護者も教員も、彼らの将来を思って取り組んでいました。
責任も強く感じましたが、やりがいももちろんありました。
この社会で、彼らが生きていくために必要なことだと思って取り組んでいました。
でも、自分の小学校時代にを振り返ってみると、無邪気にピアノの先生になりたいとか、雑貨屋さんになりたいとか、いろんな夢を私は見ていました。
将来のことを真面目に考えたのは大学の3年生くらいからでしょうか・・・
教師になってからもそれがゴールとは思っていません。
まだ次のチャンスがあるとすら思っている自分と比較して、彼らの現実とのギャップに戸惑う自分がいたのです。
教員生活はとても楽しい。
でも、本当に、このままでいいのだろうか?
「カウントダウンが始まった」
6年生の担任をしていた時、卒業式の話題でとある保護者がいいました。
卒業式は、小学校を終えた門出の祝い。
おめでたい要素しかないと私は考えていたのですが、その保護者は「学校に守ってもらえる残りの期間が半分を切る時」と。
保護者の多くが、彼らの将来に大きな不安を抱き、地域の作業所の見学会が開催されると、小学部の保護者からも応募が殺到していました。
受け入れ人数に限りがあるので、中学部の保護者が優先されるのですが、それでも毎回熱心に多くの保護者が応募している現実に、何かが違くないか?と思うようになったのです。
障害があるとかないとか関係なく、彼らの成長をもっと純粋に喜べる環境を社会は作るべきなんじゃないのか。
彼らのできること < 社会に適合すること
でも、現実問題として彼らがこの社会で生きていくための術を身につけなくてはいけません。
教師としての責任を強く感じながら授業に向き合いますが、どうしても壁にぶつかります。
彼らは発達にバラつきがあるので、ゆっくりとしたペースで彼らのできることを一つずつ積み上げていきます。
でも、どんなに時間をかけたとしても、彼らが健常者になるわけではありません。何かしら苦手なこと、できないことは残ってしまうのです。
「できました」の報告を言葉で発するために何十回、何百回とトレーニングをします。
でも、トラブルの対応ができるようになるにはさらにもっと多くの時間がかかります。
もしかしたら、彼らは絵カードを使ったり、ハンドサインでコミュニケーションをした方がスムーズかもしれません。
でも、大人数を相手にする介護施設の方のことを考えると、言葉でコミュニケーションを取れた方がいい。
その方がいいのはわかってます。
今の社会の現状を考えて、彼らの将来的なことを想定したら、健常者が作ったこの社会のルールにできるだけ近づけてあげた方がいい。
でも、単純に適応力を考えたら、彼ら以上に私たちの方が適応力はあるはず。
彼は言葉で、彼女はハンドサインで、あの方は絵カードでコミュニケーションを取るよって、覚えて対応できるのはたぶん健常者側の方。
でも、社会はそんな対応ができるようには作られてない。
私が、何かしなくちゃいけないんじゃないか。
この教育の積み重ねた先に、彼らの明るい未来はあるのだろうか。
そもそもこの社会で生きることが、彼らにとって幸せなのだろうか。
こんな疑問を抱きだしたら、「楽しい」という思いで教員としての生活をしていることが苦しくなってきました。
自分の楽しさを優先し、彼らの将来を考えることを放棄しているような感覚に襲われます。
社会の側の意識がもう少し変われば、彼らのできることや関心のあることをもう少し伸ばして、保護者の方々の不安ももっと違う形で解消することができるんじゃないか。
私が、何かしなくちゃいけないんじゃないか。
そういった想いに駆られて、教師を辞めました。
どういう社会が理想なのか、この時の私に答えはありません。
むしろ、長い時間をかけて、探さないといけないって思っていました。
彼らにとっても私たちにとっても、今より良い選択肢があると信じて、私は大学院の門をくぐりました。
とてつもなく大きな正義感に駆られた決断でした。
振り返ってみれば笑っちゃうのだけど
今思うと、若気の至りだなぁと思います。笑
大きな驕りだったなぁと笑ってしまいます。
正義感が強すぎて、歪んだものの見方をしてしまっていた部分もあったかもしれません。
今も、社会の側の見方を変える必要があるとは思っています。
でも、当時は
私が、彼らを、守らなくちゃ。
そんな想いで頭がいっぱいだったんです。
大きな正義感でがんじがらめになっていた私は、とある選手との出会いで、自分の価値観が大きく揺らぐ体験をします。
長くなりましたので、その出来事についてはまた次回。
更新はこちらから
マガジンにしてありますのでフォローしていただくと通知が届きます^^
X(旧Twitter)もやっておりますので、雑多なことも書いておりますが、もしSNSでの通知がよろしければこちらもぜひ。
あと、ほぼ読書記録ですがinstagramもやってます。
サポートありがとうございます。Twitterではパラスポーツの情報を発信しているのでそちらもフォローしてもらえたら嬉しいです。 https://twitter.com/yukacharin
