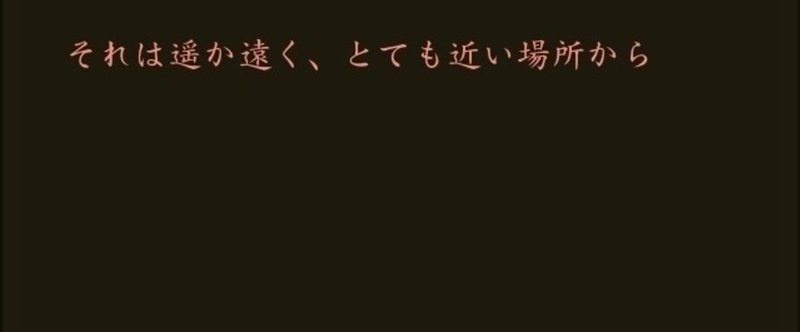
それは遥か遠く、とても近い場所から
「ル・シュナ?」
佐藤正弘は腰掛けると、いつものように正面の席に腰掛けている男に話しかけた。すると、話しかけられた金髪碧眼の男……ウェンスは仏頂面で、「レナ」と、答えた。
現在、佐藤正弘がいるのは、宮崎県にある自衛隊基地の一室だった。部屋は正方形をしており、目に眩しいような白色をしている。部屋の広さは高校等の一クラス分くらいの広さであり、また部屋のなかにはほとんど物がなかった。そのため、部屋は妙に広々として感じられた。あるものといえば、現在二人が腰掛けている椅子と、ふたりを隔てている白いテーブルがあるくらいのものである。そしてウェンスには万が一の場合を考慮して、両手両足を拘束する金属の器具が取り付けられていた。ウェンスがこれほどまでに厳重に身動きが取れないように身体を拘束されているのは、べつに彼が極悪人であるからとか、精神異常者であるから、といったような理由からではなかった。理由はもっとべつにあった。というのは、彼……ウェンスが、異星人……その可能生があったためである。そのため、自衛隊員は、いや、日本国政府は、彼からの思いがけない攻撃に備えて、彼を必要以上に拘束する必要があったのである。ちなみに、佐藤正弘とウェンスのふたりがいる部屋の入り口付近には、マシンガンを携帯した自衛隊員が立っている。もちろん、そのマシンガンの安全装置は外されており、いつでも発砲できるようになっていた。
1
宮崎県にある、鰐山と呼ばれる山の山頂に、何かが落下したのは、今から2週間前の夜間のことだった。当初は隕石が落下したのだろうと考えられていたのだが、やがて現場に駆けつけた自衛隊員がそこに発見したものは、隕石ではなく、薄っ平べったい、円盤形をした、銀色の、地球起源のものではないと思われる乗り物の残骸であった。そして自衛隊員がその乗り物の残骸を調べてみたところ、なかから人型の生命体が発見された。墜落の際、強く頭を打ってしまったのか、その生命体は意識を失っていたが、まだ生きていた。容姿は、日本人が西洋人と聞いてすぐに思い浮かべる姿をしており、身長も人間の成人男性とだいたい同じくらいの百八十二センチであった。彼は金属繊維で作られていると思われる、黒色の頑丈そうな衣服を身につけていた。自衛隊員は他に生存者がいないかと墜落機の様子を更に調べてみたが、その後、他の生存者や、既に死亡している乗組員が、新たに発見されることはなかった。どうやら墜落機に乗っていたのは、発見された金髪碧眼の男……ウェンスひとりだけであるようだった。自衛隊は意識を失っている地球外知的生命体と思われるウェンスと、未確認飛行物体の残骸を回収して、山頂をあとにした。もちろん、これらのことが、世間一般に対して公表されることはなかった。
ウェンスは自衛隊のヘリコプターに乗せられたあと、現在の自衛隊基地まで移された。その後、ウェンスは基地で手当を受け、今からちょうど1週間前に意識を取り戻した。
自衛隊は意識を取り戻したウェンスに対して、彼がどこから、何を目的としてやってきたのか、訊きだそうとしたが、ウェンスが操る言語はもちろん英語ではなく、ましてや日本語であるはずもなく、彼との意志の疎通は難航を極めた。そこで日本政府がウェンスとの意志の疎通を図るために、東京からわざわざ呼び寄せたのが、佐藤正弘であった。
佐藤正弘は言語学者で、年齢は今年で三十七歳だった。といっても、どこかまだあどけなさが残る顔立ちをしており、見た目にはとても三十七歳には見えなかった。俳優やモデルになれるほどの美男子ではないものの、顔立ちも比較的整っている方である。その綺麗な二重の瞳のなかには知的で、優しそうな光が宿っていた。髪の毛の長さは眉にかからないくらいの長さであり、その髪の毛にはやや癖があった。中肉中背で、肌の色は白かった。彼は昔からなかなか日焼けしにくい体質であった。
佐藤正弘はウェンスの顔に改めて注意を向けた。ウェンスの年齢は正直なところよくわからなかったが、しかし、見る限り、自分と同じくらいか、それよりもやや上くらいに、正弘には思えた。髪の毛は短く、よく日に焼けている。鼻筋が通り、まずまずハンサムな部類に入るだろうと正弘は思った。彼は金属を編み込んでつくられたような、よくアメコミ等のヒーローが着ていそうな、黒い衣服を身にまとっていた。そしてその衣服の下には、自分等とは違って、いかにも強靱そうな筋肉の隆起が見られた。きっと日頃から鍛えているのだろうと正弘は思った。
「ウェル・シュナ?」
正弘はウェンスの顔を見つめると、更に質問を続けた。すると、ウェンスは「エ・レナ」と、詰まらなさそうに答えた。ウェンスは毎日繰り返される質問に少々うんざりしているように見えた。ちなみに、さっき正弘はウェンスに対して、食事は美味しいか?と訊ねたつもりであった。その問いに対して返ってきた答えは、悪く無いというものであった。
「レナ」
正弘は微笑んで言った。レナという言葉は、ウェンスの世界では、良いということを意味するらしかった。正弘はこの1週間でかなりウェンスの言語を解析することに成功していた。
ウェンスが操る言語は、地球上に存在するいかなる言語とも異なっていた。そのため、最初の数日のうちはウェンスとの会話はおろか、ウェンスという彼の名前すら、把握することはできなかったのだが、しかし、我慢強くやりとりを続けているうちに、だいぶ状況も改善されてきた。その文法構造は、日本語と似ているところすらあるようだった。あとは単語の解析さえ進めば、もっとスムーズにウェンスとのやりとりができるようになるだろうと正弘は思った。
「ウェンス」
正弘はウェンスの顔を正面から見つめると呼びかけた。今日は思い切って、いつもよりも先に話を進めてみようと正弘は考えていた。ウェンスの言葉の解析はまだまだこれからの部分が多いので、たとえこの質問をぶつけたとしても、こちらが相手の言っていることを理解できる可能性は少ないのだが、しかしそれでも、とりあえず訊いてみるだけ訊いてみようと正弘は思っていた。
「ウェンス、アロ・クツ・シュナ?アヒ」
正弘はウェンスの顔を見つめると訊ねた。ちなみに、正弘としてはウェンスに、あなたはどこから来たのか?と訊ねたつもりであった。すると、ウェンスは正弘の問いに、やや顔を上気させて、早口に何かまくしたてた。もちろん、正弘にはウェンスの言葉は早すぎて、何を言っているのか、さっぱり聞き取ることができなかった。正弘は片手をあげると、その手で、ゆっくりと何かを押さえつけるような仕草をした。正弘としてはもっとゆっくり話してくれということをジェスチェアで彼に伝えたつもりであった。すると、その意味が伝わったのか、ウェンスは先ほどよりも、今度はゆっくりと話してくれた。それでも正弘にはウェンスの言っていることは、聞き取れない言葉や、わからない単語が多かったのだが、しかし、全く収穫がなかったわけでもなかった。今度は正弘はウェンスの発した言葉のなかに、遠くという単語と、近いという単語を聞き取ることができた。
「クオト?イカチ?」
正弘はやや眉を顰めるようにして、ウェンスが口にした単語を繰り返した。すると、ウェンスは正弘が繰り返した単語に、そうだというように真顔で首肯してみせた。
「……クオト、イカチ……」
遠くて近い?正弘は眉を顰めたまま、小声で繰り返した。正弘の言葉に、ウェンスは真顔で、またそうだというように首肯してみせた。
「クオト・イカチ」
と、ウェンスは繰り返して言った。
2
「近くて遠いっていうのは、一体どういう意味なんだろうね」
正弘は佐藤理香の顔を見つめると、独り言を言うように言った。それから、テーブルの上のコーヒーカップを口元に持って行く。正弘はあのあと、根気強く、ウェンスに対して、近くて遠いとはどういうことなのかと質問を続けたのだが、しかし、まだまだウェンスの言葉にはわからない部分が多く、結局、その正確な意味を捉えることはできなかった。正弘はウェンスと二時間近くやりとりを試みたあと、一旦、部屋をあとにしていた。
「案外、そのままの意味だったりするんじゃないかしら?」
理香は正弘の独り言に、口元に悪戯っぽい微笑を浮かべて答えた。
「どういう意味だい?」
正弘は理香の顔を直視した。
「だから、そのまま意味よ。近くて遠いっていう意味」
理香はそう言ってから、楽しそうに小さく微笑した。理香の返事を耳にした正弘はやれやれといった表情を浮かべると、その癖のある髪の毛を片手でなで回した。
今、正弘と理香のふたりがいるのは、基地にあるラウンジだった。そしてふたりはそのラウンジのなかにあるテーブル席に向かい合わせに腰掛けている。ちなみに、理香は、正弘と同じ言語学者であり、また正弘の妻でもあった。年齢は三十二歳。正弘にはちょっともったいないくらいの美人である。形の良い、アーモンド型をした、少し大きめの瞳のなかには、意志の強そうな光と、明るく屈託の無い光があった。ふたりは勤務していた大学を通じて知り合い、そのまま恋に落ち、一年足らずの交際期間を経て結婚した。ちなみにまだふたりのあいだに子供はなかった。
「……それにしても、彼も少し可愛そうよね」
理香はその綺麗な二重の瞳をいくらか細めるようにして、呟くような声で言った。正弘が妻の言葉の意味を探るように彼女の顔に視線を向けると、
「だって、彼はもう2週間もあんな狭い部屋に閉じ込められているわけでしょ?」
と、理香は非難するような口調で言った。ちなみに、理香も正浩と共に、ウェンスとのやりとりには携わっている。正弘は妻の発言に渋い表情で頷くと、思い出してまたコーヒーを口元に運んだ。
現在、ウェンスは基地のなかにある、六畳一間程の部屋に軟禁されている状態であった。もちろん、正弘が彼を閉じ込めているわけではない。彼を閉じ込めているのは、自衛隊、いや、日本国政府だった。日本国政府は、恐らく異星人だと思われるウェンスに対して、並々ならぬ関心をもっている様子だった。当分の間、彼が自由の身になることは難しいだろうと思われた。正弘はただ日本国政府に要請されて、彼とのコンタクトを取っているに過ぎなかった。また正弘には、ウェンスの身柄に対する、いかなる権限も与えられていない。正弘としても同じ人間として、不当に身柄を拘束されているウェンスに対して哀れみを感じないわけではなかったが、しかし、だからといってどうすることもできなかった。それに正直なところ、現金な話、この世界ではじめて異星の生命体とコンタクトを取ることができるという仕事に対して、抗い難い魅力を感じていることを、正弘は認めないわけにはいかなかった。
「……今後、彼はどうなるのかしら?」
正弘の思考の外で、理香は心配そうに表情を曇らせて言った。
「まさかとは思うけど、言語の解析が終わって、彼の目的がわかったら、そのまま解剖されてしまうなんてことはないでしょうね?」
理香は正弘の顔を問うように見つめて言った。正弘は妻の問いに、反射的にまさかそれはないだろうと微苦笑して答えたものの、絶対にそういうことがないと言い切れるかというと、あまり自信はなかった。 ふと窓の外へ向けると、自衛隊の基地から一機の飛行機が空へと向かって飛び立とうとしているのが見えた。
この物語の続きを、Amazonで購入することができます。よろしくお願い致します。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
