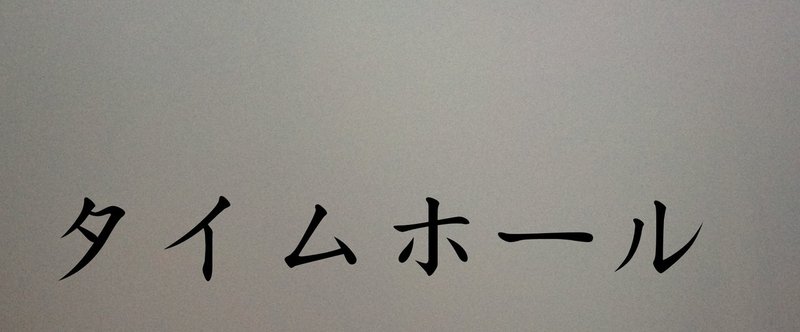
失われた火星都市の謎を追え
失われた火星都市の謎を追え!!
タイムホール
1
もともと僕も藤井美優もオカルト的な話は大好きで、気がつけばいつもそういう話をしていた。でも、そのとき彼女が僕に話してくれたことは、いつにも増して奇妙な話……というか、とてもにわかには信じがたい話だった。
一応、断っておくと、僕と彼女はべつに付き合っていたわけではない。まあ、正直に言えば、僕はちょっとは、彼女のことを異性として意識していたわけなのだけれど(それに対して、彼女には全く僕のことを異性として意識している素振りは見られなかった。そしてその事実は、少なからず僕のことを落ち込ませてもいた)。ちなみに、彼女は色が白く、どことなく子猫を彷彿とさせるような顔立ちをしていた。そしてどちらかというと小柄で、ほっとりした体型をしている。
その日、僕は大学の授業を終えると、自分が所属しているSF研究会の部室へと向かった。そこに誰も部員がいないことを予期しつつも。一応数字の上では、僕が所属しているSF研究会は、総勢37名の部員がいることになっているのだけれど。でも、実際に部室に顔を出すことがあるのは、僕と藤井美優を含めた、5名がいるかどうかといったところだった。じゃあ、あとのみんなはどうしているのかというと、月に一度定期的に行われる飲み会に顔を出すだけだった。飲み会にしか顔を出さないのであれば、ほとんどサークルに入っている意味なんてないような気もするのだけれど、でも、月一で行われる飲み会が余程楽しいのか、はたまた何か他に思惑でもあるのか、部員の大半を占める、あまりサークル活動に熱心ではない部員たちが、サークルを辞めさせてくれと言ってくることは、今のところなかった。そしてそれは僕たちにとって大変有り難いことだった。なぜなら、部員の絶対数が減ってしまうと、大学から予算が削られてしまい、部室を利用することができなくなってしまうからだ。……最も、じゃあ部室があったからといって、そこで僕たちが何か特別有意義な活動ができているのかと問われると、それは沈黙せざるを得ないところではあったのだけれど。というのも、僕たちが部室でやっていることと言えば、過去の部員が部室に残していったSF小説を夢中になって読み漁っているか、もしくはオカルト的な話題で盛り上がっているかのどちらかであったからだ。
少し話が脱線してしまったようだけれど、その日、僕が部室のドアを開けると、そこには僕の予想に反して先客がいた。藤井美優である。彼女は部室のドアが開け放たれたことに気がつくと、それまで眼差しを落としていた本から顔をあげて、部室の出入り口付近に立っている僕の顔を見た。彼女はまるで遠くの風景を見るときのように軽く目を細めて僕の顔を見た。そして、
「なんだ。哲夫か」
と、詰まらなさそうに言った。ちなみに、藤井美優は僕と同じ二十歳で、大学二年生である。そしてSF研究会の副部長を務めている。ついでに語って置くと、既に最初に説明したように、僕も二十歳で、大学二年生である。更に言えば、僕がSF研究会の部長を務めている。最も、部長といってもその役職に実態はなく、学校側に活動内容を報告する際に、それらの役職をしている人物について報告する義務があるので、一応名目上そう名乗っているに過ぎなかった。藤井美優についても然り。
「なんだとは挨拶だね」
僕は藤井美優のその綺麗なまるい二重の瞳を見ると、冗談めかした口調で言った。それから、部室のドアを閉めると、歩いて行って藤井美優とテーブルを挟んだ反対側の席に腰を下ろした。
「なにを読んでいるの?」
僕は腰を下ろすと、特にどうしても知りたいというわけでもなかったのだけれど、藤井美優の顔を見て訊ねてみた。彼女は既に目線を落として再開していた読書を中断すると、顔をあげて彼女の位置から見て正面にある僕の顔を見た。そして彼女は本の表紙を僕に掲げてみせた。見てみると、それは小説ではなく、オカルトについて書かれたハードカバーの本であるようだった。ちらりと目に入った本の帯には、世界を影で支配するフリーメイソン!と書かれてあった。
「好きだね。そういうの」
僕は微笑して言った。彼女は僕の発言に、真顔で首肯した。
「まあ、僕もそういう話は嫌いじゃないけど」
僕のオカルトに対する興味が三だとすれば、彼女の場合は七くらいはありそうだった。
「でも、実際、世界を裏で操っているのは、フリーメイソンなのよ」
と、藤井美優は至って真剣な表情で言った。
「9、11のアメリカの同時多発テロも、3、11の東日本大震災も、全て、彼等が仕組んだことなのよ」
「……もしかしたら、そうなんじゃないかって言う噂はあるよね」
僕は曖昧な笑顔で、間違いを指摘した。彼女は僕の言葉に不服そうな表情を浮かべたけれど、口を開いては何も言わなかった。彼女は再び目線を落とすと、読書を再開した。
部室のなかは静かだった。遠くで誰かがトランペットの練習をしている音が微かに聞こえた。既に日は傾きはじめていて、紅色の色素を帯び始めた日の光が、部室のあまり大きいと言えない窓辺から、どこか物憂い気に差し込んできていた。10月に入って日が傾くのが早くなり、かなり肌寒くなってきていた。僕は窓の方へ目を向けながら、もう少し厚着をしてくるべきだったな、と、軽く後悔した。朝家を出るとき、比較的暖かかったので、つい油断して長袖のシャツ一枚で来てしまったのだ。僕はなんとなく再び藤井美優の顔へ視線を戻してみた。彼女はそこに余程重要事実でも書かれているのか、一心不乱に本を読み耽っていた。
……オカルトか、と、僕はなんとなく心のなかで声に出して呟いた。それから、僕はふと昨日インターネットで見た、ユーチュウブの動画のことを思い出した。僕がそのとき見たのは、ラーチュウブという、オカルト雑誌、月刊ラーの編集長が主催している動画だった。既に述べたように、僕もオカルトの類は嫌いではなくて、半ばテレビ番組を見るような感覚でそれらの動画をいつも見ているのだけれど、昨日そうしていつものようにオカルト的動画を見ていると、偶然その動画に辿り着いたのだった。動画なかで、月刊ラーの編集長はある興味深いことを語っていた。
そのとき編集長が話題にしていたのは、過去にアメリカ海軍が極秘に行ったとされる実験についてだった。編集長の話によると、その実験はフィラデルフィア計画と呼ばれるらしい。ときは1943年のことで、ペンシルバニア州のフィラデルフィアという場所でその実験は行われたということだった。実験の目的は消磁だったらしい。つまり、敵のレーダーに探知されることがないよう、駆逐艦の磁気を消してしまおうという試みである。その実験をするに当たって、エルドリッジという名の駆逐艦にテスラコイル(高周波・高電圧を発生させる変圧機)をはじめとした、様々な電気実験装置が詰め込まれたらしい。そしてその後、実験装置のスイッチを入れると、発生した強力な磁場によって、見事に駆逐艦エルドリッジ号の姿は、レーダー上から姿を消したということだ。でも、実験が成功したと思われたその直後、奇妙な現象が起こったらしい。というのは、駆逐艦エルドリッジ号は、周囲の海面から突如として発生しはじめた緑色の光に包まれたかと思うと、宙に浮き上がって、そのまま忽然とその場から姿を消してしまったようなのだ。ちなみに、このとき、実験の様子を見守っていた海軍関係者の前から姿を消したエルドリッジ号は、驚くべきことに、フィラデルフィアから2500キロ以上も離れた、ノーフォークの沖合の海上に姿を現していたということである。更にその数分後、駆逐艦エルドリッジ号は、再び瞬間移動してフィラデルフィアに戻ってきたらしいのだけれど、実はこのとき、駆逐艦エルドリッジ号艦内は、阿鼻叫喚の、地獄絵図と化していたらしい。恐らく、充分な装備がない状態で時空間を移動したことが原因だと考えられるのだけれど、その駆逐艦に乗っていたほとんど全員に、常識では考えられないような異変が起こっていたみたいなのだ……ある者は現実空間に戻った瞬間に身体が燃え上がり、またある者は身体と船体が融合してしまい、またある者は身体の半身が透明になってしまったということだ……。他にも、発狂してしまった者や、身体がバラバラになって死んでしまった者までいるということである……この実験結果に恐れおののいた海軍上層部は、その後も継続されるはずであった実験の一切を中止し、実験の結果は闇から闇へと葬りさられることになったということである。現在記録として残っているのは、単にかつてフィラデルフィアにおいて、消磁の実験が行われたということのみであるらしい。もちろん、アメリカ政府もフィラデルフィアに計画についてマスコミ等から問い合わせを受けると、そのような事故が起こったというような事実は一切ないとこれを否定しているらしい。かつてフィラデルフィアで極秘に消磁の実験が行われたのは事実だが、でも、単にそれだけのことであり、そのような事故が起こったという事実はどこにもないということである。当時、極秘に実験を行ったことが、人々の様々な憶測を呼び、恐らく、このような都市伝説が生まれるに至ったのであろう、というのが、アメリカ政府の公式見解であるようだ……まあ、実際そうなんだろう。でも、僕としては月刊ラーの編集長の話にすっかり魅了されてしまった。ほんとうにそんなことがあったかどうかはともかくとして、話としてかなり面白いし、藤井美優もこの話を聞いたらさぞかしびっくりすることだろうと僕は思いついた。というわけで、僕は昨日自分が見た動画について、藤井美優に話して聞かせることにした。でも、藤井美優は、僕がフィラデルフィア計画の序盤まで口にしたところで、
「あ、それ、知ってるわ」
と、無感動に告げた。それから、彼女は軽く目を細めるようにして僕の顔を見ると、
「というか、それ、わりと有名な話で、みんな知ってることだと思うけど」
と、少し呆れたような口調で言った。
「……そっ、そうなんだ」
僕は藤井美優の指摘に、軽く動揺して言った。僕が斬新で面白いと衝撃を受けたオカルトネタは、どうやら既に使い古されたネタであったようだった。それにもかかわらず、どこか誇らしげな口調で語ってみせた自分がひどく滑稽に感じられた。そしてそんなふうに僕が恥じ入っていると、
「ところで」
と、藤井美優は何か思いついた様子で僕に声をかけてきた。僕はショックのあまり、それまで俯き加減していた顔をあげると、彼女の顔を見た。
「実はその話には続きがあるって知ってた?」
と、藤井美優は僕の顔をじっと覗き込むようにして訊ねてきた。
「続き?」
と、僕は彼女の言葉を反駁した。
この物語の続きをAmazonから購入することができますので、もしご興味をお持ちの方がいらっしゃいましたら、よろしくお願い致します。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
