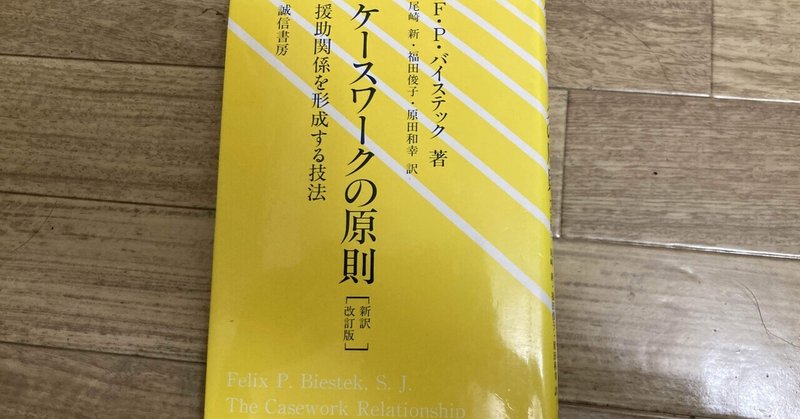
対人援助:バイステックの7原則
福祉関係の方なら一度は聞いたことあるバイステックの7原則の元ネタ=「ケースワークの原則」を読みました。
まずソーシャル・ケースワークとは、クライエントと彼の環境全体との間に、あるいは環境の一部との間に、よりよい適応をもたらすため、人間関係についての科学的知識と技術を用いながら、個人の能力や地域の資源を動員する技術である。とのこと。分かるようで分からない。だけど、目的としてはクライエントがより良く適応するよう援助すると書かれています。
私が勤める児童養護施設を例にすると、虐待や経済的な事情等から保護者と離れて暮らす入所児童が家庭に、社会に羽ばたけるように援助するということではないかと私は捉えました。
さらに児童養護施設を例にすると、児童相談所の児童福祉司がケースワーカーであり、私(保育士)は援助の一端の担い手であり、対象が生活する上で最もそばにいる支援者ということになります。
援助のためには人間ほとんどに関する知識の他、援助関係(人間関係)が大事だと書かれています。そのために必要なのがバイステックの7原則ということです。
※以降、クライエント=Clと略します。
・Clを個人と捉える
・Clの感情表現を大切にする
・援助者は自分の感情を自覚し吟味する
・受け止める(受容)
・Clを一方的に非難しない
・Clの自己決定を促し尊重する
・秘密を保持して信頼関係を醸成する
以上7つ。学生時代、テストで書かされたなぁと懐かしく思います。字面だけ見ると働いている身としては当たり前のことが書かれているのですが、本書を読むと実践の難しさを痛感します。
受容する。非難しない。
特に難しい…。なぜこの2つが大切なのか本書を用い以下で伝えますね。
受容とはClのありのままの姿を受け入れることです。喜びの感情だけではなく悲しさ、怒りなどの負の感情を含めて受け止めるということです。そしてなぜ感情を受け止めることが必要なのかというと、援助関係を深めるためです。人間、感情を出して受け止める他者がいて、感情を乗り越えて前に進めるからです。ただ、負の感情を受け止めるの難しい。働いて分かるのですが子どもの泣く姿を目の当たりにするとこちらも胸が痛くなり、どっと疲れます。。ましてや暴言なんて受けたらイライラが半端ではない。この暴言についても受け入れよ!というのが
→非難しない。につながります。
クライエントを一方的に非難しない態度は、ケースワークにおける援助関係を形成する上で必要な一つの態度である。クライエントに罪があるのか無いのか、罪に対して責任があるかを判断すべきでは無い。クライエントの態度や行動を、あるいは判断基準を多面的に評価する必要がある。
(本書より抜粋)
働く上で、子どもからの暴言はよくあります。あるいはリストカットや無断外出等、いわゆる問題行動に私の心は乱され、子どもに対してムカつく負の感情が芽生えるのです。そして最終的に「あの子は悪い子」と捉えて落とし所をつける他ない。
この原則からすると、私の心の動きは良くないことが分かります。でもアンガーマネジメントのためには止む無くでジレンマが。。
なぜ審判してはならないのかというと援助のための理解を深めるため。
問題児と捉えると問題を起こす心情背景を考慮する視点が曇ってしまうからです。
ただ、悪い行為を良しとし受容するのかというとそうではないとも書かれているところが本書の親切なところ。つまり、罪(行為)を憎んで人を憎まず。子ども支援では、ダメなことはダメだと伝えることが必要ということです。
子どもをより良く伸ばす支援のためには知識と人間関係が必要で、人間関係を作るために7つの原則が大切だということが分かりました。
自身の児童への関わり方を見つめ直すのにうってつけな本ですね。年に1度は読み返したい!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
