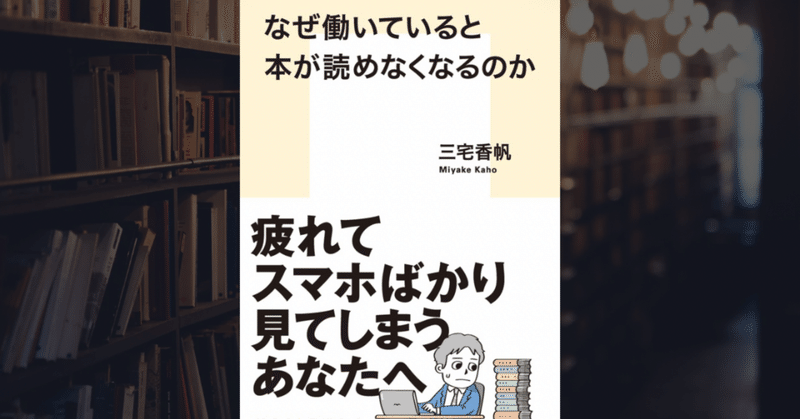
#185 三宅香帆 著『なぜ働いていると本が読めなくなるのか 』(集英社新書)

昔は一億総中流時代で、文学作品は自分と社会の関係性を描いていました。しかし80年代以降、私小説が主流になり、内面重視から行動重視へと変わっていきました。
90年代に入ると、自己啓発本が花盛りに。他人や社会はコントロールできないから、自分の行動を変えることで人生を変革しようという発想が広まりました。ノイズ(偶然性)を排除して効率的に自己変革するのが自己啓発の真髄です。
2000年代に入ると、新自由主義の影響で格差社会が生まれ、個人の自己責任が重視されるように。消費より労働そのものが自己実現の場になりました。ゆえに行動=情報が重視され、読書によるノイズ混じりの知的育ちは軽視されがちでした。
しかし、この情報社会の中でも、ぜひ「半身で働く」社会を作るべきです。仕事に専念しつつ、もう半身で読書を続けることで、豊かな人生を送れるはずです。全身で一つのことにコミットするのは楽かもしれませんが、別の文脈を持つことで新しい視点が生まれるのです。
情報社会の次は、読書社会。働き方改革の次に来るべきは、読書する余裕を作ることなのかもしれません。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
