
短編|レストランでまちあわせ
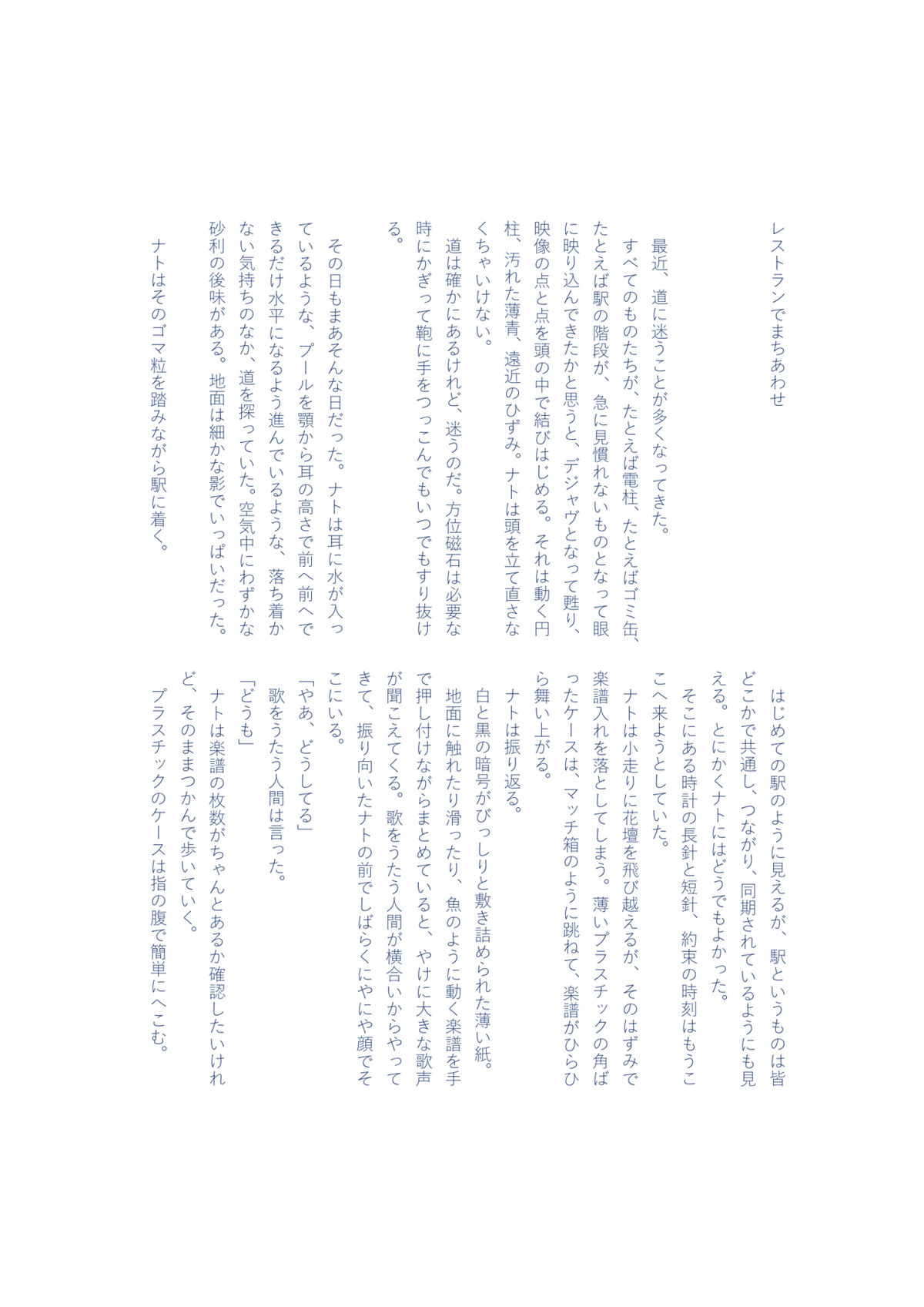







最近、道に迷うことが多くなってきた。
すべてのものたちが、たとえば電柱、たとえばゴミ缶、たとえば駅の階段が、急に見慣れないものとなって眼に映り込んできたかと思うと、デジャヴとなって甦り、映像の点と点を頭の中で結びはじめる。それは動く円柱、汚れた薄青、遠近のひずみ。ナトは頭を立て直さなくちゃいけない。
道は確かにあるけれど、迷うのだ。方位磁石は必要な時にかぎって鞄に手をつっこんでもいつでもすり抜ける。
その日もまあそんな日だった。ナトは耳に水が入っているような、プールを顎から耳の高さで前へ前へできるだけ水平になるよう進んでいるような、落ち着かない気持ちのなか、道を探っていた。空気中にわずかな砂利の後味がある。地面は細かな影でいっぱいだった。
ナトはそのゴマ粒を踏みながら駅に着く。
はじめての駅のように見えるが、駅というものは皆どこかで共通し、つながり、同期されているようにも見える。とにかくナトにはどうでもよかった。
そこにある時計の長針と短針、約束の時刻はもうここへ来ようとしていた。
ナトは小走りに花壇を飛び越えるが、そのはずみで楽譜入れを落としてしまう。薄いプラスチックの角ばったケースは、マッチ箱のように跳ねて、楽譜がひらひら舞い上がる。
ナトは振り返る。
白と黒の暗号がびっしりと敷き詰められた薄い紙。
地面に触れたり滑ったり、魚のように動く楽譜を手で押し付けながらまとめていると、やけに大きな歌声が聞こえてくる。歌をうたう人間が横合いからやってきて、振り向いたナトの前でしばらくにやにや顔でそこにいる。
「やあ、どうしてる」
歌をうたう人間は言った。
「どうも」
ナトは楽譜の枚数がちゃんとあるか確認したいけれど、そのままつかんで歩いていく。
プラスチックのケースは指の腹で簡単にへこむ。
建物の傾斜を影が黒々と支えているのが見える。その下にはやわらかい歯のような草。
ナトはどんどん歩いていく。耳の中の水が大波をたてるのも気にせず、電柱を数えながらぐんぐん歩いていく。三本、五本、十一本。
濡れたしっぽのようなものが肩に当たって振り返る。
そこには顔がある。
「東口はどこですか」
ナトは視線を足元のでこぼこしたタイルに落とし、人差し指とそれに連なる中指薬指を持ちあげ、すくうように横へ動かす。
頭上の空は鍋の底であった。煙が目に見えない速さで渦をまきながら、どんどん暗くなっていく。今にもザルの間から雨が落ちてきそうである。
水たまりにうつる影。直線の醜い波が走るごとに、ひかりが灰色の丈の長いコートを映しだす。
通りの店々は針のようにどこもかしこも尖っている。
ナトはそのいちいちに手を触れながら歩いていきたくなる。無性に。
道端にいるよくわからない人たちは針と針のあいだに詰まったゼラチン質のなにか。ナトは電柱を数えながらまだ歩く。
あった。
たしかにそこだ。おそらく。
そうでないとしても入ってみなければ。ナトは立ちいる前からもうそこにいた。背後の風は生ぬるく手応えがない。「場所」は毎回変わるが、関係がなかった。ただ向かわなくてはならないし、逃げても次があり、不可が倍になってそこに控えているだけで、やはりナトは戸をくぐる。
中は薄暗かった。天井が低く入り組んでいてどのぐらい広いのかわからない。ナトはひと足ごとに床板三枚踏みこえながら奥へ進む。
食器の音。ことばに分類できない人間の無数の声、会話。目に入り込んでくる皿の上の色、反射する湿ったひかり、食欲の上にべったり張りついている。
トワがいた。
樹木のように静かで硬い目でそこにいる。奥で水が流れているのが確かなようで確かでない。
ナトは自分の喉が閉まっていくのがわかる。
トワの前髪がかぼそい音で揺れた。
席につくと、一気に根が暴力的に張っていく、伸びていく、ナトは息をつく。
落ち着かないけれど、いるべきところにいる。水銀が磁石の重みを持って胃の底で増幅する。ひと粒ひと粒の色を見ると義務感、正義感、責任感。そこに近く、それらのなごりのようにも見えるが、本当のところはわからない。ナトは苦しくなる。けれどこの苦しさを自分の体に帯びていれば誰からも責められない、そんな根拠のないいびつな安心感の誘惑がそこにある。
机には穴があいている。真っ黒な浅い穴。虫が食べたのだろうか。指を入れて大きさを確認していると、ウェイターがやってきた。
ウェイターは白色のシャツにエンジ色のチョッキを着て、先端に葉っぱのついたペンを胸元のポケットに差していた。
「こんばんは。お加減いかがですか」
ナトはトワを見てトワはナトを見た。ウェイターはそれを見る。
「まあ、こちらはこちらでやってますので食べたくなったら言ってください」
ウェイターはそう言って水の入ったピッチャーをテーブルの真ん中に置く。
ナトはうなずく。トワは次のテーブルに去っていきそうになったウェイターの背中に呼びかける。
「ひととおりよろしくお願いします」
そしてまたナトとトワは空間を挟んで向かい合った。
店内は壺の内部のようにひかりが籠って、さんざん雨漏りをしたあとのような匂いがそこらじゅうから芽を出してくるようだった。
ウェイターはまたやってくる。つぎつぎと、ちょっとした料理をちょっとずつ。ナトとトワのあいだに立って中腰になる。トワが魚の天ぷらを皿に盛ると、ウェイターは天井近くからシロップのようなものを一滴ずつ落としていき、牡蠣の汁のようにそれは匂う。
ナトはそれを嗅ぐ。天ぷら越しにトワを見る。なんでここにいることになったんだっけと思う。
そう、ナトにとってトワの機嫌がわるくなっていることは明白な事実であった。原因はわかるようでわからない。とにかくこのレストランがきらいなのだろう。けれどナトとトワはしばらく、なにかが終わるまでそこにいなくてはならない。ここで意味を全うしなくては。
ナトはうんざりしてきて自分の皿を見る。トマト。
そもそもなんの約束だったろうか。
ナトは皿の上の輪切りトマトを眺めながらトワを観察する。箸を置くトワ。フォークの柄をしきりにこするトワ。急に自分が責められているような気持ちになって、ナトはナイフのまるいギザギザ部分を指の腹でなぞる。
トワの前髪が一本立っている。暗闇のなかで白く浮かびあがる顔、首。オレンジのライトが透き通る。誰だろうこれはと、ふと思う。でもきっと関係のあるひと。
ナトは皿を見る。トマトではなく皿の縁を。
するとすっと巨大なスプーンが横合いから出現し、緑色の液体が注がれる。
ナトは視線をあげる。
ウェイターの三本の指のあいだから、白い粉が降る。緑色の平面をわずかにへこませながらそこに粉が並ぶ。
自分の一部なんだろう。ナトは考える。
いつから自分の一部になったのか。遠く遠くの枝の先の、鳥に半分かじられかけた実のへこんだ断面を見る。そこでは雨が降っている。雨の一筋一筋が凍ってしまうような季節がじきにくる、そんな時期になっている。
最近はすべて、そういうふうに受け入れることに慣れてしまっていた。ナトは千里眼を三重に閉じる。めんどうなことが多い。それも続くとただ愉快なことに、なるだろうか。これは疑問だ。
「一杯どうですか」
ハイエナがリキュールの入った小瓶を手に、椅子に寄りかかってくる。
それはナトが思うに随分紳士的なハイエナだった。ナトは自分の今までのハイエナに対する認識を恥じることとなる。トワが我関せずという体で壁紙を爪で削っている。
ナトはそれを横目で観察しながらハイエナから社交辞令に一杯もらう。
「今宵はすてきな夜でございますね」
「はあ」
「特別な夜です。そうは思いませんか」
静かにグラスとグラスを合わせるとピンク色の液体が揺れる。
「ほら、ご覧なさい。あの、柱の奥にある時計。長時計。あれは今日この店に戻ってきたばかりなのです。ご存じでいらっしゃいましたか」
ハイエナはとても嬉しそうに肩を震わせた。
「いいえ、今はじめて」
「ああ、そうですか。それはよかった。気づくと気づかない、これはとても大きくちがってしまいますからね。はあ、わたしはほっとしましたよ、お若いひと。手遅れになるところ、だったかもしれませんよね? なんらかの見地からは?」
「ええ、そうかもしれません」
「帰りにそばに見にいってみるといい。今宵、ここにあれがあるということはとても稀有なことです。もちろん、わたしとあなたがここに居合わせていること、それも稀有なことです。今からでも、見にいってみるといいですよ」
ナトがトワを見ると、トワはパンをちぎっている。パンのあいだの気泡を眺めては、指を入れたり穴をひろげたりしている。
ハイエナは意図のつかめない目くばせをする。
「教えましたよ。教えましたよ。それではすてきな夜を」
ナトはグラスの中にしずんだ種抜きチェリーを指で取りだす。それはとても気味の悪い色をしていた。
「ちょっといいですかな」と言って割り込んでくる客。セイウチだった。
セイウチの声はひどく聞きとりづらい。なにやら噂話をしているようだが、空気が牙と牙のあいだで膨れては潰れる、その沼地のような音しかナトにはわからない。ナトはトマトをナイフで切る。
セイウチを受け流すと、今度は猫がやってきた。犬山猫。ヒョウのような体をしている。
猫は無言で近づいてきて側面としっぽを椅子、ナト、机にゆっくりとした歩みですりつけてそのまま去っていく。
トワは拳をふたつ、テーブルの上に置いていて、それはゆるむ気がないようだ。動物は皆、トワには近づかない。そのことにナトもトワも気づいていた。
ナトは一度、体を投げ出して天井付近に浮遊していきたくなる。無性に行きたくなる。
その後もやってくるのだ。いろんな客。イソギンチャク。悪魔、まりもの集合体、ミミズク。
愛らしい生き物たち。ナトは声を出してその時わらった。
トワはパンを手にしながら終始落ち着かないようだった。ナトは自分の様子をうかがっている。それがわかる。それがふたりの関係を輪をかけて面倒で複雑なものにしてしまっていた。
トワはこの場所が信じられなくなっている。隣のテーブル、遠くのテーブル。気配だけ感じるがそこでどんな料理が繰り広げられているのかわからない。主菜がもう来たのかどうか。デザートがあるのかどうか。それはあたたかいチョコレートなのか、つめたいチョコレートなのか。そもそもどのような文化規律の上に成りたつ儀式なのか。どうか。
トワはウェイターを呼ぶ。「ちょっとここの客らはなれなれしくはないかな」
えへんと咳払いしながら今度はナトを見る。横目でちらりと。
ウェイターは訳がわからない様子で、無言のままくるりと踵を返す。頭の足りないふりをして、実はとても目端が利く、ウェイターはそういうやつだった。
ナトはというと、こちらにちらちら視線をやりながら今はうってかわって土佐犬と会話をしている。トワはナトの視線の意味に少しだけ恥ずかしくなって参ったなぁと思い、けれどまたすぐに勢いを取り戻す。
トワはパンを皿に置く。粘土のオブジェのように変化した白い塊。
ナトはというと、どうしたものかと思っている。
犬を適当にあしらうと、自分の皿に向かうことにする。料理を食べる。そのかたちを受け入れる。
そこにはステーキがのびている。食べにくそうなとても活き活きとしたステーキだった。
本音を言うとナトはステーキのことが苦手だった。とりすましていてプライドがたかく、気軽に言葉をかけることができない。やかましいけれど開けっ広げな野菜たちの方が断然よい。断然。
でももうステーキはここに来てしまっている。
眠ったふりをしているけれどじっとナトを感じている、それがわかる。
ナトはステーキから視線を上げ、トワをちらりとうかがう。
こんな人物がいたかしら。
いつからわたしの一部になったのかしら。
すると泥にまみれた馬がやってきて、「ステーキが冷めてしまいますお若いの、ステーキが冷めてしまいますよ、せっかくのステーキが」と鼻をテーブルの上に突き出しながら言った。
ナトは軽く会釈をする。馬は両の眼でナトとトワを五秒間じっと見据えた後、くるりと踵を返し去ろうとする。そのはずみでしっぽが皿にぶつかり、土の塊がいくつも料理の上に落ちる。ステーキの上、鰹のたたきの上、ヨーグルトの上、アップルパイの上。
トワは立ち上がると、不満を抑えきれず、馬のしっぽを叩こうとする。けれどそれは空振りする。
拳をふたつ、テーブルの上に勢いよく置く。大きな手応えがあっただろう。それなりの音がした。その一秒後に皆、料理や皿や一輪挿しがガタガタと大げさに震えだす。大音量で。
ナトとトワと、周りの様子に気づいてから三秒間じっとしていた。そして口を開く。
「ごめんなさい。わたしが遅れたことで気分を害しているのでしょう」
トワはナトの首元と顎の辺りを見る。そしてまた、ふと気づいたようにパンを取り上げ、気泡の穴を覗き込みに行ってしまう。
ナトはもう今ではステーキを食べる覚悟を持つに至る。ナイフとフォークでそれを細長く切り、つぎつぎと口に入れて喉をすべらせる。
トビウオはウェイターのお盆の上からふたりに向かって謎かけをする。
「世界一記憶力のいい人は一体だれでしょう?」
ナトはトワを見た。
そして案の定、トワはゆっくり立ちあがり、そしてゆっくり爆発する。
次の瞬間、地面から店全体がぐらぐら揺れて、揺れと揺れのあいだですべてのテーブルがしゃんと整列し、こちらに向き直る。
ナトははずみで小さな叫び声を喉から放る。それは机の脚にすぐにつぶされる。
そこにいたありとあらゆるすべての細胞がトワの方を向いていた。様子をうかがっていた。まわりのものたちがトワから影響を受け始めていた。
店内がぐにゃぐにゃと様相を変え始める。
やけにすばしこいウェイターがあわてた様子でやってきて大きな声でこう尋ねる。
「ステーキはもうお持ちしましたでしょうか」
「ええ、きました」
ナトは椅子につかまりながら早口で答える。
すかさずトワは若いウェイターをつかまえて、かんしゃくをぶつけ始める。それはひとつひとつ醜い音を立ててぶつかり、やぶけて、中からどろどろとした液体が漏れでて床に落ちた。それは消費期限が切れたペンキのような匂いがする。
ナトとトワと、トワのやっていることを眺め、地面で未だ続く揺れを感じながら両目をゆっくり閉じた。
ここでいつもは終わってしまう。ここでいつもははじまりに戻る。
またどこかで会うだろう。動物たちも植物たちも様々にかたちを変えて。
でも今日だけそうじゃない。
突然、馬のいななきのような猫の鳴き声のような音が聞こえたかと思うと、目の前に白いワンピース姿の女が座っている。
みんながこちらを見ていた。生野菜だって皿の縁だって。
狭く何もないホールで女が頭を腕で隠し、体を小さく丸め、無限に後ずさりしていくのが見えた。繰り返し。トワは後悔する。料理をもっと食べておけばよかったと思ったのだ。無限に後ずさりする女の腕の間から見える口が小刻みに動くのを見ていた。
背後に手を置かれて、振り返ると女がいる。
見覚えがあるが思い出せない。
女はこう言う。
なにを勘違いしているの
あなたもあれらと同じなの
なかよくしなさい
せっかくあなたはここにいるのに
それができないのね
諦めて目をつむり、席につくと、目の前に見たことのない女がいる。
トワは自分がぞっとしたのがわかった。
自分は誰と待ち合わせていたのか、何のための食事か、
「わからなくなる」
いいや、本当はその瞬間にわかったのだ。
店中に広がる黒々とした海が、その時もそして今後のある一瞬からも、繰り返しこちらを見返してきていた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
