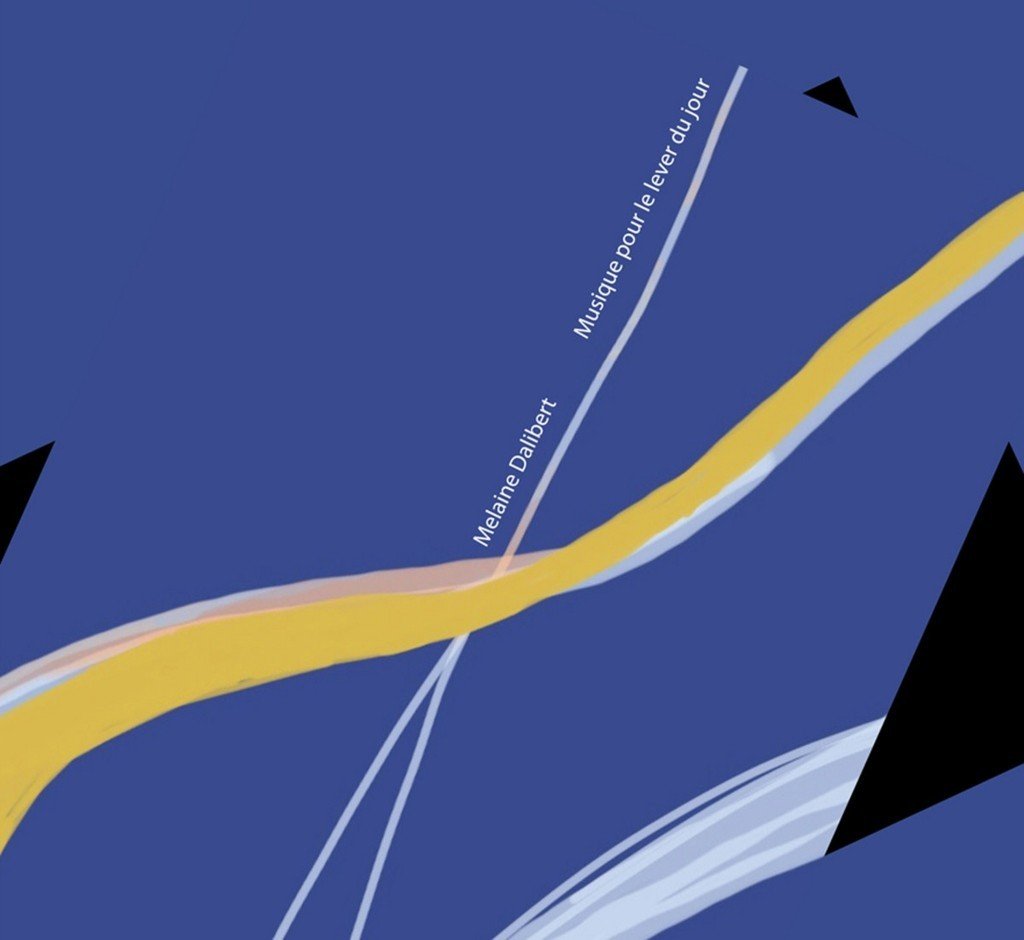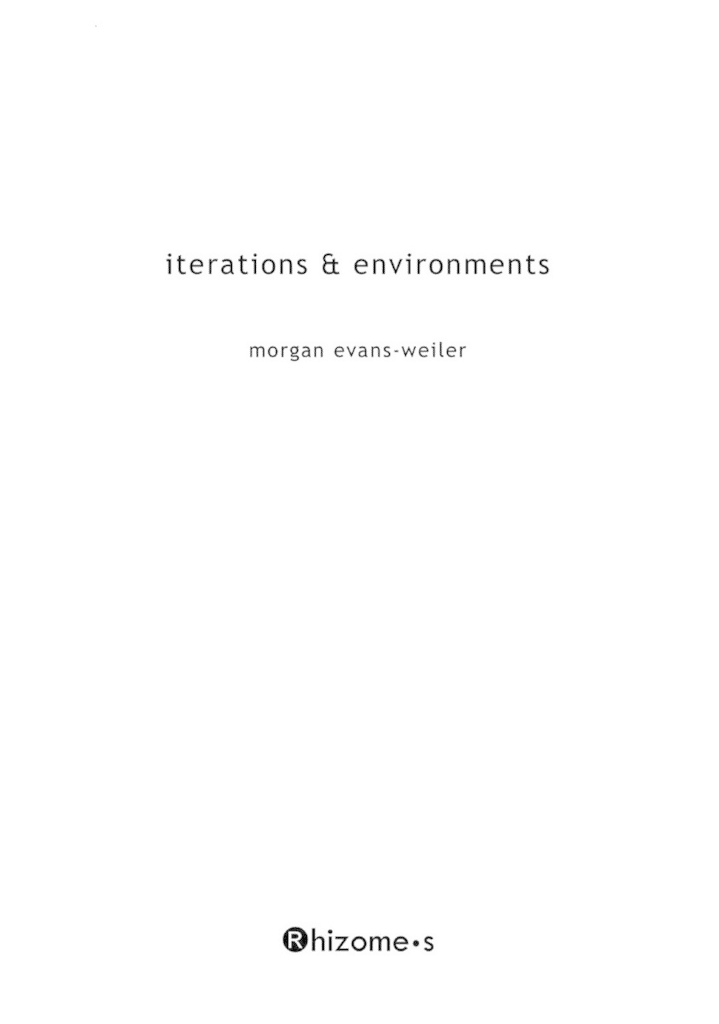2018年のベストアルバム - 現代音楽

2018年は個人的に現代音楽で気に入る作品に多く出会えた年でした。普段からそれほど熱心に追っている分野ではないのですが、おそらく多くの音楽をよく聴くリスナーにとってもこの辺りはなかなかとっつき難いイメージを持たれているのではないかと思いますし、よって専門的な知識がなくインサイダーでもない人間の視点によるセレクトが役に立つ部分もあるのではと考え、特に好きな作品を10作選んでみました。一応全作私なりにどう聴き、どこに魅力を感じたかなどは書いていますが、高度な論理的裏付けが重視される分野の作品でもありますのであくまで個人の感想であることに強く留意してお読みいただければ幸いです。(一応それぞれの作品のコンセプトなどについては出来る限り調べたりしていますが、鑑賞の際には必ずしもそれに沿った側面ばかりを集中して聴いているわけではないですし、感想は自分が魅力的に感じた部分を優先しています)
順位などは特になしですが、思いついた作品から順に書いているので上にあるものがより強く印象に残っているという面はあるかもしれません。最初の3作はブログのほうにアップしている年間ベストでも取り上げたので、文章の内容は同じです。
画像には試聴などが行えるサイトへのリンク付けをしていますので、興味を持ったものは是非クリックして聴いてみてください。
・The International Nothing『In Doubt We Trust』
主に即興演奏の分野で活動するクラリネット奏者2人による特殊奏法などを活かした作曲作品。2つの(重音奏法なども用いているため時にはそれ以上の)音の重なりや完璧にコントロールされたうなりがとにかく美しい。オシレーターから発せられる電子音の扁平な持続や規則的な周期を持った音色の変化といった面を楽器演奏でトレースするような視点を強く感じさせるサウンドですが、人力の楽器演奏ゆえの音のパラメータのあるゆる部分における揺らぎもどうしようもなく混在していて、結果的に電子音とアコーステックな楽器音の境界をフラフラと行き交うような危ういバランスが独自の美しさを生み出す音楽になっています。重音奏法で音が重ねられる瞬間の音の立ち上がりや、一つの音程が抜けて隙間ができ他の音が違った距離感で聴こえてくる瞬間などそこかしこにハッとさせられるような場面がありますし、20分辺りからの比較的小さな音量でいくつかの音程が持続的に重ねられる場面なんかは、例えばJim O'Rourke『sleep like it's winter』における小音量のパートにも通じるような繊細な手触りが本当に素晴らしい。
・Linda Catlin Smith『Wanderer』
2017年のベストに挙げた『Drifter』も素晴らしすぎたカナダの作曲家Linda Catlin Smithの作品。『Drifter』が2枚組でかなりボリュームのある作品集だったので今年も出してくるとは思いませんでした。しかもクオリティ的に全く遜色なくもしかしたらこの先より多くリピートするのはこっちかもってくらいの素晴らしい出来。音型の繰り返しなんかもありますし、音程の面でも平均律の調性音楽の範囲で作曲されていると思うんですが、リズムの面でもハーモニーの面でも絶妙に掴みどころがなく不安定に揺らぐような印象を与え、しかもそれが美しさとして伝わってくるような作品が並んでいます。かなり複雑で抽象的な音楽ではあると思うんですが、聴けば誰もが美しいと思うような場面がそこかしこに散りばめられているような音楽で、最初から最後まで同じテンションで気に入る人は少ないかもしれませんが(私も決してそうではありません)どこかしらで琴線に触れるところがあるはず。難しいイメージのある現代音楽ですが、その中でこの人はクラシカルな楽器と調性音楽の語法を比較的多く用いつつ聴き覚えのない音楽を作ってるタイプだと思うので、多くの人がそれぞれの知っている音楽と何らかの接点を見出しながら聴くことが可能な気がします。なのでいろんな人に聴いてみてほしいですね。特にピアノ&ヴィブラフォンと弦&管楽器がそれぞれ別の秩序で演奏しているような微妙に収まりの悪い絡みからこの人の音楽でしか味わえない美しさが立ち上がる①、ピアノではなくチェンバロを使用しその音色がハマりまくっている⑤、そして2つの楽器による音型の部分的反復が昨年の「Drifter」を思わせる⑥が好き。中でも⑥は美しすぎる。
*3月3日には東京オペラシティで井上郷子さんによる『リンダ・カトリン・スミス ピアノ作品集』のリサイタルがあるようです。
https://www.n-b-music.com/concert-information-3
・Melaine Dalibert『Musique pour le lever du jour』
フランスのピアニスト/作曲家による長尺のピアノ作品。この人は昨年Another Timbreから出したアルバム『Ressac』も素晴らしかったですが、本作もそちらに収められている楽曲と傾向は近く、規則的な歩みを思わせるミニマルなリズムと、螺旋階段をイメージさせるような変化とも循環とも認識されるような音階の扱いが大きな特徴。そのうえでそこで用いられる音階がより和声的に透明度の高いものになっていて簡素な美しさが際立った内容になっています。Jurg Freyのピアノ曲にも通じる真っ白な部屋を思わせるような簡素な美しさのある音楽ですが、ハーモニー的な移ろいの頻度や音の足取りのリズムや間といった点で個人的にはこの人の音楽はより素直に馴染む感覚があって、いい意味で必要以上の緊張感を感じずに聴くことができます。Jurg Freyの音楽には音楽における “退屈さ” の発生や音楽が意識の内と外を行き交う存在であることをハードコアなかたちで見つめさせるという側面があるように思いますが(別の作品についてのものですが、こういった感覚を非常に詩的かつ端的に記しているのがこちらのページの山形一生さんの文章)、本作は後者の側面を柔らかに内包しつつ前者についてはそれをギリギリのところで巧みに避けようとする設計がなされていると感じます。この辺の意図の方向性やバランスもすごく好みですね。ちなみにアートワークはDavid Sylvianによるもの。
・Eva-Maria Houben『Breath For Organ』
ドイツの作曲家/オルガン奏者のEva-Maria Houbenの作品。Edition Wandelweiserから多くの作品をリリースしており、いわゆるヴァンデルヴァイザー派の代表的な作曲家の一人としてご存知の方も多いかもしれません。非常に多作な方で作風も器楽曲からフィールドレコーディングなど幅がありますが、今作は彼女のメインワークといっていいオルガンによる作品。自分が聴いたことのあるものでは彼女のオルガン作品というと扁平かつミニマルなドローン的アプローチのイメージが強いのですが、本作はわかりやすく一つの音程が持続するようなものではなく、まばらにたてられるカタッやカチッといった作業音のような音、空気がパイプから漏れ出るような音、それがクッキリとした音程をあらわにした場合に聴こえてくる舟の汽笛のような音、そして終始鳴っている(というより録音に混入している?)ヒスノイズのようなサウンドなどが主な構成要素となっています。有機体としてのオルガンという道具に対する評価(appreciation)が作品の主眼としてあるようで、たしかにそれを意識して聴くとパイプやバー、弁、そして風を用いることで楽器としての機能を果たす構造物としてのパイプオルガンの仕組みを調べる作業の実況録音的な趣向が感じられます。この録音で用いられているクレーフェルトにある聖フランツスキー教会のパイプオルガンは現在は取り替えられている(displaced)そうなので、この個体の存在を記録するような意味合いもあったのかもしれません。正にタイトル通り、オルガンの呼吸を聴かされているようなサウンドであり、オルガンを生き物のように捉え接しているようにも感じられる本作のアプローチは、長年オルガン作品/演奏をメインワークとしてきた彼女ならではといえるのかもしれません。淡々とした楽器の点検作業を環境ごと捉えただけの録音のようでありながら、作品全編からどこか優しい眼差しや慈愛が感じられる一作であるように思います。
・Alvin Lucier『Criss-Cross/Hanover』
物理的な空間における音の振る舞いの探求を続けるアメリカの作曲家/パフォーマーAlvin LucierがOren Ambarchi、Stephen O’Malleyのために書いた作曲作品2つを収録したがアルバム。1曲目「Criss-Cross」はOren Ambarchi、Stephen O’Malleyの2名によって演奏される作品で左右のチャンネルに分かれた両者がギターとe-bowを用いてCの持続音を発し、そこから(半音の範囲を上限に?)ピッチに即興的にベンド操作を加えるシンプルな作風。結果としてリスナーの耳にはほとんど中央チャンネルで発声するうなりのみが認識されることになるのですが、即興的なピッチの操作によってうなりの具合は常に変化し、時にはほとんどうなりがないような状態となったり、またはヘッドホンで聴いていると音が左右に動くような効果が感じられたりして、意外なほど情報量の多い聴取体験ができます(結構疲れるくらい)。
アルバム収録のものとは演奏者は違いますが、youtubeに投稿されている「Criss-Cross」の演奏の様子も貼っておきます。動画で見たほうがいろいろわかりやすいです。
2曲目「Hanover」はエレキギターを演奏するAmbarchiとO'Malleyにアルトサックス、テナーサックス、ヴァイオリン、ピアノ、ヴィブラフォンの弓弾きが加わった編成。音程がスライドしていく持続音(ギターで出してるのか?)と他の楽器の単一の持続的な発音が重なって干渉の具合が刻々と変化していく作風で、ピッチが突っ張ったような非常に緊張度の高い場面や、様々な音色の折り重なりやうなりから複雑かつ美しい音響が現れる場面などが入れ代わり立ち代わりに延々と発生し続けます。おそらく何らか法則に基づいて決定されたピッチ間を音程がスライドしていっているのか、螺旋模様のような循環性や無限性を感じさせる作品でもあります。
・Morgan Evans-Weiler『iterations & environments』
米国ボストン在住の作曲家でありヴァイオリンとエレクトロニクスの演奏家でもあるモーガン・エヴァンス・ウェイラーの作品。35分ほどのヴァイオリンのための作品と20分ほどのピアノとエレクトロニクスのための作品を収録。複数本のヴァイオリンがオーバーダビングされた1曲目の擦れた持続音の連なりやその中から浮き上がってくるような倍音はHarley Gaberの作品を思わせます。霞がかり、霊的な存在の声が立ち上ってくるような音響空間にはいつまでもそこに留まっていたくなるほど魅了されました。
・Mark Fell『Intra』
脱臼させたようなリズム構築と非常に硬質でクールな音響からなる特異なダンスミュージックを長年作り続けている電子音楽家のマーク・フェルが発表したアコースティックな打楽器作品。クセナキスが考案した微分音を演奏可能な打楽器Sixxenを使用し、ガムランなども思わせる涼し気でチルな響きが味わえる作品になっています。しかしながら冒頭の2曲などはかなり細かに打音が敷き詰められた作風で、それにもかかわらず残響の干渉や飽和といった面は前面化せず、カチャカチャやカサカサといった渇いたアタックの音ばかりが耳に留まるような状態になっていて、その様子はよく言えばクールですががらんどうな音響ともいえ、打楽器というもののみで構成される音楽がその残響成分の具合や扱い如何によって印象が非常に異なったものになるということを実感させられます。端的にいうと冒頭の2曲はチル・アウト的な快楽性という観点から聴くと結構肩すかしに感じますし、そういうものを求めるなら3曲目から聴いたほうがいいかも。6曲目なんかも心地いい響きを発するものとかなり雑音的に響くものが意図的に混在させられている印象で、全体的に打楽器の持つ(必ずしも快楽的なだけでない)音響特性についていろいろと考えさせられる作品でした。
・Catherine Lamb & Johnny Chang『Viola Torros』
ともにヴァンデルヴァイザー派と関わりの強い作曲家/ヴィオラ奏者であるCatherine LambとJohnny Changによる、絵画等でしか情報の残っていない女性作曲家(演奏家?)であるViola Torrosについての調査や研究を行うプロジェクト「Viola Torros Project」、本作はそれによって得られた成果や自身のフィルターを通した知見を反映させた作曲作品が収められた2枚組アルバムです。各ディスクに長尺の2曲、トータルで4曲を収録。
Disc1収録の2曲はタイトルが「V.T. Augmentations II」「V.T. Augmentations III」となっていて、ヴィオラの2人にresonances(電子音?)のBryan Eubanks、更に声を担当する3名が加わるという編成も共通するためコンセプトの近しい姉妹作的な感じかと思われます。どちらもヴィオラ2本の絡みが中心となり、途中から控えめに電子音、更に遅れて声が加わるという構成。2曲の大きな違いとして聴き取れるのは、「II」ではヴィオラの音程の移動がフレット楽器的に瞬時に行われるのに対し「III」では比較的ゆっくりとベンディングするような動きが多用されていること、そして後者ではそのベンディングに絡めるかたちで微分音(おそらく四分音?)単位の動きが多用され独特な(インド音楽を連想させるような)メロディアスさを持った演奏になっているという辺りでしょうか。作曲を行っているCatherine LambとJohnny Changは作品において微分音を多用するイメージがあるので「II」でもそういった音程は用いられているのかもしれませんが(音程の聴き取りは私はかなり苦手です…)、「III」はかなりわかりやすく、そして旋律的に聴こえるかたちでそれが用いられているので、なんというかすごく強く耳を引く音楽になっているのが印象的でした。収録されている4曲の中でもこの「III」は特に好きです。
Disc2の1曲目「Citaric Melodies III」はJohnny Changによる作曲。演奏は自身をはじめ水道橋・チェンバー・アンサンブルの面々などを加えたオクテット。基本的にはいくつかの楽器が同じ音程で持続的な音を発している状態が延々と続いていくような作風。発音のタイミングの違いや音程の移動は一定のペースであるので、そういった動きによってアンサンブルであることは知覚できるのですが、音楽の中心になっている複数の持続的な発音が綺麗に溶け合ったサウンドは楽器の数や個々の音色の性格などが無化されるような感覚というか、架空のひとつの楽器から発せられる美しい響きのように聴こえてきたり。こういった部分の魅力は試聴音源だけでも結構伝わるので、youtubeにアップされているものだけでも是非聴いてみてください。
Disc2の2曲目「Prisma Interius VI for v.t.」はCatherine Lambによる作曲。演奏はヴィオラ、チェロ、メロディー的な動きのあるパートを受け持つもう一本のヴィオラ(Johnny Changが担当)、シンセサイザーによって行われています。シンセサイザーは厳密には “Secondary Rainbow Synthesizer” と記載されていますがこれは2014年からCatherineがBryan Eubanksと取り組んできた楽器だそうで、リスニングスペース近くに置かれたマイクが拾った響きにlive resonant band pass filters(いわゆるレゾネイター的なものでしょう)を適用するんだそう。40分の中でこのシンセの響きが前に出てくるような場面が何回かあるんですがどの場面も美しい響きが出てて聴きどころ。あと終盤になるにつれてメロディー的な動きが他のパートに溶け合い埋没していくような感覚もあって、特に35分辺りはその感覚がかなり強く出ている気がします。そしてそれが調和や安定、美しさを感じさせてとてもいい。
・Schiaffini - Prati - Gemmo - Armaroli『Luc Ferrari Exercises D'Improvisation』
イタリアのジャズ~即興やクラシック、現代音楽などの分野で活動する音楽家4名がリュック・フェラーリの作曲作品であるExercises D'Improvisation(即興のエクササイズ)を取り上げた一枚。演奏者の裁量に任せられている部分が多い作品と思われますが、本作はクリアさ、明晰さを保ったサウンドが持続していて、意識がどこまでも醒めていくような、メディテーティブともいえる感覚をもたらす興味深い作品となっています。詳しいレビューはこちら。
・藤倉大『ダイヤモンド・ダスト』
1977年大阪生まれ、15歳の時に渡英し現在もイギリスを拠点に活動している作曲家、藤倉大の作品集。アルバムタイトルにもなっている「Diamond Dust - Piano Concerto No.2」をはじめ全6曲を収録。個人的に特に耳を引かれたのが1曲目「korokoro for shakuhachi」と6曲目「yurayura for horn」。前者は “ころころ” という尺八の伝統的奏法による非常に風変わりな響きを中心的に扱った作品で、私個人が普段よく聴くフリーインプロヴィゼーションの分野における特殊な奏法を多用した管楽器演奏(例えばジョン・ブッチャーのサックス演奏など)に接した時のような新鮮な驚きがありました。後者はホルンのソロ演奏なのですが、おそらく発音に声を混ぜているのか歌唱と管楽器の間をグラデーションを変えながら行き来するような作品になっていて、その響きはなぜかゆったりと弾かれる二胡のようであったり時には変調された声明のようであったりで、とても面白くかつ美しいです。他の作品も面白いんですが、特にこの2曲は全く楽器または楽理への専門的な知識などがなくても響き一発でその魅力を堪能できる作品だと思うので、今回の記事で挙げた作品の中でも特にとにかくまず聴いてみてほしいですね。
以下のリンクは「korokoro for shakuhachi」についてのご本人のサイトでの簡単な紹介
https://www.daifujikura.com/prog_korokoro.html
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?