
「政治とカネ」の問題についての二つの視点 - 司法の恣意と不全、田中角栄の「金権」
6/6、自公維の合意による政治資金規正法改正案が衆議院を通過した。早速、6/10 にNHKが世論調査を発表、非常に厳しい結果が出ている。(a) 全体として、積極的な評価は33%、否定的な評価は60%。(b) 政策活動費の領収書公開を10年後とした案には、妥当が13%、不当が75%。(c) パーティー券購入の公開基準額を20万円を5万円にする案については、是認が25%、反対が64%。(d) 企業団体献金についても、容認が35%、禁止が50%となった。自民党の改正案を正面から否定する国民世論が示されたと言える。この世論の結果に狼狽した維新の音喜多駿と馬場伸幸が、「参院は独自の対応をせざるを得ない」「うそつき内閣」などと蝙蝠のダンスを始めている。6/9 の鹿沼市長選では、茂木敏光の地元であるにもかかわらず、自公系候補が圧倒的大差で立憲系候補に敗れていた。

NHKの世論調査は、6/8 に麻生太郎が福岡で「民主主義にはコストがかかる」と言い、ザルの改正案に対してすら不満を言い放った倨傲と非常識に対する国民の反発の表明でもあるだろう。改正案が通過した 6/6 の夜、NW9に登場したNHK政治部長の中田晋也は、「政治にはお金がかかるんですよね。これからどういう手を打っていくのかにかかっています」と言い、麻生太郎を代弁しつつ、岸田文雄を援護射撃した。田崎史郎らと同じコメントであり、泉房雄が批判するところの、政策活動費で遊興三昧させてもらって、自民党のために世論工作に励んでいる政権のイヌだ。中田晋也にこの発言をさせ、NW9のキャスターは(シナリオよろしく)受け流しただけだったので、私は直後の週末のNHK世論調査がどうなるか、やや不安に思うところがあった。が、蓋を開ければ、それは杞憂に終わった。

テレビの報道番組が、この件について基本的な前提を言わない点が気になる。基本的な前提とは、30年前に山口二郎らの扇動で法制化された「政治改革」であり、そこで導入された政党助成金である。政治にはカネがかかるという政治家の言い分を受け入れ、企業団体献金の規制強化をする代わりに(実際には何も規制しなかったが)、国民の税金から政党にカネを入れる仕組みにした。つまり、政党助成金は企業団体献金の代替措置だったのである。企業団体献金を放置すると、企業に政党・政治家が買収されて政策が歪む。賄賂として機能する。弱者への政策が後回しにされる。民主主義を不全にする。このセオリーとテーゼは今も言われる。今回も長妻昭が報道1930で弁じていた。正論だ。30年前も同じ主張が言われ、そこから国民が税金でコストを払おうという方向に化け、政党助成金が正当化された。

麻生太郎や中田晋也や田崎史郎が言うところの、「政治にはカネがかかる」の主張に対しては、「だから政党助成金を払っているじゃないか」と反論しないといけない。彼らは「政治にはコストがかかる」と言いつつ、政党助成金の制度を捨象している。プリミティブなトリックだが、テレビはそうやって大衆を騙している。一体何にそんなにカネが必要で、いくら政党助成金(税金)を払えばいいのだねと、そう訊き返さないといけない。それが国民の立場に立ったテレビ報道の本来のあり方だろう。実際には、必要なカネとは選挙買収の費用であり、政治部記者や御用論者との飲み食いの原資である。選挙区地元の秘書と事務所の経費が必要で、とゴネる中身は、陳情で利権話を聞き付けて口利きを得るための装置の経費であり、選挙買収でカネをばらまく組織の運営費にすぎない。民主主義政治に不要で有害なものだ。

今回の政治とカネの問題は、昨年11月の赤旗新聞のスクープを発端にして、そこから半年以上も延々と政局となって続いている。報道1930の定番ネタとして貼り付き、自民党の支持率を25%にまで引き下げる政治問題となった。が、これまで見渡したところ、政治学者や政治記者の本格的分析に接した記憶がない。話題となって影響力のある議論がない。岩波の「世界」で誰かが何かを書いたとか、論壇で注目する言説がない。テレビを見てもネットを見ても、本質を射抜いて膝を叩く言論に接しない。ただ政局の猿芝居が惰性で続いていて、テレビがそれを消費コンテンツにして配信しているだけだ。それが理由で、私はこの問題に関心が向かなかった。言葉が出なかった。本当は30年前の「政治改革」に遡って、それを批判する視角で30年間を整理し、積分的に総括する政治学者の問題提起が欲しいが、それはないものねだりだろう。

私自身にはそのような能力はなく、任を負える身ではない。ただ、少しだけ、二点ほど意見があり、マスコミやネットに出ていない論点と発想を持っている。その第一は、この問題については司法とマスコミこそが決定的な責任者だという確信である。政治資金規正法違反や公職選挙法違反については、これまで、列挙できないほど数多く事件が発生し、われわれの前を通り過ぎて行った。最近では、安倍晋三の「桜を見る会」が最も大きな事件だったと思う。だが、司法は不問に付し、マスコミも追及を止めた。この種の問題で、私がいつも不審に思ったのは、「政治資金収支報告書を訂正しました」と政治家が言えば、逮捕されず、それで一件落着して片づいてきた点である。ところが、場合によっては、例外的に議員辞職になったり、あるいは(運悪く)地検に逮捕される議員がいたことである。捜査は全くフリーハンドだった。恣意で免責免罪した。

今回も、萩生田光一や西村康稔には何のお咎めもない。根拠は不明。森喜朗にも、五輪電通汚職のときと同様、司直の手は伸びなかった。マスコミが説明するところのザル法の一般論とか、本当はザルに最も責任がある佐々木毅の「細部に悪魔」とかは、法律に責任をなすりつける司法とマスコミの詭弁であり詐術なのではないか。最近、特にそう意識するようになった。司法とマスコミはそれを立法(政治家)の責任にしているけれど、ザルがザルとなるのは、基本的に法解釈の問題であり、司法当局が積極的にザル化に加担しているのだ。ここでは細かく条文とケースを並べて論証し説得する余裕はなく、大雑把な断定で恐縮だが、本質はそういう問題なのだろう。政治家の不正を取り締まる法律を、逆に不正を合法化して政治家を守る楯にしているのが司法で、司法の歪みがこの悪弊を生んでいる。問題は法律の条文ではなく、司法自身がザルを作っているのだ。

どれほど精緻な条文の法律を制定しても、人間の力で解釈を変えてしまえば、法律の本旨は殺され効力は失われる。それが、30年間の「政治とカネ」問題の本質だったのではないか。カネが欲しい政治家はあの手この手で不正をする。が、司法が厳正に対処していれば、すべて法律の趣旨どおり摘発され検挙されただろう。法律に不備があるとか、議員たちが法律に抜け穴を作ったとか言うのは、政治家に責任を転嫁して大衆を騙す逃げ口上だと私は思う。抜け穴は解釈と運用で作られ、一個一個の司法判断の経験で既成事実(既成制度)になるのだ。結論を端折って言えば、司法から倫理が失われているのである。いま「政治とカネ」の問題と呼ばれる範疇は、40年前は「政治倫理」の問題と呼ばれていた。「政治倫理」の呼称が消え、政治家だけでなく「政治とカネ」を追及する司法とマスコミから倫理が消えた。

日本の「政治とカネ」の問題については、政治家以上に司法に責任がある。今回も、どれほど厳重・細密に改正条文を仕上げても、司法が一度でも解釈で政治家の不正を許せば、それが既成事実となって空文化が定着する。われわれは、もっと司法批判の声を強く上げるべきではなかったか。司法は、なぜかあまり批判されず追及を受けない。中立で適正な判断をしているものという予断がまかり通っている。マスコミは、ネットで大衆が言論するようになって以降、手厳しく批判されるようになった。今は、マスコミ批判が当然の環境になっていて、マスコミを疑い、マスコミを糾弾するのは、現代人のデフォルトの行動パターンである。だが、司法は批判されない。説明責任を問われない。記者会見しろと声が飛ばない。それゆえ、司法は、安倍晋三にも森喜朗にも手を出さず、森友も加計も桜を見る会も平気で不問で終わらせた。
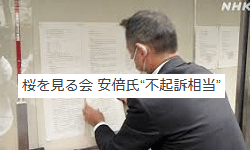
第二の論点は、賄賂(企業団体献金)が政策を歪めるという問題についてである。たしかにそのとおりだろう。20年間、最低賃金は引き上げられず、医療や介護の負担は無闇に上がった。保育士や介護士の給料は上がらず、社会保障の予算は削られ、教育予算も削られまくった。その一方、例のアベノミクスの三本目の矢の「成長戦略」の名の下で、大企業には優遇税制や助成金の恩恵がとめどなく配給され、金持ちが豪邸を新築する住宅ローンには国の補助が付いた。防衛予算は青天井でバラ撒かれた。だが、過去を振り返ると、そのテーゼと矛盾する政治の実例が視圏に入る。それは田中角栄だ。金権政治の権化のような男だが、この男がやったのは、高齢者の医療無料化であり、「福祉元年」と銘打った年金の大幅拡充だった。教員の給与も引き上げた。田中角栄は「政治は力、力は数、数は金」を実践しながら、弱者にも予算を配分する社会政策を打った。

安倍晋三とは違っていた。つまり、企業団体献金が政治を歪めるというテーゼは、一般論としては正しいが、例外があるということになる。田中角栄は例外で、財界大企業からたっぷりと献金(賄賂)を受け取りながら、政治は強者だけでなく弱者にも目を向けた。国民全員に目配りした政策を行った。すなわち、この一般論は普遍的法則性ではない。何が、この一般論を普遍法則でなくしているかと言うと、それは政治家の資質と責任倫理だという答えになる。田中角栄と安倍晋三とは違うのだ。70年代の自民党はこの傾向が強く、地方と第一次産業に目配りし、「弱者を救済するのが政治の役目だ」と信条を述べていた。そうやって票を集めていた。弱者の庶民は、政治家が権力者になるためには、カネ集めとカネばらまきが必要悪の契機だと知っている。アメリカは堂々と金権賄賂政治をやっている。民主政治が衆愚政治である以上、民主政治には賄賂と買収がつきものだろう。

以上、倫理という言葉をキーワードにして、「政治とカネ」の問題をめぐる議論で死角になっている、盲点かもしれない二つの視点を取り上げた。
蛇足ながら、自民党の派閥も簡単にはなくならないだろうと、悲観的にと言うか冷徹にと言うか、溜息まじりに観察している。なぜ派閥が解消されないかと言うと、議員たちが世襲2世3世だからである。世襲制が維持されるかぎり、派閥は解消されない。例えば、茂木派は解体されても、旧経世会の流れは残り、小渕恵三の娘とか、青木幹雄の息子とか、そうした血脈を中心に再び群れ集まる動きは起きるだろう。安倍派には福田康夫の息子がいる。谷垣G(宏池会系)には加藤紘一の娘がいる。血筋で仲間を組んで結集しようとする古代日本以来の習性は絶えないだろう。今後の派閥の行方について、世襲と血脈の観点から考察している政治記者や政治学者はいない。掘り下げが弱いと思う。自民党の派閥がなくなるときは、戦争か革命が起き、政治に激しい断絶が起きたときである。






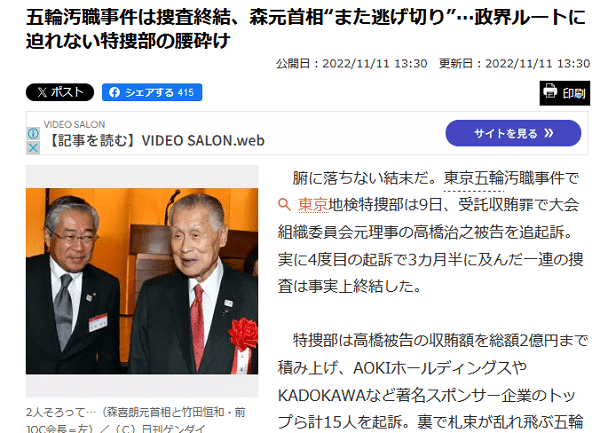





この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
