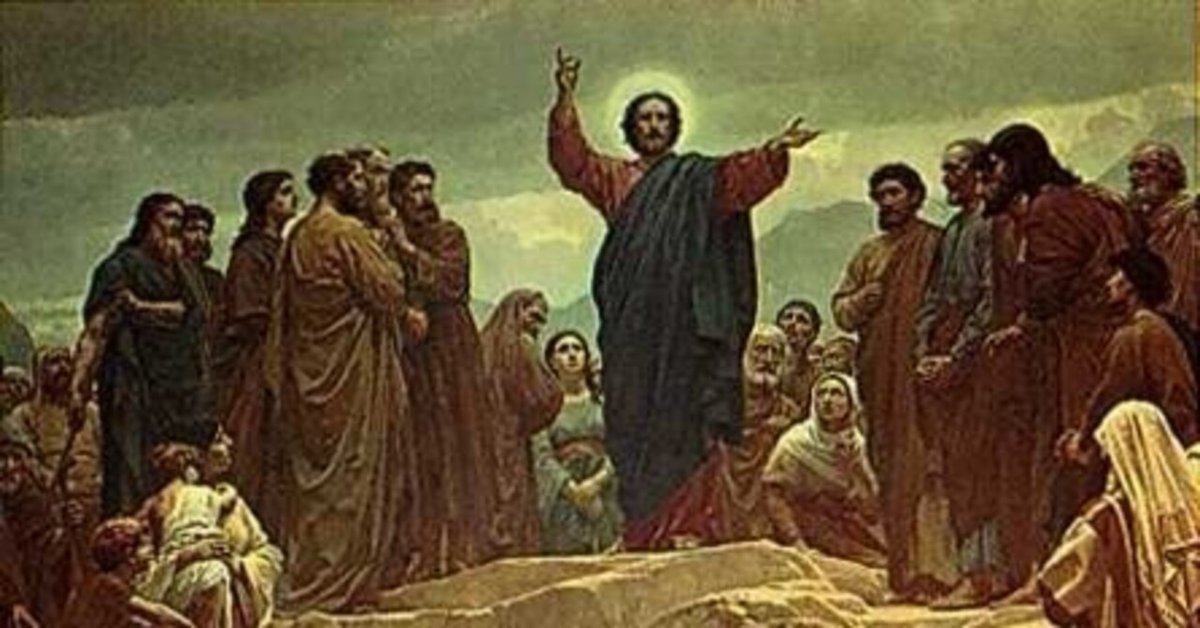
初期キリスト教信仰について(おわり)
パウロの受難物語
福音書においては、イエスが逮捕されるところから内容的には「イエスの受難」を主に取り扱うようになります。使徒言行録では、あたかも「イエスの受難」を扱うように、21章においてパウロが逮捕されてから、最後28章にかけては、「パウロの受難物語」のような印象を受けます。ただし、ローマについてからのパウロがどうなったかについては、紀元150~200年頃に書かれた新約聖書外典の「パウロ行伝」にパウロがローマで皇帝ネロによって殉教したことが書かれています。しかし、およそパウロの殉教はそうした伝説によれば紀元64年ごろということで、使徒言行録が成立した紀元90年には、「パウロのローマでの殉教」は既に聞き知っている可能性があり、その意味で、使徒言行録はパウロの逮捕~ローマでの殉教までを描くのではなく、ローマにおいて「自由に妨げられることなく福音宣教をした」というかたちでハッピーエンドのような終わり方にしてある点に特徴があります。(以下に、使徒言行録でパウロがどのように記述されているかを示した資料を載せます。)

さて、使徒言行録22章1節以下のところで、パウロはヘブライ語でユダヤ人たちに自分の回心体験を話し、さらに自分が異邦人に対する福音宣教者とされた次第を語って聞かせます。
この点については、使徒言行録9章1節以下における回心体験についての記述と平行した内容となっています。
パウロはヘブライ語を話せたのか?
実は、パウロがヘブライ語を話せたかについては、パウロがタルソス出身のユダヤ人の家庭に生まれ、幼少のころから「ファリサイ派」としての教育を受け、自分自身「ファリサイ派の中のファリサイ派である」と「フィリピの信徒への手紙」の中で書いています。
ただし、パウロが引用する『聖書』のことばは、ヘブライ語の聖書ではなく、紀元前1世紀に成立したギリシャ語『七十人訳聖書』の記述によるものであって、パウロがヘブライ語を話せたのかは、あまり良く分かってはいません。(上記の「Acts of Paul」で、パウロがヘブライ語を話すことがかかれている)
わたしは生まれて八日目に割礼を受け、イスラエルの民に属し、ベニヤミン族の出身で、ヘブライ人の中のヘブライ人です。律法に関してはファリサイ派の一員、熱心さの点では教会の迫害者、律法の義については非のうちどころのない者でした。(フィリピの信徒への手紙3章5~6節)
パウロが生きていた時代においては、およそ「ギリシャ語」が一般的に公用語として使われており、ペルシャ帝国の公用語であるアラム語が使われていたことも知られています。ただ、およそ1世紀においてギリシャ語の『七十人訳聖書』が、広く離散のユダヤ人たちに受け入れられていたことを考える時に、パウロがどこまでヘブライ語を話したかについては、かなり微妙であるというところです。
第一は、エルサレムの神殿の異邦人の外庭とユダヤ人のみが入ることを許されていた内陣との境に適当な間隔で立てられていたという、内陣への非ユダヤ人立入禁止の高札である。これはヨセフスやフィロンの言及によって知られていたが、近年実物が二枚発見された。ヨセフスは、高札はギリシア
語とラテン語で記されていた、と言っているが、発見された実物はいずれもギリシア語のみである。
われわれはこれら硯学の説が基本的に正当なものであることを認めるにやぶさかではないが、フィッツマイヤーの言うように、この時代の口語としてのヘブル語の位置を余りに過大評価することに対しては慎重にならざるを得ない。口語としてのヘブル語の使用はやはり限定されたものであったと思われる。また紀元前後頃の口語ヘブル語がすなわちミシュナ・ヘブル語であったと言うわけではなく、後者は前者から発展したものと考えるべきであろう。
異邦人への宣教者としてのパウロ
パウロが「異邦人への宣教者」であるという情報は、「使徒言行録」を除いては、パウロの「ガラテヤの信徒への手紙」に記述があります。「ガラテヤの信徒への手紙」が「使徒言行録」よりも早くに成立したことを踏まえると、「使徒言行録」は①パウロの手紙について内容を知っており、②パウロの手紙を下敷きにして「使徒言行録」を記したということが考えられます。
それどころか、彼らは、ペトロには割礼を受けた人々に対する福音が任されたように、わたしには割礼を受けていない人々に対する福音が任されていることを知りました。割礼を受けた人々に対する使徒としての任務のためにペトロに働きかけた方は、異邦人に対する使徒としての任務のためにわたしにも働きかけられたのです。また、彼らはわたしに与えられた恵みを認め、ヤコブとケファとヨハネ、つまり柱と目されるおもだった人たちは、わたしとバルナバに一致のしるしとして右手を差し出しました。それで、わたしたちは異邦人へ、彼らは割礼を受けた人々のところに行くことになったのです。
ただ、わたしたちが貧しい人たちのことを忘れないようにとのことでしたが、これは、ちょうどわたしも心がけてきた点です。(ガラテヤの信徒への手紙2章7~10節)
「使徒言行録」は、およそパウロの手紙にある記述を元にして、パウロの回心体験と、またパウロの語った自身の信仰について、総督フェリクス(使徒24:10~23)に語り、また同様に(ヘロデ・)アグリッパ王(使徒26:1~32)に対しては、福音を宣教するということを記録しています。
これは、およそ使徒言行録9章の「サウロの回心」(使徒9:1~19)のところにある復活のイエスが、弟子のダマスコに在住の弟子であるアナニアに対して語って聞かせた内容になっています。
すると、主は言われた。「行け。あの者(パウロ)は、異邦人や王たち、またイスラエルの子らにわたしの名を伝えるために、わたしが選んだ器である。(使徒言行録9:15、()の注は永野よる)
その後、パウロはローマ皇帝に上訴した事により、船便でローマに護送されることになるのですが、パウロが乗った船が暴風によって航行不能になり、最終的にマルタ島に不時着することになります。
マルタ島でパウロは蝮(ヘビ)に噛まれ(噛まれたとは書いてない)たけれども毒を受けることなく、またマルタ島の長官プブリウスの父親の病を癒すなどの奇跡をおこないました。こうした、波乱に飛んだ宣教旅行の末に、パウロはローマに到着するのですが、こうした「波乱に富んだ」という記述については、以下のパウロの手紙に記述があり、恐らくはその記述を元にして、こうした物語を記したのでないかと推測します。
ユダヤ人から四十に一つ足りない鞭を受けたことが五度。鞭で打たれたことが三度、石を投げつけられたことが一度、難船したことが三度。一昼夜海上に漂ったこともありました。しばしば旅をし、川の難、盗賊の難、同胞からの難、異邦人からの難、町での難、荒れ野での難、海上の難、偽の兄弟たちからの難に遭い、苦労し、骨折って、しばしば眠らずに過ごし、飢え渇き、しばしば食べずにおり、寒さに凍え、裸でいたこともありました。(コリントの信徒への手紙2 11章24~27節)
使徒言行録が描くパウロの最期
そして、パウロはローマに到着し、軟禁状態ではあったものの、ユダヤ人たちと語り合い福音を宣教したというかたちで、使徒言行録は、最後、以下のような記述で物語を締めくくっています。
パウロは、自費で借りた家に丸二年間住んで、訪問する者はだれかれとなく歓迎し、全く自由に何の妨げもなく、神の国を宣べ伝え、主イエス・キリストについて教え続けた。(使徒言行録28章30~31節)
以前、説明したように、パウロの死は、伝統では紀元64年にローマで殉教したという話になっています。使徒言行録の成立は紀元90年代ということで、当然「パウロの死」について知っており、「パウロのローマでの殉教」を知った上で、「あえてパウロの死を描かずに、パウロが自由に福音宣教をした」というかたちで終わっています。
もちろん、これは「ルカによる福音書」「使徒言行録」が、洗礼者ヨハネにはじまりイエス・キリスト、そして使徒たちの働きからパウロに至るまで、「神の救済史」という価値観によるものであると同時に、こうしたすべての事柄を「聖霊が導いたのだ」と示すところに「使徒言行録」が書かれた一番のポイントがあるかと思います。
およそ2世紀において、使徒や教父といった人たちの「殉教伝」(例えば『ポリュカルポスの殉教』など)が書かれるようになります。使徒言行録は、そういう意味では「殉教者」としては唯一「ステファノ」ひとりをあげており、ペトロについてもパウロについても「殉教者」としては描いていません。
そうしたことから、「使徒言行録」はペトロについてもパウロについても、その最期はあえて書かずにキリスト教会の働きが、将来に繋がっていく様子を描いてみせたという事ができるかと思います。
そして、そのような描き方をした「使徒言行録」が、2~3世紀のキリスト教会において評価が高かったことが、2世紀に、マルキオンが自分が考えるキリスト教正典として「ルカによる福音書」「使徒言行録」「パウロの手紙」を選んだことからも理解できます。
後に、マルキオンは「異端」として退けられるのですが、こうした2世紀頃から「護教家」と呼ばれる人たちによる哲学的なキリスト教の教理を論述することが盛んになっていきます。以下に、有名な人物を紹介しておきます。
キリスト教の教理の成立について
そして、この後、キリスト教会は迫害を受けながらも、ローマ帝国の各地において活動を進め、また、教理的にもこうした護教家たちによる論述によって、次第にキリスト教信仰のかたちが固められていき、最終的に4世紀になってローマ帝国の国教に認められるようになっていくのです。
さて、護教家たちの解説をするのも良いですがここでは取上げません。
わたしの原稿ではいわゆる「教理史」で扱うところではなく、「使徒言行録」や「パウロの手紙」などを手がかりにして、1世紀から2世紀にかけてのキリスト教会の変遷をおもにこれまで見てきました。
そして、実は、キリスト教の信仰・教理について、最初から「キリスト教教理」「キリスト教信仰」というものが確定していたのではなく、実際問題として、さまざまな信仰の要素の組み合わせがあり、そうしたものの上澄みだけを取り上げて、何となく「キリスト教信仰はこういうものだ」とい感じであり、それがローマ帝国の国教化と共に次第に細かく定義されていったという事になるかと思います。
わたしたちはそれを今日的には「キリスト教教理史」というかたちで学ぶのですが、それはおよそ4世紀以後に確定した信仰であって、以下の図は、「キリスト教教理史以前」の信仰の事柄についてになります。

教理史においては、ある意味で「正統・異端」の区分けが最初から明確であり、その意味では「正統信仰ありき」の話になるのですが、こうした1~2世紀におけるキリスト教信仰は、まだまだそうした「正統・異端」というような考えはなく、かなり自由な感じで、様々な信仰のスタイルを持つキリスト教会が各地に点在したということが言えるかな、と思います。
そして、そうした1~4世紀にかけてのキリスト教信仰を今日わたしたちに教えてくれるものとして「ナグ・ハマディ文書」の発見があります。
ナグ・ハマディ文書についての解説はWikiにゆずるとして、この文書の発見によって、実は1~4世紀にかけてのキリスト教信仰をうかがい知ることのできる文書がいくつも見つかったのです。そして、そうしたナグ・ハマディ文書の中から、今日的にキリスト教信仰に益する文書をいくつか厳選し、今わたしたちが手にしている「新約聖書」と異なる、新しい時代の「新約聖書」として、数年前にアメリカで『A New New Testament』という本が試験的にできました。
この中には、「新約聖書」に含まれていない「パウロの書簡」もあり、これまでわたしたちが見たことのないパウロの信仰に触れることができます。もちろん、これが今すぐに「新約聖書」に取って代わるわけではありませんが、しかし、そうした1~4世紀にかけてのキリスト教信仰のダイナミックな息吹を知ることができる点で、個人的には「良い新約聖書だ」と思います。
A New New Testamentへと続く
まあ、まだまだ翻訳というほどに訳してはいないのですが、そのうちに日本語訳が出ないかな~と密かに考えています。(っていうか、わたしがやらないと誰もやらないか…)(終わり)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
