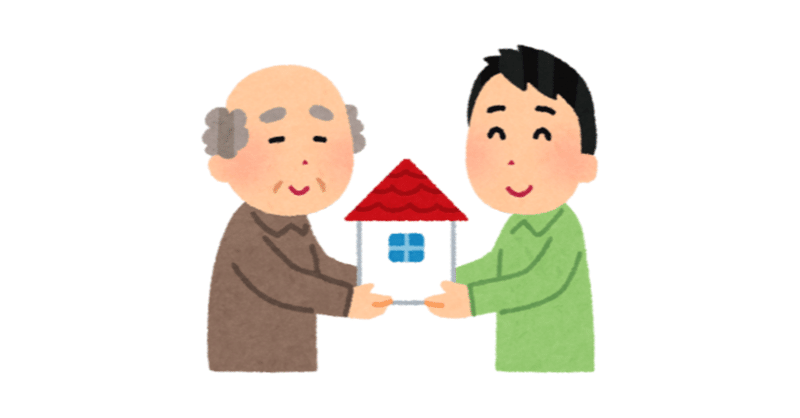
保険本来の趣旨に沿った営業活動に役立つ備忘録①-どうなる?相続・贈与税一体課税(1)-
はじめに
個人的な環境も変わりましたので、約1年振りにnoteを復活いたしました。
現所属先の業務に差し障りのない範囲で、生命保険営業に関連する情報、法令・通達、裁判例などについて、不定期で発信できればと思っております。
生命保険業界に関連する方や、ご興味のある方は、宜しければ、お付き合いください。
※発信内容は、過去も含め、所属・関与する団体等とは一切関係ありませんのでご留意ください。
いわゆる「相続・贈与税の一体課税」について
いよいよ年の瀬も近づいて参りました。
保険業界に関係する皆様も含め、多くの方が注目する与党税制改正大綱、今年は12月15日(木)にも取りまとめられる予定との報道がされています。
保険業界として注目が集まっているのは、なんといっても、いわゆる「相続・贈与税の一体課税」、正確には「資産移転の時期の選択に中立的な税制の構築」という名称で議論がなされています。
当記事では、今までどのような議論がなされてきたかについて、私が把握・理解している範囲で、時系列にまとめていきたいと思います。
機会が許せば、次回、そもそも現行制度がどういうものか、どういう経緯でそうなったのか、結局どうなる見込みなのかという点についても、まとめていきたいと思います。
本格的な議論のはじまり
そもそもの発端は、(2021年度に向けた)2020年11月13日の第4回政府税制調査会にて、本格的な議論がはじまり、マスコミ報道などもあり、世間の注目も浴びたと記憶しています。
終了後の記者会見での中里実政府税調会長の記者会見を勝手に要約すると、「①相続時精算課税制度が開始され20年以上が経過し、諸外国の制度の踏まえ、より根本的なことを考えるきっかけがほしい、②より中立的な制度を」とのことでした。
「相続時精算課税制度」、「諸外国の制度」、「中立的」というキーワードが気になります。
【ご参考】税制改正の流れと税制調査会について
因みに、税制調査会は大きく政府税制調査会と与党税制調査会に分かれ、政府税調は年初から専門家の先生や官僚の方々が議論を重ね、11月末~12月頭にかけて担当の国会議員の先生方が優先順位などを取りまとめ、12月中旬に与党税制改正大綱として、公表されます。
そして、税制改正大綱を元に、官僚の方々を中心に、年末年始返上で法案が作られ、年明けの通常国会にて成立、4月以降順次施行というのが一般的な流れかと思います(税制改正大綱には注目が集まるのに、その後の法案の成立、法令の公布、施行には関心が寄せられないと、個人的に感じています)。
ちなみに政府税調の資料は公表されますが、与党税調の資料は非公表です。
2021年度税制改正大綱について
2020年11月に議論が始まったばかりですので、さすがに2020年の大綱では取り上げられず、2021年以降の動向に注目となりました。
(2022年度に向けた)2021年の政府税制調査会と日本税理士連合会税制審議会について
(2022年度に向けた)2021年の政府税調が気になって仕方がありませんが、新型コロナウイルスの影響なのか、開催回数が少ないようです。
ところが、待てど暮らせどまったく議題には上がってこず、多くの関係する方々がどうなっているんだと、突っ込みを入れたくなったのではないかと思います。
それもそのはず、実は、2021年10月26日に日本税理士連合会が日税連の諮問機関である税制審議会において「資産移転の時期の選択に中立的な相続税・贈与税のあり方について」を諮問をするとの公表がありました(諮問日は2021年10月25日)。
税理士の会報誌「税理士界」第1406号(11月15日付)の記事では、2022年3月を目途に答申、2022年6月に決定予定の日税連建議書にも反映予定とあったと記憶しています。
というわけで、議論が開始されたばかりなので、2021年の大綱には載ってくるはずもなく、2022年以降の動向に注目となりました。
税制審議会の答申と日本税理士会連合会の建議書について
そして、2022年年2月 21 日に、税制審議会より「 資産移転の時期の選択に中立的な 相続税・贈与税のあり方について -令和3年度諮問に対する答申」が公表されました。
答申の「おわりに」を勝手に要約しますと、①「資産の世代間移転を促進するための税制」と②「資産移転の時期の選択に中立的な税制」の2つが必要。
①については、暦年課税制度を見直すことで対処、②については、相続時精算課税制度を改善する ことによって対応すべきことを提言する、とのことです。
因みに、暦年贈与などによく利用される、贈与税の基礎控除の110万円について、一般によく知られていると思いますが、相続税法本法に定められた非課税枠は、実は、60万円です。
平成13年より特例措置(租税特別措置法第70条の2の四(贈与税の基礎控除の特例))として導入され、現在、実質恒久化しています。
そして、上記答申も踏まえ、日税連は、令和4年6月29日に開催された第1回理事会において「令和5年度税制改正に関する建議書」を決定し、8月4日に、財務省、国税庁、総務省、中小企業庁などに提出しました。
当建議書の【相続税・贈与税】の箇所を勝手に要約しますと、
①暦年課税制度は多くの国民に使用されており、その廃止は現実的ではない。相続開始前3年内に贈与を受けた 財産の相続財産への加算の制度について、現行の期間を延長することなどで対応する。
②資産の世代間移転の促進については、贈与税の暦年課税の基礎控除や税率構造を見直すことなどで対応する。
③教育資金や結婚子育て資金の贈与に係る特例 については、適用期限の到来を見据えて廃止又は縮小すべきである。
④相続時精算課税制度は、相続贈・与税の一体化措置として資産移転時期にに中立性の高い税制であり、今後一層の利用促進を図る。
そのため、小規模宅地の評価減の特例との併用や、対象財産の価額が下落した場合の措置等を講じるべき。
⑤他にも、少額贈与の取り扱い変更、相続税の遺産取得課税方式の導入、取引相場のない株式の評価の適正化を図る。
などについて、建議がされました。
暦年贈与は維持、その代わりに現行の相続開始前3年以内の持ち戻しの延長、相続時精算課税制度の使い勝手を良くする、富裕層向けの一括贈与の特例措置は廃止といった流れでしょうか。
※税制審議会答申、日税連建議書共に上記URLから閲覧可能です。
(2023年度に向けた)2022年の政府税制調査会について
日々繰り広げられる政府税調、いつ議題に上がるかと気になって仕方がありませんが、ついに、2022年9月16日の第16回税制調査会において、ついに資産税が議題に上がります。
会議の結論は、
議論を踏まえ、資産移転の時期の選択により中立的な税制の構築等に向けた相続税・贈与税のあり方について、今後の総会における議論の素材を整理するため、専門家会合を設置する。
とのことです。
ここにきて、専門家会合を設置とのこと…果たして結論が出て税制改正に至るにはいつまでかかることやら…
因みに、当会議終了後の記者会見において、中里実政府税調会長より、「一部には、近々暦年課税が廃止されるのではないか、あるいは110万円の基礎控除が使えなくなるのではないかといった見方、御懸念があるようですが、そういった議論を行うのではなく、理論的・実務的な観点も踏まえて御議論いただければと考 えています。」というコメントがあり、マスコミ報道等もされたので、ひとまず、胸をなでおろした保険業界関係者の方も多いのではないでしょうか。
まだまだ時間がかかると思いきや、なんと、2022年11月8日の政府税調において専門家委員会の報告がされています。
論点整理の当面の対応を勝手に要約しますと、
相続税の課税形態について、遺産取得課税方式が理想だが、当面は現行の法定相続分課税方式の維持が現実的である。
当面の対応としては、①相続時精算課税制度、②暦年課税における相続前贈与の加算、③経済対策等として時限的に講じられている贈与税の非課税措置について検討することが考えられる。
①相続時精算課税制度は平成15年に導入され、中立的な制度だが、広く活用されているとはいいがたい。
暦年贈与との一部併用や、小規模宅地の評価減の特例との併用や対象財産の価額が下落した場合などの例外的取り扱いの新設について、公平性を考慮しつつ慎重な対応必要。
②暦年課税における相続前贈与の加算は、現行期間を延ばすことが適当、事務負担を軽減の観点から、 少額贈与に係る取扱いについても検討が考えられる。
③教育資金や結婚・子育て資金に係る非課税措置については、制度創設 当初と比べ、適用件数も大きく減少している。
相続時精算課税制度の使い勝手の向上と併せて、廃止する方向で検討することが適当ではないか。
こちらをもって政府税調は終了、あとはブラックボックスの与党税調に突入し、12月中旬の与党税制改正大綱を待つばかりです。
マスコミの独自報道が伝え漏れてきますが、果たして結果はどうなるか…
さいごに
最後に生命保険営業の観点から、個人的に気になるポイントを述べさせていただきます。
世代間の資産移転促進を目的とするなら、相続前贈与の加算期間延長とバランスを取り、租特法上の贈与税の非課税枠の拡大があってもよいのでは思ったりもします。
また、現行法では、相続前贈与の加算については、相続・遺贈等によって財産を取得した者が対象(相続税法第19条1項)ですので、例えば、原則、孫への贈与は対象外となります。
このあたりの法構成もどうなるか、注目です。
当記事とは関係ありませんが、令和4年4月19日最高裁裁判例を受けての賃貸用不動産に関する財産評価基本通達の改正や、NISA関係の改正も気になります。
駄文・雑文にも関わらず、最後までお読みくださり、誠にありがとうございました。
頭ではなんとなく整理がついているつもりでも、文章に落とすには、想像以上の時間がかかってしまいました。
次回、そもそも現行制度がどういうものか、どういう経緯でそうなったのか、結局どうなる見込みなのかという点についても、早急に、取りまとめたいと思います。
※当記事は、著作権法、税理士法第52条、弁護士法第72条などに抵触しないよう、細心の注意を払い作成しているつもりですが、万が一、内容に誤り、不適切な点、法令に抵触するような点がある場合は、その旨ご指摘くだされば幸いに存じます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
