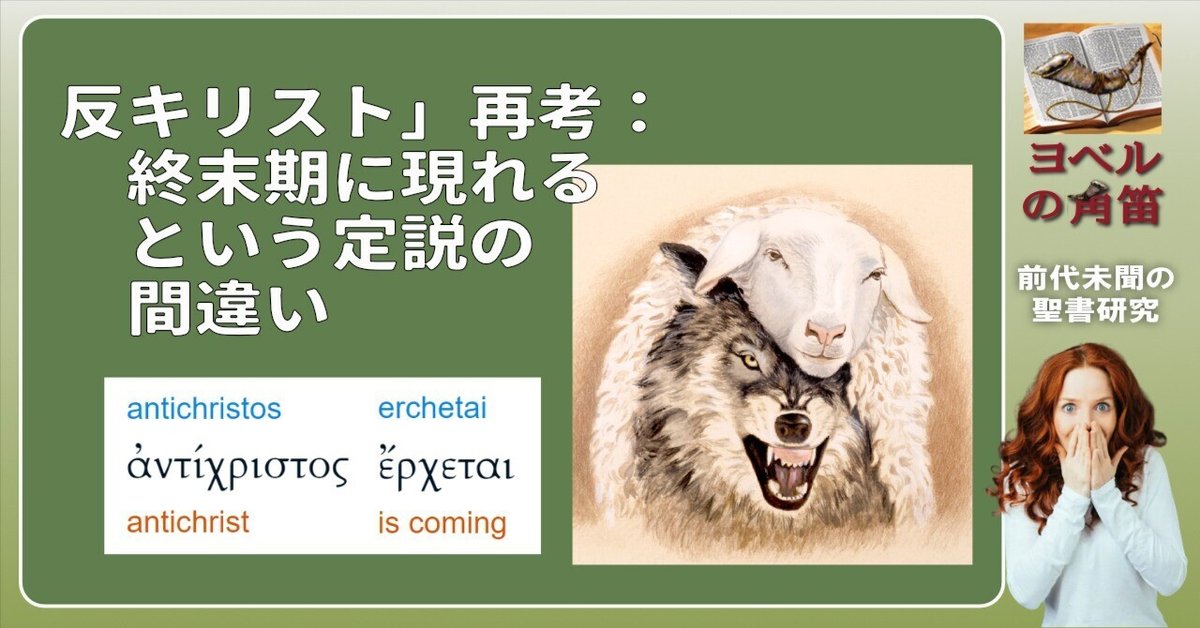
「反キリスト」再考: 終末期に現れるという定説の間違い
【ヨハネの手紙だけに見られる「反キリスト」】
この語は聖書中に5回出現します。すべて使徒ヨハネの手紙ですが、まずこれらをすべて引用しておくことにしましょう。
《子供たちよ、終わりの時が来ています。反キリストが来ると、あなたがたがかねて聞いていたとおり、今や多くの反キリストが現れています。これによって、終わりの時が来ていると分かります。》Ⅰ ヨハネ 2:18
《偽り者とは、イエスがメシアであることを否定する者でなくて、だれでありましょう。御父と御子を認めない者、これこそ反キリストです。》Ⅰ-2:22
《イエスのことを公に言い表さない霊はすべて、神から出ていません。これは、反キリストの霊です。かねてあなたがたは、その霊がやって来ると聞いていましたが、今や既に世に来ています。》Ⅰ-4:3
《このように書くのは、人を惑わす者が大勢世に出て来たからです。彼らは、イエス・キリストが肉となって来られたことを公に言い表そうとしません。こういう者は人を惑わす者、反キリストです。》ⅱ-1:7
Ⅰ-4:3では、「やってくると聞いていた」のは、イエスが肉体で来られたということを否定する【霊(精神、論調)】であり、必ずしも「反キリスト」という特定の人物が登場するという事ではなく、そうした傾向を示す(吹聴する)者が実際に現れているゆえに、あれもそう、これもそう、つまり反キリスト(の霊を表す)という部類に属する人間。ということを示そうとしているのでしょう。
これから注目したいのは「今や既に世に来ている」(Ⅰ-2:18; Ⅰ-4:3)とヨハネが述べている「今」とはいつのことでしょうか。
ヨハネの福音書と3通の手紙は、およそ西暦85~90年頃に記されたとされています。
この頃すでに「反キリスト」は現れていました。 そして、そのことは、かねてから聞いていたことだと述べています。
しかし、先に述べましたように「反キリスト(アンティ クリストス)」という単語自体、ヨハネによるこれらの書簡にしか見あらたらず、聖書中に、これら以外に「終末期に反キリストが現れる」という記述は存在しません。
つまり、1世紀当時の弟子たちには何らかの形で、そうした話が知られていたのでしょうが、明らかに、ヨハネによる「反キリスト」に関する記述は、当時の出来事として、以前から聞いていたことが、今(西暦85~90年頃)、実現していると指摘しているもので、明確に「聖書預言」という形で聖書に記されていることではないということです。
実際ヨハネは、「反キリスト」が将来現れるというようなことを仄めかしてさえいません。
マタイ24章やルカ21章などの預言に見られる、2重の意味を含んだ「予言的雛形」でもなく、完全に過去の、あるいはキリスト教歴史上の存在であって、今後の終末期を特色づける存在ではないということです。
実のところ、当時の弟子たちは、どういう風に「反キリストが来る」というようなことを聞いていたのでしょうか。
そして、そのタイミングと「終わりのとき」がシンクロしているということをどのように聞き及んでいたのでしょうか。
「反キリスト」というネーミングはヨハネによるオリジナルですから、別の表現で言及されていたに違いありません。
ヨハネの記述の「反キリスト」の特徴から、それ以前に、それらがどのように表現、言及されていたのかを探ってみることにしましょう。
【「反キリスト」の特徴】
「小麦と毒麦」
まずイエス・キリストご自身による喩えですが、
《人々が眠っている間に、彼の敵が来て麦の中に毒麦を蒔いて行った。麦が芽ばえ、やがて実ったとき、毒麦も現れた。》マタイ13:25,26
《毒麦を抜き集めるうちに、麦もいっしょに抜き取るかもしれない。》13:29
特色: 後から蒔き足された。一見見分けがつかない。
パウロは西暦56年ごろ,ローマのクリスチャンにこう書き送っています。
《あなたがたの学んだ教えにそむいて、分裂とつまづきを引き起こす人たちを警戒してください。彼らから遠ざかりなさい。そういう人たちは、私たちの主キリストに仕えないで、自分の欲に仕えているのです。彼らは、なめらかなことば、へつらいのことばをもって純朴な人たちの心をだましているのです。》(ローマ16:17,18)
特徴: 「分裂と躓きを引き起こす」「純朴な人たちの心をだます」(人を惑わすもの)
こうした状況は,使徒たちが亡くなるとさらに悪化することが考えられます。パウロは警告しました。
《私が出発したあと(去った後:新共同訳)、凶暴な狼があなたがたの中に入り込んで来て、群れを荒らし回ることを、私は知っています。
あなたがた自身の中からも、いろいろな曲がったことを語って、弟子たちを自分のほうに引き込もうとする者たちが起こるでしょう。》―使徒 20:29,30。
エペソからエルサレムに帰った後、聖霊により「なわめと苦しみが私を待っている」と繰り返し告げられたこともあり、自分の生存がもう長くないことを悟っていたことが伺えます。20章の最後の節は《彼が、「もう二度と私の顔を見ることがないでしょう。」と言ったことばによって、特に心を痛めた。それから、彼らはパウロを船まで見送った。》という文で終わっています。
エペソの教会を立ち去ったら直ちに入れ替わりにということも考えにくいので、おそらく、「曲がったことを語る者が教会内に入り込んで来ること」の抑止力となっていたパウロが地上の表舞台から去った後ということを意味しているに違いありません。
これが書かれたのは西暦60-61年頃ですから、それ以降、そうした兆候はすでにみられ、ヨハネが「反キリスト」について記した西暦85~90年頃には、明確なかたちで大勢現れていたということです。
【随所に見られる「反キリスト」の影響に関する記述】
《というのは、もしある人がきて、わたしたちが宣べ伝えもしなかったような異なるイエスを宣べ伝え、あるいは、あなたがたが受けたことのない違った霊を受け、あるいは、受けいれたことのない違った福音を聞く場合に、あなたがたはよくもそれを忍んでいる。 こういう人々はにせ使徒、人をだます働き人であって、キリストの使徒に擬装しているにすぎないからである。しかし、驚くには及ばない。サタンも光の天使に擬装するのだから。だから、たといサタンの手下どもが、義の奉仕者のように擬装したとしても、不思議ではない。彼らの最期は、そのしわざに合ったものとなろう》 2コリント11:13,5
《しかし、“霊”は次のように明確に告げておられます。終わりの時には、惑わす霊と、悪霊どもの教えとに心を奪われ、信仰から脱落する者がいます。》1テモテ4:1
《かつて、民の中に偽預言者がいました。同じように、あなたがたの中にも偽教師が現れるにちがいありません。彼らは、滅びをもたらす異端をひそかに持ち込み、自分たちを贖ってくださった主を拒否しました。自分の身に速やかな滅びを招いており、 しかも、多くの人が彼らのみだらな楽しみを見倣っています。彼らのために真理の道はそしられるのです。 彼らは欲が深く、うそ偽りであなたがたを食い物にします。このような者たちに対する裁きは、昔から怠りなくなされていて、彼らの滅びも滞ることはありません。》
2ペトロ 2:1-3
(※この引用聖句中の「異端をひそかに持ち込み」という訳は問題がありますが、ここではタイトルから逸れますので、巻末に脚注として記しておくことにします。)
《兄弟たち、あなたがたに勧めます。あなたがたの学んだ教えに反して、不和やつまずきをもたらす人々を警戒しなさい。彼らから遠ざかりなさい。 こういう人々は、わたしたちの主であるキリストに仕えないで、自分の腹に仕えている。そして、うまい言葉やへつらいの言葉によって純朴な人々の心を欺いているのです。》ローマ16:17,18
《一度光に照らされ、天からの賜物を味わい、聖霊にあずかるようになり、 神のすばらしい言葉と来るべき世の力とを体験しながら、 その後に堕落した者の場合には、再び悔い改めに立ち帰らせることはできません。神の子を自分の手で改めて十字架につけ、侮辱する者だからです。》 ヘブライ 6:4-6
(ここでは”十字架”は救いのシンボルどころか、”侮辱”の象徴だとしています。)
《人々が健全な教えに耳を貸そうとせず、自分につごうの良いことを言ってもらうために、気ままな願いをもって、次々に教師たちを自分たちのために寄せ集め、真理から耳をそむけ、空想話にそれて行くような時代になるからです。》2テモテ4:3,4
「後の時代になると」とは、パウロを初め、他の使徒たちが順に死に、その影響力が弱まるにつれて、教会内に「毒麦」のような不純なもの、つまり偽クリスチャン、偽教師たちが次第に幅を効かせて行ったということでしょう。
そして、晩年のヨハネの頃には、「大勢の反キリストが現れている」という状態になっていました。
【「反キリスト」が現れる「終わりのとき」とはいつ?】
ヨハネが、「終わりの時に」と述べているのは、そうした、クリスチャン会衆(教会)が発足したペンテコステのとき以来、奇跡的な賜物の故に華々しく一時代を彩った世代の終わりの時に。という意味に違いありません。
このことは、ヨハネの手紙の一つの特徴からも伺い知ることができるかと思います。
その特徴とは、ヨハネは「最初から」とか「最初の」という言葉を多用していると思えることです。
拾い上げてみましょう。
《初めからあったもの、私たちが聞いたもの・・》
1ヨハネ 1:1
《これはあなたがたが初めから持っていた古い命令です》1ヨハネ 2:7
《あなたがたは、初めから聞いたことを、自分たちのうちにとどまらせなさい。もし初めから聞いたことがとどまっているなら、あなたがたも御子および御父のうちにとどまるのです。》1ヨハネ 2:24
《互いに愛し合うべきであるということは、あなたがたが初めに聞いている教えです。》1 ヨハネ 3:11
《私が新しい命令を書くのではなく、初めから私たちが持っていたものなのですが・・》2 ヨハネ 1:5
《命令とは、あなたがたが初めから聞いているとおり、愛のうちを歩むことです。》2 ヨハネ 1:6
言い換えれば、年月の経過とともに、様々な変節の影響を危惧して、あたかも、今が、「終わり」を迎えつつあるという感覚が強く働いていた故に、今後の継続すべきものを確認し念を押す響きが感じられます。
それらの記述から「初めから」聞いているクリスチャンとしての基本を死守するよう言い残しておきたいというヨハネの思いを感じます。
ヨハネ自身 老齢でしたが、それだけでなく、ペンテコステ以来の使徒たちを中心とした偉大イベントの幕が降りようとしていることを悟っていたに違いありません。
ですから一つの結論として、ヨハネだけが用いている「反キリスト」という呼び名と、それらが現れる「終わりの時」とは「使徒たちの時代が終わる時」を示す限られた期間に違いないということです。
「反キリスト」にはそれ以上を意味する、終末期に関わる預言とみなす聖書的根拠は存在しないということです。
「反キリスト」はすでに、1世紀当時の終わり頃現れ始め、ヨハネの晩年には「大勢」現れていました。
そして、それは、消えることなく勢力を増し、むしろ人数的に逆転し多数派になってゆきます。
イエスが、「狭い門を見出しているものは稀であり、滅びに至る者のほうが多い」と言われたのはそういうことです。
そしてそれは現代にまで及び、「反キリスト」はこれから出現するものではなく、「小麦」とされるクリスチャンを凌駕し、実際は「反キリスト」である、「毒麦」からなる自称クリスチャンが圧倒的に多数存在しているということです。
これはすなわち、端的に言えば、使徒たちが去った後の時代の「キリスト教」には「反キリスト」の影響が色濃く反映されているというのが真実の姿だということです。
さて、少し話が前後しますが、ここで改めて、ヨハネの述べる「反キリストの霊」とはどのようなものなのかを明らかにしておきたいと思います。
【「み父とみ子を否定する」とは?】
「み父[と]み子を否定する」とは、具体的にどういうことでしょうか。
例えば「み父[も]み子[も]否定した」としたら、それは単に無神論者か、少なくとも「キリスト教」とは全く無関係な存在でしょう。
では「神(ヤハウェ)は認めるし、イエスという人物も認める」人はどうでしょうか。
それは「み父とみ子を肯定している」と言えるでしょうか。
Ⅰ-4:3には「イエスのことを公に言い表さない霊はすべて反キリスト」という表現がありますから、そうした人々も「反キリスト」の部類に入るのでしょうか。
それは違うでしょう。なぜなら、多くのユダヤ人の見解はそのようなものでしょうから、1世紀初頭から常にそうしたスタンスですから「後に現れると聞いていいる者」というものではないからです。
つまりこの表現は取りも直さず、そのお二方の「関係性」を否定するということでしょう。
そしてこれは極めてセンシブルな問題を含んでいます。
み子ご自身が、ご自分と神について語られた部分は、文字通り「神妙」なものであり、改めて背筋を正すことをすべてのクリスチャンに促すはずです。
「子がどういう者であるかを知る者はなく、父がどういう方であるかを知る者は、子と、子が示そうと思う者のほかには、だれもいません。」(ルカ 10:22)
・・何と「誰も見たことがない」み父以上に、人間となって人々の間に生活された、み子こそ、よりミステリアスな存在だと言うことです。
それゆえ「・・こう考えられるが、「誰も知らない」と言われている故に、今のところ、神とは誰か、(何か)と言う事を断言できる聖書的な根拠がありません。」と言うのが、本来あるべき「神学」の姿勢ではないでしょうか。
「キリストによって蒔かれた「小麦」の畑に「毒麦」が大量にバラまかれるというキリストの警告的な預言を忘れてはなりません。
さてそれはともかく、ここで、325年のニケーア公会議に始まる数回の公会議を通じて、キリスト教の正統教義とされた「三位一体」について、若干の言及をしておきたいと思います。
「子」がどういう者なのかは「誰も知り得ない」と断言されている以上、神は三位一体かもしれませんが、しかし、全くそうでない可能性も否定はできないという事実を覚えておくべきでしょう。
あくまで、キリストは、元来神の独り子であり、肉体を持った人間として、み父によって地に遣わされたということを認めるということであり、それ以上でもそれ以下でもないということ。聖書に明らかに示されていることを、そのまま素直に受け入れ、信じ、そして公言するというシンプルな姿勢が一番です。
「子」がどういう者なのかは「誰も知り得ない」にも関わらず「父と子は一体であり同等である」というような主張が、もし間違いであったなら、「み父とみ子」を「否定」しているわけではないかもしれませんが、その関係性を甚だしく捻じ曲げていることになり、やはり「反キリスト」の部類とみなされるのは必至でしょう。
ですから、分からないこと、分かりようのないことを、断定的に、声高に公言したりせず、「神の実態についてはよく分からない」としておくのが身のためだと思います。そうすれば、万が一でも自分が「反キリスト」の部類に入ってしまうことを避けられるでしょう。
この点の詳細は下記記事を御覧ください。
ともかくキリストそのものを否定するものではなく、キリストの出自、源、み父との関係などを否定する者ですから、「反キリスト」の立場は、無神論者でも、異教徒でもなく、いわゆる「クリスチャン」(キリストに属するものであることを公言して者)の中から、そうした逸脱した神学的な主張をするようになった個人あるいは教派のことでしょう。
なぜなら、反キリストは「人を惑わす者」であるということですから、クリスチャンを自認する人が、信仰の全く異なる立場からの見解に惑わされることはまず、ないでしょう。
むしろ、仲間の意見だからこそ、惑わし兼ねない影響力を持つものと言えます。
ヨハネが手紙の中で懸念していた事は、まさしくそのことです。
さて「反」キリストという訳語ですが、確かに否定する者もそうですが、ギリシャ語の元の言葉にはさらに別の意味も含まれています。
「アンティ クリストス」というのは、厳密には「キリストに反対する」という意味ではありません。
ギリシヤ語の [ anti ] という言葉は、「反対」というよりむしろ「~に代わって」という意味が強い語句です。英語ですと、instead of~になります。
したがって、反キリストとは、「キリストに代わるもの」あるいは、「キリストの代替物」ということになります。実際このアンチというギリシャ語が使われている他の聖句のほとんどはその語を「・・に代わって」と訳しています。
従って、正確に訳すと、「反キリスト」ではなく「擬似キリスト」「代替キリスト」と訳すのが本来の言語意味をもっともよく伝える訳と言えると思います。
というわけで、後述のテサロニケ人への手紙にあるように、「不法の人」は、自分こそが神であると主張する、あるいはキリストにしかできない事を行おうとする人間であり、「アンティ クリストス」です。
【なぜ終末期に「反キリスト」が現れる、と言われているのか】
「終末期には反キリストは現れないという聖書的根拠」というのがこの記事のテーマですが、これは厳密に言うと、固有名詞的に、特定の人物を指すという一般の理解に基づいての表現であり、実際は、いつの時代も、そして終末期にも、「反キリスト」は途切れることなく存在し続けるというのが、本来の聖書に適った正確な認識とすべきものです。
さて、では、なぜ終末期に「反キリスト」なる人物が現れるという解釈が定番となっているのでしょうか。
それは、ヨハネの手紙の「終わりの時」という表現と、終末期を指す「終わりの日(時)」を混同しているからに他なりません。
これから、その終末期を表す「終わりの日」と、ヨハネの手紙の「終わりの時」が全く異なる別のタイミングであると言える聖書的根拠について取り上げることにしましょう。
まず、改めて第一ヨハネ2章18節に二度登場する「終わりの時」と訳される原語を紹介します。


ἐσχάτη ὥρα (エスカテー ホーラー 終わりの時)
単数形 last, finally, ラスト、最終
ギ語:ホーラー:a time or period, an hour, アワー、時刻
【終わりの時】は英語では(last hour)です。それでこの部分を直訳的に訳すと、節全体はこうなります。
《今は【最終時】です。あなたがたが反キリストの来ることを聞いていたとおり、今や多くの反キリストが現れています。それによって、今が【最終時】であることがわかります。》1ヨハネ2:18
しかも単数形ですから、数年に及ぶ期間を示すようなものではなく、ほんのひととき、あるいは一時期を指し示すという意図がヨハネにはあったのかもしれません。
そして銘記しておくべき点は、この「終わりの時(エスカテー ホーラー)」はこの節に2度登場しますが、このフレーズは聖書中にただ1節、この「1ヨハネ2:18」のみに見られるということです。
これだけでも、「反キリスト」の出現タイミングが、多く語られている終末期とは別個の期間であることが分かります。
実際「ホーラー」は最も短い時間(期間)を表す単語です。当然ギリシャ語にも、ときの長さに関する複数の異なる単語が存在します。
《四人の天使は、人間の三分の一を殺すために解き放された。この天使たちは、その【年(エニーオートス)】、その【月(メン)】、その【日(ヘメラー)】、その【時間(ホーラー)】のために用意されていたのである。》黙示録 9:15
そしてこの語は聖書中に106回使用されていますが、多くの箇所では単数形で「その時、この瞬間 (moment)」と訳されています。またそのうち3箇所だけ、複数形ですが、いずれも限られた文字通りの数時間を指すために使用されています。
単数形の例:
《ちょうどその時 (that very moment)》マタイ8:13
《ちょうどこのとき (At that very moment)》 ルカ2:38
《即座に(at that very moment)》使徒16:18
複数形の例:
《昼間は十二【時間】あるではないか》ヨハネ11:9
《それから三【時間】ほどたって》使徒5:7
《二【時間】ほども叫び続けた》使徒19:34
これらのことから「反キリスト」が現れるタイミングとしての「終わりの時」は決して「終末期」のような一時代を特徴づける、一定期間(年数)を指しているとは到底言い難いと思えます。
【「終末期」を指す「終わりの時」との相違点】
では、終末期あるいは、その特定の期間に関連した、世の末とみなされる時代についてはどのような語で記されているのでしょうか。
最後にその点を明らかにしておくことにしましょう。
〘 ヨハネの手紙の「終わりの時」という表現と、終末期を指す「終わりの日(時)」を混同している 〙ということを先に述べましたが、これから、聖書中の「終わり」(~の時、~の日)という表現を比較してみることにしましょう、
まず、いくつかの「終わり」に関する似通った聖句を引用することにしましょう。
《「終わりの時には、自分の不敬虔な欲望のままにふるまう、あざける者どもが現れる。」 この人たちは、御霊を持たず、分裂を起こし、生まれつきのままの人間です。》ユダ18,19
この聖句の「終わりの時」は「ギ語:エスカトウ トゥ クロノウ (語根で記すと「エスカトス と クロノス」という語で構成されています)
英語では「last time」ですが、ギ語:クロノスは、ホーラーとは違い、一定の定まった時間、連続した期間というニュアンスを持った単語です。
《ヘロデは・・彼らから星の出現の時間(クロノス)を突き止めた。》マタイ2:7
《さて月(クロノス)が満ちて、エリサベツは男の子を産んだ。》ルカ1:57
ではユダの記したこの「終わりの時」とはいつのことでしょうか。
これも、ヨハネの記した「終わりの時」と同様の時を指し示しているといって良いでしょう。(つまり終末期ではない)
その根拠は次のようなものです。
ユダはこの手紙の冒頭で、「あらゆる努力をしていましたが、聖徒にひとたび伝えられた信仰のために戦うよう、あなたがたに勧める手紙を書く必要が生じました。というのは、ある人々が、ひそかに忍び込んで来たからです。彼らは、このようなさばきに会うと昔から前もってしるされている人々で、不敬虔な者であり、私たちの神の恵みを放縦に変えて、私たちの唯一の支配者であり主であるイエス・キリストを否定する人たちです。」と記しています。
つまりヨハネが指摘した「反キリスト」に関する勧告です。
ユダの手紙全体が正にこの目的のものだということが分かります。
ユダの記述の「クロノス」の方が、ヨハネの用いた「ホーラー」に比べ、より厳密な、一定期間に見られる状況をよく表していると言えます。しかしユダの手紙も将来の出現の預言ではありません。
「反キリスト」的人物に常に警戒しているべきという普遍的な勧告です。
では、更に別の「終わり」についての記述を調べてみましょう。
ここで論じている「終末期」とは、サタンが天から放逐され、その権化である「不法の人(小さい角、海から上がる獣、666)」が世界的に一世を風靡することになる、イエス・キリストの再臨に先立つ苦難の期間のことです。
その「終末期」を指してヨハネがどんな語句で表現しているかにまず注目してみましょう。
《・・ひとりひとりを終わりの日によみがえらせることです。事実、わたしの父のみこころは、子を見て信じる者がみな永遠のいのちを持つことです。わたしはその人たちをひとりひとり終わりの日によみがえらせます。 わたしは終わりの日にその人をよみがえらせます。》ヨハ6:39,40,44,54
《私は、終わりの日のよみがえりの時に、彼がよみがえることを知っております。》ヨハネ11:24
《わたしが話したことばが、終わりの日にその人をさばくのです。》ヨハネ12:48
ここに挙げた聖句は紛れもなく、終末に関する記述であり、そこで示されている「終わりの日」あるいは「終わりの時」と訳されている語はすべて「エスカテー ヘメラ」です。
さらにヨハネ以外の、同じ終末に関する聖句もいくつか上げておきましょう。
《これは、預言者ヨエルによって語られた事です。『神は言われる。終わりの日に、わたしの霊をすべての人に注ぐ。すると、あなたがたの息子や娘は預言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。・・』》使徒2:16、17
《金持ちたち。あなたがたの上に迫って来る悲惨を思って泣き叫びなさい。・・あなたがたの金銀にはさびが来て、そのさびが、あなたがたを責める証言となり、あなたがたの肉を火のように食い尽くします。あなたがたは、終わりの日に財宝をたくわえました。》ヤコブ5:1-3
《終りの時には、苦難の時代が来る。その時、人々は自分を愛する者・・》2テモテ3:1
《終わりの日に、あざける者どもがやって来てあざけり、自分たちの欲望に従って生活し、次のように言うでしょう。「キリストの来臨の約束はどこにあるのか。・・」》2ペトロ3:3,4。
これらはいずれもすべて「エスカテー ヘメラー」です。つまりヨハネが「反キリスト」ついて記している「エスカテー ホーラー」とは異なる時を指し示していることが分かります。
聖書が明らかにしている、キリストの再臨に先立って現れるとしているのは「反キリスト」ではなく「不法の人」「滅びの子」です。
《だれがどのような手段を用いても、だまされてはいけません。なぜなら、まず、神に対する反逆が起こり、不法の者、つまり、滅びの子が出現しなければならないからです。この者は、すべて神と呼ばれたり拝まれたりするものに反抗して、傲慢にふるまい、ついには、神殿に座り込み、自分こそは神であると宣言するのです。・・今、彼を抑えているものがあることは、あなたがたも知っているとおりです。それは、定められた時に彼が現れるためなのです。 不法の秘密の力は既に働いています。ただそれは、今のところ抑えている者が、取り除かれるまでのことです。その時が来ると、不法の者が現れます・・不法の者は、サタンの働きによって現れ、あらゆる偽りの奇跡としるしと不思議な業とを行い・・》2テサロニケ2,3-9
終末期のイベントが主に演じられる舞台は「イスラエル」です。
「反キリスト」と「不法の人」の決定的な違いは、「反キリスト」はあくまでキリスト教会内に現れてクリスチャンを惑わす者です。
先に述べたとおり、ユダヤ教では、イエスが肉体で来られたことや、イエスがメシアであることなどを否定しますが、ではユダヤ教徒が「反キリスト」かというと全くそんなことはありません。
しかし「不法の人」は、キリスト教の範疇を凌駕し、ユダヤ教やイスラームを含む全宗教の上に、自らを神として君臨しようとする者です (どこかの教団を乗っ取るというようなものではなく、神殿に座り込む)。
また、「不法の人」は、「定められたときに現れるため」つまりキリスト臨在の直前に現れるまでは、強制的に引き止められているとされています。さらには、「あらゆる偽りの奇跡としるしと不思議な業とを行う」という点も「反キリスト」とは異なっています。
巻末の脚注:
《同じように、あなたがたの中にも偽教師が現れるにちがいありません。彼らは、滅びをもたらす異端をひそかに持ち込み、自分たちを贖ってくださった主を拒否しました。》2ペトロ 2:1
この中で「異端」と翻訳されている語は「ギ語:ハイーレシス」という語で、これは「取る、選ぶ、好む」という意味を持つ「ハイーレオマイー」という動詞から派生した語で、「ハイーレシス」は「個人的な選択」というニュアンスの語で「異端」というような特定の意味はありません。完全な誤訳です。
この語は多くのところで、パリサイ派、サドカイ派、ナザレ派などと「派、もしくは宗派」と訳されています。例えば
パウロはアグリッパ王に自己紹介する際に次のように述べています。
「私は、私たちの宗教の最も厳格な【派】(ハイーレシス)に従って、パリサイ人として生活してまいりました。」使徒26:5
「ハイーレシス」が「異端」であるなら、パリサイ派、サドカイ派、ナザレ派など全部が異端で、主流派は一つもないということになります。
現代であれば、○○派 という教派(宗派)も一つ残らず「異端」ということになってしまいます。
なんという乱暴で馬鹿げた翻訳なのでしょう。
塚本訳では、この部分を 《(勝手な)教義を持ち込み》と訳しており、原文のニュアンスに近いでしょう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
