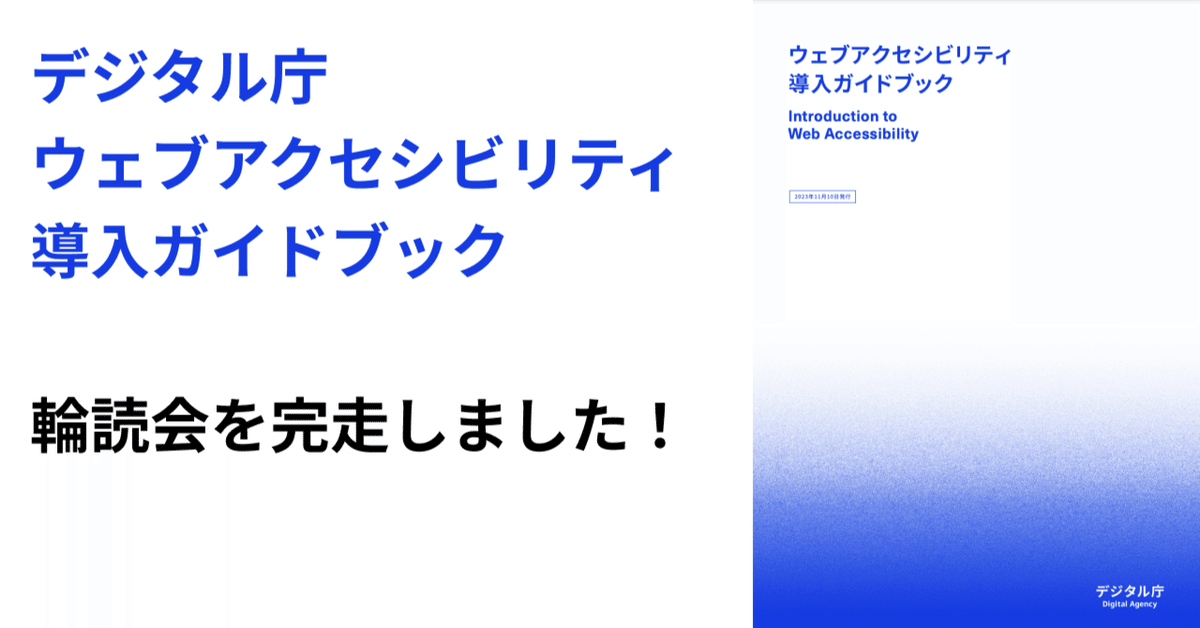
デジタル庁『ウェブアクセシビリティ導入ガイドブック』の輪読会を完走しました!

これは、株式会社ゆめみ 23卒Advent Calendar 2023 22日目の記事です🎄
こんにちは! 株式会社ゆめみでフロントエンドエンジニアをやっているやぎたです。
社内で行っていたデジタル庁が公開している『ウェブアクセシビリティ導入ガイドブック』の輪読会を先日完走しました!
この記事では、始めたきっかけや、完走してどうだったかなどを話せたらと思います!
輪読会を始めたきっかけ
10月、書籍『Webアプリケーションアクセシビリティ』の輪読会を完走しました。
参加メンバーのアクセシビリティへの熱を冷ますことなく次に繋げたいと思い、メンバー間で話し合って『ウェブアクセシビリティ導入ガイドブック』の輪読会を行うことを決めました。
以前書籍『Webアプリケーションアクセシビリティ』の輪読会参加メンバーで開催した「ゆるアクセシビリティ雑談会」という勉強会で、『ウェブアクセシビリティ導入ガイドブック』の一部を資料として使用したことがありました。そこでもっとこのガイドブックを読みたいと思ったことが理由です。
『ウェブアクセシビリティ導入ガイドブック』には、以下のような特徴があります。
無料で公開されている
図が多くてわかりやすい
WCAGやJIS X 8341-3:2016をはじめ、様々な資料が参照されており、アクセシビリティを学ぶ最初の一歩にできる
これらの特徴を活かし、全社に告知しより多くの参加者を募ることにしました。(書籍『Webアプリケーションアクセシビリティ』の輪読会は主に新卒の知り合い中心で行っていました。)
参加のハードルを下げるため、開催時間を1回30分と勉強会としては短めに設定し、1回分はすぐ読める量にして「間に合わなければ読んで来なくてもOK」というようにしました。
輪読会は、以前『Webアプリケーションアクセシビリティ』の輪読会を行っていたチャンネルにてハドルで行うことにしました。このチャンネルが日常的にアクセシビリティの情報が流れてくるチャンネルになっており、チャンネルを覗いてくれる人を増やしたいという意図がありました。
告知は、社内の勉強会共有チャンネルのほか、運営メンバーのojtチャンネル(個人チャンネル、よく「times」と呼ばれるものと似ている)や所属するチームのチャンネル、さらに24卒メンバーがいるチャンネルでも共有しました。

よかったこと
参加者が幅広くなった
会の最初にチェックイン(アイスブレイクのようなもの)として職種とアクセシビリティについてのイメージを聞きました。アクセシビリティへのPM、フロントエンド、モバイルエンジニア、バックエンドエンジニア、デザイナーなど本当に様々な職種、色々な考えを持っている方が参加してくれました。

特にPMの方が「これを実際の案件でやるとしたら?」という風に考えてくれたのは新鮮な視点で、とても勉強になりました。「デジタル庁」という名前の知名度で、エンジニア以外の人も来てくれたような気がします。
ガイドラインを参加者のみんなで覗いてみることができた
『ウェブアクセシビリティ導入ガイドブック』では、WCAGやJIS X 8341-3:2016などの参照が書かれており、輪読会で「話題のついでにちょっとガイドラインを覗いてみる」ことができました。ガイドラインを読んだことが無かった人の始めの一歩になりました。
アクセシビリティカンファレンス福岡 2023を有意義なものにできた
11月11日に開催されたアクセシビリティカンファレンス福岡に筆者は参加者として、もう一人の運営メンバーがスタッフとして参加しました。
そこでデジタル庁の伊敷政英(@cocktailzjp)さんに挨拶することができました。「ガイドブック」の輪読会やってます! と伝えると応援してくださいました。
また、アクセシビリティカンファレンス福岡にて伊敷さんはその前日にガイドブックが改訂されたことを話されていました。後日勉強会で改訂された箇所を確認できました。
課題
勉強会の進行について、『Webアプリケーションアクセシビリティ』輪読会は全員該当箇所を事前に読んできて、気になるところを議論する形でした。参加者の数や幅が増える中で、事前に読んできて議論する前提だと、アクセシビリティ聞いたことあるなぁくらいのメンバーは声を出しづらそうに見えました。一つの勉強会の中で、資料を読み合わせして知見を得る時間と、それをもとに議論する時間を分けるなど、やり方を工夫していきたいと思います。
参加者の声(一部抜粋)
「この勉強会がなかったらアクセシビリティに興味を持たなかった」
「積極的にアクセシビリティ勉強していこうという姿勢がすごいと思った」
「聞いているだけで勉強になって楽しい」
「普段PMなのでフロント寄りの方と話せて楽しかった」
「自分が不便さを感じてないことへ興味を持つ難しさを感じた」
まとめ
『ウェブアクセシビリティ導入ガイドブック』の輪読会では、一人一人で勉強するよりも多くの人が深くWebアクセシビリティを学べたと思います。Webアクセシビリティについて詳しい人が増えると、結果的により多くのWebサイトがアクセシブルになると考えています。アクセシビリティの勉強会を開く意義はそこにきっとそこにあるのだなと感じました。
2024年も輪読会やLT会など、イベントをいろいろ考えています。何も決まっていませんが、社外イベントや他社様とのコラボイベントなどもできたらいいなぁ と考えておりますので、よろしくお願いします。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
