
最高のやり方





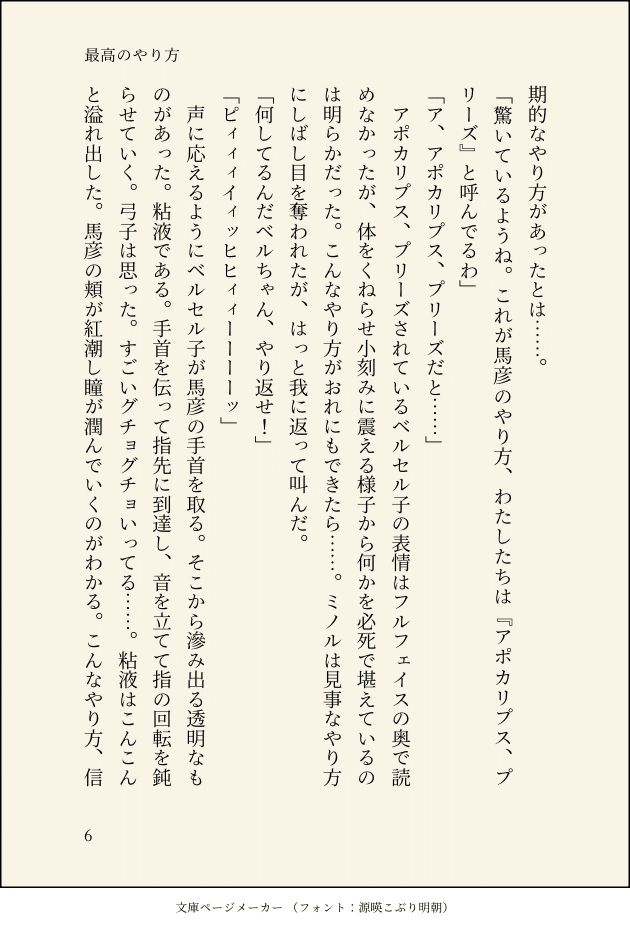

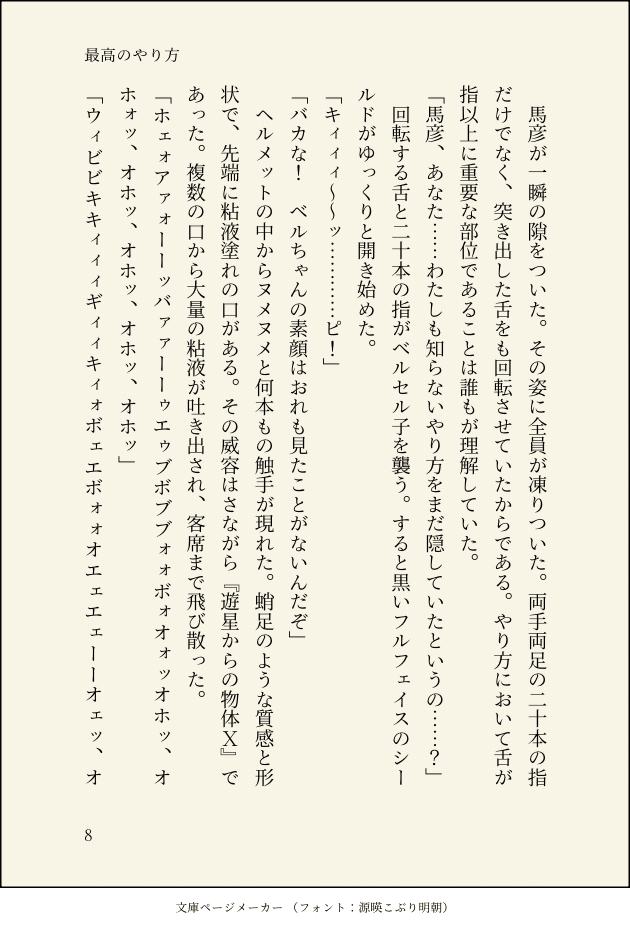



最高のやり
きっかけは同窓会であった。白取弓子の「夫のやり方は凄い。あんなやり方されたら他のやり方じゃ満足できない」という発言に中嶋ミノルが反応したのが全ての始まりだった。
「お前の旦那がどんなやつだか知らねえけどな、うちの嫁さんのやり方に比べたら全然大したことないと思うぜ」
座敷にはビールの空き瓶が転がり、水割り用の氷はすっかり溶けてしまっている。酔ったミノルの顔面は脂ぎって、髪の薄くなった額に蛍光灯が映り込んでいた。
弓子はミノルを睨みながら、着ていたニットの裾を引っ張って広げた。腹の肉のシルエットを誤魔化すためであった。弓子はその日、隣席の同級生の分までサザエの壷焼きと南瓜プリンを胃袋に流し込んでいた。
「彼はね、全部の指がドリルみたいに回転するのよドリルみたいに」
ミノルの眉毛がハの字になった。
「そんな人間がいるか、ばかやろう」
「嘘じゃないわよ」
短いセンテンスに「ドリルみたいに」が二度も登場するセリフを浴びせられるのは生まれて初めてだった。ドリルみたいに指が回転する男だと? 指の回転を利用したやり方ってことか? ミノルは想像して一瞬怯んだが、悟られないように泡の消えたビールを一息に煽った。
「指が回転するから何だってんだ。おれの嫁はな、手のひらから自由自在に粘液が出せるんだよ、ヌルヌルのな」
「な、あんたこそ何言ってんのよ、そんな女いるわけないでしょ」
弓子は自分の目が泳いだことに気づいていた。手から粘液が出せる女ですって? 一体どんな粘度の? どんな量の? 弓子はニットの毛玉を毟って丸め、ミノルに向かって指で弾いた。
「嫌よ、そんな女。気持ち悪い」
ミノルの口角から侮りを帯びた笑みが漏れた。
「それがな、気持ちいいんだよ」
こうして火蓋は切って落とされた。弓子の夫、白取〝ア・ドラゴン〟馬彦と、ミノルの妻、中嶋ベルセル子との一夜限りのやり合いである。
「そんなに言うなら皆の前で二人にやらせてみてはどうかね」と言い出したのは七十歳になる担任の元教師であった。「皆の前で」には躊躇したが、弓子もミノルも引くつもりはなかった。自分の配偶者のやり方が宇宙一に決まっている。担任がなぜか大張り切りで審判をつとめ、同窓会参加者はそのまま観客になった。
ルールはいたってシンプルである。やり合って失神せずに最後まで立っていられた方の勝ち。「それほどの二人がやり合うのだから、最低でもどちらか一方は失神くらいするであろう」という予測から決まったルールであった。実際に弓子とミノルは配偶者のやり方によって毎日のように失神させられていた。
先に現れたのは中嶋ベルセル子であった。まず観客の目を引いたのは彼女の格好だった。黒いフルフェイスのヘルメットをかぶり裸に数匹のカブトムシを這わせていただけだったのである。ヘルメットは表情を完全に覆い隠し、カブトムシはカサカサ動いては客席を角で威嚇したが、猥褻物陳列罪の限界に挑戦するかの如き位置と表面積が常に保たれていた。
遅れて登場したのは白取〝ア・ドラゴン〟馬彦であった。背格好は平均的な日本人男性、上半身はグレーのTシャツ(胸には「Flying Lotus」と書かれていた)、下半身は色褪せたジーンズ姿だったがよく見るとそれらは全て地肌に彫られた刺青であった。ジーンズのジッパー部分に寄った皺はマニアであれば喉から手が出る見事な色落ちに見えたが、股間をカモフラージュするために陰毛を巧妙に利用してヴィンテージに見せているだけであった。要するに全裸だったのである。
「只今より、白取〝ア・ドラゴン〟馬彦くんと中嶋ベルセル子くんのやり合いを開始する!」
客席から拍手が起こった。弓子が夫を送り出す。
「さっさと片付けちゃってよ、あんな女!」
「オオッホッホォォオオオオオォォォオオ」
ミノルは妻の肩を抱いて耳打ちした。
「ベルちゃん、今日は手加減しなくていいよ」
「ピィィィキィィイイィーーーーーーーー」
先に仕掛けたのは白取〝ア・ドラゴン〟馬彦であった。十本指を全て回転させながら中嶋ベルセル子との距離を一気に詰めたのである。ミノルは実際に目にするまでとても信じられなかった。くそったれ。本当に指が回転してやがる。
「馬彦、アレやっちゃいなさい」
「オホ」
コクリと頷くと馬彦は回転する指を用いた独特のやり方を始めた。ミノルは言葉を失った。やり方において指の技術を重視する者は多いが、馬彦のそれは全く次元が違っていた。指が回転するだけでも異常だが、こいつはそれだけじゃない。回転の運動特性を完全に理解し、最良のやり方でやっている。この世にこんな画期的なやり方があったとは……。
「驚いているようね。これが馬彦のやり方、わたしたちは『アポカリプス、プリーズ』と呼んでるわ」
「ア、アポカリプス、プリーズだと……」
アポカリプス、プリーズされているベルセル子の表情はフルフェイスの奥で読めなかったが、体をくねらせ小刻みに震える様子から何かを必死で堪えているのは明らかだった。こんなやり方がおれにもできたら……。ミノルは見事なやり方にしばし目を奪われたが、はっと我に返って叫んだ。
「何してるんだベルちゃん、やり返せ!」
「ピィィィイィッヒヒィィーーーーッ」
声に応えるようにベルセル子が馬彦の手首を取る。そこから滲み出る透明なものがあった。粘液である。手首を伝って指先に到達し、音を立てて指の回転を鈍らせていく。弓子は思った。すごいグチョグチョいってる……。粘液はこんこんと溢れ出した。馬彦の頬が紅潮し瞳が潤んでいくのがわかる。こんなやり方、信じられない……。
「見たか、これがベルちゃんの『お地蔵さん』だ」
「お地蔵さん……なんて恐ろしいやり方……」
粘液を使ったやり方は知っていたが、意志で量をコントロールできる無尽蔵の粘液となると話は別だった。膝をガクガク震わせ息を切らしながら何度もお地蔵さんされる馬彦を見て、弓子は同じ女としてベルセル子のやり方に畏怖を感じざるを得なかった。
「オオッ、オホッ……ホォォオオオ」
「イイイッ……キキキキ」
やり合いは膠着した。馬彦がやればベルセル子がやり返し、ベルセル子がやれば馬彦がやり返す。対等にやり合える相手がいるのが信じられなかった。二人とも既に消耗し切っていた。気力も体力も底をつき、今にも失神しそうだった。その刹那。
「ホォッ」
馬彦が一瞬の隙をついた。その姿に全員が凍りついた。両手両足の二十本の指だけでなく、突き出した舌をも回転させていたからである。やり方において舌が指以上に重要な部位であることは誰もが理解していた。
「馬彦、あなた……わたしも知らないやり方をまだ隠していたというの……?」
回転する舌と二十本の指がベルセル子を襲う。すると黒いフルフェイスのシールドがゆっくりと開き始めた。
「キィィィ〜〜ッ…………ピ!」
「バカな! ベルちゃんの素顔はおれも見たことがないんだぞ」
ヘルメットの中からヌメヌメと何本もの触手が現れた。蛸足のような質感と形状で、先端に粘液塗れの口がある。その威容はさながら『遊星からの物体X』であった。複数の口から大量の粘液が吐き出され、客席まで飛び散った。
「ホェォアァォーーッバァァーーゥエゥブボブブォォボォオォッオホッ、オホォッ、オホッ、オホッ、オホッ、オホッ」
「ウィビビキキィィィギィィキィォボェエボォォオエェエェーーオェッ、オェェーーーオェーーェレエレェレエレェレエレエレビチャビチャビチャビチャ」
馬彦とベルセル子はやり合ったまま激しくやり合い、やってやってやり続け、やりながらやりまくった。客席からは二人が輝いて見えた。やればやるほど生命の尊厳が剥き出しになるようであった。限界はとっくに超越している。発光するふたつの駆動体。波打つ不規則な呼吸。やり合う肉体がやがてひとつに融解する。
「中嶋ァ、いい嫁さん見つけたな!」
「弓っぺいいなぁ、あたしもあんなやり方されてみて〜」
会場を出た弓子とミノルは駅に向かって歩いた。
「凄いやり方だった、二人とも」
「そうね」
ミノルは冷えた両手に息を吐きかけた。
「ベルちゃんは……あんなやり方、おれには一度も見せてくれなかった」
ふと学生時代を思い出す。マクドナルドのテーブル席で待つ弓子の背中。そこに二人分のトレーを運んでいく時の気持ち。
弓子は久し振りに履いたヒールのせいで右足の踵を擦り剥いていた。
「彼も同じ。わたしには本気のやり方でやってなかったのね」
「やれなかったんだろ」
「……」
「お前のせいじゃない」
卒業間際のホワイトデーにミノルからもらったマカロンの詰め合わせ。就職したあとも空き箱を捨てずに飾っていた。
「わたしこっち。三丁目から乗るから」
「ああ」
「またね。ベルセル子ちゃんによろしく。いいわね、若い奥さんのあんなやり方」
「笑わせんな。ドラゴンも歳下なんだろ」
雑踏が二人を飲み込む。さっき担任が言っていた。
「美しいものしか映さない魔法の鏡に二人の姿は映らない……しかし! 二人の〝やり方〟は映るッ」
彼は二度と同窓会に呼ばれなかった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
