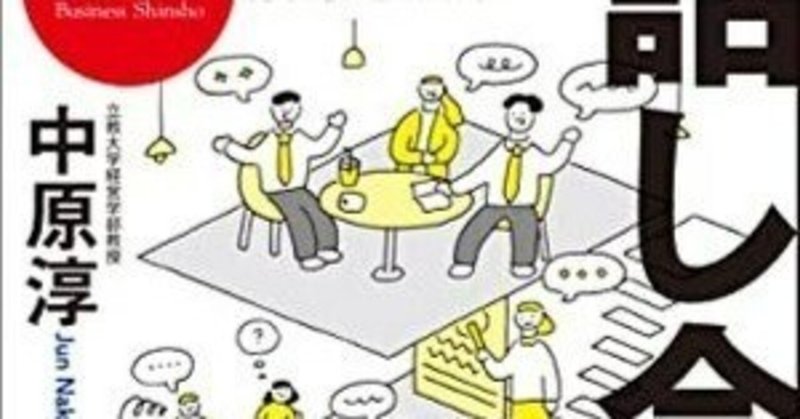
「本を囲んだ語り部屋」2023/12/17 中原淳さん『話し合いの作法』
日曜朝のX(Twitter)スペース「本を囲んだ語り部屋」
12/17は中原淳さんの『話し合いの作法』を取り上げました!!
flier要約のおすすめポイントにはこのような言葉が書かれていました。
『会社、学校、自治会、ありとあらゆる場面で日々行われる「話し合い」。あなたは、そんな日常にあふれる話し合いについて、自ら積極的に学んだことがあるだろうか。おそらく多くの方が、“いいえ”と答えるのではないだろうか。』
中原さんの本の紹介を見ると『ひとびとがいかに「対話」をおこなえばいいのか?』という問いに加え、『ひとびとが成果をだすためには、どのように決めればよいのか?』を探究されたものと書かれていました。
この本では話し合いのプロセスを大きく「対話」と「決断(議論)」の2つのフェーズに分けています。「対話」ではお互いの意見の違いを明確にして認識し合うコミュニケーションを行い、「決断」ではどれが優れている(マシである)意見かを理性的に比較検討し決めるための議論をするものと書かれていました。
語り部屋では組織の中で良い話し合いをしていく上でのポイントとして、組織の成熟度と硬直度の2つからいろいろと語り合いました。組織の中ではそれぞれの立場があり、主語も「〇〇部としては」「会社としては」という言葉が使われることが多いです。しかしその立場もありながら、様々な立場を主語にして言葉を発していけることが成熟している組織なのではという話をしました。
また「忖度と話し合い」というテーマから硬直度についても考えました。忖度の本来的な意味は「他者の気持ちを察すること」ですね。他者を理解しようとする気持ちがあれば、その言葉の背景にあるものを察して表面的な言葉に左右されない話し合いができるように思います。しかし他者を記号として見てしまったとたんに、表面的な言葉に左右されてしまうように感じました。いかに他者を記号と見ずに人として見ていく関係性を日頃から作っていくことが大事なように思いました。
より良い話し合いをするためにはどんな作法がこの組織、チームでは大事なのか、そのようなことを考え続けていくことが大切なように思います。新しい価値を見出すための話し合いを深めていきたいですね!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
