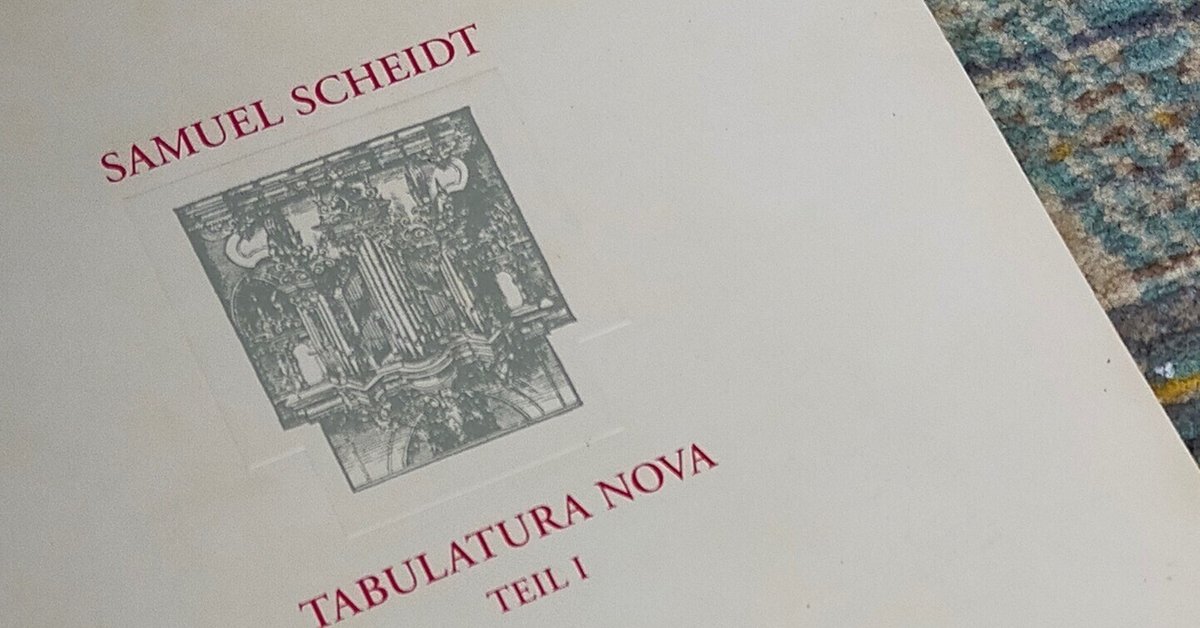
楽譜のお勉強【52】ザムエル・シャイト『カンティオ・サクラ「我々はみなただ一人の神を信ず」』
ザムエル・シャイト(Samuel Scheidt, 1587-1653)はドイツ・バロック音楽を大きく発展させた作曲家の一人です。同世代のハインリヒ・シュッツ、ヨハン・ヘルマン・シャインとともにドイツ・バロックの3S(苗字の頭文字)と呼ばれたりもします。今日シャイトの功績のうち最も大きなものとして数えられるのは、1624年に出版された『タブラトゥーラ・ノヴァ』(Tabulatura nova)という3巻からなる鍵盤楽曲集です。今日はこの中から1巻の第1曲カンティオ・サクラ『我々はみなただ一人の神を信ず』(Cantio Sacra „Wir gleuben all an einen Gott“)を読みたいと思います。

本日ご紹介するYouTube動画は曲の演奏の前におよそ30分にもわたる楽曲解説、作曲家解説、歴史解説があります。ドイツ語ですが、YouTubeの自動翻訳機能を使えば何となく意味が分かるかもしれないので、関心を持たれた方は是非ご覧ください。記事内のリンクは楽曲開始時点のリンクを貼っています。
https://youtu.be/OOy6UiZ_IzM?t=1823
シャイトの『タブラトゥーラ・ノヴァ』は18世紀より前に出版されたドイツの鍵盤楽曲集の中で最も重要なものとされています。全3巻には何と58曲もの楽曲が収められており、楽章や組曲を分割すると255曲にも上ります。またこの曲集は当時大変珍しいオープン・スコア・フォーマットで印刷されました。各声部を段分けして、スコアとして記譜したフォーマットです。この方法で記譜されると、多くのスペースを取るので、全3巻は実に764ページにも及びました。動画の解説では、当時興味深いことに多くの地域で同様の重要な鍵盤楽曲集がほとんど同じ時期に出版されたことも解説しています。マヌエル・ロドリゲス・コエーリョによる『音楽の花束』(1620, リスボン)、ジャン・ティトルーズの鍵盤のための聖歌集とマニフィカト集(1623, 1626, パリ)、ジローラモ・フレスコバルディの有名な『カプリッチョ集』第1巻と『トッカータ集』(1624, 1627, ローマ)、フランシスコ・コレア・デ・アラウホの『ファクルタート・オルガニカ』(1626, アルカラ(マドリード))です。鍵盤音楽の歴史上極めて重要なこれらの曲集がほとんど同じ時期に別々の作曲家によっていろいろな国で出版されていたことは本当に興味深いことです。時代とは一人の天才が独力で作るものではないということを実感します。

シャイトは鍵盤演奏をアムステルダムでオルガンの大家ヤン・ピーテルスゾーン・スウェーリンクに師事しました。シャイトの見事な鍵盤書法は彼の影響があることは明らかです。生まれ故郷のハレでブランデンブルク辺境伯の宮廷オルガニストとして活躍した彼はまた、ミヒャエル・プレトリウスとも一時期同僚として働いたこともあります。大音楽家の周りには大音楽家ばかりがいるものなのだなぁ、と変な感慨があります。
『我々はみなただ一人の神を信ず』は、シャイト自身のオルガン・コラール作品を編作し、4つのコラール・ヴァリエーションのような形にした作品です。この原曲は同じタイトルで、「カンティオ・サクラ」という部分がありません。ゲルリッツ・タブラトゥーラ集(Görlitzer Tabulaturbuch, 1650)に他のシャイトの作品たちと合わせて収録されました。シャイトの作品は演奏会のプログラムで作品番号が書かれることは稀ですが、研究者が付けた作品整理番号は存在しており、本日の「カンティオ・サクラ」はSSWV 102、コラールの方はSSWV 470です。「ゲルリッツ・タブラトゥーラ集」にはSSWV 441から540の楽曲が収めされています。
シャイトは『タブラトゥーラ・ノヴァ』に収録されている作品を演奏する鍵盤楽器を指定していません。さまざまな大きさのオルガンで演奏されることが想定されているばかりでなく、チェンバロも前書きで触れています。どの楽器で演奏するかというときに、実は私は現代のピアノで聴いてみたい欲求を持っています。なぜなら、シャイトが『タブラトゥーラ・ノヴァ』の中で作り出した意義深い記譜法・演奏法の中に、「イミタティオ・ヴィオリスティカ」(Imitatio violistica)というものがあるからです。当時の声楽曲の中でメリスマ(1音節に2音以上当てる旋律作法)を記譜するときに、レガートのような印を記すことがあったのですが、その方法をシャイトは鍵盤楽器に応用しました。2つないし4つの音(それ以上も理論上は可能)の細かい音価(今日の16分音符等)にスラーを書き「イミタティオ・ヴィオリスティカ(ヴィオール奏を模して)」と書くことで、複数の音を一つの運弓で弾くような滑らかな演奏を指示しているのです。ピアノのペダルが作り出す滑らかさは他の鍵盤楽器にはないもので、シャイトが狙った以上の大きな効果が聞こえるかもしれないと考えているのです。
カンティオ・サクラ『我々はみなただ一人の神を信ず』の第1ヴァースは4声で書かれていて、コラールの定旋律(cantus firmus)はカントゥス(ソプラノ)に現れます。アルト、テノール、バス、ソプラノの順に導入し、それぞれの声部は定旋律を変奏したものになっていますので、答唱から始まるフーガのように開始します。ソプラノが定旋律を弾くときにそこまで聞こえていた導音が消失し、ドリア調になるので、完全なフーガではありません。また、導入に定旋律の変奏を持ってきて曲のセッティングを整えたあとは、適宜自由唱中心に定旋律を彩っていきます。

第2ヴァースはビチニウム(Bicinium)で、2声部のみのスッキリした対位法楽曲になっています。定旋律は第1ヴァースから続いてソプラノに現れます。バスは定旋律を2分の1の音価に変更した変奏から開始し、曲の進行に従ってどんどん加速していきます。元から定旋律の2倍の速さで進行するわけですが、基本音価に8分音符(4倍)を多く含むようになり、付点八分音符と16分音符(8倍)の音階的パッセージでノリを増します。8分音符と16分音符2つのパターンが出てきて16分音符の割合がまし、いよいよ16分音符で疾走し続けるパターンへと加速します。定旋律の基本音価2分音符は変化しないので、曲が進行するほどにコントラストは際立ち、ビチニウムならではのスッキリした音の立ち上がりを良く生かしたセクションになっています。
第3ヴァースで初めて定旋律が潜り、テノールになります。3声で書かれたこのセクションは第1、第2ヴァースに比べてとても複雑で、基本的な曲の構成は第2ヴァースに近く、後半になるほど音価が細かくなっていきます。また、イミタティオ・ヴィオリスティカの技法が初めて現れ、奏者にアーティキュレーションの弾き分けを強く要求します。オルガンのヴィルトゥオーゾであったシャイトらしい音楽です。特にイミタティオ・ヴィオリスティカが2度目に出てくる場所で、スラーのフレーズが終わった直後に似たような音形の16分音符が続くので、オルガンやチェンバロではかなり意識して弾き分ける必要があります。動画の演奏でもよく意識して弾き分けていますが、もしこれがピアノだったらそのコントラストはもっと大胆にできるだろうなと想像したりしてしまうのです。バッハをピアノで弾くんだし、シャイトをピアノで弾いても良いのではないでしょうか…。まあ、ピアノという楽器を知る術もない作曲家がそのような極端なコントラストを意識して楽曲を書いたかどうかは別ですが…。

最後の第4ヴァースはこれまでの集大成という感じで、いろいろな技法が現れます。3声で書かれていて、定旋律は堂々とバスに置かれます。イミタティオ・ヴィオリスティカの技法も再び用いられ、最後の方では音価が極めて細かく分割され、32分音符のフレーズまで出てきます(トリル的用法が中心ですが)。定旋律のバスがしっかり受け止めるので上2声がどれだけ細かく変奏していっても安定感のある響きで、曲の締めくくりに相応しい楽想になっています。
シャイトの鍵盤音楽が今日それほど演奏されないのは、バッハの出現が大きいです。イミタティオ・ヴィオリスティカの技法はある意味では装飾の新しい模索ですが、その後のバロックの鍵盤音楽の装飾技法の発展に比べると、後期バロック音楽を聴き慣れ親しんだ私たちの耳にはやや優しすぎるきらいがあります。しかしシャイトの創造性はやはり無視できないものですし、演奏されなくなることはないと思っています。古楽を楽しむ方以外にも彼の音楽をライブで聴いてみてほしいです。
作曲活動、執筆活動のサポートをしていただけると励みになります。よろしくお願いいたします。
