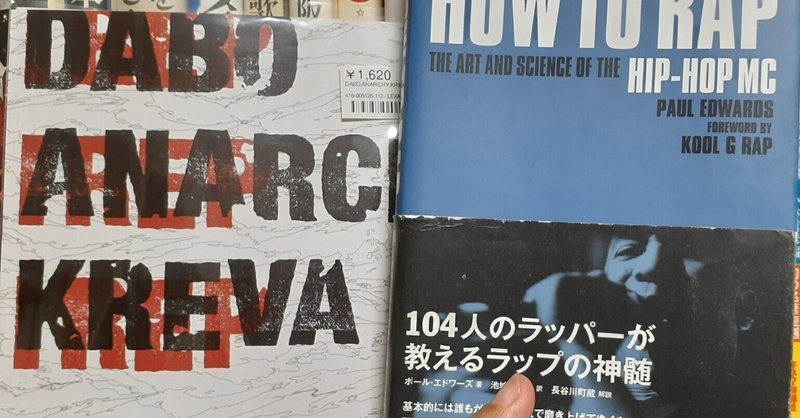
ヒップホップはいかにしてそうなるのか――空虚な主体による表現として3/4
※本記事は、2012年に執筆し、同人誌『F』第11号に掲載したものです。
空虚で濃密なラップの主体
さて、このように、愚直に〈反復〉し、不断に〈変身〉する主体は、ヒップホップをめぐる自己目的的な主体である。というのも、KRSワンが言うところの「ヒップホップそのものになる」というのは、目的であると同時に手段でもあるからだ。主体は、〈あの身振り〉の〈反復〉を通して「ヒップホップそのものになる」のだが、同時に、その〈反復〉こそがヒップホップたる根拠でもある。ここには、〈変身〉という運動を担保するに過ぎない空虚な主体があるだけだ。
ダボ「I REP」という曲は、近年の新たなクラシックとして呼び声が高いが、フックでは「I REP HIPHOP」――「オレがヒップホップの表象である」という意味に取れ、これはKRSワンの「オレはヒップホップだ」と響き合う――と叫ばれる。そして、ダボは自身のヴァースで次のようにラップする。
誰が勝者 誰が敗者 誰も決めれるわけなどないさ
だが今ここにたしかにある オレという現象がただただラップ
あって無いようなもんさ目的は 後付けでかまわんねオレ的には
ただただとめどなく溢れるフロウ これがオレの命の鼓動
ここ数年、これまで述べてきたようなことをずっと考えていたので、そんな折に出会ったこのリリックには本当に感動した。とくに、ここでダボが「オレという現象」というフレーズを使っているのは見逃せない。このフレーズは、かつて安藤宏が提唱した「現象としての私」を連想させる。「現象としての私」とは、とくに私小説の表現において、「語る私」と「語られる私」が混乱することで生じる自意識の連鎖過程を指したものである。安藤は「「描く私」と「描かれる私」の対応関係(「私」の眺め方)そのものの変換がせまられてゆくというプロセスこそが重要なのである」(注41)と述べるが、そこでは「私」の自明性が問い直されている。「私」は語っているのか、それとも語られているのか、と。このような問いに対して、安藤は、〈語る主体〉にも〈語られる主体〉にも還元できない、ただただ「私」をめぐる運動体と化した「現象としての私」を指摘する。
同じように、「オレはヒップホップだ」と言うときの、〈変身〉する主体である「オレ」について考えたとき、果たして、「オレ」がヒップホップを表象しているのか(=I represent HIPHIP.)、それともヒップホップが「オレ」を表象しているのか(=HIPHOP represents me.)。〈身振り〉の模倣によって不断に〈変身〉する主体は、同時に、その〈身振り〉によって不断に〈変身〉される主体にもなっている。だとすれば、ヒップホップたる「オレ」とは何なのか。ダボのヴァースにおいては、このようなヒップホップをめぐる原理的な問いの果てに、「ただただラップ」をする「オレという現象」という運動体が見出される。そこには、「ヒップホップそのものになる」という点で目的と手段が同一化した、不断の〈変身〉運動そのものが存在するばかりである。だからこそ、「目的」は「あって無いようなもん」なのだ。このヴァースには、〈身振り〉としての「ただただとめどなく溢れるフロウ」こそが、すなわち「命の鼓動」である、したがって「ヒップホップそのもの」に他ならない、ダボの「絶対的」(小林秀雄、佐藤雄一)にヒップホップな「姿」を見ることができる。これこそが、ダボによるレペゼン・ヒップホップである。こう言ってはナンだが、ダボという人は、本当に愛すべきイタさを持ったラッパーなのである。MSCの漢というストリートに根ざした新世代のラッパーに、「ギャグラップ」とディスられてもいる。しかし、そのようなピエロ的な〈身振り〉を〈反復〉する先に、「オレという現象がただただラップ」だなんて言われると、僕は本当に感動してしまうのだ。
では、「オレという現象」はいかにラップするのか。この水準でラップする主体を捉えたとき、もはや、語るべき話題をあらかじめ想定することなどできない。自分を取り巻く現実をラップすればいいのだ、なんて素朴なことを軽々に言うことはできない。ダボは「ただただとめどなく溢れるフロウ」と歌っていた。ならば、とにかくやるだけやってみよう。KRSワンは「俺がラップし始めた頃、俺の言葉は身体全体から出てきたものだった」(KRSワン「Health, Wealth, Self」)と言っている。自分にはラップできることなんて無いよ、などと、語るべき内容(=「意」)に捕われる必要すらない。〈あの身振り〉を〈反復〉するように、言葉を紡いでみよう。その言葉は次の言葉を捕まえるはずである。なぜなら、僕らはライミングというゆるやかなラップのルールを知っている。無数の言葉のなかからひとつの言葉が選ばれたとき、その言葉のライムと呼応するかたちで、次の言葉は選ばれるのを待ち受けている。そうして、とりあえず韻さえ踏んでしまえば、マミー・Dが言うように「韻踏んじゃったらお前もライマー」(ライムスター「グレート・アマチュアリズム」)なのである。最初の一語が見つからなければ、それこそ「ヨー、チェケラッチョー!」というクリシェだってかまわない(フレッシュかどうかは別として)。あるいは、誰かのパンチラインを拝借してもかまわない。長谷川町蔵が、ヒップホップの著作権のあり方について「世に出てみんなに愛されたらそれはコミュニティの財産」(注42)と言うように、ヒップホップには無数のデータベースが共有財産として開かれている。誰かのパンチラインでもクリシェでも、なんでも利用して、まず最初の一語さえ見つければ、不断に〈変身〉する主体はラップを開始する。これは別に、ラップを書いてみたい初心者へ向けて言っているわけではない。どんなラッパーだって、少なからずそうなのだ。なぜなら、ヒップホップのヒップホップたる根拠は、〈あの身振り〉を〈反復〉することに他ならないからである。優先されるべきは、いかに〈リアル〉な自分を表現するか、ではなく、いかに〈あの身振り〉を〈反復〉するか、なのである。仮に〈リアル〉な自分を表現するという目的があっても、「絶対的にHIP HOPであらねばならない」という意識がある以上、それはあくまでも二次的な段階である。〈リアル〉な自分はつねに、〈身振り〉の〈反復〉やパンチラインの引用、ライミングなどといった、ヒップホップのヒップホップたる根拠との結節/妥協点で表現されざるを得ない。それがヒップホップである限り、である。大和田俊之の言葉を借りれば、「作品を作り出すきっかけが「内」にあるのではなく「外」にある」(注43)。しかし、言葉というもの自体が少なからずそういうものなのだ。松浦寿輝(注44)は、次のように述べる。
自分の声ならざる誰かの声の不意の訪れという超=主観的な体験一般として事態を捉えれば、それはなにも特殊な生得能力をもつ選ばれた人々のみの専有するところではなく、われわれの誰もがよく親しんでいる日常的な体験であると言わねばならぬ。
言語の習練と洗練化の過程とは、未だ言葉たることができないまま言葉以前の音と映像との漠たるアマルガムとして震えている超=感覚的な波動が、不意に唇にのぼってくるという予期しがたい体験の不連続的な連鎖によってかたちづくられているのかもしれない。
松浦は、このような「不意」な言葉の現れ方を、異化された詩的言語の議論へと展開するが、詩的言語が、「唇」という、この上なく具体的な「姿」に端を発している点に、先の小林秀雄の「先ず動作としての言葉が生まれたのである」という言葉を思い出さずにいられない。詩的言語としてのリリックはやはり、あらかじめ決められた内容に沿ってのみ紡がれるわけではなく、したがって、ラップの「不意に唇にのぼってくる体験の不連続な連鎖」としての性格はおおいにあり得る。どころか、ラップにはむしろ、詩的言語を生み出すシステムが内包されている、とさえ言えるかもしれない。先ほど触れたように、ライミングはそのひとつだ。選ばれた言葉が、そのライムと呼応するかたちで次の言葉を捕まえようとする。ポール・エドワーズは、104人のラッパーに取材をして各々の「ラップの技術」をまとめたが(注45)、そこには次のような方法が紹介されていた。
まず言葉を考えついて、それからその言葉にライムする言葉を考え、まとめることもある。(ターマノロジー)
あるラインを完成させたい時に次のライムに詰まったら、同じ母音を持っている言葉を全部考えてみるといい。(エル・ダ・センセイ)
「ブラック」とライムする言葉が欲しかったら、俺はライムする言葉を紙に全部書き出す。「ブラック」、「タック」、「ラップ」、「キャット」とかね。それから、それらの言葉を使って文を組み立てるんだ。(フレドロ・スター)
松浦が言う「不意」性とは少し異なるが、ライミングとは、韻の共通性をフックに言葉を紡ぐことによって、リリックを日常言語から異化していくシステムだと言える。ボーズは、ラップで韻を踏もうとすると体言止めになることが多いと指摘しつつ、「その文章の面白さはラップにしかない」と、宇多丸はブッダブランドについて、韻を利用するからこそ「それまでの日本語史にはありえない言葉使いとか表現」を生み出した、と、それぞれ語っている(注46)。ライミングとは、詩的言語を次々と組織化するのだ。したがって、最初の一語さえ発してしまえば、「その言葉にライムする言葉を考え」(ターマノロジー)「それから、それらの言葉を使って文を組み立て」(フレドロ・スター)れば良いのである。いや、最初の一語さえいらないかもしれない。いつか聴いた、あのラップのフロウさえあれば。ノリエガは「フロウだけがあって、言葉はまだないことはよくある」と、タジャイは「俺はよくスキャットで骨組みを作って、言葉を埋めていく」と答えている。松浦の言う「未だ言葉たることができないまま言葉以前の音と映像との漠たるアマルガムとして震えている超=感覚的な波動」は、フロウによって捕まえられるかもしれない。それは鼻歌のラップのフロウとして、おぼろげながら姿を現す。そのフロウは、その響きにふさわしい言葉を探すだろう。探された言葉は、そのライムにふさわしい次の言葉を探すだろう。こうして次々に「唇」にのぼってゆくラップの言葉は、意味的な必然性とは別の論理でもって、それぞれを切り結ぶ。すなわち、詩的言語が構造化されていくのである。このようなことを考えると、ライミングというより枕詞的に言葉を紡いでいった「案ずるより産むがやすしきよしこの夜/また縮まる距離」(T.A.K.ザ・ライムヘッド「銀河探検記」)というパンチラインが思い出される。「案ずるより産むが易し」という諺を出発点に、「やすし」から「きよし」が、「きよし」から「この夜」が導かれ、そして、「ふたりの距離が縮まる」という物語らしきものに着地していく。なんというか、ユーモラスな歌詞だと思う一方で、ラッパーの〈リアル〉とは別の場所で、別の論理で、言葉が自己駆動していく様子がよくわかる。ラップの風景を一変させてしまったラキムには、次のようなリリックがある。
ドアから入り込んだ俺、前にも言ったんだ
もう二度とマイクを俺に近づけないと
それなのにマイクは俺に噛みつき、俺を挑発してくる、ライムしてみろと
もう我慢できない 俺は言葉(ライン)を探している
ラップは、「俺」の意志や気持ちとは無関係にやってくる。マイクは、「俺」を理不尽にラッパーにさせるのだ。くり返すが、〈リアル〉な自分の表現はつねに、このような格闘を前提にしている。そのリリックが、いくらラッパーの〈リアル〉に見えようとも、それはつねに/すでに、ラップ自体が組織化する詩的言語的側面との結節/妥協点で成立している。詩人でもあった吉本隆明が文学者について述べた言葉を、ラッパーたちに捧げたい。「かれは当為よりもさきに〈書く〉もの、表現者だった」(注47)。
エドワーズは、ラップにおける比喩表現を「言いたいことをはっきりさせる」ための手法だと捉えているが、半分間違っている。例えばそこでは、マスターP「Hot Boyz and Girlz」における「俺は指輪のダイヤ、俺はおまえが考えているその脳」というリリックが紹介されている。エドワーズの立場からすれば、自分のことをいつも考えている、という内容をラップするために、ダイヤの指輪という比喩が使われたということだろう。しかし、本当にそうか。ここで少なからず意識されていたのは、における「指輪(ring)」と「考えている(think)」というライミングではないのか(「I'm a diamond on a ring, I'm your brains when you think」)。自分を「指輪」に喩えるということの意味的な必然性は、どれほどあったのか。おそらくこのラインも、自己表現と詩的言語との結節/妥協点において成立している。だとすれば、エドワーズの言う「言いたいこと」とは、あるいは巷で言われるラップの〈リアル〉とは、ラップの制約の上で構築された限りにおいての「言いたいこと」や〈リアル〉に他ならない。2パックを意識しつつ母への感謝をラップした、Kダブ・シャイン「今なら」における「ホントいつもしてた親不孝/そのうち連れて行くよオアフ島」という「親不孝/オアフ島」で韻を踏んだラインも、病弱だった幼少時を振り返ってなされる母への感謝という限りにおいて、リリックに嘘は無いだろうが、「親不孝」という言葉を捕まえる以前に「オアフ島に連れて行きたい」という気持ちは、どこまであったのか。「オアフ島に連れて行きたい」という気持ちが嘘でなかったとしても、その気持ちはやはり、ライミングとの格闘を経たのちに出現している。つまり、ヒップホップにおける「言いたいこと」とは、巧妙に〈擬装〉された「言いたいこと」なのである。
〈フェイク〉な共同体、〈フェイク〉な歴史
しかしそもそも、外在的な要因から無縁でいられる「言いたいこと」というもの自体が幻想である。現代思想の領域において、〈内面〉の自明性はいくどとなく問われてきた。したがって、詩的言語云々に限らず、ラッパーの〈リアル〉とは、少なからず〈擬装〉されたものである。だとすれば問われるべきは、そのラップが〈リアル〉であるか〈フェイク〉であるかという点ではなく、どのように〈擬装〉されたかという点、あるいは〈擬装〉そのものがいかなる意味を持つかという点である。大和田俊之は、アメリカ音楽史を「他者を〈擬装〉する文化」として捉え直すなかで、ギャングスタ・ラップについて次のように述べる。
歴史的にアメリカの「黒人音楽」は、白人と黒人双方の欲望が交錯する領域にいわば「虚構」として立ち上がるのであり、ギャングスタ・ラップも例外ではない。「黒人音楽」はアフリカ系アメリカ人コミュニティの内発的な表現ではなく、ラッパーも現実の白人の欲望を微調整しながらそのイメージを〈擬装〉する。(注48)
しばしば日本人がヒップホップの〈リアル〉性として見出す、黒人を取り巻くハードな現実それ自体が、〈擬装〉された〈フェイク〉なものだった、という指摘である。大和田も引用するように、マイク・デイヴィスによれば、NWAが描くハードな現実のイメージも、「あるがまま」を語っているように見えて、ハリウッド映画をなぞっているという(注49)。この指摘は重要だ。大和田によれば、ヒップホップを含め「「黒人音楽」はアフリカ系アメリカ人コミュニティの内発的な表現ではな」いということだが、初期のヒップホップをめぐる人脈にイタリア系白人やユダヤ人などが関わっていたという事実を考えても、ヒップホップが黒人による音楽だという前提は修正されなければならない。もちろん、アメリカのヒップホップが〈リアル〉で日本のヒップホップが〈フェイク〉だ、という素朴な図式も修正されなければならない。
では、なぜ僕たちは、ヒップホップを「黒人音楽」だと思ってしまったのか。端的に言えば、そのように〈擬装〉されたからである。大和田は別のところで、〈擬装〉するユダヤ人について、「アメリカ社会でサヴァイヴするための戦略」(注50)と述べているが、同様の構図はおそらく、ヒップホップにおいても指摘できる。前述のようにジブラは、〈フェイク〉な〈身振り〉を〈反復〉することによって、日本におけるヒップホップ・シーンの拡大と継続に寄与した。日本におけるヒップホップ・シーンとは、言い方を変えれば、日本におけるヒップホップの〈疑似共同体〉ということでもある。〈疑似共同体〉は、〈疑似〉(=〈フェイク〉)というだけあって、もちろん正統性があるわけではない。したがって、まず共同体性の根拠となるのは、〈あの身振り〉だけである。KRSワンの「ヒップホップと一体になる時、君は何百万というヒップホッパーたちと一つになる」という言葉が思い出されるが、つまり共同体性とは、〈身振り〉を共有することによって、うっすらと立ち上がるものなのである。村上裕一は、ゲーム・アニメ・インターネットなどの虚構空間について論じる際に、「我々がキャラクターと同じ踊りを踊ることは、踊りを通じて、虚実の境を超えて、二者が繋がり合うことに他ならない」と述べ、この「繋がり」を「共同体」と呼んでいる(注51)。虚構空間と現実空間を貫く「共同体」概念については議論の余地もあろうが、ここで見るべきはむしろ、たとえ虚構空間であろうとも、〈身振り〉さえ共有すれば「共同体」たりえると、村上が判断している点である。酒井隆史が正しく指摘するように、「ヒップホップ自身がいわばヴァーチャルなレベルで黒人公共圏として再生」(注52)するのである。
ユダヤ人、黒人音楽、日本におけるヒップホップは、社会性の水準は異なるものの、いずれも、居場所を持たないがゆえに「サヴァイヴ」を余儀なくされた、という点では共通している。先述の取材時に、佐々木敦氏は、「90年代の日本のヒップホップっていうのは、自分たち自身がジャンルの形式をきっちり守らないと、あっという間に他のジャンルに飲み込まれてしまうのではないのか、というオブセッションがあるんだと思う」と話していたが、日本のヒップホップがシーンとして確立し「根付く」ためには、ある種の共同体性を創出させる必要があったはずである。佐々木によれば、「さんぴんCAMP」も「シーンが成熟してきて、満を持して放ったというよりも」「無理矢理やった」という側面があったのではないか、とのことだ。最初の方でも触れたが、当時のシーン全体が、実際は様々な交流があったにもかかわらず、「マス対コア」という図式を積極的に採用していたのは、おそらく、「コア」という共同体性を積極的に演出して、可視化する必要があったからである。ここに、なにを〈差異〉化して、なにを〈反復〉するか、という問題がある。「コア」という共同体性を演出するハーコー勢は、いかに〈変身〉しようとも、「コア」的な〈身振り〉を手放さない。現在では違和感ありありのライムスターの態度の大きさを思い出せ。「ワケがあんだよ/このデカい態度は」(ライムスター「ウワサの真相」)。その意味で、90年代に言われていた「日本語ラップ」――「Jラップ」ではなく――的な〈リアル〉は、やはり〈擬装〉された〈リアル〉だったと言える。「さんぴんCAMP」はその後、ビデオ作品となり、そのサウンドトラックも発売されたが、まさにそのサウンドトラックCDを図書館で借りたことがきっかけでヒップホップを聴くようになった僕からすると、例えばブッダブランドとスチャダラパーの交流などは信じがたいものだった。おそらく、その僕の感覚自体も〈擬装〉された〈リアル〉に依っていたのだ。
最初は正統性を持たない〈疑似共同体〉であっても、〈身振り〉が〈反復〉され、〈疑似歴史〉が編まれ、次第に共同体として可視化される。そうして、Jヒップホップは〈フェイク〉にも関わらず、結果的に居場所を獲得/捏造していく。先述したジブラ的な態度とは、そういった運動を意識したものだった。まさに、その運動の果てにアナーキーのようなラッパーが誕生し、〈リアル〉と呼ばれ得るシーンが、あとを追って発生したように。この、〈疑似共同体〉と〈疑似歴史〉をめぐる運動は当然、アメリカにおけるヒップホップにも見ることができる。すなわち、ヒップホップは「アフリカ系アメリカ人コミュニティの内発的な表現」であるという、ともすれば〈リアル〉性を担保する歴史観こそ、事後的に付与された〈疑似歴史〉に他ならないということである。
新しい音楽が生まれたとき、それを拡大・継続していくためには、共同体性や歴史性が求められる。ときには、その共同体性・歴史性が上手にパッケージングされることで、資本主義のマーケットに乗っていく。ヒップホップがおこなってきたことは、おそらくマーケット的な戦略も含め、〈疑似〉でも良いから共同体性・歴史性を立ち上げようということだった。したがって大和田と佐々木が、黒人音楽と「さんぴんCAMP」についてそれぞれ、「内発的な表現ではな」い(大和田)、「満を持して放った」のではない(佐々木)、と言っているのは、まったく同じ意味においてだと言える。黒人音楽も「さんぴんCAMP」も、後追い世代からすれば、あらかじめ存在していた共同体による内発的な表現だと捉えてしまいがちだが、それは事後的に見出された歴史観に過ぎない。あくまでも、〈フェイク〉な〈身振り〉を〈反復〉するという運動そのものが、共同体性を孕んでいるのだ。「先ず動作」という小林秀雄の言葉を、あらためて思い出したい。そして、その〈疑似共同体〉はその後、例えば「コア」「社会的抑圧者の表現」「サンプリングの表現」などと、可視的に体系化され、パッケージングされ、歴史化されていく。
もちろん、〈疑似〉的な共同体性・歴史性が副作用を持っていることは忘れてはならない。「黒人音楽」という〈疑似共同体〉が、実際に存在していたユダヤ人や白人などの交流を排除した上で〈疑似歴史〉を編んだように、「コア」という〈疑似共同体〉が、実際に存在していた他ジャンルとの交流を排除した上で〈疑似歴史〉を編んだように(Jヒップホップ史においては、キミドリとA.K.I.の存在がどうも見えづらい。彼らはむしろ、オルタナティヴ・シーンにおいて発見されていた)、〈疑似歴史〉が正史化する過程では、つねに排除や抑圧が付きまとっている。だから、「黒人音楽」にせよ「日本語ラップ」にせよ、固定化された正史は不断に検証されなければならないと思うし、Jヒップホップについては、僕自身もそういう仕事をしたいと思っている。磯部涼『ヒーローはいつだって君をがっかりさせる』(太田出版 04・9)も、その意味でやはり重要な仕事だった。しかし本稿においては、そういった問題も踏まえた上で、共同体性・歴史性を組織することの重要性について考えている。というのも、ハーコー・ヒップホップに出会う必然性のなかった僕は、共同体性・歴史性をめぐる運動があったからこそ、「さんぴんCAMP」のサントラ盤を通じてそれに出会ったのだ。一方、アナーキーは、共同体性・歴史性をめぐる運動があったからこそ、少年院でジブラを目撃したのだ。杉並区の図書館にいた僕と京都の少年院にいたアナーキーと、ヒップホップの行き先はまったく違うが、ヒップホップの共同体化・歴史化という同じ運動の結果である。そして、その根底に、つねに〈身振り〉の〈反復〉という個別具体的な運動が流れていることには、いつだって注意しなくてはならない。「コア」「社会的抑圧者の表現」「サンプリングの表現」といった共同体の可視化は、あくまで二次的な段階である。可視化した部分だけを、素朴に〈リアル〉だと捉えてしまうと、その根底に流れる〈身振り〉の〈反復〉という、絶え間なき運動を見落とす。それは、ラッパーの〈擬装〉された「言いたいこと」を〈リアル〉だと捉えることで、リリックの詩的言語の側面を見落とすこととまったく同じ構造である。(④へ続く)
注
(41)安藤宏『自意識の昭和文学――現象としての私』(至文堂 94・3)
(42)長谷川町蔵・大和田俊之『文化系のためのヒップホップ入門』(アルテス・パブリッシング 11・10)。
(43)前掲注42。
(44)松浦寿輝『口唇論――記号と官能のポトス』(青土社 97・6)。
(45)ポール・エドワーズ、池城美代子訳『HOW TO RAP――104人のラッパーが教えるラップの神髄』(Pヴァイン・ブックス 11・12)。
(46)TBSラジオ系『ライムスター宇多丸のウィークエンド・シャッフル』(09・4・7放送)の「食わず嫌いに捧ぐ! あんなに嫌いだった日本語ラップが好きになる特集!」における発言。
(47)吉本隆明『言語にとって美とはなにかⅠ』(勁草社 65・5、のち定本として、角川選書 90・8、のち角川文庫 01・9)。
(48)『アメリカ音楽史――ミンストレル・ショウ、ブルースからヒップホップまで』(講談社選書メチエ 11・4)。
(49)マイク・デイヴィス、村山敏勝・日比野啓訳『要塞都市LA』(青土社 01・3、のち増補新版として、青土社 08・9)。
(50)前掲42。
(51)村上裕一『ゴーストの条件――クラウド巡礼する想像力』(講談社BOX 11・9)。
(52)酒井隆史「ヒップホップにおいて「リアル」とは何か?――〝ONLY THE REAL SURVIVE〟」(陣野俊史編『21世紀のロック』青弓社 99・9)。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
