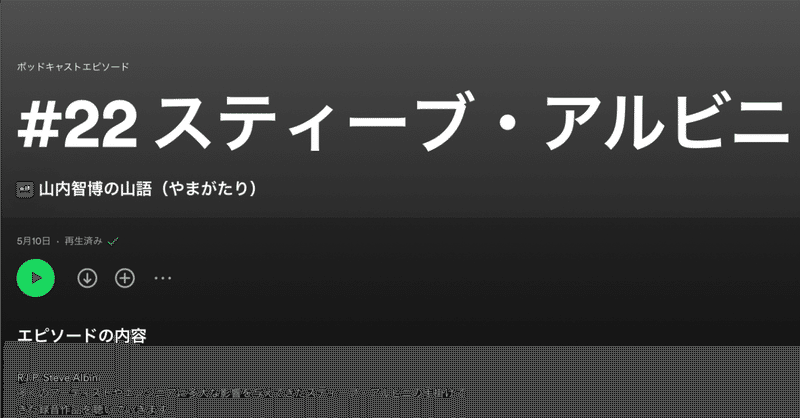
山語#22 スティーブ・アルビニ
Podcast「山語」22回目、配信致しました!
今回は急遽の内容で収録しています。
USインディーロックの代表格といえる、プロデューサー・レコーディングエンジニア・ギタリストのスティーブアルビニさんが現地時間5月7日の夜に亡くなられたとのことです。
SNSや音楽関連のWEBサイトで様々な追悼記事が出ていますが、本当に多くの方に影響を与え続けてきた方だよなと改めて思います。
ご冥福をお祈り致します。
僕自身も大きく影響を受けた方のお一人ですので、今回は彼の手掛けてきた作品を聴く回とさせていただきました。
今回の配信のプレビューはこちらです。
山語#22 編集後記
タイムラインに流れてきたSNSの追悼コメントの中で、とても懐かしい映像がありました。
アルビニのスタジオ「Electrical Audio」でのドラムレコーディングに関する映像なのですが、こちら2017年の映像のようですね。
今回の配信の中でもこの映像について触れているのですが、僕はもっと2017年より前にこの映像を見ていた記憶があったのですよね。どうやら別の映像と勘違いしていたのかもしれません(僕が他の世界線からやって来たのでない限り)。
とにかくElectrical Audioでのレコーディング風景には多大な影響と共にとても強く刺激を受け、僕は以前勤めていたスタジオで沢山の録音実験を行ってきて、今もなお録音などの音に関する実験が日々の暮らしの中に生活の一部として存在していないと自分の人生じゃ無いような、ある種の落ち着かなさを感じるほどに実験大好きっ子なままです。
その原点はここにあったのだな、と改めて気付かされた想いです。
アルビニさんは鳴っている楽器の音をありのままに収録することを最重要視してきた方ですが、PCとDAWでの処理・プラグインやエフェクターでのサウンドメイク・様々な補正が当たり前になってから久しく、AI技術の発展が進む現代において、僕はその在り方というものはやはり基本であり、とても重要なものに感じています。
(※動画4:55〜引用)
※大きくエネルギッシュな音が鳴っているのに、そこに空間の音が入っていなかったとしたら、私は人工的で加工された音のように感じる。だから部屋の音、アンビエントの音も録音に入っているのが自然なことだと思う。という話の流れから
So my default is always to try to record the sound of the room that the band is playing in addition to the direct sound of the instruments.
(私の基本スタンスはバンドが演奏している部屋の音を録ること、そして楽器のダイレクトな音を録ることです)
I have always favored that as a default like if you can start from the natural presentation it's easy and sometimes happens accidentally that you stylize it from there that it gets slightly that it gets made more eccentric from there.
(それがいつも基本として気に入っています。もし自然な音から始められたら凄い簡単なんです。時々アクシデントとしてそこから加工して元の音よりエキセントリックなものになったりはしますが)
But if you start from a position of artificiality if you start with everything alien and everything different from the way it normally is then it's very difficult to get to a naturalistic presentation from there.
(でも人工的な音から始めたり通常の自然な音とは違うところから始めると、そこから自然な音の表現を得るのはとても難しいんです)
このあたりが特に作品の音として明確に表れていると思い、抜粋して引用させていただきました。
他にも興味深い話が聞けるインタビュー映像はたくさんありますので、ご興味のある方は色々と探してみて下さい。
そういえば前回の編集後記で「デッドな音」というようなことを書きましたが(思えば、前回選曲したOWLSはアルビニが手掛けた作品でした)、そこで僕の意図したデッドな音というのは「エフェクター的な、加工された響き(リバーブ)の無い音」という意味合いでして、USインディー的なバンドサウンドの実際の音の質感としては部屋の鳴りやルームアンビエンスというものはとても豊かな音が多いようにも思います。
ちょっとわかりづらい表現となってしまっているので、改めて補足として書かせていただきました。
そう、このルームアンビエンスの感じはやはり凄まじくて、録音の段階で考えられていないと実際、こういう音は得られないよなと思います。いや、これだけだと単に上記インタビュー引用の内容をなぞってるだけに聞こえると思うのですが、「自然な音」と「加工された音」の両極端を振り子のように行ったりきたりしてみたり、その「あなたはどちら派?」のような振り子からは完全に日々の意識を離してみたり、僕自身としては僕なりの守破離のつもりなのです。
それでも結局、何度も「ルームアンビエンスが豊かで自然で、聴感に近い音って凄いよな」というところに戻ってきて、アルビニさんの言葉に何度も頷いているのでした。同じところを行ったり来たりしているだけでなく、少しずつでも僕の知識や技術も深まっていっていることを願っていますけれど。
ということで今回は自分語りも沢山入ってしまいましたがスティーブアルビニさんの特集となりました。
それではまた来週!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
