僕を構成する7つのもの ②『本』
暇があれば、本屋やブックオフへ足を運び、おもしろそうな本をチェックする。
買う予定もないのに本を手に取ってしまう。
積読がタワーのように積まれていく。
そんな生活を送っている。
僕はいつから本が好きだったんだろう?
そうだ、母のお腹に入っていた頃から僕は本好きだった。
妊娠するまで熱心に本を読んだことがなかった母。
だけども僕を妊娠した途端に赤川次郎などのライトなミステリー小説をむさぼるようにして読んだらしい。
幼少期は、両親から毎晩寝る前に絵本を読み聞かせてもらった。
小学生の時に漫画と出会い、夢中になって読んだ。その頃の将来の夢は漫画家。
中学生の時に「活字を読んでいる俺、カッコいい!!」と中二病全開で読み始めた小説だったが、あまりにもおもしろくて小説の中の世界に魅了された。
高校生の時に読んだファッション誌や音楽誌から得た情報を自身のライフスタイルやカルチャーの参考にした。これは今も変わらない。
僕は本とともに大人になった。
僕のライフワークの一部ともいえる『本』。
少しでも恩返しがしたいと考える。
今後の目標として、自分でカルチャーに関するZINEをつくったり、音楽イベント等で自分の所有する本を売ってみたいと思っているところです。
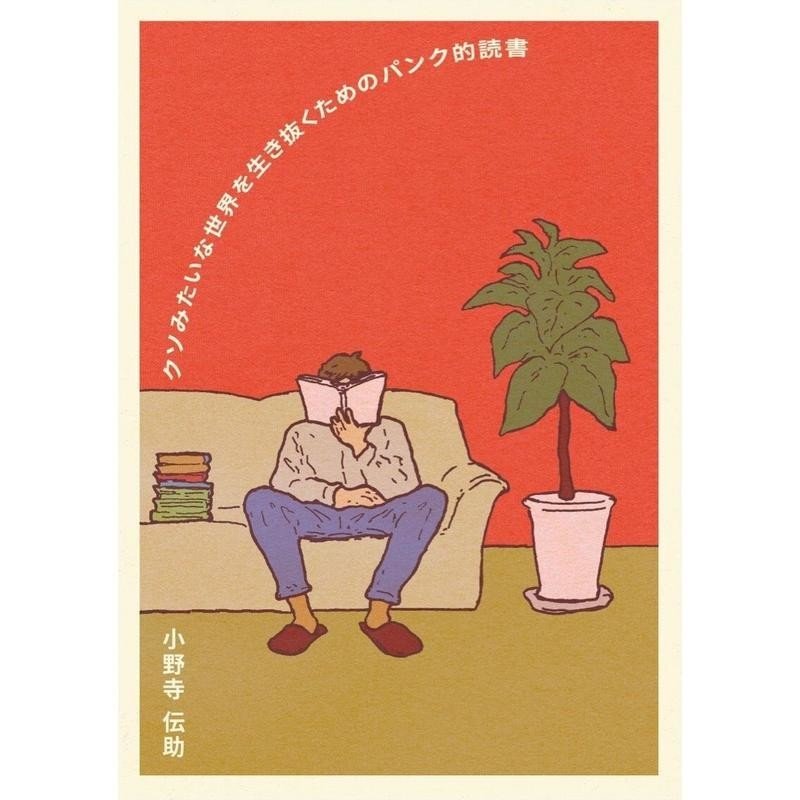
ZINE:個人でつくった本のこと。テーマは自由。Wordで文章を作成してコピーしてホッチキスで綴じるだけでもそれはZINEである。僕が最近買ったZINEは秋田ののら珈琲で購入した小野寺伝助『クソみたいな世界を生き抜くためのパンク的読書』。必読です。

本のまち八戸ブックフェス:青森県八戸市で年1回行われる本のイベント。ブックフェスでは「はっちの一箱古本市」という本好きの方々がそれぞれ古本を売っており、そこから購入したり出展している人と話したりして、僕も個人の古本屋をしてみたいと思った。2019年は会場BGMとしてDJをやらせていただき、少しでもブックフェスに関わることができて光栄でした。
最後に僕を構成する10冊を紹介したい。
ここに紹介した本以外にもたくさんの本が僕の糧になっている。
これからも素敵な本と出会えますように。
僕を構成する10冊
1.赤川次郎『三姉妹探偵団』シリーズ

母が僕を妊娠している時に読み漁っていた本。僕も小学生の時に学級文庫にあった『三姉妹探偵団』シリーズを読み漁った。僕の本好きの原点。3回ほどテレビドラマ化されていて、僕は1998年版のドラマを夢中になって観ていた。このドラマでの共演がきっかけでIZAMと吉川ひなのが結婚したのは有名な話。
2.藤子・F・不二雄『大長編ドラえもん』

ドラえもんの長編アニメ映画の原作。映画公開の前にコロコロコミックで連載されていた。『ドラえもん のび太とブリキの迷宮』はトラウマ。物語終盤に向けてのいいところで武田鉄矢による主題歌の歌詞が見開きのバックで書かれているのに毎回笑ってしまう。
3.ガモウひろし『とっても!ラッキーマン』

小学生だった僕をもっとも魅了したジャンプ作品は、『ドラゴンボール』や『SLAM DUNK』、『幽☆遊☆白書』でもなく、『とっても!ラッキーマン』だった。運の良さだけを武器とするヒーロー・ラッキーマンが活躍するギャグ漫画。でも、ラッキーマンはけっして運だけで戦っていたわけではない。運を取り入れる為に努力もするし、他のヒーローとの友情、そして最終的には勝利して地球を守る、実は王道的なジャンプ漫画だ。最終回は泣ける。ジャンプ誌上最強のヒーロー。
4.宮崎哲弥+藤井誠二『少年をいかに罰するか』

中学2年生の時に出会った本。この本が発売される前年に少年法が半世紀以上ぶりに改正・重罰化された。その少年法について、評論家の宮崎氏とノンフィクションライターの藤井氏により対談形式で構成されている。当時中学生の僕でもわかりやすく書かれていて、今の自分の考え方に大きく影響を及ぼしている。
5.土田世紀『同じ月を見ている』

3人の幼馴染について描く青春漫画。天才・土田世紀の中期の名作。
土田世紀の漫画が好きだ。土田世紀作品に出てくる登場人物は人情で溢れている。心の底から嫌な奴なんて出てこない。中でも『同じ月を見ている』は教科書。人生のお手本としている。
6.『rockin’on』・『ROCKIN’ON JAPAN』

ロキノン系と呼ばれる音楽が苦手だ。アーティスト側がロッキング・オン側に広告費を支払うことで記事を掲載するという手法が嫌だ。そのくせ、アーティスト側の原稿チェックは認めない。本当に大嫌いだ。でも、そういえるのは十代の頃にワクワクしながら正座して好きなアーティストの2万字インタビューを読んでいたからこそ。ロッキング・オンは今では僕の嫌いなものの代名詞だが、確実に僕を構成する上で重要な存在といえる。
7.新井英樹『宮本から君へ』

営業マンである宮本が仕事や恋に全力でぶつかって成長していく青春漫画。
作中の宮本のセリフである「俺がカッコいいと思ってるものをそうじゃないって言う人間に認めさせたいです」は僕の座右の銘。
8.爆笑問題『爆笑問題の日本原論』

人間関係に悩み、社会になじめずにいた10代後半の僕が学校のトイレで隠れて読んでいたのは『爆笑問題の日本原論』だった。笑いとは理不尽である。理不尽だからこそ笑ってしまうし、誰かに優しくなれる。太田光のピュアな部分に共鳴するし、心から尊敬している。
9.若林正恭『社会人大学人見知り学部 卒業見込み』

オードリー・若林がM-1グランプリ2008で敗者復活戦から準優勝して人気者となり、社会とのズレに戸惑いながらも適合していく過程を記録したエッセイ。
僕にとって人生の一冊といっても過言ではない。ヘタな自己啓発本よりも生き方を考えさせてくれる。
広義でみれば僕も人見知りなんだろうけど、三十歳を過ぎた今、人見知りといってはいられない。
10.『POPEYE』

日本を代表する男性向けファッション誌・情報誌。僕にとって『POPEYE』とはシティボーイを前面に押し出した2012年以降である。ファッション誌としてではなく、ポップカルチャーとしての情報誌。コロナ禍で発売された「東京物語」。僕はその表紙を見ただけで泣いた。東京は晴れたり曇ったり。それでもやっぱりこの街が好き。僕の好きなお店や場所が収束後も残っていますように。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
