(5)(追記:「試合の流れ」と「ポジティブフィードバック」、寄生虫撲滅にはライフサイクルの把握) 「ボールを持ったらリングを見ろ?」と 「パス概念の拡張」について
「試合の流れ」とは何なのか? について考えてみると
制御工学の
「ポジティブ フィードバック」と
「ネガティブ フィードバック」で理解できそうな気がします。
ポジティブフィードバック(英: positive feedback、正帰還、正のフィードバックなどとも)するシステムとは、出力の一部を入力にフィードバックし
符号を逆にせず加算するシステムである。
出力の解が発散することから非安定平衡となる。
これとは逆に符号を逆にして加算する(減算する)フィードバックが
ネガティブフィードバックであり、そちらは安定するシステムとなる。
ポジティブフィードバック(流れが良い時 もしくは 悪い時)

ポジティブフィードバックでは、正の方向か、負の方向に発散(行ったっきりで戻ってこない)
(生物学では細胞の分化=スペシャリスト化にも関わる)
ネガティブフィードバック(こう着状態:一進一退の攻防)

(試合で言うと、点を取ったり取られたりの膠着状態に似ている)

https://deltapower.site/2021/02/15/vibration-damping-type/
バスケの試合で「流れが来ている時」というのは、
ポジティブフィードバックが生じている時だと思われます。
(別の言い方をすると好循環が起きている)
「DFの質や強度が増加した」ことにより
「OFでも速攻が出しやすくなった」とか、
「外のシュートが入り出した」ことにより
「中のスペースが空いて攻めやすくなった」とか。(逆も然り)
試合に勝つためには「流れを制する」ことが大事ですが、
試合の流れをつかみ(ランを発生させ)、
相手チームの流れを断つためには、
「何が増加したことによって」得点が伸びているのか?
という視点が重要になると思います。

「湘北の得点」が増加しました。
山王は河田兄を桜木につかせて、そこを断とうとしたわけです。
好循環のサイクルのうち、どこが一番断ちやすい部分なのかを見抜けば、
相手のチームの流れを止めやすくなるし、
自分のチームの流れを保ちやすくもなると思います。
「寄生虫の増加」による「風土病患者の増加」を止めたい場合、
寄生虫の「生活環(ライフサイクル)」を把握することが特に重要で、
そのライフサイクルのうちの一部分を破壊することができれば、
最終的に、寄生虫を全滅させることができます。
「日本住血吸虫」を撲滅するには「貝の駆除」が急所でした。

日本住血吸虫症は日本住血吸虫の寄生によって引き起こされる病気で、
かつて日本の一部の地域に流行し恐れられていました。関係者の多くの努力の結果、日本は世界で初めてこの病気を克服した国となりました。しかし、山梨県で終息宣言が出されたのは1996年、筑後川流域で撲滅宣言が出されたのが2000年のことで、じつはそう遠い昔のことではありません。
日本住血吸虫の生活史は以下の通りです。糞便(ふんべん)とともに排出された卵が水中でふ化し、中間宿主であるミヤイリガイに寄生します。貝中で分裂増殖した後、ふたたび幼生が水中に泳ぎだし、終宿主であるヒトなどほ乳類の体内に皮膚を通して侵入し、腸と肝臓をつなぐ肝門脈中に寄生します。寄生した吸虫は成熟するとメスとオスが一緒に生活し、腸の内壁に産卵して腹痛を起こすほか、卵が血流に乗って移動し、とくに肝臓に肝硬変を引き起こしたり腹水がたまるようになり、やがて患者は死に至ります。日本住血吸虫の幼生は流れのあまりない水中にいるので、これらの地域で素足で水田や湿地を歩くと感染が起きました。山梨県の流行地では 「中の割にお嫁に行くなら、持たせてやるぞえ棺桶に経帷子」 といった悲しい謡(うた)が伝えられています。
住血吸虫症の撲滅の難しさの一つは、人獣共通感染症である点です。感染者を治療しても、イヌ、ネコ、ウシといった家畜のほか、ネズミなど野生の動物にも感染するため、感染環を絶つことが困難でした。そこで取られたのが流行地に生息する中間宿主であるミヤイリガイの撲滅でした。撲滅の方策としては、貝を手取りしたり焼き払ったりしたほか、ペンタクロロフェノール (PCP) などの殺貝剤(さつばいざい)が散布されました。また生息環境を破壊するために、用水路のコンクリート化などの農地基盤整備が徹底的に行われました。
各地のミヤイリガイは根絶され、現在は甲府盆地の一部と小櫃川(おびつがわ)流域(千葉県)の個体群が残るのみです。これらの個体群は現在でも監視が続けられています。日本住血吸虫も日本の個体群は絶滅したと考えられます。
2023/10/22に追記 ↑
元の記事↓
「ボールを持ったらリングを見ろ?」と 「パス概念の拡張」について
「ボールを持ったらリングを見ろ」とは
高校のコーチに口を酸っぱくして
言われた言葉なのですが、
最近、リングを見ない方が
いいのではなかろうかとも思うようになりました。
味方やDFの位置は、時事刻々と変わりますが、
リングの位置は変わりません。
シュートモーションに入るまで
リングを見る必要は特にないと思われます。
(ドンチッチやヨキッチは、リングをそんなに見てるだろうか?)
「リングを見る」という行為は
DFに「シュートかも」と思わせる効果がありますが、
本当にシュートを狙っている場合、
DFにその意図を悟られるのは、いいことではありません。
ですので、
シュートではなく、
パスやドライブを狙っている選手が、
あえて「リングを見る」のは理にかなっていますが、
シュートを打ちたいと思っている選手は
「リングを見る」ではなく、
「フロアを見る(味方やDFの配置を見る)」
方が、良いのだと思います。
「ゴール下」でボールを持った選手が「リングを見る」と、
激しいプレッシャーを受けまくるので、
むしろ「キックアウト先などを見て」、
DFをちょっと油断させてから(パスか?と思わせてから)
シュートに行った方がよいかも。
シュートを打つ気のない(自分のシュートレンジではないところで
ボールを持った)選手が、リングを見ずに、パス相手だけをみて、
パスをするというのは良くないプレーと言えます。
あまりシュートを打ちたがらない選手に対しては
「リングを見てからパスをしろ」と言う方がいいのだろうと思います。
シュートは「ゴールへのパス」
ドリブルは「自分への連続パス」
パスは 「味方へのパス」
というように
「パスの概念を拡張」させて考えることもできるように思います。
「ノールックパス」が有効なのも
「パス先を見てない」から
「DFに意図を悟られずに済む」ということなので、
「ノールックシュート(ゴールへのノールックパス)」をする選手が
いつか出てきても不思議ではない気がします。
シュートは「ゴールへのパス」だと考えると、
「ブロック」は「パスカット」
「DFリバウンド」は「スティール」 と言えるように思います。
DFの成功とは
「点を取られる前に、相手からボールを奪うこと」
DFとは
「プレッシャーをかけてバッドパスをさせ、それをスティールすること」
相手に余裕がある状態で、
いきなりボールを奪うことはまず無理なので、
まずはプレッシャーをかけて(間合いを詰めて)、
「バッドパス(悪いドリブル、悪いパス、悪いシュート)」をさせ、
それを「スティールする」のがDFの基本。
( バイオレーションやテイクチャージも
相手チームへボールを渡してしまうという意味で、バッドパス。)
ディフェンスで
「相手に不味いシュートを打たせる」というのは、
「バッドパスをさせるのに成功した」というだけなので、
それを「スティール(DFリバウンド)」して初めて
ディフェンスの成功と言えます。
(DFリバウンドをさぼって、相手にリバウンドを取られてしまうのは
DFの大失敗と言えます。)
(「バッドパスをさせる技術」と
「スティールをする技術」の両方が、DFには必要と言えます。)
ディフェンスでまずやるべきは
「相手にバッドパスをさせること」(そしてそれをスティールすること)
(たとえば、相手にシュートを打たせないDFというのは、
24秒と言う時間のプレッシャーをつかって
バッドパス(苦し紛れのシュート)をさせる技術と思われます。)
おまけ
ヨキッチのプレーなど

リバウンドからボールプッシュするヨキッチ(左上)










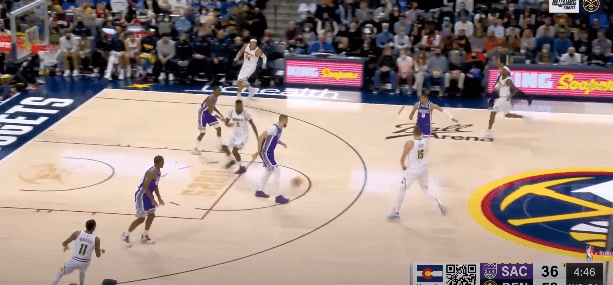
ドンチッチのプレーなど

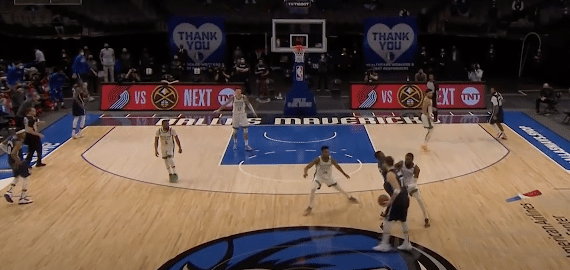




















この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
