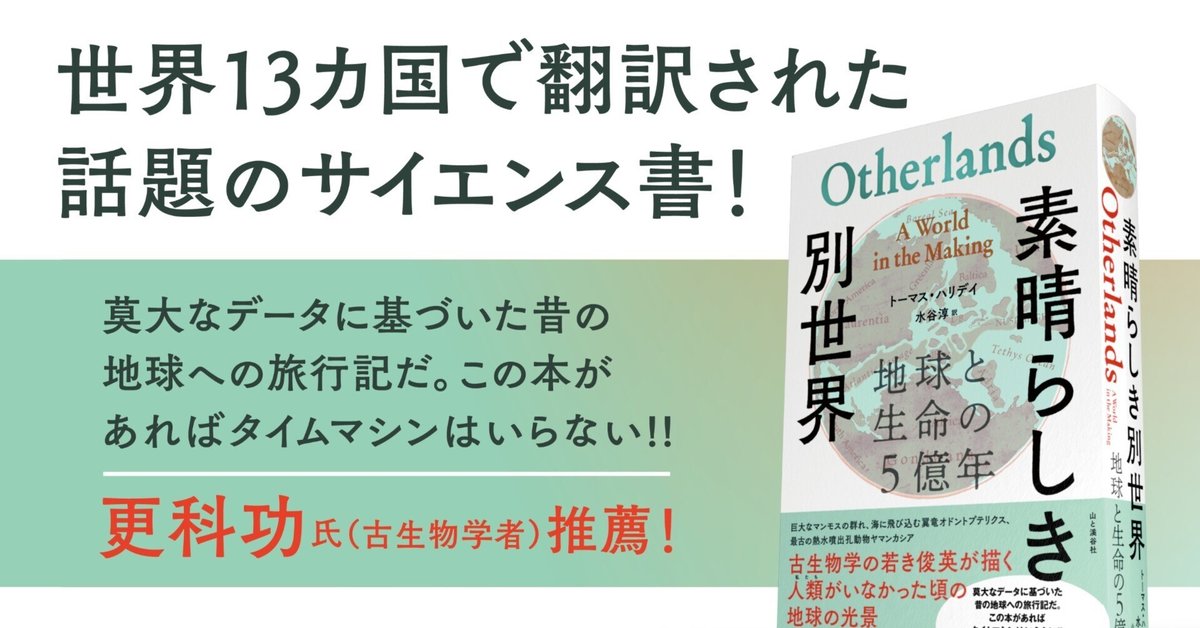
地球と生命の5億年の旅を叶える一冊!『素晴らしき別世界』の「はじめに」公開。
◎過去を知ることは、未来を知ること
「莫大なデータに基づいた昔の地球への旅行記だ。この本があればタイムマシンはいらない‼」
――更科功氏(古生物学者)推薦
アラスカを渡る巨大なマンモスの群れ、泥地にダイヤモンド模様の高木が屹立し、翼竜が水中に獲物を見つけて湖にダイブ! 海には透明で巨大なガラス建築が広がり、海底では最古の熱水噴出孔動物ヤマンカシアが生きている――。本書で描かれる地球の光景は、まるで別世界です。

『素晴らしき別世界 地球と生命の5億年』トーマス・ハリデイ/著、水谷淳/訳(山と溪谷社)の発刊を記念して、本書冒頭の「はしがき」を全文公開いたします。

“素晴らしき別世界”へ、ようこそ。
◎はしがき――億千万年の館
「過去は死んでいるなんて誰にも言わせるな。過去は我々に関わるものであって、我々の内にある」
―ウジュルー・ヌナクル『過去』
「どんな大嵐が私を大昔の深い海に吹き飛ばしたのか、それは分からない」
―オーレ・ヴォーム
窓の外に目をやって、畑や家々、公園の向こうを見渡し、何百年も前から「世界の果て」と呼ばれてきた場所を眺めている。そう呼ばれているのはかつてロンドンから遠く離れていたからだが、いまでは拡大した都市に飲み込まれてしまっている。しかしそう遠くない昔には確かに世界の果てだった。
その場所の土壌は最終氷期に形成されたもので、かつてテムズ川に流れ込んでいた何本もの川が堆積させた砂礫混じりの土である。氷河の前進によってそれらの川の流路は変わってしまったし、テムズ川もいまでは当時と比べて150キロメートル以上南の地点で海に注ぎ込んでいる。氷の重みでねじ曲げられた粘土層の丘陵から、生け垣や庭、街灯を頭の中で剝ぎ取れば、何百キロメートルも先まで広がる氷床の縁に張りついたもう一つの大地、冷たい世界を思い浮かべることがかろうじてできる。
その凍りついた砂礫の下に横たわるロンドン粘土層の中には、さらに昔にこの土地に暮らしていたワニやウミガメ、ウマの祖先が保存されている。彼らの暮らしていたこの一帯には、ニッパヤシやポポーの森、海草や巨大なスイレンの葉に埋め尽くされた水面が広がり、そこは暖かい熱帯の楽園だった。
過去の世界なんて、想像もできないほど遠い昔のことに思えてしまう。地球の地質学的歴史は約45億年前にまでさかのぼる。生命はこの惑星上に40億年ほど前から存在していて、単細胞生物よりも大きい生物となるとおそらく20億年ほど前だ。古生物学的記録から明らかになるとおり、地質学的時間にわたって存在してきた風景は多様で、ときに現代の世界とは似ても似つかない。
スコットランドの地質学者で作家のヒュー・ミラーは、地質学的時間の長さに思いを巡らせて、「人類の全歴史ですら地球にとっての昨日にまでも達せず、その先に広がる無数の時代になんてとうてい手が届かない」と言っている。その「昨日」は確かに長い。地球の歴史四五億年を一日に圧縮してそのフィルムを再生すると、300万年以上におよぶ一場面が1分間で過ぎ去る。
生態系がめまぐるしく盛衰を重ね、その生態系を形作るさまざまな生物種が出現したり絶滅したりする。大陸が移動して、まばたきする間に気候条件が変化し、長く生きてきた生物群集が突然の劇的な出来事によって壊滅的な影響を受けて絶滅する。翼竜や首長竜、そして鳥類以外の恐竜を消し去った大量絶滅が起こったのは、フィルムの終わる21分前。文字に残る人類の歴史は最後の10分の1秒にすぎない。
この圧縮した過去の最後10分の1秒の中ほどで、エジプトに葬祭殿が建てられた。現代のルクソールの近くに立つラムセス二世の墓である。そのラメッセウムの建設にまでさかのぼれば、長い地質学的時間の目もくらむような断崖絶壁を垣間見たことにはなるが、それでもその建造物は儚さの象徴として知られている。ラメッセウムから着想を得たパーシー・ビッシュ・シェリーの詩『オジマンディアス』では、絶大な権力を握るファラオの大言壮語と、この詩が詠まれた頃には砂ばかりになっていた風景とが対比されている。
私は初めてその詩を読んだとき、そのあたりの知識がなくて、オジマンディアスというのは恐竜か何かの名前なのだと勘違いしてしまった。長くて変わった名前だし、正しい発音もよく分からない。この詩に使われている叙景的な表現は、暴虐さと力強さ、石、そして代々の王に関するものだった。
要するに、子供の頃に読んだ先史時代の生物の絵本と同じパターンだ。「由緒ある土地からやって来た旅行者が言った。石でできた、胴体のない二本の巨大な脚が砂漠の中に立っていると」。私は、先史時代の凶暴な獣の死骸にギプスをはめた光景を思い浮かべた。真の暴君だった爬虫類の王も、いまでは骨の破片になって北アメリカの荒地に転がっていることだろう。
破片になったものがすべて失われるわけではない。「その台座にはこんな銘が刻まれている。『我が名はオジマンディアス。王の中の王だ。権勢を誇るお前たちよ。我が成したものを見よ。そして絶望せよ!』そのほかには何一つ残されていない」。
この一節は、尊大な統治者も結局は時の流れに屈するのだという意味に取れるかもしれないが、とはいえそのファラオの世界は確かに記憶に残されている。その立像はファラオが実在した証拠だし、銘文の内容やその文体からは当時の様子をうかがい知ることができる。そのように『オジマンディアス』を読むと、化石化した生物や彼らが暮らしていた環境について考える一つの道筋が見えてくる。傲慢さにさえ目をつぶれば、現在まで残されている遺物から過去の現実を見つけ出すという意味の詩として読めるのだ。
たった一個の破片もれっきとした物語を語っていて、人っ子一人いない平坦な砂漠以外の何か、かつてそこに存在していた何かの証拠になりうる。もはや存在していないがそれでも垣間見られる世界を、石の中に横たわるものから読み取れるのだ。
ラメッセウムはもともと「億千万年の館」と呼ばれていて、この呼び名は地球にもぴたりと当てはまる。この惑星の過去も土の中に隠されている。地殻の形成と変化によってすり減ってはいるが、そこに暮らしていた生物を石の中に記録した死体安置所でもあって、その墓標の役割を果たすのは頭部や胴体の化石だ。
そうした世界、そうした別世界に、少なくとも物理的な意味で訪れることはできない。巨大な恐竜が闊歩していた土地を訪れて、その土の上を歩いたり水の中を泳いだりすることはけっしてできない。その世界を経験する方法は一つだけ。石に目を向けて、固まった砂の中に残された跡を読み取り、姿を消した地球を想像することだ。
*****
本書で掘り下げていくのは、かつて存在していた地球の姿、その歴史の中で起こってきた変化、そして生命が適応した、あるいは適応しなかった経緯である。それぞれの章で、化石記録を道しるべに地質学的過去のある地点を訪れて、動植物を観察し、風景に身を委ね、その絶滅した生態系から我々の世界に当てはまる教訓を学ぶ。
サファリツアーに参加する旅行者の気持ちで、いまは亡き地点を訪れることによって、遠く離れた過去と現在を橋渡しできればと思う。風景が見えてきて、現在のように感じられれば、生物たちが暮らし、競争し、つがい、食べ、死んでいく様子をもっと身近に感じられるだろう。
我々の生きる顕生代はいくつもの世からなる。「ビッグファイブ」と呼ばれる大量絶滅、その最後のものが起こったのは6600万年前で、それ以降の歴史については一つの世ごとに一つの地点を選んでいる。その大量絶滅より昔については、5億年以上前のエディアカラ紀に起こった多細胞生物の誕生にさかのぼるまで、一つの紀(いくつかの世からなる)ごとに一つの地点を選んだ。
生物学的に大きな意味を持つ地点もあれば、珍しい環境の地点もある。また、非常に詳細に残されていて、かつて生命がどのように暮らして関わり合っていたかを手に取るように垣間見られるという理由で選んだ地点もある。
旅というのはいまいるところから出発するしかないので、今回の旅でも現代から時間をさかのぼっていく。最初に訪れるのは比較的見慣れた更新世の氷期、地球上の水の大部分が氷河に閉じ込められて、世界中で海水位が低かった時代だ。そこから旅は時間をさかのぼりながら進めていく。生命や地勢はどんどん馴染みの薄いものへと移り変わっていく。新生代では、人類初期の時代を通り過ぎて、地球史上最大の滝や、森林の広がる温暖な南極を巡り、最後に白亜紀末の大量絶滅を目撃する。
そこから先では中生代や古生代に暮らしていた生物と出合い、恐竜の支配する森、全長数千キロメートルにもわたるガラス質の礁(リーフ)、モンスーンで濡れそぼった砂漠を訪れる。生物がまったく新たな生態環境に適応して陸上や空中に進出したさま、新たな生態系を作り出してますます多様化する道を開いたさまを探っていく。
我々の暮らす顕生代より以前、約5億5000万年前の原生代をしばし見物したら、我々の地球、現代の地球に戻ってくる。現代の世界の風景は、人類の引き起こす混乱のせいでめまぐるしく変化している。地質学的な過去に起こった劇的な環境変化と比べて、近未来、あるいはもっと遠い未来にはどんなことが起こりそうだろうか?
二酸化炭素の豊富な大気中でどのような大陸規模の変化が起こるかを実験するのは容易ではないし、地球生態系の崩壊がどのような長期的影響をおよぼすかを我々自身の目で確かめていたら、その変化を抑える前に手遅れになってしまう。そのため、世界の成り立ちに関する正確なモデルに基づいて予測をするほかない。その際には、地質学的歴史を通した地球のダイナミズムが自然の実験室となってくれる。
長期的な疑問に答えるには、過去の地球が未来の地球の姿を映し出しているような時代に目を向けるしかない。五回の大量絶滅が起こり、大陸塊が分裂・合体し、海洋や大気の化学組成や循環が変化してきた。それらをデータとして加えることで、地質学的なタイムスケールで地球上の生命がどのように作用するかを理解できるのだ。
*****
この惑星に関する疑問はいくらでも浮かんでくる。過去の生物は、戸惑いの目で見つめる単なる珍奇な代物でもなければ、現実離れした異質なものでもない。現代の熱帯雨林や、地衣類に覆われたツンドラに当てはまる生態学的原理は、過去の生態系にも同じく通用する。役者は違っても劇の演目は同じだ。
化石はそれ単独でも、形態の多様性、形や機能を見事に教えてくれるし、基本的な発生プロセスに少し手を加えることで生物に何ができるのかを見せつけてくれる。しかし古代の彫像が文化的背景の中に位置しているのと同じように、動物か植物か、真菌類か微生物かを問わずどんな化石も、それ単独で存在することはけっしてない。
どんな生物も無数の生物種や環境が作用し合う一つの生態系の中で暮らしていて、地球の自転、大陸の位置、土や水の中のミネラル、以前その地域に暮らしていた生物による制約条件が、生命と気象と化学作用の複雑な絡み合いを左右していた。化石が形成された世界、その化石を作った生物が暮らしていた世界を再現するという難題に、古生物学者たちは18世紀から取り組みつづけている。そしてここ数十年でその取り組みはスピードも詳しさも増している。
古生物学の近年の進展によって、過去の生物のことが、少し前までなら不可能だと考えられていたはずの細かさで明らかになっている。化石の構造を徹底的に調べることで、いまでは鳥の羽毛や甲虫の翅鞘、トカゲのうろこの色を再現したり、動植物がかかっていた病気を特定したりできるようになっている。また現生生物との比較によって、食物網における相互作用、嚙む力や頭蓋骨の強さ、社会構造や交尾習性、さらに場合によっては鳴き声まで明らかにできる。
もはや化石記録は、石に残された単なる痕跡のコレクションや、分類学的な名称のリストではない。最新の研究によって、求愛されたり病気にかかったり、明るい羽毛や花を見せびらかしたり、鳴いたり羽音を立てたりと、現代の生物と同じ生物学的原理に従う世界に暮らす実際の生物からなる、繁栄して活気に満ちた群集の姿が明らかになっている。
多くの人が古生物学と聞いて抱くイメージはそれとは違うだろう。ヴィクトリア朝時代の紳士然としたコレクターが文化の異なるほかの土地に旅して、ハンマーを手に地面を叩き割ろうとしているというイメージが定着している。物理学者のアーネスト・ラザフォードは「すべての科学は物理学か切手収集のいずれかである」と見下し気味に言ったとされているが、そのとき彼が思い描いていたのは、剝製にされた獣の並んだ棚や、しみ一つない翅を大きく広げたチョウの標本の入った引き出し、針金でつなぎ合わされた不気味な骸骨といったものだったはずだ。
しかし現代の古生物学者は、暑い砂漠に出ているのと同じくらい、コンピュータの前で一日過ごしたり、実験施設の円形粒子加速器で化石の奥深くにX線を当てたりしている。私は研究活動のほとんどを博物館の地下収蔵庫の中やコンピュータアルゴリズムを使って進めていて、最後の大量絶滅の直後に生きていた哺乳類どうしの関係性を、共通する形態的特徴に基づいて解き明かそうとしている。
現代に生きている生物だけから生命の歴史に関する知見を得るのもけっして不可能ではないが、それでは小説の最後数ページを読んだだけで筋書きを理解しようとするようなものだ。前のほうで何があったかをある程度推測したり、最後まで登場する人物の現在の境遇を知ったりすることはできるだろうが、筋書きの奥深さや無数の登場人物、物語の大きな山場は見過ごしてしまうかもしれない。
化石を考え合わせてもなお、専門家以外の人にとって生命の歴史の大部分はぼんやりとしか見えない。ヨーロッパや北アメリカに暮らしていた恐竜や氷期の動物は広く知られているし、この分野にもう少し馴染みのある人なら、三葉虫やアンモナイト、あるいはカンブリア爆発についても聞いたことがあるだろう。しかしそれらはストーリー全体の断片にすぎない。本書ではその空白のいくつかを埋めていきたい。
本書ではどうしても過去を主観的に解釈するしかなかった。遠い過去、真の「太古」というのは、人それぞれ別々のものを意味する。ある人にとっては気分を高めてくれるものであって、何兆ものプランクトンが堆積して圧縮され、隆起して、ケント州やノルマンディーの白亜の大地、生物の死骸でできた田園地帯になるのにかかった歳月を考えるとめまいを覚えてしまう。
また別の人にとっては現実逃避であって、現代の我々が経験しているのとは違う生き方、人間が引き起こす絶滅に対する懸念が生まれる以前、ドードーが未来の生物にすぎなかった時代について考える機会を与えてくれる。
とはいえ、いまから見ていくのはいずれも事実に基づいていて、化石記録から直接観察可能、あるいは強く推測される結論、または情報が不完全な場合には、確実に言える事柄から見てもっともらしいような結論である。諸説ある事柄については、競合し合う仮説の中から一つを選んでそれに従った。それでも、藪の中で羽ばたく翼、半分しか見えない獣の毛皮、暗闇で何かが動いたという感覚は、経験される自然の要素としてすべて一体だ。ちょっとしたあいまいさも、確実な真理と同じく驚きを生み出すものだ。
本書で再現する過去の姿は、200年以上にわたって何千人もの科学者が進めてきた研究の成果である。彼らによる化石の解釈が、最終的に本書の中の事実に関する記述へとつながった。古生物学者にとって、骨や外骨格や木材に見られる膨らみやこぶや穴は、現代に生きているかどうかにかかわらず、生物の一個体の姿形を組み立てる上で欠かせない手掛かりとなる。
現生の淡水ワニの頭蓋骨を見れば、その特徴の記述を読んだのも同然だ。ゴシック建築を思わせる控え壁状の隆起やアーチが見られるが、ここでは大聖堂の天井の重みを支えているのではなく、顎の筋肉の強い力に耐えるためだ。目と鼻孔が高い位置にあるのは、ほぼ完全に身を沈めて泳ぎ、水面すれすれであたりを見回したり呼吸したりするため。すぼまっていて先端の丸まった歯が長い曲線状の鼻面に沿ってずらりと並んでいるのは、つるつるした魚を食べるのに適した、獲物を叩いてからしっかりくわえるという食餌スタイルをうかがわせる。生きていたときの傷跡があちこちにあり、骨折してつながった跡も見られる。生命は詳細で再現可能な形の跡を残すのだ。
いまや古生物学では、一点一点の標本を超えて、過去の生態系の特徴や生物どうしの相互作用、ニッチ(生態的地位)や食物網、ミネラルや栄養分の流れを解き明かすことが当たり前のようにおこなわれている。化石化した巣穴や足跡から、形態ではうかがい知れない運動様式やライフスタイルの詳細を明らかにできる。生物種どうしの関係性からは、各生物種の生態や分布にとってどのような要素が重要だったのか、何がそれらの進化を促したのかが読み取れる。
堆積岩中の砂粒のパターンや化学組成はその土地の環境を記録している。この断崖面の地層はかつて三角州であって、その干潟をヘビのように曲がりくねった川が流れ、絶えず流路を変えていたのか? それとも浅い海だったのか? その海は外洋から隔てられたラグーンで、静かな海底に細かいシルトが徐々に堆積していったのか? それとも波が打ち寄せる場所だったのか? 当時の気温はどうだったのか? 世界の海水位は? 卓越風の風向は? いずれも、必要な情報があれば容易に答えられる疑問だ。
どこか一か所でこれらの情報がすべて得られることはないが、場合によっては何本もの糸をたぐり寄せて、気候や地勢からそこに暮らしていた生物まで、その土地の様子を生き生きと描き出せることもある。現代と同じく活気に満ちた過去の環境の姿は、我々が現代の世界に対峙する上で多くの重要な教訓を与えてくれるものだ。
*****
現代の我々が当たり前だと思っている自然界の多くの部分は、比較的最近になって現れたものである。今日の地球で最大の生態系の主役であるイネ科植物〔葉の細長い、いわゆる「草」〕は、白亜紀の最終盤、いまから7000万年足らず前に、インドや南アメリカの森林のごく一部で生まれたにすぎない。イネ科植物に支配された生態系が出現したのは約4000万年前だ。恐竜が草原を闊歩したことはけっしてなく、当時の北半球にはイネ科植物は存在していなかった。
現代の生物種をそのまま過去に当てはめたにせよ、絶滅してはいるが互いに何百万年も時代の異なる生物をひとまとめにしたにせよ、過去の風景に対して抱いているそのような先入観は捨てなければならない。最後のディプロドクスから最初のティラノサウルスまでの歳月は、最後のティラノサウルスからあなたが生まれるまでの歳月よりも長い。ディプロドクスなどジュラ紀の生物は、イネ科植物だけでなく花もけっして見たことがなかった。花を付ける植物が多様化したのは白亜紀中期になってからだ。
生息地の破壊や分断化と、気候変動の継続的な影響とが相まって、生物多様性が危機に陥っている今日、次々と生物が絶滅していくというのは我々にとって非常に身近な問題だ。我々は六番目の大量絶滅の渦中にあるという主張がたびたび聞かれる。サンゴ礁の広範囲の白化、北極の氷床の融解、インドネシアやアマゾン盆地の森林破壊といった話はしょっちゅう耳にする。
そこまで頻繁には取り上げられないが、湿地の乾燥化やツンドラの温暖化の影響も同じく非常に重要である。
我々の暮らすこの世界は、見渡す限りのレベルで変化しつつある。その規模と影響を把握するのは往々にして難しい。多様性に富んだグレートバリアリーフのような巨大な生態系がいつか消滅するかもしれないなんて、そもそもありえないように思える。しかし化石記録を見るとかるとおり、そのような大規模な変化は単に起こりうるだけでなく、地球史を通して繰り返し起こってきたのだ。
現代のリーフはサンゴでできているが、かつては貝などの軟体動物や殻を持った腕足動物、さらには海綿動物がリーフを作っていた。サンゴがリーフの主要な作り手になったのは、軟体動物のリーフが最後の大量絶滅によって姿を消したときである。リーフを作る貝類はジュラ紀後期に出現して、海綿動物からなる大規模なリーフの跡を継いだ。その海綿動物は、腕足動物からなるリーフがペルム紀末の大量絶滅で姿を消したのちに、リーフを作るというニッチを埋めた。
大陸規模のサンゴ礁は、長期的視点から見ると二度と復活しない生態系の一つであって、人類の引き起こす大量絶滅によって幕を閉じる新生代に限られた存在なのかもしれない。サンゴ礁など危機に直面する生態系もいまのところはバランスが取れているが、化石記録を見ると分かるとおり、優勢種もあっという間に衰退して姿を消す。化石記録は記憶と警告の役割を果たすのだ。
*****
未来の生命を推測する上で化石がふさわしい存在だなんて思えないかもしれない。化石の跡はまるでヒエログリフのように奇妙で、過去を遠くへ追いやってしまう。何か超えられない壁があって、魅惑的な存在にはけっして手が届かないのだと思わせる。
詩人で学者のアリス・ターバックは、『自然という分類法に小さな骨はことごとく抗う』という詩の中でその隔たりを表現し、「我にレビヤタン〔旧約聖書に登場する海中の聖獣〕の痕跡を与えよ、怒り狂う海獣を与えよ」と詠んでいる。また、「何世紀もつながっていて未知の地下室に通じる足跡」を希うとともに、博物館の分類命名法をはねつけて、「誰にも分類法を歌わせるな」と言っている。
かくいう私も門=綱=目という入れ子状の箱の中に生物を収めることに研究人生の一部を費やしている人間の一人だが、それでも分類よりも実際の生き物のほうに親近感を覚える。名前は意味があるし心に訴えかけるが、たいていの場合、その生物のイメージを呼び覚ますことはない。
学名は単なる記号、いわば生物学における図書十進分類法にすぎない。数字で事足りるし、本質的なしくみはそのとおりだ。それぞれの種や亜種ごとに、それが何を意味するかを示したタイプ標本が世界のどこかに存在する。たとえばイタリアアカギツネの学名はヴルペス・ヴルペス・トスキイといい、そのタイプ標本はボンのアレクサンダー・ケーニッヒ博物館に所蔵されているZFMK 66 -487 である。
ある個体をこの亜種と同定するには、その形態と遺伝子構成が、一九六一年にイタリアのガルガーノ山で捕獲されたこの理想的な成体と十分に近くなければならない。だが実際にそうだったとしても、街なかに暮らすキツネが庭のぐらついた柵の上を危なっかしく渡ったり、意味ありげに急いで歩いたり、童話のように人をだましたり、子ギツネがのんきに外で寝ていたりすることについては何一つ分からない。しかもいまでも身近に見られる生き物だ。
ましてや、絶滅した生物について名前だけから何が分かるというのか? そうした生物を紹介する上で私に課せられたのは、名前と現実、いわば異国の切手と金塊との隔たりを埋めるという難題。古代の生物を、我々の世界にたびたび姿を現す存在、震えて怒りをたぎらせる肉体と本能を備えた獣、幹をきしませて葉を落とす植物であるかのようにとらえるという難題である。
今日、絶滅生物を生きているものとして表現する場合には、果てしない食欲を持った邪悪なモンスターとして描かれることがかなり多い。この風潮は19世紀初頭、地質学をセンセーショナルに取り上げた人たちにさかのぼる。彼らは自分たちの思い描いたドラマチックで冷酷な過去のイメージを売り込もうとするあまり、当時ですら植物食であることが知られていたマンモスや地上生ナマケモノを大食いの肉食動物として表現した。
たとえばマンモスは、湖に身を潜めて獲物のカメを待ち伏せする強力な捕食動物として世間に紹介された。おとなしい植食動物である地上生ナマケモノは、「険しい断崖のように巨大で、血に飢えたヒョウのように残酷で、舞い降りるワシのように素早く、夜の天使のように恐ろしい」とされた。今日でも数えきれないほどの映画や本、テレビ番組に、容赦なく残酷に攻撃してくる先史時代の動物が登場する。しかしどのくらい血に飢えていたかで言えば、白亜紀の捕食動物も現代のライオンと同じくらいだ。もちろん危険だが、モンスターではなく動物である。
化石を骨董品として淡々と集める営みと、絶滅生物をモンスターとして表現する姿勢、どちらにも欠けているのは実際の生態学的状況だ。植物や真菌類はたいてい取り上げられないし、無脊椎動物にもおざなりな視線しか向けられない。しかし岩石記録にはそのような生態学的状況も収められており、そこからは、絶滅生物が暮らしていた環境、彼らをいまでは非常に奇妙に思える姿へと変えた環境が明らかになる。それはいわば可能性の百科事典、いまでは失われている風景の百科事典である。
本書ではそれらの風景をいま一度甦らせることで、針金でつなぎ合わされてほこりをかぶった絶滅生物のイメージ、あるいはテーマパークにいるようなセンセーショナルでうなり声を上げるティラノサウルスのイメージから脱却し、リアルな自然を今日と同じように体験してもらうことを目指す。
かつて存在していた風景に思いを巡らせると、時の旅人になった気分に浸れる。各訪問地は空間的というよりも時間的に隔てられているのだが、本書を博物学者の旅行記のつもりで読んでもらって、過去5億年の歳月を計り知れない時間の流れとしてではなく、途方もないと同時に身近でもある世界の数々として見つめてもらえれば幸いだ。
◎『素晴らしき別世界』発売中
若き古生物学者が、生物学×地学×環境科学の最新かつ膨大な知見をもとに、絶滅してしまった生命と地球の姿をリアルによみがえらせます。最も新しい氷河期(ラムセス2世のエジプト新世界)から生命の夜明け(エディアカラン期)まで、16の時代を旅し、7つの大陸すべてを舞台にした、時間を超える旅行記。



●著者略歴
トーマス・ハリデイ(Thomas Halliday)
地学、古生物学、進化生物学、環境科学が専門。ケンブリッジ大学で自然科学の学位、ブリストル大学で古生物学の修士、ユニバーシティカレッジ・ロンドンで博士号を取得。理論と実際のデータを組み合わせ、化石の記録、特に哺乳動物の化石から今まで地球上に何が起こったかを研究している。現在はバーミンガム大学地球科学科とロンドン自然史博物館で特別研究員を務める。スコットランド、ハイランド地方のランノホ湖のほとりで育ち、家族と一緒にロンドンに暮らしている。
●訳者略歴
水谷淳(みずたに・じゅん)
翻訳者。主に科学や数学の一般向け解説書を扱う。主な訳書に『僕たちは、宇宙のことぜんぜんわからない』『「ネコひねり問題」を超一流の科学者たちが全力で考えてみた』(いずれもダイヤモンド社)、『量子力学で生命の謎を解く』、(SBクリエイティブ)、『この世界を知るための人類と科学の400万年史』(河出書房新社)などがある。
