
マネキン・コンプレックス
手元のマスクを二枚持って仕方なく立ち上がり、俺は玄関に向かった。
いや、玄関とは名ばかり、扉一枚の向こうはもはやアパートの廊下である。古ぼけたアパートに似つかわしい木製のドアを、誰かがせわしなく叩き続けており、それがあまりに鳴り止まないせいだろうか、音はいつしか俺の内部でこだまになっている。
とんとんこん、こんこんとん、こんとん。
名前が呼ばれない以上、彼女のわけがない。あの娘はまだここの住所も知らないのだ。住所を教えていなかったのは迎えに行けばいいと思っていたからで、迎えに行くのも、その直前に電話でやり取りすることになっていた。けれどもドアノックの一撃の時は、さすがに心が躍ってハッとなった。でも彼女ではない。
とんとんこん、こんとんとんとん、こっこここっこ、こんこん。
時代に取り残され、都会の片隅に捨て置かれたアパートの、貧乏学生の部屋のドアを、逢魔が刻にこれほどしつこく叩くからには、どのみちろくでもないNHK集金人か、やさぐれた新聞勧誘人だろう。宅配便、頼んでないし、扉を素直に開けないぞと思いつつ、勝手に動いた手が俺の口元に一枚目のマスクをつける。
とんとんこんこん、こんとんとん。
俺は扉の前で息を殺す。このノックが止んで沈黙が来て、靴音が遠ざかればそれでいいのだ。
板一枚向こうの世界の沈黙をはかるこちらの沈黙を、あちらの沈黙がはかる気配。重すぎる沈黙だ。沈黙ゆえの息苦しさに、俺は胸騒ぎを覚えた。果たしてドアの向こうに誰かいるのか?咳払いひとつ聞こえない。かといって遠ざかる靴音は聞こえなかった。
俺は沈黙には慣れている。中学時代に父は、俺と母を捨てた。生活のために母は水商売を始めた。淋しいと言う言葉は十三歳で飲み込んだ。北国の田舎町は狭い世間であり、俺の母が夜の世界に身を投じたことは、たちまち級友の噂になった。生来無口だった俺の口は、いっそう固く閉ざされることとなった。
過去との決別を夢見ていたのだと、俺は一年数ヶ月前の自分を笑いたくなる。大学合格を機に、人生を変えるべく始めた都会の一人暮らしだが、思いがけなくコロナ禍がたたって授業はオンラインがメインで、生活のために始めたコンビニのアルバイト以外社会との接点もなく、広い都会の片隅で俺は未だに一人の友達も作れずにいた。
ところが、我ながら信じられないことに二週間前、ひょんなことから彼女とファミレスで知り合い、思いがけずに会話がはずんだ。母親以外の女と二分以上話したのは生まれて初めてだった。あの時と比べれば嘘のような静けさ、いや、嘘のようなあの時と違って、こっちの方がいつもだ。
たとえいつもみたいな静けさだとしても、俺は息を殺し疲れた。沈黙の探り合いに音を上げたのだ。ドアを開けたら九割方、相手と向かい合うだろう。気まずいに決まっている。それでもそいつがもし人間だったなら、相手だって気恥ずかしいはずだ。居留守を使っていたのと鳴りを潜めていたのは、失礼さで比べたらどっこいどっこいだろう。
無意識に二枚目のマスクを付けた俺のオートマチックな手は、次にドアの鍵に伸びた。そっと開けた鍵がカチャッと忍び音をもらす。大雨で冠水した道路の水嵩が増すように、鍵を開けた後のためらいは俺を浸して行く。俺の手はドアノブをゆっくり時計回りに回した。
ドアを薄く開ける。さっきまで漂っていた気配の影すらない。俺は思い切って廊下に半身を出し、左右を確認したが誰もいない。
とんとんこん、こんとんとんとんってなんだよと言いながらドアを閉め、振り向いた俺の目に、西の窓から差し込む黄昏の光が作った、女の形らしき逆光のシルエットが飛び込んできて、俺はのけぞって、「わっ!」
「『わっ!』ってなあに?」
「だれ?」
道がありました。壁に挟まれた道を、いつしか私は歩き出しました。私は、黙々と歩いて行く人の群れの中にいたのです。時代という名のその大道がどこにつながっているのか、果たしてそれが正しい道なのか知りませんでした。
隣の人に、「小雪」と呼びかけられたりしました。その人に、「この道でいいの?」と聞いたけれども、答えてもらえませんでした。不安と共に歩く道。たった一つの安らぎは、いつも視界に太一の姿があることでした。太一だけがいつでも心の支えでした。
その大道は土埃を立てながら歩く人々を誘うかのように、急勾配の下り坂となったので、誰もが転がり落ちるように夏の道の上に黒い影を走らせました。私も太一も駆け下ったのですが、その時道は上り坂になり、突然途切れました。一歩先を走っていた太一が「わっ!」と言ったなり、消えました。
「『わっ!』ってなあに?」「君は…誰?どこから入った?」
「どういうことですか?」「どろぼう?なんで?どうやって?誰?」
「名前すらお忘れ?ご自分が『おいで』って…」「俺が?」
「ひどいわ。どろぼうあつかい」「すみませんが…中に入っていいでしょうか?」
「あなたのお家でしょう?」
私と体を入れ替えて、直樹さんは部屋に入って私をこわごわ見ています。体全体に不審が色濃く滲んでいます。ところが直樹さんの目は「ちょっとお目にかかれないような美人だ」と語っています。分かりやすいお方。
「どうなってるんだ」
「『好きだよ』って、あれはウソですか?」「俺が言ったの?」
「直樹さん!」「えっ!俺の名前、知ってるんだね。それにしても、君は…。ヒントだけでも」
「あなたのその手で…」「いや。手ってうそだあ。だって自慢じゃないけど、この手は母親以外の女の手をまだ握ってないんだ」
「情けなく、言う甲斐なく、浅ましい」
直樹さんはしばらく私の顔色をうかがっていましたけれど、不意に何かを思い出し、
「そうだ!悪いけど、話はまた後で聞くから、とにかく今日は帰って下さい」
「どういうことですか」「いや。まずいんだ。頼むよ。帰って」
「納得できませんわ。きちんと説明してくださらない?」「つまり、えーと。困ったなあ。そう。弟が来るんだ」
「お兄さんではなくて?」「えっ?そうそう。兄貴」
直樹さんのスマホが鳴り出しました。直樹さんは気配を察して逃げるトカゲのような素早さで慌ててスマホを持って部屋の隅に行き、電話に出ました。声を殺しながら、
「はい。あっ、ちょっと待って」と言いつつ、私の脇をすり抜けて廊下に出ました。
「結菜さん?今ちょっと…。えっ?そう。そうなの?うんうん」
廊下の声は、扉一枚隔てた私の耳にまる聞こえです。
「うん。分かりました。いいよ、いいよ。じゃあね」
と電話を切り、部屋に戻ってきた直樹さんの顔に、「どうやって取り繕うか」と書いてあります。分かりやすいお方。
「お兄さんの名前が『ゆいな』さんなんですね」「いや。あっ。ええと、それは兄貴の彼女の名前で」
「それで?」「彼女の親戚に、不幸ができて、兄貴も一緒に行くってことで、うちには来られなくなった」
「では私、帰らなくていいですわね」「でも弟が」
「よくてね」「はい。ええと…。そうだ。行ってきます」
「どちらへ?」「どちらへ?…買い物、かな?ほら、男は外に狩りに行くもんだよね。あはは」
「投げ槍はお持ちになりました?」「と、とにかくだ。じゃあね」
「私の名前は?」「はい。買ってくるね」
分からないお方ね。
接客マニュアルの言葉以外を発したのは久しぶりだ。ルーティンで対応できないから焦った。違う、焦ったどころではなかった。玄関で振り返ったら女がいた。背筋がゾクッときた。熱が籠もっているはずの夕方の部屋の温度が、下がった気がしたよ。
それにしても、いい女だった。背の高さは、結菜さんくらいかな。時代がかった半袖の刺繍のワンピース、粋なたたずまい、古風な話し方、それでも若々しい雰囲気。肌が日焼けして小麦色だったからよかったものの、あれで色白だったりしたら怖すぎだよ。やっぱりどこかで見たことがある。でも思い出せない。
今更ながら気がついたのだけど、俺は我知らずかなり狼狽していたらしい。さっきからあてどもなく歩いており、ここは…ゴミ集積所だ。
俺は目の端でちょっとゴミ集積所を見て、そのまま通りすぎようとして、ハッとした。俺は黄昏時の「ここ」で固まってしまったのだ。
まさか。あの娘はもしかしたら?いやいや、まさか。ユキは今朝、そうだよ「ここ」に、俺がこの手で捨てたんだ。さっとこの場を見、次に気をつけてくまなく見回し、俺は愕然とした。「ない!捨てたはずのユキがない!」
俺が捨てたはずのマネキンは「ここ」にあるはずだ。それなのにそれの影も形もなくなっているのは、何故なんだ。
「ははは!」俺は安堵の笑い声を立てた。
なくていいんだよ。そうか、回収業者が持っていったんだよな。そうだ、ここはゴミ集積所なんだ。マネキンはモノだ、物体だ。その物体を俺はゴミとして捨てた。不要なゴミは回収されて当たり前。ユキは回収されたんだ。運ばれていったんだよ。捨てた物体が戻ってきてあの女になったなんてありえない。ドアをコン、コン、コンと叩いたりするはずがない。だからアパートに帰っても俺の部屋にユキがいる訳ないし、あの女だってさっきいたのが何かの間違いで、もう今頃はさすがにいないだろう。
アパートはもう大丈夫だ。そもそもあそこは古いアパートだけど、幽霊の噂は一度も聞いたことがなかったし。
でももし、帰ってドアを開けてユキがあったとしたらどうする?あるいはあの娘がにっこり笑って、「そうよ。やっと分かったの?私、ユキよ」とか。
いやだ、いやだ。ちょっと状況を整理してみよう。ある満月の晩、俺はマネキンを拾ってきた。マネキンを部屋に入れ、「お前は俺のガラテアだ。イライザだ。色が白いから、ユキって名前にしよう」と声をかけた。それ以来毎日、いろんな話を語って聞かせた。昔飼っていた猫の話とか、好きな小説の一説とか。あの頃は、考えようによっては今までの人生の中で一番幸せだったかも知れないな。
それから俺は、突然結菜さんと知り合い、上手い具合に仲良くなった。そしてついに、結菜さんは今日俺のアパートに来ると言った。ところが困ったのはユキの存在だ。「さすがにマネキンはまずいだろう」と俺はユキを捨てた。その捨てたユキが戻ってきて、ドアをこん、こん、こんと。
こんこんこん。
「うわ~!」飛び上がって振り向くと、近所のおばあさんが杖で道路を叩いていた。
「ちょっとどいてくれませんか。まったく、それ」
「な、なんですか…。びっっっくりしたなあ。もう…」
「『びっっっくりした』はこっちのセリフですよ。それよりおにいさん、それ。それですよ。その壊れた椅子」
「椅子?椅子がどうかしましたか?」
「燃えるゴミの日にそんなの出しても。いや、あんたじゃないのは分かってますよ。誰か捨てるんですよ。今日は燃えるゴミの日ってのが分からないんですね。何でも好き勝手に出しちまう。持ってってもらえるわけないじゃありませんか」
「はい。どうも。じゃあ。さよなら」
「んんん」おばあさんの咳払いだ。目で「手伝え」って言っている。仕方がないから俺は、椅子を端に寄せた。
「ありがとうね。どうも。さよなら」
「さよなら」「やれやれ。…。待てよ。ということはだ。ユキは回収業者が持っていった訳ではないってことだ。やだなあ。おい」と独りごちて、俺は立ち止まった。
次の瞬間、俺の血が逆流した。
なんだよ!どういうことだ?目が釘付けになる。でも言葉は出ない。
俺のちょっと前を、男と女が手を握って歩いてゆく。愕然とした俺は、次の瞬間、思わず電信柱の影に隠れた。何で俺が隠れているんだ。
「急に会えるようになってよかった。ありがとう。リョータさん」と女が言った。
男は「出張がなくなってよかったよ」と言って、二人で楽しそうに去って行く。その女は結菜だった
「ありがとう。リョータさん」ふんっ!リョータってのはどこのどいつだ?どういうことだ?
さっきの電話では「直樹くん、ごめんね。親戚に不幸ができちゃって、今日これからお通夜なの。今日、行けなくなっちゃった」とか言いやがって。あれ、どう見てもお通夜じゃないよな。ふざけんなよ、結菜!
宵闇がひたひたと寄せる頃、彼が帰ってきたわ。「ただいま」
「おかえりなさい。元気ないわね。いやなもの、ご覧になったのでしょう?」「えっ!なぜ分かる?」
「顔に書いてありますわ」「俺の顔に?」
直樹さんが私の顔をまじまじと見ています。「さっきと、変わった…何か変わったよ」
「そんなことより、気づいて下さらないの?」「うわ~、ごちそうだ。おいしそう。いい匂い」
「冷蔵庫にあるものでありあわせで作ったから、適当なんです。ごめんなさい」
「すごいすごい。麻婆豆腐に、野菜炒め、キュウリとワカメの酢の物、阿房飯店の麻婆定食みたい」
「おいしいかどうか…」「でも、なんで俺の好物を?」
「女の勘です」「もしかして、俺が落ち込んで帰ってくると察して?」
「猫のニャルコも引越の時にはお別れに来た」「なんでそれ知ってんの?やっぱり、ユキ?」
「ユキってどなた?」「違うの?」
「違わないと思いますの?」
私のひと言で、直樹さんは固まってしまいました。いけない、いけない。
「ユキだよ。だってその話、他にしてないもの。いくら俺がアホだって自分が言ったことくらい覚えてるよ」
声が硬いわ。簡単にはいかなそうね。でも何とかしましょう。今頃太一もきっと、苦労しながらがんばってくれているわね。
「ユキだの結菜だの、直樹さんには女が多いのね」「結菜のヤツ…。男と歩いてたんだよ」
「好きだったの?」「好きだったのかな…。よく分からない。でも、その男を見て頭にきたよ。むしゃくしゃした。悔しかったよ。俺、おかしいのかな」
「誰でもそうなると思いますわ」「そういってもらえると。ちょっと聞いてもらえるかな。そいつ、白い麻のスーツに黒の細いタイ、おまけにカンカン帽を被ってたんだぜ、信じられる?変だよね。ねえ。ユキ…」
「『ユキ』じゃないけれど」「ねえ、色が白くなったね。何で?」
「さあ。目の錯覚ですわ」「違うよ。何かこう、ゾクゾクって来る白さだね」
「色白の女性がお好み?私、ユキさんじゃありませんけれど、実は、よく似た名前なんです」「何て名前?」
「小雪よ。何日も一緒にいたのに覚えて下さらなかったのね」「ごめん。…でも、よく分からないな。何日も一緒にいたって、どういうことかな」
「これからも一緒にいれば、これからの時間が積もります。それでよくてよ」「これからも?ここに?」
「はい。さあ、お食べになって」「ああ。ありがとう。いただきます」
俺の気のせいだった。毒でも盛られていないかとこわごわ手を付けた御飯だったけれど、食べ始めてみるととても美味しかった。
「ああ、美味しかった。まるで阿房飯店みたいだったよ」「ありがとう。阿房飯店て?」
「うん。近所の中華料理店。月一の贅沢で…、つまり仕送りが来た日にだけ食べに行った店なんだ」「……」
「コロナ禍でソーシャルディスタンスが推奨された時、テーブル席にマネキンを置いて距離を確保したんだ。それがニュースで取り上げられて、結構繁盛したんだけど。でもね、度重なる緊急事態宣言だろう?時短営業のしばりで経営悪化してゆき、とうとうこの間、閉店になっちゃったんだ」
ユキとの出会いはあの店だった。そのマネキンが一目で気に入った俺は、自分であの席を勝手に指定席に決めて、月一に通ったもんだ。中一の時から九年間、ずっと個食だった俺に、始めて会食の相手ができて、俺は嬉しかった。だから食事の時はいつも、怪しまれないようにと周りに気を配りながら、俺はひそかにいろんな話をした。自分の生い立ちも彼女に語った。
けれども店は閉店。好物の麻婆定食を食べられなくなったことより、俺はそのマネキンとの別れがショックだった。
その後すぐだった。ゴミ集積所でそのマネキンと再会したのは。
「無口ですね」
「あっ、ごめん。食べ過ぎたかも」「胃薬、ありますわよ。はい、お水。スウッとするわよ」
「うん」あれ?何で受け取っているんだろう。
「はい。鼻をつまんであげましょうか」
「いらない、いらない」飲んじゃった。スウッと?するな。そういえば小雪さん、なんでマスクしないんだろう…。
「マスクなんてまっぴらです。物言わぬ奴隷の象徴。もう、うんざり」
「そう…。じゃあ、キスしていい?」何か眠くなってきたぞ。でも、俺は小雪さんにせまった。小雪さんはずっと見ている。嫌そうではない。体がふんわり重い。あれえ、小雪さん、まばたきしないぞ。こ・ゆ・き・さ・ん…。
「いい子はおやすみ。直ちゃんはいい子よ。いい子だし、幸せな子。ただ、それに気がついてなかったわ。そりゃあ、母子家庭はさみしかったでしょう。個食?そうよね。でも、食べられないことはなかったでしょう?」
返事をしようにも口が重くて動かせない。眠い…。
「コンビニの賞味期限切れや新商品のサンプルは、経営者の店長がこっそり食べさせてくれたじゃない。着る服だって日替わりで着る程度にはあるわね。なんといっても、その年になるまで勉強できたじゃない…」
そこから先は覚えていない。
郵便受けで見てきたけど、時田直樹だと。名前だけは立派だぜ。でも、油断だらけの部屋だぜ。カーテンが開いているのに人影はない。洗濯物を見れば一人もんだ。学生だったら、そして仕送りの後とかバイトの給料日後だったら、うまくいけばタンス預金にありつける。
いつもの手口だ。ドアをノックして出てきたら新聞の勧誘員になればいいし、出てこなければノブを回してみる。ごく稀に空いてることがあり、その時には仕事をさせてもらう。さて、今日はこの部屋からだ。
とんとんとん。こんとんとん。
人気なしと…。ドアは?しめしめ、初っぱなからラッキーだぜ。よっぽど脳天気なヤツだな。こういうヤツで間違って地方出のお坊ちゃん…、まあこんなぼろアパートだからお坊ちゃんというほどじゃあないにしても、多少の小金持ちのガキがいるからな。さてと、お邪魔しますっと。
えっと、流しは片付いているし、冷蔵庫は、おっ、やった、ビール三本、後でゲット。テーブルの上に小銭は…ゲッ!な、な、な、何だ!部屋の隅でこっちを見てる。
マネキン?こわかった…。まったく、どういう趣味してんだ。
「ただいま~。まだいるかな」
まずい!どこに隠れよう。いや、ダメだ。隠れる暇がない。
「駅前でたこ焼き買ってきたよ。あれ?誰か来てる?だれ?」
「い、いや、えええええと」部屋の主は俺をじろじろ見て、…、やばい。殴られるか通報されるか。
「ガス屋さん?」
こ、こいつ、おかしい。マネキンの方を向いて何か言ってる。いいや、この際、一か八かだ。
「ガガガガガガス屋です」ダメか…。待てよ。またマネキン見てる。
「そうですか、警報器の確認に来てくれたのですか。ご苦労様です」
もしかしてこいつ、このマネキンと話してるつもりなんだろうか。やば過ぎるところに入っちゃったよ。何とか早く逃げ出さなきゃ。「だ、大丈夫でした。そ、その、ガスは大丈夫。警報器はちゃんとコンセントに刺しといてくださいね」
「了解です。お世話になりました」
「そ、それでは」これで脱出できる。長居は無用。
「あの」
ドキッとするぜ。バレたか。謝るか逃げるか…。
「ちょっと待って下さい。うちのが『薬を飲め』っていうので。ああ。う~ん。お待たせしました。ところで、いいんですか?」
何の話だろう。怖いなあ。訳分かんないけど何言い出すんだろう…。何かだるそうな雰囲気だぜ。こいつ、大丈夫か?
「サインとかは?」「い、いや、証拠を残すと…」「えーと。証拠って?」「こ、こ、こ、こっちのこと。さよなら」まったく冗談じゃないぜ。
それにしてもさっきの男、おかしかったぜ。マネキン見て「うちの、美人でしょう?」だとよ。狂ってるよ。狂ってる上に、まったく生気ってもんがなかったぜ。それから、どんどん変になっていったな。見てらんなかったぜ。あそこは鬼門だ。金輪際、近寄るめえ。
あこがれの赤い屋根の女学校に入ったと思いましたら、授業はほとんどなく、毎日毎日勤労奉仕。働いても働いても満足に食べるものがなくて、ひもじかったですわ。あの頃に比べたら、どうってことのない労働ですね。ゴミ捨てくらい。
昨日までかかりきりだったあれ、やっと片付きました。それにしてもあのお方、母子家庭が珍しくない世の中に生きていながら、女々しい男でした。捨てられたとしても文句は言えないでしょう。
あのお方はあの年まで、食べられたし、着られたのです。今日に至るまで、あのお方の上に空から爆弾が降って来た日は一日たりとてなかったのですから。そういう時代に生まれながら、家とバイト先と大学の三点移動だなんて。生きていると言えないようなグズグズな人が一人二人消えたところで、どうってことないはずですわ。
やれやれ。お仕事はちょっと難しかったですけれど、「今時分、太一も頑張ってるのでしょう」と思うことが心の支えでした。
母子家庭にしても、今とは別物でした。大家族が当たり前とは言っても物がない時代ゆえ、母の実家に母子で転がり込んだ居候暮らしは、やっぱり肩身が狭うございました。母はお針子をやって必死に働いてくれましたわ。でも、お金持ちの着物を縫い上げた後で私の着物を縫う余力は、母にはありませんでした。ええ、母自身も着た切り雀でしたから、それを恨みがましく思ったりはいたしませんでした。けれども、物心ついてからおひな祭りの記憶もなく、満足に着たい服を着たこともなかったのです。綺麗な服と食料との交換を望んだ金持ちが、風呂敷包みを提げて都会からやって来たのを、勤労奉仕先の農家で目撃した日には、「農家の子に生まれたかった」と思ったものでしたわ。
さて、マネキンの下半身に次いで上半身、これで終了。少し待てばきっと太一がやって来ます。待ち遠しいな。「人目につかない時間帯」って約束してありましたから、間もなくですね。
やって来ました。お互いこれで、積年の願いが叶いましたわ。
「おはよう」
「待ってたわ。いい朝ね」「うん。終わったね」
「はい、でも」「でも?」
「放置、ちょっと可愛そうじゃないですか。あっ、ほら。こんこんこんって」「中で叩いているね。でも、そのうち静かになるよ。もともとが巣ごもりやってた二体だったし。だから閉じこめて放置が相応しいんじゃないかな。それに、置いておけばそこいらのドロボウが、きっと自分の部屋に持って行くさ」
「そうね、じゃあ取りに行きましょう」「そうだね。お互いの体を取ったら、どこで待ち合わせる?」
「あそこはどう?あのファミレス」「いいね。今日の日にふさわしいね」
朝焼けの中、私たちが振り返ることはありませんでした。
とんとんとん、こんとんとん。
音は遠ざかってゆくばかりです。 了
著・二宮 ヒロ
こちらの作品は、「山田組文芸誌vol.6」に収録されているものです。
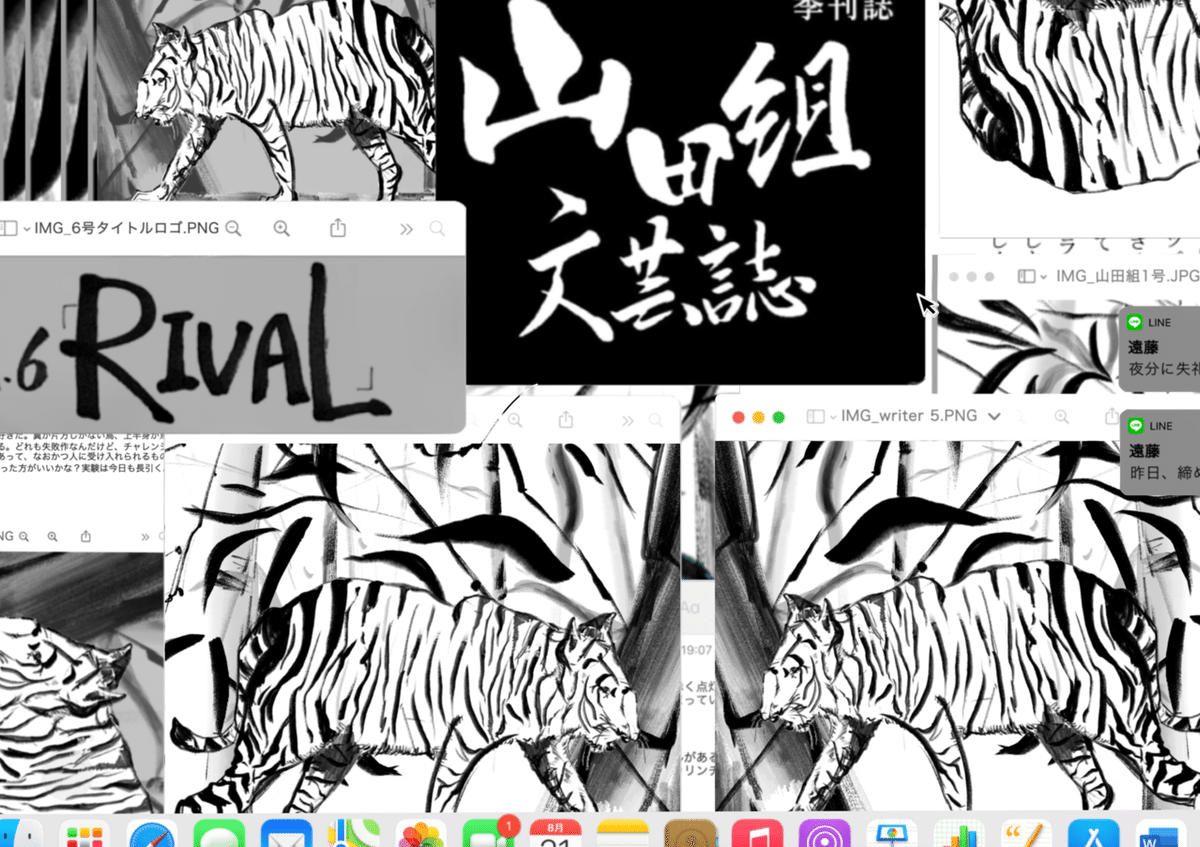
「山田組」とは、2019年に発足された文芸部です。現在は会員4人、準会員1人で活動しています。指定されたテーマに沿って小説を書き、季節ごとに文芸誌を発刊します。
最新号『山田組文芸誌vol.6「ライバル」』はこちらから無料ダウンロードできます。お読みいただく際には、PDFリーダーの使用を推奨しております。↓
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
