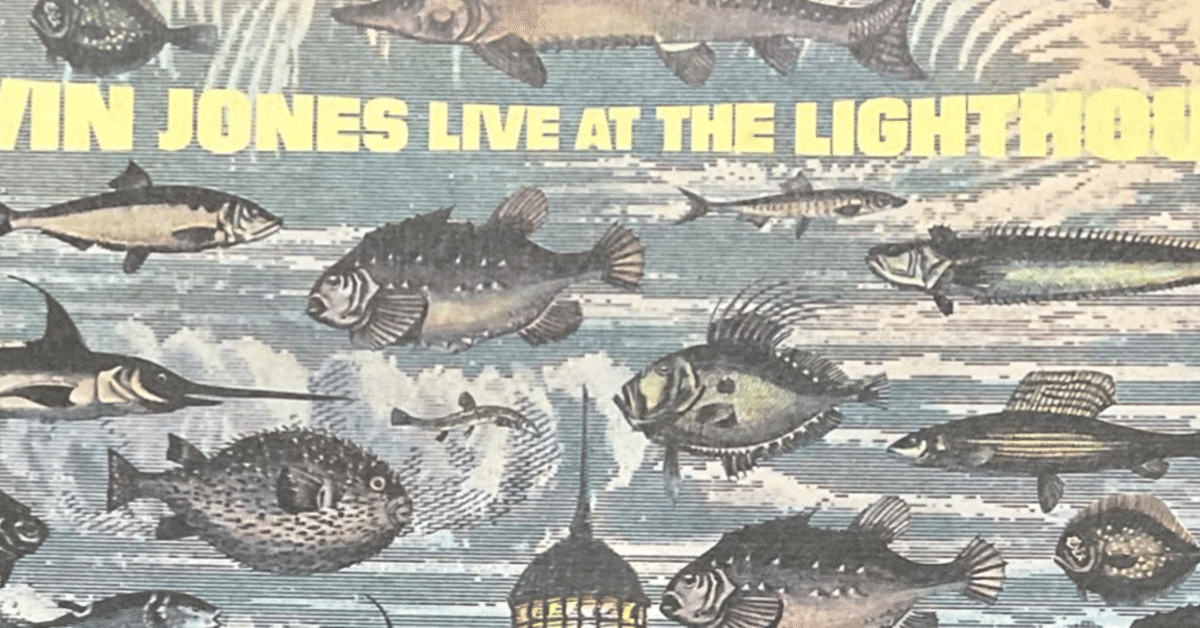
Steve Grossman研究-70-80年代のスタイル変遷を検証する―その6 謎の路線転換とハードコアビバッパーとしての復活 82-86年
前回採り上げた81年夏のギルエバンスのライブアルバム以降、グロスマンの録音は一時途切れる。
1980年代の(ニューヨーク)ジャズシーン考察
この時期、私もすでにリアルタイムでジャズ界状況を見ている。当時は、ジャコ入りWeather Reportがそのピークを迎えており、マイルスの復活もあって、いわゆるシリアスなフュージョンが全盛であったといえるかもしれない。ニューヨークジャズ シーン的には、ブレッカーブラザーズが経営していた7th Avenue Southあたりで、毎夜強烈なセッションが繰り広げられていた時期であった(それが表に出てきたのがStepsやマイクマイニエリのセッション)。
一方、マルサリス一派がシーンに表れてそれなりの影響力を持ち始めたのもこのころ(82-3年頃?)であり、60年代、50年代(さらにはもっと前)への回帰とフュージョンムーブメント、あるいはそれを消化したうえで、フュージョン方面へと発達していたニューヨークジャズを否定するような動きが起こり始めた時期といえる。
そういえば、この同じ時期(82-84年ぐらい)にマイケルブレッカーも音源が極端に少なくなっている。これは喉の手術が原因といわれているが、 いわゆる麻薬過から抜け出すために入院をしていたという要因もあるはずである(81年12月のジャコのバースデーライブは、その手の病院への入院直前、あるいは、入院の最中に抜け出して参加したという記録もある)。
あくまでも想像だが、この時期、ニューヨークのジャズシーンは急激に変わっていたのではないかと思う。スリクでイケイケで、観客を無視したような過激な演奏バリバリ、みたいな環境から、クリーンでクールで大人しい「仕事」中心みたいなシーンになってきたというか。
NYの街全体としてクリーンになりつつあったとか、ジャズがいわゆる伝統音楽として観光資源的な扱いになっていったという要因もあるかもしれない(マルサリス一派はそれを後押ししたともい える)。音楽的にも生活態度的にも、そのクリーン化に乗り遅れて自滅したのがジャコだったりするわけだが。
そんな中、生粋のスリクイケイケニューヨーカーだったグロスマンもニューヨークでは肩身が狭くなっていたのではないか。音楽的にもシーン全体が混乱期に入る中、自分の生きる道を考え直したとしてもおかしくはない。
グロスマン、バッパーとして復活
というわけで、84年以降、グロスマンはそれ以前のリーダー作とはまったく異なる路線のアルバムを立て続けに録音している。86年までで私が確認しているのは以下。
(1) 【Way Out East Vol.1, 2】1984/7/23-4@Milano, Italy
(2) 【Hold the Line】1984末 or 1985初め?@ New York
(3) 【Love is the Thing】1985/5@Italy
(4) 【Standards】1985/11@New York
(5) 【Katonah】1986/2/4@日本
(1) と(3)はイタリアのRedレーベルの制作で、イタリア録音であるが、バックのミュージシャンはすべて米国ジャズマン。(2),(4),(5)は日本人ドラマーで ある我らが吉田正宏さんの働きかけで作られた日本制作盤である。特に(5)は来日時に日本人のミュージシャンとともに録音された作品。
1984-5年あたりは、大学生の私がすっかりグロスマンにハマっていつつ、その活動が見えなくて寂しい思いをしていた時期であるが、こうやって改めてみるとす、っかり活動を復活させていたんだなあ。ちっ。確か、私が大学の4年生だった1985年の初めあたりから、グロスマンが日本人と一緒にアルバ ム録音した、みたいな噂がジャズ研界隈に伝わり始め、同年半ばに”Hold the Line”がリリースされたのが(日本に居た我々にとっての)グロスマン復活の第一弾ではなかっただろうか。ものすごくダサいジャケットのレコードを手に入れ妙に興奮した記憶がある。

演奏フォーマットとしては(1)はテナートリオ、そのほかはピアノ入りのワンホーンカルテットである。グロスマンフリークの皆様はすでにご存じのとおり、 ここら辺のアルバムはすっかり「スタンダードをロリンズのように」というスタイルに変貌している。以前のレパートリーは(5)に入っているKatonahと Taurus Peopleぐらいだ。1990年代以降はスタンダードを演奏するのがすっかり普通で、モードの曲やると驚かれるようになってしまったグロスマンだが、当時はアルバムがリリースされるたびに、スタンダードのあの曲が、この曲が、と狂喜乱舞したものだ。
この時期の重要アルバム:Love is the Thing
さて、この時期のほとんどのアルバムは「その場の思いつきで適当に選曲した」感満載なのだが、その中で異色なのは(3)だろうか。シダ―ウォルトントリオという世界一端正なピアノトリオをバックに、極めてストイックかつスタイリッシュな演奏をしている。もう少しわかりやすく言うと、無駄に熱くならず、短いコーラス で極めてキッチリと構成されたソロ、要は50年代中盤のロリンズみたいな演奏だ。曲も普段やらなそうな”I didn’t know what time it was”なんて渋い曲やってたりするし。ちなみにこの曲のソロは恐らくグロスマンベストソロ集の中には必ず入ってくるであろう名演。時折グロスマンフレー ズも織り交ぜつつ非常によく唄っていてしかもまとまりのあるソロ。っていうかこのアルバムごとグロスマンアルバムベスト5には必ず入るであろう名盤なので、まだお聴きでない方はぜひ。ブチ切れグロスマンを期待すると裏切られますが。
サブスクもあります。
当時のNY隠し録りテープにみるスタイル変貌
さて、私は当時のライブ録音というのも多少持っている。86/2の来日時の演奏はすでにみんな知っているので、自慢含みでその多少前のニューヨー クでの隠し録りのことをちょっと書いてみる。この音源そのものを入手したのが1985年で、結構複雑な入手経路のはずなので、おそらく実際のライブは 1984年あるいは1983年とかであろう。というわけで、要は(我々から見て)お隠れになっていた時期の演奏の可能性あり、ということだ。
隠し録りには二つのセッションがあり、片方はラッパにトムハレル(!)、ドラムにビリーハートが入っているクインテット。もう一方はドラムにアー トテイラー(!)、ピアノにロニーマシューズが入っているカルテット。選曲としては、やはりもう完全スタンダード路線で、おなじみのFourとかStar Eyesとか、Mr.PCとか。いや、どちらも凄いんだが、やっぱりアートテイラーが凶悪なんすよ。すげースイングしてる。OleoとかMr. PCとかグロスマンを煽りまくりでグロスマン普通に負けてるしw。
というわけで、1984年ごろにはニューヨークに拠点を置きながらすでにその後のスタイルに繋がる路線転換を遂げていたわけで、82-83年ごろに 何があったのかは非常に興味深い。一番上の方に書いた様なニューヨークジャズシーンの変化の中、身の置き所を考えたという仮説は結構面白いんじゃないかと思う。その後ヨーロッパへの移住という事件もあるし。しかし、残念ながら現状私が持っている情報ではこれ以上の分析は不可である。
結言:テナーサックスに魅せられた男
上であえて「路線転換」と書いてみた。というのは、それ以前とはっきりと変わったのは、「回りのメンツ」と「選曲」であり、グロスマン自身のハイ ブリッドスタイルは実はあんまり変わっていないと思うからである。当然、その時期に改めてロリンズをはじめとするコルトレーン以前の巨人を相当研究したも のと思われるが、日本での86年、87年のライブでもわかるように、なんだかんだ言って盛り上がるとグロスマンフレーズオンパレードになっちゃうし、やっ ぱりフラジオは使うし、ソロ始まると終わんないし、さらに言えば八分音符のドライブ感や、音色、音量といったジャズテナー奏者としてのエッセンスは1975年のピットイ ンライブ、あるいは前に紹介した”New Moon”に入っているOut of Nowhereなどとあまり変わらないと思うのだ。多少変わったとすると、ベタなバップフレーズが増えたってところですかね。
さて、上記に上げたアルバムのうち最後の(5)は、86/21-2月に掛けて単身来日した時の演奏である。その来日の時は私も見に行ったし、翌年の 来日時には驚愕の(?)ライブアルバムを残しているし、活動がトレースしやすい状況であるので、本論ではこれ以降のことは取り扱わないことにする。それはともかくとして、この(5)のアルバムのライナーを見ていたら面白いエピソードが載っていたのでそれを紹介して終わりたい。
曰く、ライナーの筆者が70年代はソプラノの演奏で著名だったグロスマンになぜ最近はテナーしか吹かないのかと質問したところ(86年のツアーはテナーだけで通した)、グロスマンが以下のように答えたということである。ちなみに当時グロスマン35歳。
テナーは男の楽器である。テナーの持つ音の表現力のすばらしさに取りつかれてしまって他の楽器を持つことができない
おいおいホントにそんなこと言ってたのかよw、とか、そういいながら翌年のツアーではソプラノ吹いてたじゃんかよw(確かに借りものだったらしいが)、とか突っ込みどころ満載の発言ではあるが、なんとなく変に納得するところもある。
そうなのだよ。やっぱりこの人は、音楽よりもテナーサックスなのだ。テナーは男の楽器で、いかに男らしくテナーを吹けるか、を追及していったら、 コルトレーンからロリンズ、さらにデックスやベンウェブスターやレスターヤングやら、といった歴史上のテナー吹きの演奏を意識するのは当然といえば当然で、当時の"路線転換"も当人としては当たり前だったかもしれない。
当人以外から見ると、グロスマンはデビューした当時から今に至るまで、その「男の楽器」の魅力に満ち溢れた「稀代のハイブリッドテナー吹き」であり続けており、それが故に私を含む世界中のテナー吹きをいまだに魅了して已まないのだ。その後、数多くの有望テナー奏者が表れているが、「男らしさ」と いう観点ではだれが逆立ちしてもグロスマンにはかなわないと私は強く信じている。よって、信者としては、どんなスタイル、どんなフォーマットでも構わないので、生演奏をまた聴きたいし、どんな時代の録音でも入手したいのだった。教祖様万歳(笑)。
というわけで、スタイル変遷の背景などの考察はほとんどできない表題倒れの研究もどきでしたが、いったん終了ですかね。ご愛読ありがとうございました。
(2023/3/30追):上記文章の初稿は2006年ごろ?書いたものですが、わが心の師、Steve Grossmanは、2014年に再来日を遂げたのち、2020/8/13に亡くなりました。2014年は仕事の都合で行けなかったので、結局これを書いた後、生演奏を観ること叶わなかったわけです。残念です。
その代わりと言っては何ですが、亡くなった直後、1987年に来日した時の超貴重なライブ映像が数本You Tubeにアップされたので、それを次の投稿でご紹介してこのシリーズの最終回にしたいと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
