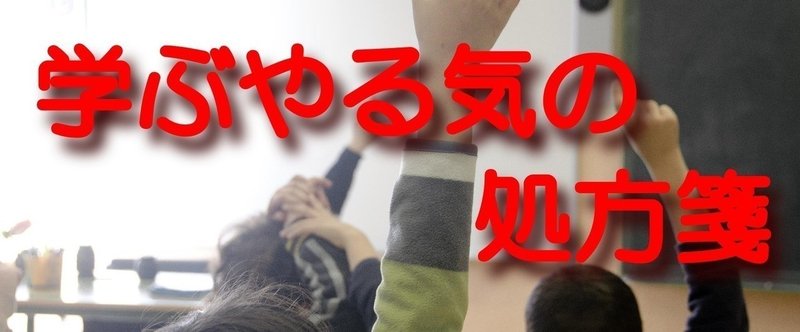
12 PDCA-2-1 「反復する」
次に学習効率を上げる「技」を見て行きたいと思います。
まず学習の「技」として最も思い浮かびやすいのは、「くり返し」つまり「反復」だと思います。
私たちの脳は入出力の多い情報、つまりよく使われる情報を重要だとして記憶する性質があります。
その点で、「反復」は記憶・暗記においては、最も基本的なスキルと言うことができます。計算など、他の学習でも基本的なスキルであることは変わりませんね。ただ、計算練習などでは、手順になれる、という側面もありますね。スポーツの場合などは、むしろこの側面の方が強いですよね。
確かに、学習でもそうした側面はあるのですが、「反復」が効果的なのは、何と言っても「覚える」場合です。
では、その「覚える」ための「反復」スキルの具体例を見てみましょう。
落語家は多くの噺を覚えていますよね。
俳優だって何時間ものお芝居のセリフを覚えるわけですが、落語が他のお芝居と違うのは、いつでも噺を引き出せなくてはいけないという点です。俳優の場合は、舞台に上がって何を演じるかは決まっています。「ハムレット」が突然「オセロ」に変わることはありません。
ところが、寄席では出演者は決まっていても、どの噺を口演するのかは事前には決まっていないんです。
つまり、落語家の場合、自分がやろうと思っていた噺や、それに似た噺を先にやられてしまうと、別の噺に代えざるを得ない、という特殊な事情があります。
だから、落語家は常に、直ぐに引き出せる形で噺を記憶していないといけないんです。
これは、何が出るか分からない問題に備える受験勉強に似ていますよね。
さて、そんな事情もあってか、落語の立川流では、昇進に明確な基準があります。前座から二つ目になるためには、古典落語の噺(五〇席)や歌舞音曲(四〇〇曲) を覚えなくてはならないのです。
立川談笑師匠はそれをなんと、入門後わずか半年でクリアされました。
その記憶術の基本は、
・徹底して再生する
五分、十五分、二時間と徐々に間隔を広げて再生する。
・計画的に復習する
五日間連続で復習。
そのあと、二日、三日、五日、七日と間隔をあけて復習。
口演することを前提にしているので、「反復」といっても徹底した再生主義です。
これは先ほどご紹介した脳の特徴、「よく使われる情報を重要だとして記憶する」に見事に適合したやり方です。
学習でも同じで、単に何度も書くのではなく、テスト形式で再生した方が覚えはいいのです。
私が実際に子ども達に指導していた漢字を覚える為のスキルを一つご紹介しましょう。
よく、「一つの漢字を30回ずつ書いてくるように」という指導がありますよね。
「反復」の典型的方法ですが、実はあまり効果がないことはご自身の経験で、多くの方がおわかりなのではないでしょうか。
なぜ、効果がないのか。
それは、30回書くという作業になってしまうからです。
漢字を書く目的は何ですか?
ノートを埋めること? 勉強している気分になること?
違いますよね。漢字を覚えることです。
だったら、回数は関係ない。1回で覚えられればそれでもいいはずです。逆に30回で覚えられないなら、もっと書かないといけないかも知れない。
しかし、実際にはそんなに回数を書く必要はありません。
先ほど、脳はたくさん使われる情報ほど重要だと捉えて覚える、という話をしましたよね。
だったら、漢字の入出力を増やしてあげればいい。
だから、回数を増やすというのは、間違いではないですが正しくない。効率が悪すぎる。
私が子ども達に教えたのは「看・念・写」という三文字です。
これは、見てだいたい意味は分かっていただけると思いますが、中国語の標語になっています。それは、「なんだかちょっと違っていて凄そう」と思わせる演出なのですが、日本語でわかりやすく言うと「見て、唱えて、書け」ということなんです。
入出力を増やすなら、違った入出力装置を同時に使ってやっても同じことです。
この場合、入出力装置というのは感覚器官ですよね。
見ることで目を使います。
唱えることで口と使い、それを聞くために耳も使っています。
書くというのは手を使いますから、これは触覚ですね。
ということは、鼻=臭覚以外は同時に使っている。
こうすれば、情報は単純ではなく複合的なものになり、脳はより重要だと判断します。
加えて、私は「文」で書かせていました。漢字テストの問題文ごと、ということです。
そうすれば、使い方も自然と身につきます。
ただ、この「反復」は、手順の習得と正確さの獲得、処理速度の向上、暗記のいずれをとって見ても、比較的単純なものの場合に威力を発揮するのであって、複雑な問題にはあまり効果はありません。前にもご紹介しましたが、「反復」と「成績」は関係性が弱いんです。つまり、成績上位になるために必要な、難易度の高い問題には対応できていないと考えることができるわけです。
逆に言うと、基礎から応用に手を出そうかというレベルまでは、「反復」が有効だと言うことができます。
「反復」は再生主義でくりかえす、というのが肝心です。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
