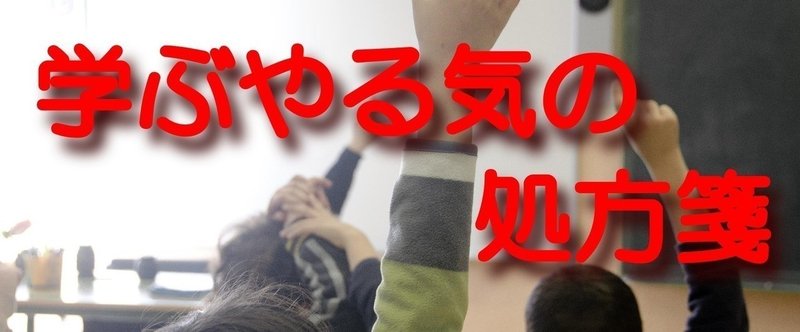
09 PDCA-1-3 目標を具体的にする
人間にとって一番辛いことは何か、考えたことがありますか?
これには色々な答えがあると思いますが、その内の一つは、意味の無いことをさせられることだと言われます。
かつて旧ソ連の強制収容所などで行なわれた拷問に、囚人たちに半日かけて地面に穴を掘らせ、半日かけてそれを埋め戻させるというものがあったそうです。これは非常に精神的な負担が大きかったと言われています。
それは全く意味が無い作業だからです。
でも、それを自ら望んでやった人がいたとしらどうでしょう。驚くのではないでしょうか。
しかし、実際にそんな人が、しかもこの日本にいるのです。
それは、元ラグビー日本代表選手で、京都産業大学ラグビー部コーチを務める元木由記雄氏です。
元木氏は、あるインタビューの中で次のように語っています。
「高校はラグビーで有名な大阪工業大学高校へ進み、いよいよラグビー一色の学生時代が始まりましたね。( 中略 )授業が終わって4時ぐらいから練習が始まり8時ぐらいまでやるんです。そして、その後は自主トレというか、僕の場合は練習帰りに近くの河川敷で穴を掘っては埋めるというトレーニングをしていましたね。それも自分の身長ぐらいの深さの穴を。高校時代の監督の話によると、「ニュージーランドのプレーヤーが筋肉強化のためにやっているらしい。やってみたらどうだ」ということで、毎日掘ってました。当時、河川敷は穴だらけだったでしょうね(笑)、もちろん埋めてましたよ。( 中略 )練習で毎日くたくたの高校時代だったけど、強くなりたいという気持ちがすごくあったから、がむしゃらになれました。」(JS日本の学校「有名人スポーツワンポイント講座」)
どうでしょうか、やっていることは強制収容所の囚人も元木さんも同じですよね。でも前者ではそれは拷問になり、後者ではトレーニングでしかも夢中になれることになっています。
一体何が違うのでしょうか?
それは、その行為についての意味づけです。
元木選手は強くなるための筋力強化だと考えて実践していました。しかし、囚人たちは何の目的も見出せずにそれを行なっていただけです。
別の例も挙げておきましょう。
2010年の映画「ベストキッド」。
この中で、ジェイデン・スミス演じるドレは、ジャッキー・チェン演じるハンにカンフーを習います。しかし、ジャケットを着たり脱いだり、木人樁に掛けたりするトレーニングを命じられて、ふて腐れてばかり。
あるとき、ドレは我慢の限界に達して、こんなことは意味が無いとハンに食って掛かります。
そこでハンは今までの訓練が、すべてカンフーの動きに繋がっていたのだと、その意味を教えます。そこで、ドレはようやく熱心に訓練に臨むようになります。
また、一見単純に見えるダンベルやベンチプレスのような筋力トレーニングでも、どうすれば何処の筋肉が鍛えられるのか、今どの筋肉を鍛えているのか、という意味が分かっているのと分かっていないのとでは、効果にも違いがあるそうです。
こうしたことは、学習、受験勉強でも同じです。
受験というのは、非常に大きな壁であり、絶大な存在感があります。その特別な存在感は、日々の学習との親密さが薄く、壁であるがゆえに、そのあとの生活への思いをはせがたくさせるところがあります。
それもまたやる気を不安定にさせる要因の一つといっていいと思います。
その不安定さを解消する一つの方法は、日々の学習と受験ががっちりとかみ合うこと。受験という目標がはっきりしていればいるほど、両者がかみ合ったとき、日々の学習の必要性はより強く認識されることになるでしょう。
ですから、受験勉強という比較的目標が明確な学習にしても、単に受験に出るから、というのではなく、「この形式の問題は●●高校の何年と何年の入試にでた頻出問題だからやっておく必要がある」といった、より具体的且つ個別的な意味づけがあった方がいいでということです。
または、受験がその先の生活や子どもたちが抱いている夢や希望と関係があること、もしくは日々の学習が受験すら超えて、それら未来と直結していることを意識することが有効です。ただこれは、周りがサポートしても非常に難しい。しかし、ある意味では理想の形だと言えます。
そもそも学校の勉強というのは、実社会とは直結しているわけではありませんよね。だから、たとえば比較的「スキル」的な英語にしたところで、英会話は世界で活躍する役にたつけど、受験勉強の英語なんて役に立たない、という声も出たりするわけです。
そう思っているのでモチベーションが上がらないという子どももいるかも知れません。
でも、私の友人で、シンガポール南洋工科大学や、イギリスのブリストル大学の研究所に勤めた経験もある国際政治学者は、「受験英語なんて役に立たないと言われるが、僕が今まで海外で研究者としてやってきた上で、一番役に立ったのは、受験勉強で身に着けた英語だった」と語ってくれたことがあります。研究職なので、硬い文章を読み書きしなければならないわけですから、ある意味当然ではあるのですが。
しかし、こんな体験談を語ってあげれば、一見無意味に思えた受験英語が、現実と繋がっていることが認識でき、そこに自分なりの意味を見出すことが出来るかもしれません。
第一義的には、子どもたちが自分で明確な目標を定めることが必要なのですが、発達段階や状況に応じて、周囲の大人が手助けをしてあげる必要はあるでしょう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
