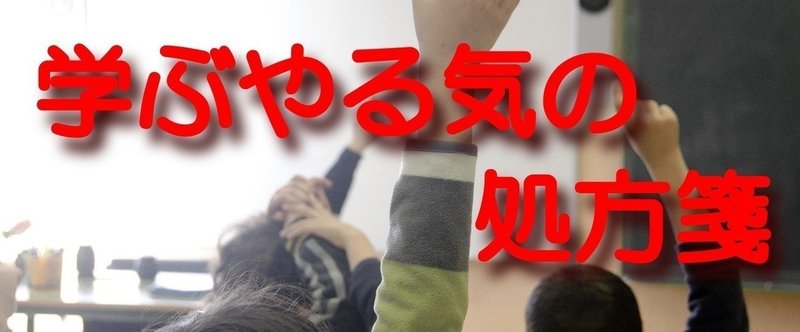
11 PDCA-1-5 運動する
進学校というと、ひたすら勉強ばっかり、というイメージをお持ちの方が多いかもしれません。
しかし、毎年東京大学に百名前後の合格者を出している灘高校は、柔道が必修科目になっていて非常に熱心です。

実は、灘高校は酒造メーカ三社が設立した学校で、その内の一社「白鶴」の創業家は嘉納という姓です。
どこかで聞いた苗字ですよね。
そう柔道の生みの親、講道館の嘉納治五郎と同じです。
実際に、治五郎の嘉納家と、「白鶴」の嘉納家は親戚で、治五郎が灘高校の初代顧問を務めています。校是「精力善用」「自他共栄」も嘉納治五郎が柔道の精神として唱えたものです。実際に戦前は進学校ではなく柔道の強豪校として知られていました。 灘出身者の著作には、「実は柔道が学習によい影響を与えていた」という話が、しばしば見られます。
一見すると、ノスタルジーのようにも思えますが、そうではないのです。
柔道は、ある程度長時間にわたって身体に適度な負荷がかかり続ける有酸素運動です。つまりきちんと呼吸をしながらする運動です。同種の運動としては、ウォーキングや水泳などがあります。
逆は無酸素運動。ごく短い時間、呼吸をほぼ止めた条件で行なう負荷の大きな運動です。短距離走とか、ウエイトリフティングとかですね。
最近の研究では、柔道や水泳などのような、心拍数が適度に上昇し、心肺機能に持続的に負荷がかかる運動が学習にとってプラスに働くことが分かってきました。こうした運動の後では、脳への血流も、それによって送られる酸素量も増えているので、それも影響していると言われています。実は学習するというのは、脳が活発に活動するため、非常に多くの酸素を消費しているのです。
また、運動は脳と体のバランスを調整してくれます。
もともと人間の心身はバランスは、農耕なり狩猟なりといった活動のために設定されています。 ですから、坐っている姿勢というのは本来休んでいる状態のはずで、当然脳も休もうとするのです。
しかし、学習というのは坐って脳を酷使する行動ですから、心身のバランスを崩していることになるわけです。ストレスが溜まってくるのもその所為です。 そこで、軽い運動すると、本来のバランスが取れた状態にもどり、ストレスも軽減されるということになります。
以上の二つから、学習の合間に、伸びをしたり、あたりを一回りするなどの軽く体を動かす休憩をとった方が、効率的で意欲的な学習ができる、ということができます。
また、《分散効果》といって、長時間集中して学習するより、間に休憩をとった方が、その間に短期記憶が長期記憶に移動するため、効率的だという研究報告もなされています。
また別の面から運動の効果をみてみると、セロトニンやドーパミンといった化学物質が増えることで、うつ状態になりにくくなると同時に、気持ちが前向きになり、集中力も増すとされています。また、ストレスも軽減されるため、ストレス性の諸症状の緩和にもなります。さらに、脳由来神経栄養因子やインスリン様成長因子が増えることで海馬が刺激されて神経細胞が作られ、記憶力も増すと言われています。

さらに最近では、イギリスのスポーツ医学誌「ブリティッシュ・ジャーナル・オブ・スポーツ・メディシン」に発表された研究で、定期的な運動は学業成績を上げ、特に女子では理科においてそれが顕著だということが統計的に示されています。
この研究は、アメリカとイギリスの研究者が、五千人の十一歳児を対象に、一週間の身体活動を測定し、十一歳時だけではなく、経年で十三歳、十六歳の時点での英語・数学・理科の成績を調査したものです。 その結果、十一歳時の身体活動が活発だった子供ほど、どの時点でも成績が高く、一日あたりの運動時間が、男子では十七分、女子で十二分増えるごとに得点の向上がみられたそうです。
しかし、いくら運動が学習効率を上げるといっても、時間を使いすぎると、折角の効果を、学習時間の減少分が相殺してしまい、場合によっては収支はマイナスになってしまいます。また、運動負荷をかけすぎることはストレスにもなり、当然体にはよくありません。
なにごともほどほどということですね。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
