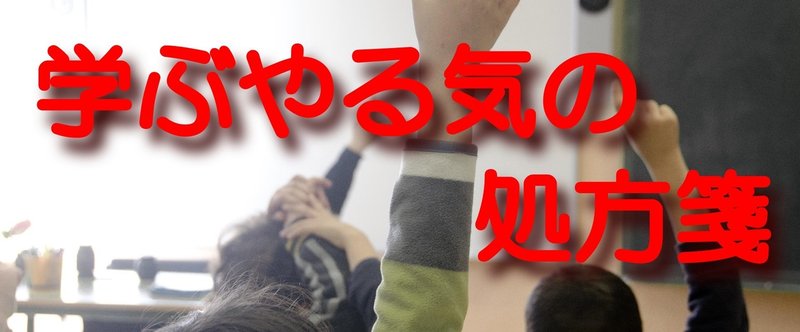
04「できる?」「できた」「おもしろい」
「やる気」を起動させる重要な「刺激」として、「学習する理由」つまり「学習動機」を紹介しましたが、実はもう一つ、重要な「刺激」があります。
それは「自己効力感」です。
「自己効力感」は、「有能感」という言葉とほぼ同義で使われることがあります。この「自己効力感」というのは、狭い意味では「具体的な、ある状況下において、適切な行動を成し遂げることができるだろうという、自分の能力や可能性についての予期や確信」と定義されます。つまり、「やればできるだろう」という自信ですね。
それに対して「有能感」は、「自分の行動によって周りに働きかけ、その結果意図したことが達成され、それにもとづいて自覚する達成感」と定義されます。つまり、「自分はできた」という確信です。
「自己効力感」が予測・自信、「有能感」が結果・確信ということで、未来を志向しているか、過去に基づいているかという違いはありますが、広い意味では「可能である」という意味を含んでいますので、ほぼ同じものを指す場合があります。
ここでは、「自己効力感」という言葉で通して生きたいと思います。
さて、「自己効力感」が未来への自信だとしても、それはやはり実際の試行錯誤の結果として、達成した結果がなければ、高まることはありません。中には根拠のない自信を持った人もいるかもしれませんが、ここではそういう少数派の人のことはひとまず置いておきます。
「学習動機」つまり「勉強する理由」において、自分で決めている度合いが高い、つまり、より内発的であるということは、学習の理由に「他者からの強制性」を感じるのではなく、それ自体の興味や好奇心から学習しているということでした。であるならば、それは高い「自己効力感」に基づいているはずです。
だって、できもしないことが面白いはずはありませんから。
実際、さまざまな調査によって、「自己効力感」と「学習動機」は相関関係が指摘されています。
つまり、「学習動機」が内発的であれば、「自己効力感」も高い。「自己効力感」が低ければ、「学習動機」も外発側に振れてくる。
では、「自己効力感」はどうやって高めればいいのか。
先ほど述べましたように、「自己効力感」も過去の結果に基づくものであるの、よい結果を出してあげればいいのです。
ということは、よい結果を出すための学習方法を考える必要があるわけですが、これは後ほど改めてご紹介することにします。
その前に、「学習目標」と「自己効力感」の関係を述べておきたいと思います。
先に記しましたように、「自己効力感」と「学習動機」には相関関係があります。これは簡単に言えば、「できるだろう」と思えばやろうという気にもなるし、「できないだろう」と思えばやるのが億劫になるということです。
このことを「熟達目標」と「遂行目標」に重ねて考えると、すっきりとした構図が浮かび上がってきます。
例えば、「熟達目標」である場合には、達成可能性が高い目標を立てやすく、実際に達成が見込めるわけですから、「できるだろう」という気になる、つまり、「自己効力感」が強くなります。
そして、目標が達成されることによって「わかった」「できた」という感覚が生まれ、「自己効力感」の好循環が起こります。そうすると、やっていて「楽しい」という感情が起こり、、それによって学習すること自体に積極的なって行く、つまり内発的な「学習動機」が引き出されるようになる。
ところが、「遂行目標」の場合には、目標が達成できるかどうかは、自分の努力とはあまり関係がありません。評価は他人との関係で決まりますから。
自分がいくら頑張っていも、周りの方がもっと頑張っていれば、相対的には「頑張っていない」ことになる。つまり、負けてしまう。
その場合には、劣等感・敗北感がつきまといます。その結果、課題はやってもやっても意味のない「つまらない」ものになり、「やりたくないけど仕方がない」という「自己決定性」の低い状態に陥ってしまう。
このように考えれば、「やる気」の為には「自己効力感」が必要で、そのためには「熟達目標」である方がが効果的だということが、理解していただけるかと思います。
でも、いまひとつ納得はできないんじゃないでしょうか。
だって、実際に子供たちが置かれているのは、圧倒的に「遂行目標」の世界です。
大人が仕事や活動のなかで生きる世界も、努力するプロセスが評価されるだけではとどまらず、否応もなく優勝劣敗という「相対評価」の中で結果責任が問われる厳しい世界です。
なかんずく、受験というのは典型的な「遂行目標」の世界です。そこで評価基準とされる「偏差値」はまさに「相対評価」の産物以外の何者でもありません。
確かに、受験勉強でも、その必要性を強く意識していれば、内発的な「学習動機」をもてるでしょうが、実際には、不得意科目などを意識せざるを得ないですし、周りを見れば自分よりよくできる者がたくさんいる。ついつい「合格できないかもしれない」と自分の可能性について不安が頭をもたげてくるものです。そうすれば、「自己効力感」が揺らぎます。
受験勉強において、「やる気」が不安定なのは、そうした「遂行目標」の世界であるが故です。
だからこそ、周りの人間も学習者本人も、より強く「熟達目標」を意識して、「自己効力感」を高めて、「やる気」の安定を図る必要があるのです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
