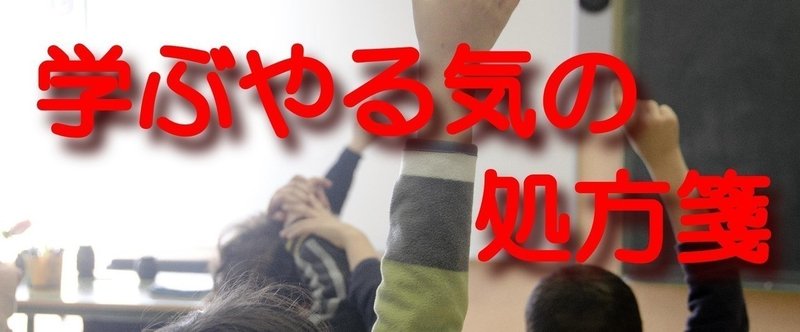
13 PDCA-2-2 「整理」〜花緑師匠の台本〜
「整理」は情報をまとめること。ノートにまとめるだけではなく、テキストへの書き込みなどもこれに当たる場合があります。
特に暗記・記憶においては内容をまとめるというのが基本になります。
ここでもまず、落語家さんの例を見てみましょう。人間国宝であった故・五代目柳家小さんの孫に当たる柳家花緑師匠は、ネタをノートに書き写して台本を作って覚えるそうです。
落語の稽古というのは、師匠からの口伝え、メモを取ってはいけないのがルールです。
しかも、一人で演じる芸で、基本的に座布団の上からは動けません。ですから人物の違いは、口調の違いと、「上下(かみしも)」と呼ばれる身体の向きで表現します。
今誰が何処にいて誰とどういう位置関係で喋っているのかを理解しないと成立しません。
花緑師匠はそれを、台本の形に整理しているんですね。それによって効率的に噺を覚えているんです。
学習でも、覚えるべき内容、ポイントを明確にしなければ効率が上がりません。しかし、女の子に多い例ですが、いろんな色のペンを使って見た目にも華やかなノートを丁寧にまとめているのに、暗記の方はおぼつかないという子がいます。
これは、覚えるべき情報が整理されていないんです。そんなこと言ったって、ちゃんと整理しているじゃないかという方もいるかもしれませんが、ノート作りが目的化してしまって、内容は二の次になっていることがあるんです。また、たくさんの色を使うことで却って情報量が増えて、わかりにくくなっているとも言えます。
ここに一つポイントが含まれています。
図表を使ってわかりやすく示す、要点を整理する、これらの工夫を行う際に、一番必要なのは、「情報量を減らす」ということです。
つまり、覚えるべき内容とそうでない内容を峻別するということです。
それは覚えるときだけではなく、国語の課題文やその他の科目の設問文を読んでいる時でも実は同じなんです。
必要な情報を取り出すということが、大切なんです。
しばらく前にベストセラーになった齋藤孝氏の「三色ボールペン」はまさに、この整理を読みながらやっていこうということなんですよね。
実際に、国語の苦手な子というのは、読んでいる時に情報の整理ができていないんです。
これは実際に私が教えたことのある子どものケースですが、「大切だと思うところに線を引きながら読んでみなさい」と指示すると、全文にマーカーを引いてしまうんです。
そういうことだと、当然ですが他の科目でも必要な情報がどれか分からないので、問題が解けないという状態になってしまいます。
こういう状態だと、気持ちを表す言葉、数字、方角、など、その都度必要になるものを具体的に指示してあげる必要があります。整理の前提となる情報の価値判断をするための基準が身についていないからです。
基準が身につけば、情報を取捨選択できる。
取捨選択ができれば、まとめやすくなります。
情報はそぎ落としてから区別する、これが「整理」のキーワードです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
